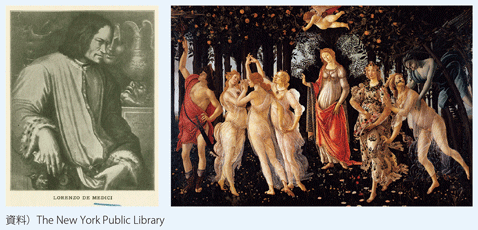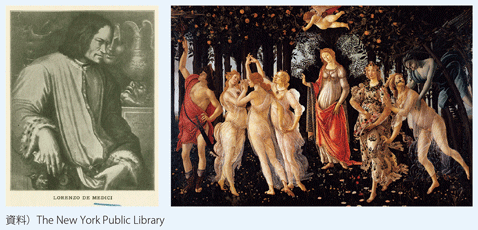コラム アートの支援者
「芸術」や「芸術家」という概念が誕生したのは、ルネサンスの頃と言われています。ルネサンスは、14世紀、イタリアで興った、個性を尊重する古代ギリシアやローマ文化の復興を目指す運動です。ルネサンス期のフィレンツェでは、豪商のメディチ家が、美しい都市をつくろうと公共事業に芸術を取り入れたため、芸術家の支援につながったと言われています(図表I-3-2-9)。
図表I-3-2-9 メディチ家(ロレンツォ・デ・メディチ)(左)、「春」(ボッティチェリ作)注(右)
また、15世紀後半になると、レオナルド・ダ・ヴィンチがフランスの宮廷に招かれたことにより、フランスにもルネサンス文化が華開き、18世紀には、アカデミー・フランセーズや王立絵画彫刻アカデミーを創設するなど、教育面から芸術家を支援する仕組みも生まれました。
現在においても、イタリアやフランスでは、芸術家を支援しようとする風潮は根強く、例えば、公共建造物の予算について、イタリアでは最大2%、フランスでは最大1%を芸術作品の購入などに充てることが義務化されています。
日本では長い間、藤原道長や豊臣秀吉といった、権力者が中心となって、和歌や絵画などの芸術・文化の振興を行っていました。江戸時代になると、識字率の上昇や印刷技術の発展により、芸術を楽しめる層は庶民にまで広がり、彼らが中心的な役割を果たすようになります。明治時代以降は、西洋化を進めるため、政府主導による文化芸術振興が始まりますが、戦争を背景に芸術家の創作活動への規制が厳しくなり、芸術は衰退していきます。
高度経済成長期を迎えると、再び、芸術・文化に対する注目が高まります。政府では美術館の建設などが進められ、また、現在はなくなってしまいましたが、モニュメントなど芸術作品に、公共施設の建設費の1%を充てるといった地方自治体も増加し、芸術家を支援しようとする動きが生まれました。
アートは、かつては一部の人のものでしたが、現在は、様々な空間に取り入れられ、私たちにとってより身近なものになっています。美しい絵を見て心を打たれ、変わった形のベンチを見て楽しいと感じるなど、日々の生活を豊かにしてくれています。私たち一人ひとりが、もっとアートに目を向け、その支援者となる時代が来ているのかもしれません。
注 一説によれば、ロレンツォ・デ・メディチの依頼により本作は制作された。