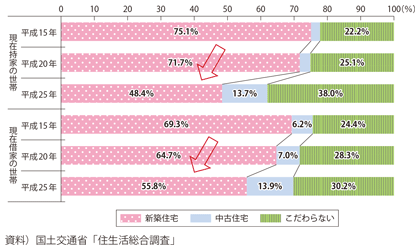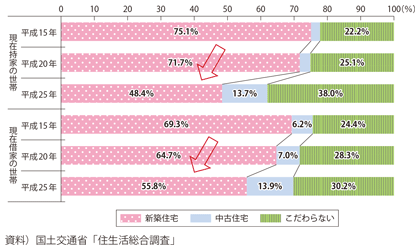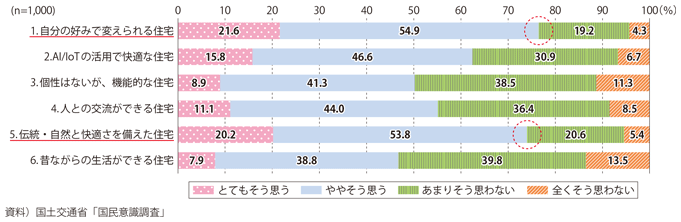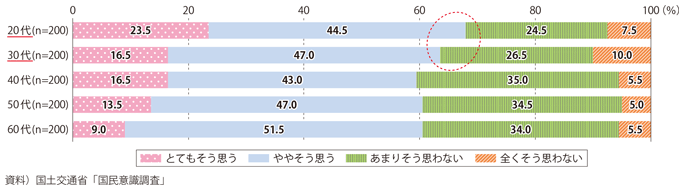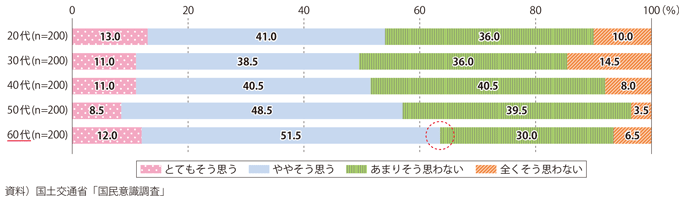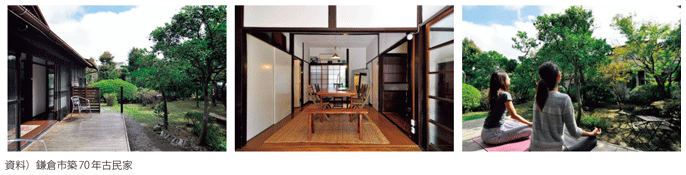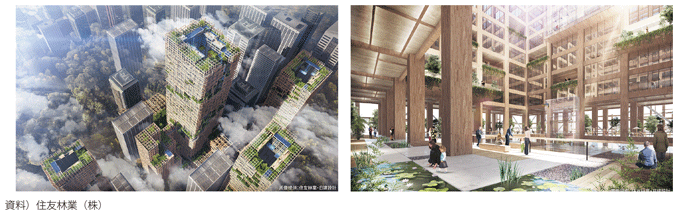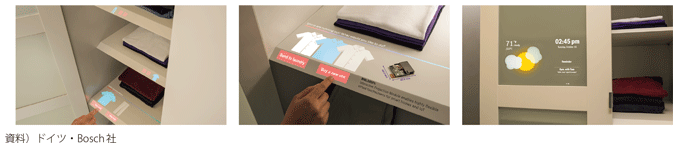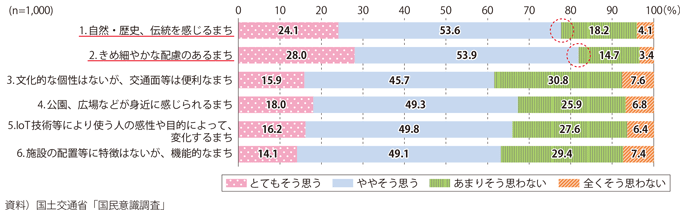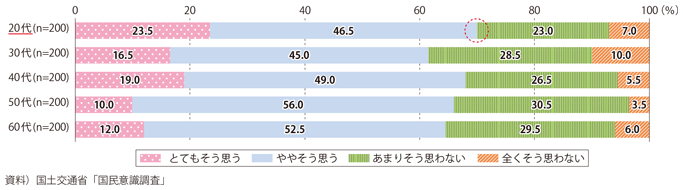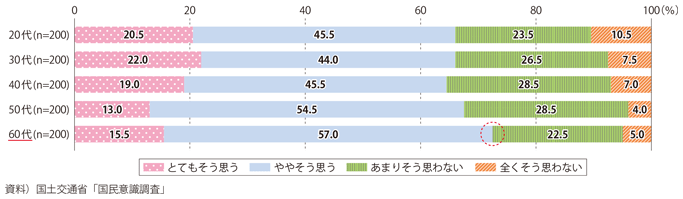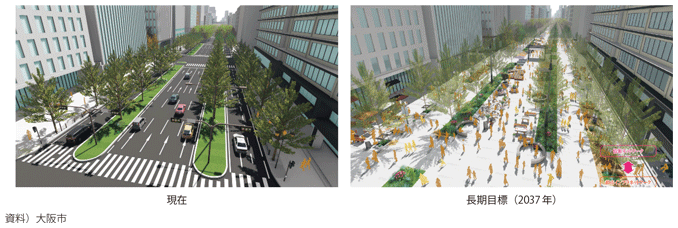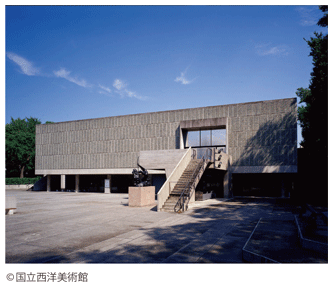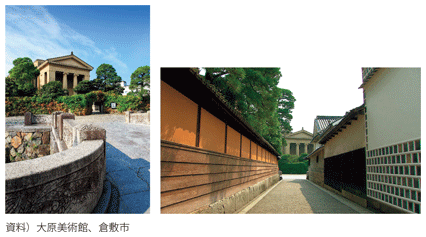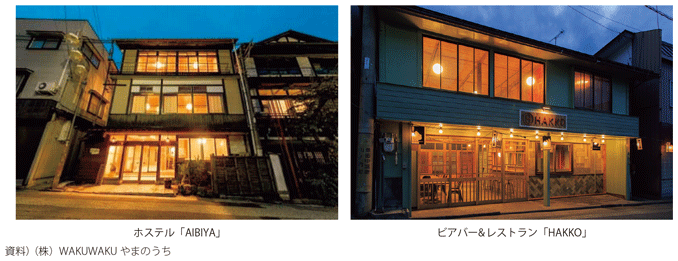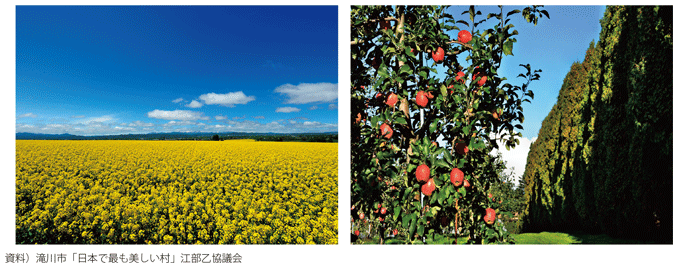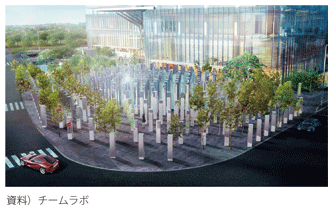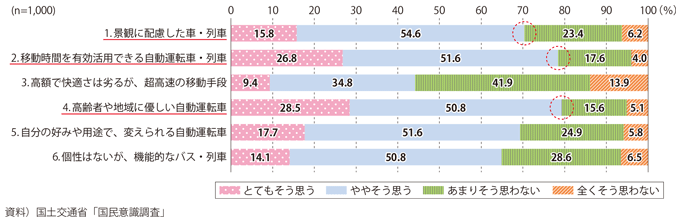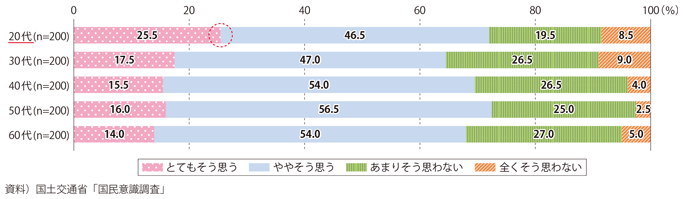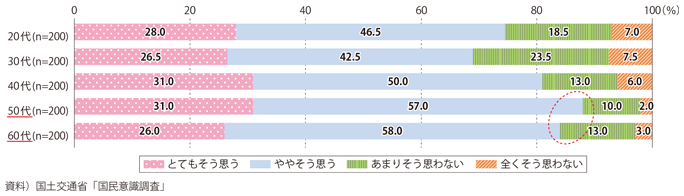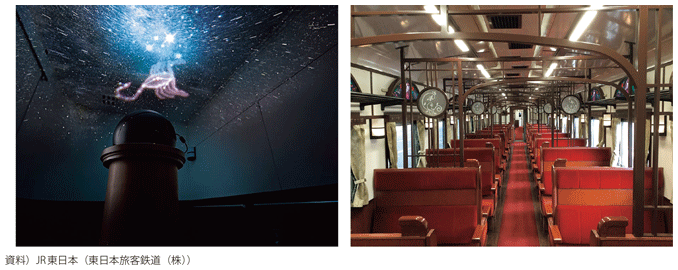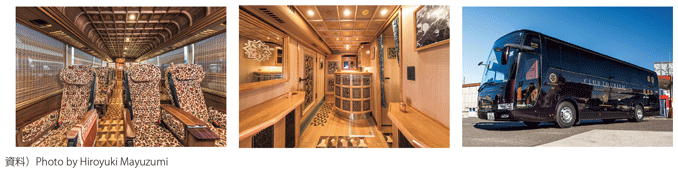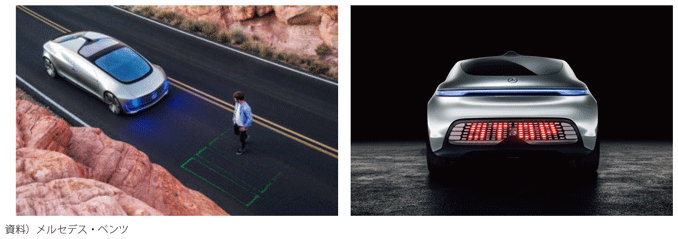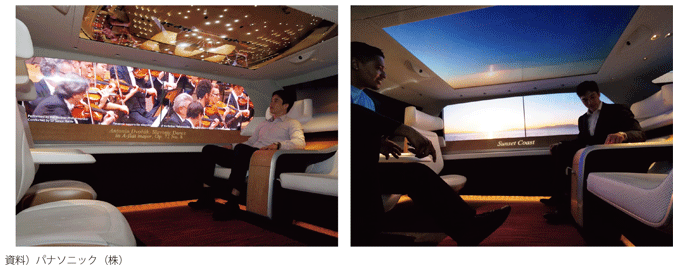■2 日本人の感性(美意識)を取り込んだ「生活空間」の方向性と今後の取組み
(1)「住空間」について
(現在の「住空間」の主な状況について)
近年は、住宅政策の後押しやリフォーム技術の進歩などもあり、以前と比較して、日本人の新築購入の希望は減少してきている(図表I-3-2-12)。一方、全流通住宅に対する新築住宅のシェアの割合は85.3%であり、米国の16.9%、英国の12.0%に比べて極端に多い状況となっているなど、依然として新築の割合が大きい。
図表I-3-2-12 今後の持ち家への住み替え方法(新築・中古)に関する意向
現在、日本においては人口減少が進み、将来は、世帯数も減少が見込まれている。このような中、地方をはじめとして使われていない住宅が増えており、それらをいかに活用するかが課題となっている。
以上を踏まえて、その造りを前提としつつ居住者の個性を可能な範囲で取り込むなど、居住者のニーズをできるだけとらえていくこと等がますます重要となっている。
(今後の「住空間」に対する国民の意識)
未来の生活を豊かなものとするために、どのような「住宅」に住みたいかについて、前述の国民意識調査により尋ねたところ、「自分の好みで変えられる住宅」と「伝統・自然と快適さを備えた住宅」について、「とてもそう思う」と「ややそう思う」があわせて7割を超え、全体として、自分らしさや伝統・自然を求める傾向がみられた(図表I-3-2-13)。
図表I-3-2-13 住んでみたい未来の住宅
また、年代別の特徴として、20代、30代において、「AI/IoTの活用で快適な住宅」について肯定的な人が多く(図表I-3-2-14)、60代において、「人との交流ができる住宅」について肯定的な人が多い結果となった(図表I-3-2-15)。若い世代は最新技術による快適さに、高齢の世代は人との交流に、それぞれ生活の豊かさを感じる傾向にあると推察される。
図表I-3-2-14 「AI/IoTの活用で快適な住宅」へのニーズ(年代別)
図表I-3-2-15 「人との交流ができる住宅」へのニーズ(年代別)
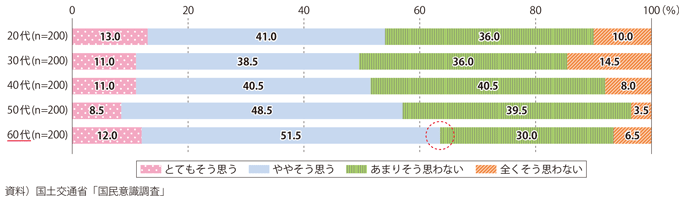
(今後の「住空間」の方向性について)
以上を踏まえると、日本人の感性(美意識)を活かした「住空間」を創出するためには、住宅の中において、伝統や文化をはじめ、居住者の感性(美意識)をさらに自由に取り込めることが重要である。例えば、部屋の間取り、絵画などの美術品を飾るスペース、壁紙などの装飾等について、リフォームや新築を問わず、もっと自由に選択し、かつ、それを実現できる環境をつくっていく必要がある。
また、
第1章第3節でも言及したとおり、日本人が昔から持つ感性(美意識)として、自然との調和、伝統・文化の尊重、義理がたさ(他者への思いやり)、和といったものがあり、このような感性(美意識)を活かした「住空間」のさらなる創出も必要であると考えられる。例えば、我が国には、多数の歴史的・伝統的な建築物が存在しており、それらを維持・活用した住宅をもっと増やしていくこと、居住者が交流しコミュニティを形成しやすい環境をつくっていくことなどが挙げられる。
技術の発展については、
第1章第2節や
第3章第1節においてふれたが、人工知能(AI)をはじめとする新技術は、今後、さらに我々の住空間に取り入れられてくることが想定される。これらの新技術と居住者の感性(美意識)が融合することにより、より快適で自分らしい空間をつくり出すことができる環境になると考えられる。また、建築技術等の進展により、木材のさらなる利活用をはじめ、日本人の感性(美意識)に応えた(活かした)新たな住空間の創出も期待される。
以下では、このような方向性を具体化する現在の取組みについて、これまでの取組みを更に進めたものを「これまでの取組みの深化」、新技術を活用した新たなものを「新技術と一体となった新たな取組み」と分類し、それぞれ紹介する。
(これまでの取組みの深化)
■居住者の感性(美意識)を自由に取り込むことのできる住宅
既存住宅はその活用が求められる一方で、間取りなどが作り込まれており、居住者が自由な空間づくりをすることは難しい。そこで、無印良品とUR都市機構は、古い建物に住む場合でも、魅力的な空間で生活者の自由を確保することを考える新たなリノベーションプロジェクトを始めた(「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト」)。このリノベーションでは、柱や鴨居
注15など味わいのある古い部分をできる限り残しつつ、設備など必要な部分は更新した。また、固定された間取り・デザインからの解放を目指し、間仕切りをできる限り取り除いた。このことにより、広い一室として使ったり、鴨居を使い個室にしたり、暮らし方の変化に合わせて、間取りを自在に変えることができる。新築にはない温かみを大切にしながら、居住者が創造力を働かせ、家具などで自由に住空間をつくることが可能となっている(図表I-3-2-16)。
図表I-3-2-16 MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト
また、既存住宅であっても、IoT照明、衣服の自動折り畳み機などの最新家電を取り入れた、IoTづくしの部屋が実現されている。IoTの活用により、家事時間は短縮され、自由時間が増加するとともに、居住者の好みにより照明の色が変更できるなど、きめ細やかで居心地の良い環境が創出されている(図表I-3-2-17)。
図表I-3-2-17 IoTづくしの部屋
■多世代が住み、交流できる住宅
核家族化等に伴い従前の地域のコミュニティ機能は弱まってきている一方で、高齢者の増加等によりその必要性は高まっている。このような中、駅前の団地において、敷地内に農園やカフェを設けるリノベーションを実施し、地域の住民に開放するとともに、団地の一階部分に、立地を活かして、公益施設である「子育て支援センター」を誘致するという取組みが行われている。これにより、地域における多世代のコミュニティの創出につながっている(図表I-3-2-18)。
図表I-3-2-18 リノベーションにより多世代の交流が広がる団地
■伝統や自然と調和した住宅の維持・増加
古民家は各地域の気象風土に合わせ、例えば、縁側は外部との緩衝地帯として暑さ寒さを和らげる役割を持つなど、自然を上手に取り入れながら暮らす造りとなっており、近年は住宅以外の宿泊施設などとしても再生される事例が増え、日本の伝統の良さを活かした空間が広がってきている。
鎌倉市にある築70年の古民家については、解体される他の古民家の材料を活用するとともに、壁塗りなどを居住者が自ら行う「DIY注16」により、リノベーションを行った。その結果、伝統を守りつつ、自然も感じられ、また、居住者の感性を活かした住空間として生まれ変わっている。また、住居のみならず、コミュニティスペース(蕾(つぼみ)の家)として国際交流やイベントなどにも活用されている(図表I-3-2-19)。
図表I-3-2-19 蕾の家
なお、DIYは、その人の感性を活かすとともに、充実感も得られることなどにより、住居などへの愛着を生むものであり、今後のさらなる広がりが期待される。
(新技術と一体となった新たな取組み)
■新技術と日本の伝統の融合による新たな住空間の創出
住友林業(株)は、2041年を目標に、70階建ての「木造」の超高層建築物を建設する研究技術開発構想を発表した。建物の構造は木材の比率が9割を占め、建物用途は店舗・ホテル・オフィス・住宅を想定している。
超高層ビルの木造化は、材料、建築分野での研究、技術開発を加速させるとともに、高層ビルでありながら、豊かな自然、木漏れ日、伝統的な木のぬくもりが感じられる空間の創出が予想される(図表I-3-2-20)。
図表I-3-2-20 木造超高層建築物
なお、ストックホルムにおいて34階建ての「木造」の高層マンション、ロンドンにおいて80階建ての「木造」の超高層ビルを建設する構想もあり、海外においても同様の動きが見られる。
■新技術を活用した自分らしい快適な住空間の創出
自分らしい快適な住空間をつくるため、AIなどを活用した技術の開発が進んでいる。例えば、クローゼット、冷蔵庫、キャビネットのドアに、収納してあるものの情報を投影するとともに、AIを応用し、その日の天候やスケジュール等にあわせ、お薦めの服や料理などを表示することができるといった技術が生まれつつある(図表I-3-2-21)。また、この技術では、選択したものの情報を学習させることにより自分の好みも踏まえた提示をさせることができ、今後、さらなる広がりを見せることが想定される。
図表I-3-2-21 スマートシェルフ
(2)「公共空間」について
(現在の「公共空間」の主な状況について)
我が国では、特に第2次世界大戦後から高度経済成長期にかけて、経済性や機能性を重視した結果、ビルや看板が乱立するなど、まちの景観が大きく変わる一方で、全国的に均一化された都市が生まれていった。しかし、平成に入り、景観法の制定をはじめ、文化や伝統など都市の特徴を活かしたまちづくりが進められてきており、さらなる広がりが期待される。
また、高度経済成長期以降、例えば、清掃など従来は地域の人々が任意に行っていた業務を行政が担うようになるなど、行政の役割が拡大してきた。平成には、民間の活力を官にとりこもうと1999年(平成11年)にPFI法の制定や2004年頃から公的空間の利用の柔軟化などの取組みが行われてきている。
さらに、公共空間におけるバリアフリーについては、平成において「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が制定され、その後改正されることなどにより、一定程度進捗してきたが、すべての国民が共生する社会の実現に向けて、全国において、バリアフリーの街づくりを推進することが必要である。
加えて、高齢化が進むとともに、子育てしやすい環境づくりなどがますます求められている中、歩行者等に優しい空間づくりを一層広げていく必要が生じている。
(今後の「公共空間」に対する国民の意識)
未来の生活を豊かなものとするために、どのような「まち」に住んでみたいか、または訪ねてみたいかについて、前述した国民意識調査により尋ねたところ、「きめ細やかな配慮があるまち」と「自然・歴史、伝統を感じるまち」について、「とてもそう思う」と「ややそう思う」があわせて約8割となり、全体として、優しさや自然・伝統などを求める傾向がみられた(図表I-3-2-22)。
図表I-3-2-22 住んでみたい、訪れてみたい未来のまち
また、年代別の特徴として、20代において、「IoT技術等により使う人の感性や目的によって変化するまち」について肯定的な人が多く(図表I-3-2-23)、60代において、「公園、広場などが身近に感じられるまち」について肯定的な人が多い結果となった(図表I-3-2-24)。若い世代では、最新技術によりまちをもっと自分の好きなように活用したいと思っており、高齢の世代では、公園や広場等が居場所などとして身近になってほしいと考えていると推察される。
図表I-3-2-23 「IoT技術等により使う人の感性や目的によって変化するまち」へのニーズ(年代別)
図表I-3-2-24 「公園、広場などが身近に感じられるまち」へのニーズ(年代別)
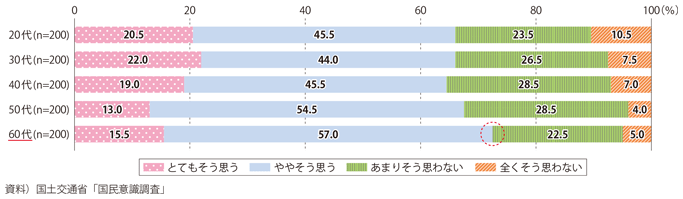
(今後の「公共空間」の方向性について)
以上を踏まえると、日本人の感性(美意識)を活かした「公共空間」を創出するためには、前述のとおり、自然との調和、伝統・文化の尊重、義理がたさ、和といった日本人が昔から持つ感性(美意識)を公共空間へ更に取り入れていくことが必要であると考えられる。例えば、美しい自然を維持・活用するまちづくり、文化財のみならずその周辺の建物や道路に連続性を設け、全体として一体となった空間づくり、バス停にベンチを設置するなど、優しさや思いやりを感じる「きめ細やかな」まちづくりなどが挙げられる。
また、公共空間でありながら、自分の感性(美意識)を感じられる(反映できる)環境を創出することも重要であり、公共空間を私的空間の延長のように身近に感じられるようにしていくことが必要であると考えられる。例えば、公共空間を私的空間のようにもっと活用できる取組み、公共施設に自分の思い出が記されることなどにより、公共空間をもっと身近に感じてもらう取組みなどが挙げられる。
新技術についても、今後、さらに、「公共空間」にも取り入れられてくることが想定される。これらの新技術と利用者の感性(美意識)が融合することにより、公共空間は、より利用者のニーズを踏まえた、快適で柔軟な空間となっていくものと思われる。
以下では、このような方向性を具体化する現在の取組みについて、これまでの取組みをさらに進めたものを「これまでの取組みの深化」、新技術を活用した新たなものを「新技術と一体となった新たな取組み」と分類し、それぞれ紹介する。
(これまでの取組みの深化)
■優しさや思いやりを感じるきめ細やかなまちづくりの推進
歩行者等に対するきめ細やかな空間づくりについては、様々な取組みがなされつつある。
兵庫県神戸市では、都心の道路を活用し、憩いや賑わいを創出するため、「パークレット」を設置する社会実験を行った。「パークレット」とは、路上の駐車スペースと歩道の一部を一体として、憩いの空間をつくろうとする取組みである。神戸市のパークレット(KOBEパークレット)では、ベンチ以外にも、花壇、カウンターテーブル、小さな子供が遊べる人工芝(ミニプレイグラウンド)まで設けるなど、歩行者に対して思いやりのある快適な空間がつくられた(図表I-3-2-25)。結果として、この取組みに対する利用者からの評価は高く、歩行者の数が増加した。
図表I-3-2-25 KOBEパークレット
また、長野県長野市は、中心地の道路である「長野中央通り」を歩行者にとって優しい空間とするため、車道の幅を減らし、歩道の幅を拡大するとともに、車道と歩道の段差をなくし、バス停留所などに休憩施設(ベンチ)を設置した。また、祭りなどにおいて道路空間を柔軟に活用できるように、車道と歩道を区分する分離柱(ポール)を取り外し可能なものにしている(図表I-3-2-26)。
図表I-3-2-26 長野中央通り
■地域の魅力を創出する「人中心の道路空間」づくり
公共空間の一つである道路において、地域の活性化や魅力・賑わい創出のため、これまでの通行機能に加えて、人々が集い、多様な活動を繰り広げる「人中心の道路空間」づくりに向けた取組みが進められている。
大阪府大阪市では、大阪のメインストリートである幅員44m延長約4.2kmに及ぶ御堂筋を将来的にフルモール注17化することで、これまでにない広大でシンボリックな空間が創出され、その空間を歩行者が安心して快適に楽しみながら回遊でき、かつ周辺地域が持つ歴史を活かすとともにシンボルとなるイチョウ並木と一体となったまちなみなど大阪らしさを感じてもらえる「みち」を目指している(図表I-3-2-27)。
図表I-3-2-27 御堂筋将来ビジョン
■公共空間における文化(アート)的価値のさらなる向上
東京都の上野公園には、多数の博物館、美術館等の文化施設が集積しており、我が国有数の魅力のある公共空間として賑わいを生み出している。このような中、2016年には、これらの施設の1つである国立西洋美術館注18が、「ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献―」(7か国17資産)のひとつとして、世界文化遺産に登録された(図表I-3-2-28)。ル・コルビュジエが日本に残した唯一の建築作品であり、また、提唱していた近代建築の思想を体現していることなどが評価されたためである。このことにより、上野公園の文化(アート)的価値はますます高まっている。公共空間において、文化(アート)をさらに取り込んでいくことに加え、既存の文化(アート)をさらに高めていくことも求められている。
図表I-3-2-28 国立西洋美術館
■文化財とその周辺が一体となった連続性のある空間づくり
文化財だけではなく、その周辺の建築物や道路なども一体となった、連続性のあるまちづくりが、日本人の感性(美意識)をさらに反映したものとして、豊かな生活空間につながっていく。岡山県倉敷市の「倉敷美観地区」には、1930年(昭和5年)に設立された日本初の西洋美術中心の私立美術館である大原美術館をはじめ、伝統的な建築物が多く残っている。地区が全体として保全されていることから、建築物だけでなく、路地(道)、道標、樹木なども一体として連続性のある空間をつくりだし、魅力あるまちとなっている(図表I-3-2-29)。
図表I-3-2-29 大原美術館とその周辺
■訪日外国人観光客増加による伝統や文化の維持・活用
昨今の訪日外国人観光客の増加をきっかけとして、各地で伝統や文化の維持・活用が行われている。長野県山ノ内町は、古い温泉地として知られる湯田中温泉(ゆだなかおんせん)や志賀高原などの観光資源を有するものの、1990年をピークに2014年には観光客数が53%減少していた。その後、「地獄谷野猿公苑(じごくだにやえんこうえん)」のニホンザルが雪景色の中で温泉に入る姿が「スノーモンキー」として海外から注目されるようになり、外国人観光客が訪れるようになった。このような中、廃業していた老舗旅館や店舗を建物の外観を維持しつつ、昔の面影を感じる内装にリノベーションするとともに、発酵食品など地域の文化を踏まえた飲食を提供するなど、外国人観光客の滞在環境を整備した(図表I-3-2-30)。
図表I-3-2-30 長野県山ノ内町の再開された旅館と店舗
その結果、外国人の宿泊者数が倍増するとともに、新たな飲食店や宿ができるなど好循環が生まれ、伝統ある温泉地に賑わいが戻りつつある。
■四季を感じる景観の維持・活用による地域づくりの推進
NPO法人「日本で最も美しい村」連合に加盟している北海道滝川市江部乙町(えべおつちょう)は、滝川市の中心地より離れた地域であるが、「日本有数の作付面積を誇る菜の花畑」や「防風林に囲まれたりんご畑」といった生活の営みなどから生まれた景観があり、これを観光などの地域の振興につなげている。この景観を守るため、地元小中学校による清掃や地元関係者による「道の駅たきかわ大収穫祭」の開催など地域が一体となった活動が行われている(図表I-3-2-31)。
図表I-3-2-31 「日本有数の菜の花畑」と「防風林に囲まれたりんご畑」
■公共空間をより身近に感じられる仕組みづくり
公共空間に、個人の記憶や名前を刻むことにより、その空間に愛着を感じてもらう取組みが進められている。東京都により行われている「思い出ベンチ事業」は、個人から、公園や動物園などの都の施設に設置するベンチの費用を寄付してもらうかわりに、そのベンチにその人の名前やメッセージを刻んだプレートを取り付けるというものである。2003年度から始まったこの事業により、すでに1,000基以上のベンチが設置されている(図表I-3-2-32)。寄付により費用が削減される一方で、その人の思い出を見える形で残すことができ、公園などの公共空間に対する愛着を生み出していると考えられる。
図表I-3-2-32 思い出ベンチ
(新技術と一体となった新たな取組み)
■利用者のニーズを反映して多様な使い方が可能となる公園
公園などの公共空間において、新技術等の活用により、利用者のニーズをきめ細やかに把握するとともに、それらに併せた柔軟な利用を可能とする取組みが進められている。
2018年、東京ミッドタウンからはじまった「PARK PACK」というプロジェクトでは、移動が可能なコンテナを公園内に設置しており、このコンテナには利用者のニーズに応じて変更する、様々な装置や道具が納められている。利用者のニーズについては、IoTを利用して、年齢、性別、人流データ等を分析することによって把握し、それらに応じて、コンテナの道具やスペースを活用しながら、公園を昼は展示場(ギャラリー)やピクニック会場、夜は映画館などに変えている(図表I-3-2-34)。
図表I-3-2-34 PARK PACK by ULTRA PUBLIC PROJECT
■個人の感性(美意識)を反映できる公共空間
新技術の活用等により、個人の感性(美意識)を反映できる公共空間が生まれつつある。
チームラボとチームラボアーキテクツは、深圳中洲集団有限公司と共同で2018年4月から、中国・深圳における総合施設「C Future City」において、「Personalized City」注19をコンセプトに都市開発プロジェクトを進めている。総延床面積300万m2のこのエリアは商業施設・オフィス・ホテル・住居から構成される予定であり、そのシンボルとして、アートでもあり建築でもある広場「Crystal Forest Square(計画中)」を建設する。「Crystal Forest Square(計画中)」には、光の点が無数に集合体として映し出されたクリスタルツリーが多数配置されている。広場全体では巨大な立体物であるが、クリスタル単体では個人のスマートフォンと連動しその動きによって色を変えるなどパーソナライズでインタラクティブな体験のできるものとなっているなど、各人に応じた個性的な空間を作り出すことが計画されている(図表I-3-2-35)。
図表I-3-2-35 Crystal Forest Square(計画中)イメージ
(3)「移動空間」について
(現在の「移動空間」の状況について)
我が国では、高度経済成長期以降、高速道路、新幹線等の整備が着実に進み、その発展に大きく貢献してきた。経済成長が重視され、全国的な人口の増加、東京など大都市への人口集中を背景に、大量の人や物をできるだけ早く時間どおりに運ぶという、輸送力の増強や速達性・定時性の向上などが特に重視されてきた。また、公共交通が十分でない地域等をはじめとして、車が広く普及し、急速なモータリゼーションが進んでいった。
しかし、2008年(平成20年)をピークに、人口減少が始まる一方で、都市への人口集中は継続していたことなどから、特に、地方の公共交通への影響は大きく、その衰退が進んできた。さらに、地方では、高齢化が進み、これまでのように自家用車を運転できる状況ではなくなりつつある。このような中、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の制度をはじめとして、様々な対策がなされてきている。
また、リタイアした高齢者の増加や観光の振興などにより、移動空間を楽しみながら過ごすというニーズが高まっている。2013年のJR九州(九州旅客鉄道(株))の「ななつ星 in 九州」の運行開始以降、多種多様な観光列車が生まれ、各地で運行されている。このような取組みは地方の活性化にもつながってきており、さらに広がっていくことが期待される。
(今後の「移動空間」に対する国民の意識)
未来の生活を豊かなものとするために、どのような移動手段が魅力的だと思うかについて、前述の国民意識調査により尋ねたところ、「高齢者や地域に優しい自動運転車」、「移動時間を有効活用できる自動運転車・列車」について、「とてもそう思う」と「ややそう思う」があわせては約8割となり、「景観に配慮した車・列車」は、約7割となった(図表I-3-2-36)。全体として、自動運転の役割に期待していること、移動空間に移動だけではない新しい価値を期待していること、また、移動空間(移動手段)にも景観との調和が必要であると考えていることなどが推察される。
図表I-3-2-36 魅力的な未来の移動手段
また、年代別の特徴として、20代において、「自分の好みや用途で変えられる自動運転車」について、「とてもそう思う。」と回答した人が多く(図表I-3-2-37)、個人の感性(美意識)を大切にしたい傾向が見られた。また、50代、60代において、「高齢者や地域に優しい自動運転車」について肯定的な人が多く(図表I-3-2-38)、自動運転が将来的に、生活の足やその他の移動の支援となることへの期待が表れていると推察される。
図表I-3-2-37 「自分の好みや用途で変えられる自動運転車」へのニーズ(年代別)
図表I-3-2-38 「高齢者や地域に優しい自動運転車」へのニーズ(年代別)
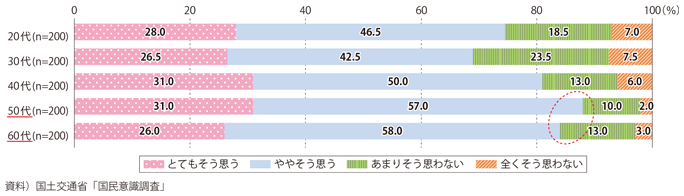
(今後の「移動空間」の方向性について)
以上を踏まえると、日本人の感性(美意識)を活かした「移動空間」を創出するためには、前述のとおり、自然との調和、義理がたさといった日本人が昔から持つ感性(美意識)を移動空間に取り込んでいくことが必要であると考えられる。例えば、まちなど周辺の風景と調和した移動空間(移動体)をさらに増やしていくこと、日本人の伝統や文化を取り入れた移動空間をつくっていくことなどが挙げられる。
また、自分の感性(美意識)を感じられる環境を創出することも重要であり、移動空間を単なる「移動」だけにとどまらず、移動空間内そのものを楽しめる環境にすることなどにより、私的空間の延長のようにしていくことが必要であると考えられる。
特に、移動空間については、「自動運転」という新技術の進展により、大きく環境が変わっていくことが想定される。ドライバーが運転から解放されることにより、車内はその感性(美意識)を自由に取り込める、自宅でも職場でもない「第三の空間」となり、今後はこの移動空間をいかに充実させるかが重要である。このような流れを受け、官民いずれにおいても既に様々な検討がなされ始めている。
さらに、新技術の発展は、より利用者のニーズを踏まえた、柔軟な移動空間(移動手段)の創出につながっていくことが想定される。自動運転技術の進展等により、無人走行が可能となるだけでなく、移動体そのもののサイズや用途も大きく変えることができる。このことにより、地方交通の衰退といった課題に対応するような、ひとに優しいモビリティなどが生まれてくることも期待される。
以下では、このような方向性を具体化する現在の取組みについて、これまでの取組みを更に進めたものを「これまでの取組みの深化」、新技術を活用した新たなものを「新技術と一体となった新たな取組み」と分類し、それぞれ紹介する。
(これまでの取組みの深化)
■地域の特色を取り込んだ車体の増加
公共交通機関は、頻繁にその地域を移動することが多いため、その地域の景観の一つとなっている。このような中、伊予鉄グループでは、電車、バス、新型車両LRTの車体を愛媛県の特産品である「みかん」の色にちなみ、オレンジ色に統一することによって、地域の特色を車体に表現しようとしている(図表I-3-2-39)。その中でも、新型車両LRTは、デジタルサイネージの導入により中吊り広告をなくすことや、通路の幅を広げることなどにより広々とした車内空間を実現するとともに、バリアフリーが進んでいるなど快適さや安全性も追及している。
図表I-3-2-39 いよてつ新型車両LRT
■移動空間の魅力の向上
これまでとは異なる「移動空間」をつくり出すことにより、移動時間を更に充実させる取組みが進んでいる。
釜石線花巻駅から釜石駅を走る東日本旅客鉄道(株)の「SL銀河」は、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の世界観を列車全体で表現している。「SL銀河」は、ガス灯風の照明やステンドグラスにより宮沢賢治が生きた大正から昭和初期を感じる車内空間となっている。さらに、宮沢賢治に関するギャラリーコーナーに加え、列車では非常に珍しい例であるプラネタリウムまで有しており、移動空間の多様化を進めようとしている(図表I-3-2-40)。
図表I-3-2-40 SL銀河
■日本人の感性(美意識)を取り入れた空間の様々な交通モードへの拡大
日本人の感性(美意識)を取り入れた移動空間が鉄道のみならず、様々な交通モードへ拡大をしている。
クラブツーリズム(株)が新たに運行する豪華観光バスは、寺院などで見られる「格天井」(ごうてんじょう)をバスの車内の天井全体に初めて採用し、また、ひじ掛け、床や壁に木材を使い、全体的に木のぬくもりが感じられる車内となっている。さらに、バス後方には、挽き立てコーヒーなどを用意するためのバーカウンターが設置されているなど、懐かしさと新しさを兼ね備えたバスとしてデザインされている(図表I-3-2-41)。
図表I-3-2-41 CLUB TOURISM FIRST
■ひとと環境に優しい新たなモビリティの普及を促進
ひとと環境に優しい、新たなモビリティ(移動体)を開発・普及する動きが生まれている。「グリーンスローモビリティ」は、時速20km未満で公道を走る、4人乗り以上のパブリックモビリティを言い、高齢化が進む地域等の交通手段などとして期待されている。
石川県輪島市においては、商工会議所が中心となり、ゴルフカートタイプの車両(WA-MO)が、市内の病院や公共施設、観光スポットなどを運行する事業を行っている。将来は、地域を支える足としての役割を担うことを目指している(図表I-3-2-42)。
また、東京都豊島区においては、2019年からデザイン性に富んだ電動低速バスタイプの車両が、池袋駅周辺の公園や観光スポットを回遊する。観光客や高齢者等にやさしいだけでなく、地域を象徴するモビリティになることも期待される(図表I-3-2-42)。
図表I-3-2-42 電動小型低速車「WA-MO」、電動低速バス
(新技術と一体となった新たな取組み)
■歩行者など周囲の人々に優しい新たなモビリティの開発
新規技術と一体になった、歩行者など周囲の人々に優しい新たなモビリティを開発する動きが始まっている。
メルセデス・ベンツが描く未来の自動運転車は、道を渡ろうとしている歩行者について、自車だけではなく他の車両の有無により、その安全性を判断する。その上で、安全であれば、前方のライトを使って、歩行者の前に横断歩道を映し出し、「お先にどうぞ」と音声で案内をする。さらに、車両後部にも「停止」と表示し、後方の車や人に対して、自車が停まっていることを知らせる。このような表示や音声など周囲の人々とのきめ細やかなコミュニケーションにより安全性を高めることをはじめ、車内のみならず、車外の人々に対しても優しい自動運転車を目指している(図表I-3-2-43)。
図表I-3-2-43 自動運転車「F 015 ラグジュアリー イン モーション」
■利用者のニーズ等を反映した内装に変更が可能な車
従来の車では難しかった、利用者のニーズ等によって、内装などを変えることのできる新たなモビリティについての議論が進んでいる。
トヨタ自動車(株)では、自動運転技術を活用した次世代の電気自動車「e-Palette Concept」を発表した。このコンセプトでは、車について、これまでの移動するための手段としてだけではなく、移動時間をより有効に活用できるように、用途に応じて、設備、内装等を変更した車体を搭載する、新しい「モビリティ」としてとらえている。そのシミュレーションでは、この車両が荷物配送などからモバイルオフィス、イベントでのピザ販売まで自動運転で行うことが示されており、本格的な実用化が目指されている(図表I-3-2-44)。
図表I-3-2-44 e-Palette Concept
■運転からの解放と車内空間の活用
完全自動運転が実現することによりドライバーは運転から解放されるとともに、移動時間の価値を大きく変え、感性(美意識)を自由に取り込める、自宅でも職場でもない「第三の空間」となる。このような状況をイメージした未来の車が生まれつつある。
パナソニック(株)が2018年に発表した完全自動運転車は、光・映像・音・空気など、五感に働きかける技術を用いた空間デザインに取り組んでいる。例えば、窓や天井は、透明ディスプレイとなって、様々な映像を映し出すとともに音や照明が変化する。このように車内をコンサートホールに変えたり、オフィスに変えることもでき、新しい移動空間を提供している(図表I-3-2-45)。
図表I-3-2-45 SPACe_L
注15 引戸・障子・ふすまなどをはめる部分の上部に渡した溝のついた横木。
注16 Do It Yourselfの略。自分自身で何かを造ったり、修理したり、装飾したりする活動のこと。
注17 歩行者に特化した道路空間
注18 国立西洋美術館(URL:
http://www.nmwa.go.jp/)
注19 デジタルテクノロジーとアートによって、都市の公共性を保ちつつ個人に合わせて変容(パーソナライズ化)する新しい都市のコンセプトである。