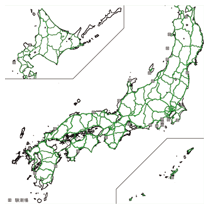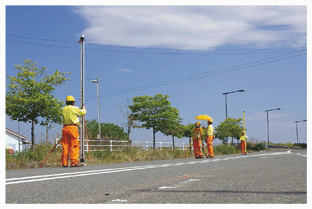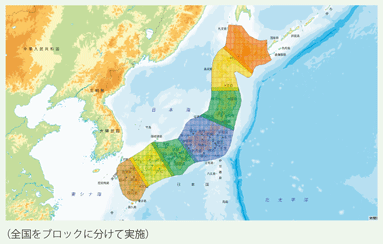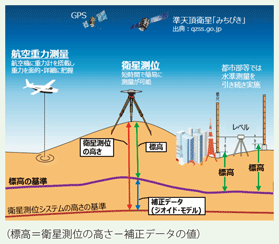コラム 航空重力測量で標高の仕組みを大転換!
江戸時代、現在の東京都羽村市から新宿区四谷に引かれた玉川上水は、約43kmの距離を標高差が約92mしかないという勾配(10mで標高差が2cm)で通されました注。このように水は、わずかでも「標高が高い場所から低い場所」へ重力に従って流れます。
我が国の標高は、東京湾の平均海面を基準としており、明治以来、国土地理院が実施する水準測量によって、全国の主要な国道沿いに約2km毎に設置された水準点の標高を決定することで維持管理されてきました。しかし、水準測量は高精度な一方で多くの時間と費用を必要とするため、全国の測量に10年以上かかるほか、地震等の後の復旧・復興に必要となる標高の改定に一定の時間がかかるという課題がありました。
図1 水準測量を実施する路線
図2 水準測量(4人一組で歩きながら行う)
こうした課題を克服するため、国土地理院では、水準測量に加えてGPSや準天頂衛星などの衛星測位システム(GNSS)も活用して標高を決定するための環境整備に向けた取組みを平成30年度より開始しました。その鍵となるのが『航空重力測量』です。GNSSで標高を決めるためには、水の流れに関わる重力を考慮した補正をしなければなりません。航空重力測量では、航空機に搭載した重力計を用いて、全国の均一な重力データを4年かけて測定し、GNSSを用いて標高を決定するための補正データ(ジオイド・モデル)を整備します。この補正データがあれば、いつでも、どこでも、誰でもすぐに位置が求まるGNSSの特長を活かした標高決定が可能となり、災害時の迅速な復旧・復興に貢献する測量作業の効率化や、自動走行あるいはドローン宅配といった標高を含む高精度な3次元位置情報を利用した新たなサービスの創出等にも繋がるものと期待されます。なお、上空視界が狭くGNSSが使えない地域や、高精度な標高を必要とする用途では引き続き水準測量を活用します。この新たな仕組みは、令和6年度までの導入を目指しています。
図3 航空重力測量の実施地域
図4 GNSSを用いた標高決定の仕組み