国土交通白書 2020
第1節 我が国を取り巻く環境変化
(1)災害を受けやすい国土
(洪水・土砂災害が発生しやすい国土)
我が国の国土は、地形、地質、気象等の面で極めて厳しい条件下にある。全国土の約7割を山地・丘陵地が占めており、世界の主要河川と比べ、標高に対し河口からの距離が短く、急勾配であり、降った雨は山から海へと一気に流下する(図表I-1-1-37)。このような国土条件において、梅雨や台風により大雨が降ることで、洪水や土砂災害がたびたび発生している。
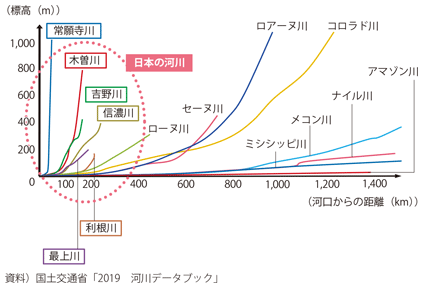
(地震・火山活動が多い国土)
我が国は、地震、火山活動が活発な環太平洋変動帯に位置している。国土面積は世界の0.25%という大きさながら、地震の発生回数は、世界の18.5%注19と極めて高い割合を占めている(図表I-1-1-38左図)。また、世界には約1,500の活火山があると言われているが、我が国にはその約1割が集まり、日本は世界有数の火山国となっている(図表I-1-1-38右図)。
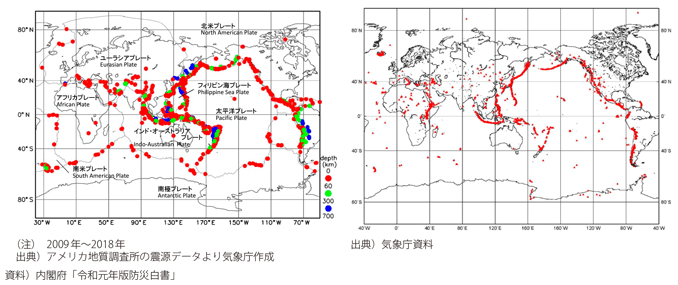
(2)地球温暖化
(地球温暖化の現状)
2015年(平成27年)12月、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)注20の第5次評価報告書注21が公表された。同報告書によると、気候システムの温暖化には疑う余地がないことが記載されている。また、IPCCの過去5度の評価報告書における評価の変遷を見ると、温暖化は我々人間の活動による影響に起因していることが、次第に明確になっている(図表I-1-1-39)。
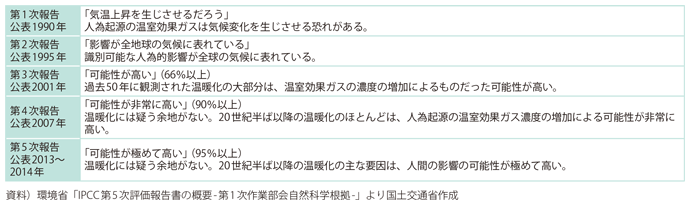
さらに、気象庁によると、世界の年平均気温は19世紀後半以降100年当たり0.74℃の割合で上昇注22しているのに対し、日本の年平均気温については100年当たり1.24℃と、世界平均を上回るペースで気温が上昇注23している(図表I-1-1-40)。
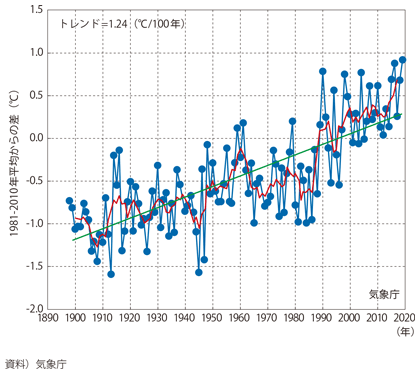
(大雨や短時間強雨の発生推移)
我が国では、洪水や土砂災害を引き起こす大雨や短時間強雨の回数が増加している。大雨について、日降水量が200mm以上となる年間の日数を「1901年から1930年」と「1990年から2019年」で比較すると、直近の30年間は約1.7倍の日数となっており、長期的に増加している(図表I-1-1-41左図)。また短時間強雨注24について、1時間降水量が50mm以上となる年間の回数を「1976年から1985年」と「2010年から2019年」で比較すると、直近の10年間は約1.4倍の発生回数となっており、同様に長期的に増加している(図表I-1-1-41右図)。
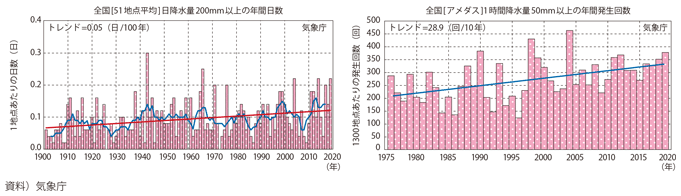
(土砂災害の発生状況)
雨の降り方に関連して、土砂災害の発生回数も近年増加傾向にある。2018年(平成30年)は過去最多の3,459件、2019年も1,996件と非常に多くの土砂災害が発生している(図表I-1-1-42)。
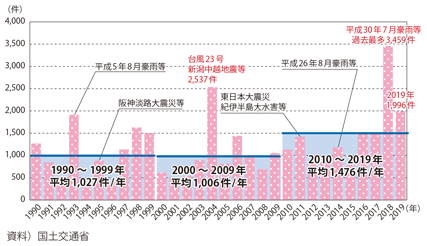
(3)毎年発生する自然災害
(自然災害の発生状況)
2000年(平成12年)以降の自然災害を見ると、2004年の台風被害注25や、東日本大震災等の地震災害、令和元年房総半島台風や令和元年東日本台風に伴う洪水・土砂災害等、毎年、多くの自然災害が発生してきた(図表I-1-1-43)。自然災害による死亡者数・行方不明者数についても、東日本大震災をはじめとして、甚大な被害をもたらしている(図表I-1-1-44)。
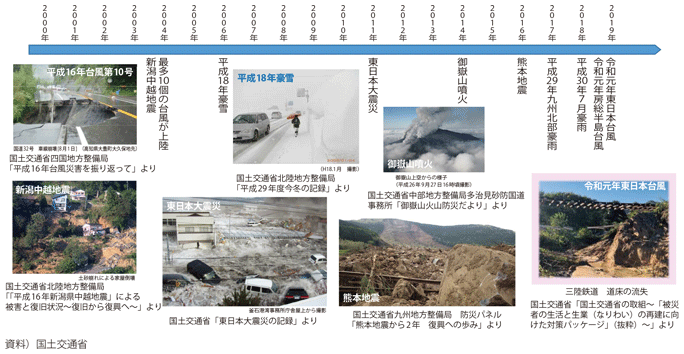
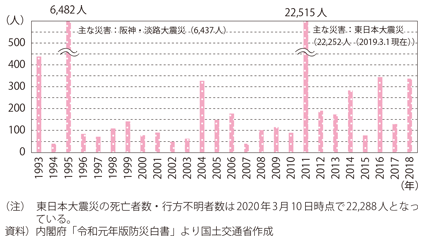
(高齢者の被災)
自然災害では高齢者の被災が多い。東日本大震災では、多くの高齢者が津波から逃げ遅れ、岩手県、宮城県、福島県での死亡者数(2012年8月31日時点)は60歳以上が66%を占めた(図表I-1-1-45)。平成30年7月豪雨においても、被害が大きかった愛媛県、岡山県、広島県の死亡者数は60代以上が約7割を占め、特に、岡山県倉敷市真備地区での死亡者数は、70代以上が約8割を占めた注26。
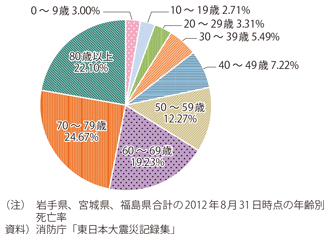
- 注19 2004年~2013年の世界のマグニチュード6以上の地震の発生回数1,629回のうち、日本は302回(18.5%)。出典)内閣府「令和元年版防災白書」より
- 注20 人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織
- 注21 第5次報告書:IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書。気候システムや気候変化について評価を行ったもの。2013年に公表され、IPCC正誤表更新分も含め2015年12月に日本語訳の最終版が公表された。
- 注22 世界の年平均気温偏差の経年変化(1891~2019年)(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html)
- 注23 日本の年平均気温偏差の経年変化(1898~2019年)(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html)
- 注24 気象庁の予報用語では1時間降雨量(mm)について、5段階に分けて雨の強さを表している。80mm以上は、「猛烈な雨」、50~80mmは「非常に激しい雨」、30~50mmは「激しい雨」、20~30mmは「強い雨」、10~20mmは「やや強い雨」となっており、「非常に激しい雨」では、「滝のようにゴーゴー降り続く」、「傘が全く役に立たない」「水しぶきで一面が白っぽくなり、視界が悪くなる」、「車の運転は危険」としている。
- 注25 2004年にはこれまで最多の10個の台風が上陸し、日本各地で多くの洪水・土砂災害を引き起こした。
- 注26 内閣府「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難の在り方について」