国土交通白書 2020
特集 新型コロナウイルス感染症への対応
(1)対策本部の設置
2020年1月30日、中国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、感染が拡大している状況に鑑み、政府として対策を総合的かつ強力に推進するため、「新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下、「政府対策本部」という。)を設置した。さらに、検疫法や感染症法に基づく「検疫感染症」、「指定感染症」に指定し、患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供を行えるようにした。
国土交通省においても、政府対策本部の設置を踏まえ、同日に「国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、省を挙げて、武漢市からの退避オペレーション、水際対策、国内感染防止対策等に取り組んできた。
(2)中国湖北省武漢市からの邦人退避オペレーション
政府は、世界で最初の感染者が発見された中国湖北省武漢市等において2020年1月23日より封鎖措置がとられたことを受け、中国湖北省武漢市等に在留する邦人等を退避させる必要が生じ、5回にわたるチャーター便により828人を帰国させた(第1便:1/29着・乗客206人、第2便:1/30着・乗客210人、第3便:1/31着・乗客149人、第4便:2/7着・乗客198人、第5便2/17着・乗客65人)。チャーター便の乗客は、到着後、医療機関における診察及びPCR検査や、一時滞在施設での健康観察を受けた。
国土交通省においては、チャーター機の運航のための特別動線等の確保や、帰国後の医療機関や一時滞在施設までの移動手段の手配、一時滞在施設の確保等への協力や、移動中の高速道路におけるトイレ休憩施設の確保を行った。
(3)ダイヤモンド・プリンセス号における感染者発生対応
大型客船ダイヤモンド・プリンセス号(船籍:英国、船社:プリンセスクルーズ(米国)、総トン数:115,906 トン、全長:290m、乗客:2,666名、乗員:1,045名)は、2020年1月20日に横浜港を出発。その後、鹿児島、香港、ベトナム、台湾、那覇を経由し、2月4日に横浜港へ帰港する予定だった。
しかし、香港から来日し1月20日に横浜で乗船した男性が、1月22日に鹿児島でオプショナルツアーに参加し、1月25日に香港で下船後、2月1日に新型コロナウイルスの陽性反応が確認された。その間、同船はベトナム、台湾、那覇に寄港し、2月3日に横浜港内の錨地に到着し、その後、同船内において新型コロナウイルスの集団感染が発生する事態へと繋がった。
集団感染が発生していた同船への対応にあたり、国土交通省では、船内の状況を正確に把握するための情報収集や、船内への職員派遣、運航会社との間の連絡調整のための同船運航会社の日本支店への職員派遣、同船を停泊させる錨地の確保や横浜港での着岸に関する港湾管理者(横浜市)等の関係機関との調整、海上保安庁巡視船艇による検体及び陽性が確認された乗客等の搬送や周辺海域の巡回、外国人の帰国や乗客の医療センター等への移送の際の円滑な通行のための高速道路におけるトイレ休憩施設の確保や無料化措置による支援、帰国チャーター便受入れのための関係機関との調整や発着枠・駐機場の確保、などの対応を行った。
また、PCR検査で陰性が確認された乗員・乗客が順次下船する際には、運航会社や厚生労働省等の関係機関と連携の上、下船後の移動手段の確保や、外国人の乗客・乗員の帰国のためのチャーター便の受入れ、発着枠・駐機場の確保等に係る関係機関との調整等を行い、同年3月1日には、乗員・乗客約3,700人全員の下船が完了した。
(4)水際対策の強化
2020年1月31日の閣議了解を踏まえ、一部の地域に滞在歴がある外国人等に対して、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づく入国拒否措置がとられた。その後、感染拡大に伴って、入国拒否の対象国・地域が順次拡大された。5月末時点で、111の国と地域が入国拒否の対象となっている。
また、検疫の適切な実施による水際対策の強化のため、3月6日には、閣議了解により、中国または韓国から来港する航空機又は船舶に搭乗していた者に、指定場所で14日間待機し公共交通機関を使用しないこと(以下、「待機等」という。)を要請することとした。その後順次、待機等の対象となる国等を拡大し、4月1日には、第25回政府対策本部決定により、過去14日以内に入国拒否の対象国等に滞在歴のある邦人又は特段の事情のある外国人入国者をPCR検査の実施対象とするとともに、待機等の対象を全ての国等に拡大した。
国土交通省としても、関係府省庁や所管業界と連携し、国内への感染者流入を最小限に抑えるための対策を講じた。主な対応としては、随時、航空会社・空港関係者や外航旅客船事業者等に、機内や船内におけるアナウンスや健康カードの配布、入国拒否措置等の旅客への周知やパスポートの確認、CIQ注3官庁との連携等を求めている。また、3月6日には、中国及び韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限るよう要請し、4月1日には、検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請した。また、邦人入国者の待機先への移送の際の円滑な通行のための高速道路におけるトイレ休憩施設の確保や無料化措置による支援を行うとともに、検査結果が出るまで待機していただくための宿泊施設及び移動手段の確保等について、厚生労働省等と連携して対応した。
(5)国内における感染拡大防止対策
国内における感染拡大防止のため、政府は、2020年2月13日に検疫法上の隔離措置等を可能とする措置を講ずるほか、無症状病原体保有者を入院措置・公費負担等の対象とする政令改正を行った。また、イベントの開催に関し、2月26日に政府対策本部において、中止、延期または規模縮小等の対応を要請し、翌27日の第15回政府対策本部において、総理より、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、春休みに入るまで、臨時休業を行うよう要請した。
国土交通省としては、1)鉄道、空港、フェリー・旅客船ターミナル、道の駅、高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)、国営公園等において、従業員に対する感染予防策(マスク着用、手洗い励行等)の徹底、従業員等が感染した場合の速やかな報告の要請、2)上記公共交通機関や施設における利用者に対する感染予防策の周知と消毒液の設置、3)日本政府観光局(JNTO)のコールセンターにおいて、医療機関の紹介や水際対策の状況等の問合せに対し、正確な情報提供を24時間365日多言語で実施、4)公共交通機関の混雑緩和のため、時差出勤・テレワークの実施や感染予防策の徹底を呼びかけるアナウンスの実施、5)広域的な人の移動を最小化するため、ゴールデンウィークに向けて、全国の主要空港、鉄道駅、道路交通情報センター、道路情報板、「道の駅」及び高速道路のSA・PA等において、都道府県をまたぐ移動の自粛の呼びかけ、同期間中の地方部に適用される高速道路料金の休日割引の適用除外、高速道路のSA・PAのレストラン等の営業自粛の要請、6)羽田空港等6空港でのサーモグラフィーによる検温の実施や鉄道の到着駅における地方自治体による検温の取組みへの協力等の対応を行った。
全国の高速道路の交通量の調査注4によると、3月以降、交通量の前年比に減少がみられていたが、4月7日に緊急事態宣言が発出され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき外出の自粛について協力要請がなされて以降、特にゴールデンウィーク期間の4/25(土)~5/6(水)では、対前年比で約3割、特に小型車は約2割と大きく減少した(図表1-1-4)。鉄道においても、4月24日~5月6日におけるJR各社の新幹線の利用状況は対前年比5%程度、航空(4月28日時点)では、4月29日~5月6日の間の前年比の予約状況について、国内線は7%、国際線は2%程度であった。
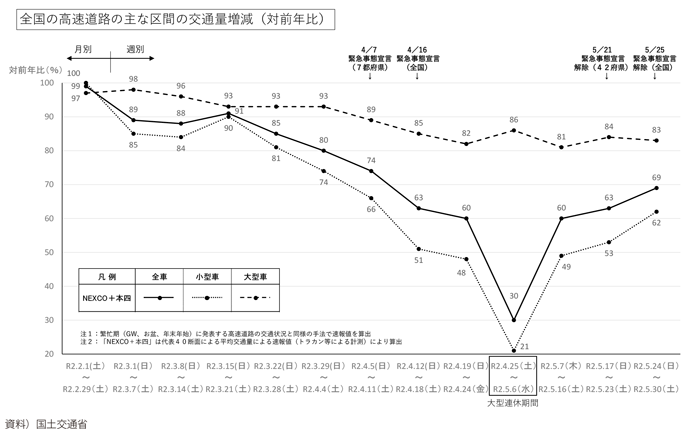
さらに、5月4日の改訂後の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、引き続き移動自粛が求められ、特に、都道府県をまたぐ人の移動については、全国的に自粛を促す必要があるとされたことを踏まえ、ゴールデンウィーク期間後も、空港や鉄道駅、道路交通情報センター、道路情報板、「道の駅」及び高速道路のSA・PA等における広域的な移動自粛の呼びかけや、地方部に適用される高速道路料金の休日割引の適用除外やSA・PAのレストラン等の土日の営業自粛の要請、主要空港におけるサーモグラフィーによる体温測定等の対応を継続した。
また、同改訂により、事業者及び関係団体によって自主的な感染拡大防止のための取組みを進めるため、感染拡大予防ガイドラインを作成することとされたことを受け、国土交通省所管の分野においては、5月末時点で、公共交通関係をはじめ、47の関係団体が37のガイドラインを作成し、公表している注5。
(6)影響を受ける産業等への対応
2020年2月13日に開催された第8回政府対策本部において、国民の命と健康を守ることを最優先に、当面緊急に措置すべき対応策として、雇用調整助成金の要件緩和や、日本政策金融公庫等における5,000億円の緊急貸付・保証枠の確保等を盛り込んだ「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(以下、「緊急対応策第1弾」という。)をとりまとめた。さらに、3月10日に開催された第19回政府対策本部において、1)雇用調整助成金の特例措置の拡大、2)中小・小規模事業者等への実質的無利子・無担保の資金繰り支援、3)魅力的な滞在コンテンツの造成、多言語表示やバリアフリー化等の受入環境の整備、観光地の誘客先の多角化等の支援等を内容とする「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(以下、「緊急対応策第2弾」という。)を決定した。
また、これらの緊急対応策に続いて、4月20日に過去最大となる事業規模117兆円(GDPの約2割)の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(以下、「緊急経済対策」という。)を閣議決定した。この緊急経済対策においては、1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、2)雇用の維持と事業の継続、3)次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、4)強靱な経済構造の構築、5)今後の備え、の柱立ての下に各種の施策を講じることとした(図表1-1-5)。また、これに基づき、4月30日に令和2年度補正予算(第1号)が成立した。
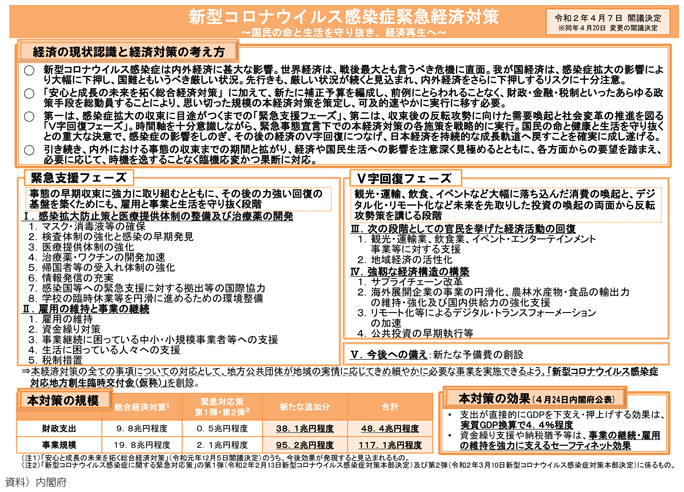
さらに、5月27日には、令和2年度補正予算(第2号)の案を閣議決定した。この補正予算案は、国費約32兆円で、令和2年度補正予算(第1号)と併せ、事業規模は230兆円を超えるものとなった。この補正予算においては、1)雇用調整助成金の助成額上限の引上げ、2)家賃支援給付金(仮称)の創設、3)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充、4)地域公共交通の感染防止対策補助金(仮称)の創設等の対策を講じることとした。
(7)緊急事態宣言
2020年3月13日には「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され、新型コロナウイルス感染症についても同法の対象となり、3月26日、新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣総理大臣に報告され、同法第15条第1項に基づき政府対策本部が設置された。そして、3月28日の第24回政府対策本部において、同法第18条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていくため今後講じるべき対策を示した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下、「基本的対処方針」という。)を策定した。その後、4月7日の第27回政府対策本部では、肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあること、また、感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある状況であることを踏まえ、同法第32条第1項に基づき、4月7日から5月6日までの間、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象区域として緊急事態宣言を行った。これにより、都道府県知事が不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限の要請等の緊急事態措置を講じることが可能となった。また、基本的対処方針により、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者においては、緊急事態宣言時においても、事業の継続を図ることが求められた。国土交通分野においては、鉄道、バス、航空等の公共交通分野、トラック、海運等の物流分野、河川・道路の管理や公共工事等の安全安心に必要な社会基盤分野等の事業者が、新型コロナウイルス感染症が拡大する環境の中にあっても、その機能維持のため、職務に従事してきた。
4月16日の第29回政府対策本部では、都市部からの人の移動等により感染拡大の傾向が見られることから、緊急事態措置を実施すべき区域を全国に拡大するとともに、上記7都府県に北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府を加えた13都道府県を特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組みを進めていく必要がある特定警戒都道府県に指定した。
緊急事態措置を実施すべき期間は、当初、5月6日までとされていたが、5月4日に感染状況の変化等について分析・評価を行ったところ、一定の成果が現れ始めているものの、引き続き医療提供体制が逼迫している地域も見られ、当面、現在の取組みを継続する必要があったことから、同日の第33回政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき期間を、5月31日まで延長することと決定した。
その後、全国的に新規報告数の減少や医療供給体制の逼迫の状況等の改善が見られ、5月14日、第34回政府対策本部において、各区域について、感染の状況(疫学的状況)、医療提供体制、監視体制等を踏まえて総合的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の8都道府県を除く39県について、緊急事態を解除することを決定した。そして、残る8都道府県についても、感染の状況、医療提供体制、監視体制の3つの区域の判断の考え方に照らし、5月21日の第35回政府対策本部において、京都府、大阪府及び兵庫県について、5月25日の第36回政府対策本部において、関東の1都3県及び北海道について、緊急事態解除宣言が行われた。
- 注3 税関(Customs)、出入国管理(Immigration)、検疫所(Quarantine)の略で、貿易上必要な手続き・施設のこと
- 注4 東日本高速、中日本高速、西日本高速、本四高速の4社の高速道路に代表40断面を設定し、日平均交通量を計測することにより調査した。
- 注5 国土交通省所管分野では、下水道、高速道路等のインフラ運営、宿泊等の生活必需サービス、鉄道、バス、海運等の交通、物流等の業種でガイドラインを策定している。ガイドラインの内容は、例えば、宿泊業では、チェックイン時では間隔を空けた待ち位置を表示すること、客室では一定時間ごとに窓を開けて換気をすることなどの対策が定められている。また、バス事業では、従業員の事業所等でのマスク着用や距離の確保の徹底や、利用者に対し、車内や待合所において会話を控えめにすること、他の利用者と距離を確保することを要請することなどの対策が定められている。