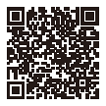国土交通白書 2023
第7節 海洋政策(海洋立国)の推進
(1) 領海及び排他的経済水域における海洋調査の推進及び海洋情報の一元化
我が国の領海及び排他的経済水域には、調査データの不足している海域が存在しており、海上保安庁では、この海域において、海底地形、地殻構造、底質及び低潮線等の海洋調査を重点的に実施し、船舶交通の安全や我が国の海洋権益の確保、海洋開発等に資する基礎情報の整備を戦略的かつ継続的に実施している。
また、海洋情報の所在を一元的に収集・管理・提供する「海洋情報クリアリングハウス」を運用している。さらに、政府関係機関等が保有する様々な海洋情報を地図上に重ね合わせて表示できるウェブサービス「海洋状況表示システム(海しる)」を構築し、平成31年4月から運用を開始した。
(2)大陸棚の限界画定に向けた取組み
国連海洋法条約に基づき我が国が平成20年11月に国連の「大陸棚限界委員会」へ提出した200海里を超える大陸棚に関する情報について、24年4月、同委員会から我が国の国土面積の約8割に相当する大陸棚の延長を認める勧告を受領し、26年10月、四国海盆海域と沖大東海嶺南方海域が延長大陸棚として政令で定められた。一方、隣接する関係国との調整が必要な海域と同委員会からの勧告が先送りされた海域について、海上保安庁では、内閣府総合海洋政策推進事務局の総合調整の下、関係省庁と連携し、引き続き大陸棚の限界画定に向けた対応を行っている。
(3) 沖ノ鳥島の保全、低潮線の保全及び活動拠点の整備等
①沖ノ鳥島の保全・管理
沖ノ鳥島は、我が国最南端の領土であり、国土面積を上回る約40万km2の排他的経済水域の基礎となる極めて重要な島であることから、基礎データの観測・蓄積や護岸等の点検、補修等を行うほか、観測拠点施設の更新等を行い管理体制の強化を図っている。
②低潮線の保全
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(低潮線保全法)」等に基づき、排他的経済水域等の外縁を根拠付ける低潮線の保全が必要な海域として185の低潮線保全区域を政令で指定し、掘削等の行為規制を実施している。
また、防災ヘリコプターや船舶等による巡視や衛星画像等を用いた低潮線及びその周辺の状況の調査を行い、排他的経済水域及び大陸棚の基礎となる低潮線の保全を図るとともに、保全を確実かつ効率的に実施していくために、低潮線に関する各種情報を適切に管理している。
③ 特定離島(南鳥島・沖ノ鳥島)における活動拠点の整備・管理
「低潮線保全法」等に基づき、本土から遠隔の地にある南鳥島・沖ノ鳥島において、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動拠点として、船舶の係留、停泊、荷さばき等が可能となる港湾の施設の整備とともに、国による港湾の管理を実施している。