国土交通白書 2024
第2節 望ましい将来への展望
インタビュー 少子高齢化時代の地域公共交通のあり方
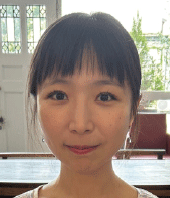
人口減少が加速していく中、地域の「足」を確保する上で、地域の公共交通の存続が鍵となる。地域経営、地域計画等がご専門で、国土交通省の審議会等委員であり、地域公共交通の課題解決に取り組んでおられる村上氏に、地域公共交通をどのように持続可能なものとすべきか、地域のまちづくりや公共交通のあり方について、お話を伺った。
●地域住民の負担と行政からの補助のバランスが重要
公共交通を維持していくために、重要なものが大きく二つある。一つは担い手の確保であり、もう一つは費用負担の問題である。これらを考慮し、地域交通を確保・維持していく仕組みづくりが重要である。
担い手の確保に関しては、各地域の状況によってできることが違うし、行政、事業者、住民それぞれの役割等でできることは違うため、役割等に応じた体制づくりが重要となる。担い手として、住民が主体となり、事業者と連携し、行政が強固なサポートをしていくことも必要である。
費用負担については、地域住民による負担のあり方について考えていく必要があり、運賃収入のほか、例えば、自家用有償旅客運送の場合、地区全体で支える「地区負担金」方式を採る地域もある一方で、行政からの補助にどのくらい頼れるかといったバランスの取れた費用負担スキームを構築していく必要がある。
●誰でも交通弱者になり得るため、路線バスへの支援が必要
「交通弱者」と一言で言われるが、様々な弱者のケースがあり、弱っていたり、困っていたりする度合いは異なる。例えば雪国(積雪寒冷地)の場合、夏は良いが冬だけ困る等、季節により弱者が生じることもある。困っている度合いやニーズにできる限り対応した対策を講じていく必要がある。
具体的には、事業者の努力により、路線バスを維持している地域であれば、それを補完する交通弱者支援策、輸送サービスの導入の可能性が考えられる。自家用有償旅客運送では、運行範囲を地域内に限定して、まちなかへ買い物に行く時は既存の路線バスに接続するケースもみられる。現在アドバイザーを務めている岩手県北上市においても、路線バスと連携した自家用有償旅客運送の取組みがあり、既存の交通機関を補完する対策が採られている。
路線バスやタクシーの事業者が撤退し、完全に公共交通空白地域になっている場合、新たな輸送サービスを別途検討する必要がある。
地方都市では、自分で車を運転ができなければ、移動や日常生活が困難になることが懸念されるため、高齢になっても、無理して運転し続けるという声も聞かれる。そのような交通弱者や、今後弱者になり得る人に対する移動支援策が必要であると強く感じている。
●地域内での共創が進んでほしい
国が進める地域公共交通の「リ・デザイン」(再構築)については、特に「3つの共創」(官と民の共創、交通事業者間の共創、他分野を含めた共創)に注目している。実証段階において、「共創」が実際にどのように実現しているか、中長期的にも検証していく必要がある。
私が設立時から研究で関わっている、秋田県大館市の「大館版mobiプロジェクト」においても、共創モデル実証事業を進めているが、その効果検証や課題分析を進める中で、新たなモビリティサービスの受け皿にならなかった需要が、既存のタクシー利用に流れた事例もみられる。様々な分野と連携することが「共創」の狙いであるが、商業施設等との連携はまだ模索段階にあるようにみえる。「共創」がさらに浸透し、その実現性や効果について、引き続き検証していく必要があり、今後に期待している。
●制度をつくる立場から積極的に地域への助言・評価をいただきたい
地域との連携・協働を進めていく上で、それが完全に地域任せであってはならない。地域でできること(できないこと)、国や自治体にできること(できないこと)はそれぞれ異なるため、地域に委ね過ぎず、役割に応じて体制を築いていくことを期待したい。
これは、事業者との連携を進めていく上でも同様で、事業者と連携したくても、あるいは補助したくても、事業者側の高齢化や担い手不足等の事情から、補助金を入れても路線を維持することが困難なケースもみられる。こうしたケースをどうするかは今後の課題であるが、体制づくりの問題であると考える。
国の場合、制度をつくる側なので、その立場から、自治体レベルに落とし込んだ時に、ぜひ助言をいただきたい。実際に制度を活用している自治体や地域で進められていることがどう評価されるのか、どこをさらに磨けばいいかという助言等あれば、自治体や地域の現場は勇気づけられるのではないか。
●新技術導入はあくまでも手段に過ぎない
新技術導入の取組事例が多く散見されているが、デジタルを活用した取組みや新しいサービスは、あくまで手段であり、目的ではないことに留意する必要がある。また、どのように地域に定着させていくかが大前提であると考えている。
大館市で実証実験が行われているmobiは、AIシステムの導入が目的ではなく、移動総量の増加や共生社会の実現が大きな目的である。事業者との連携を図りつつ、棲み分けを図っていくことをこれまでも確認してきており、事業者からは様々な意見をいただいている。顧客の奪い合いを引き起こさないよう、「共創」を前提とした体制づくりと、新たなサービスやデジタルを活用した取組みを進めていく必要がある。
デジタルの活用については、高齢者がアプリを使えるか等心配されがちだが、今は自治体を含め、スマートフォンの操作方法を教える相談室を開く等の支援を行っており、利用者である高齢者等への定着を図っている。
●車を運転できなくても移動と生活が密接につながっている状態が理想的
移動ができることにより、地域で暮らせる幸せを感じられる社会を築けるような交通サービスが望ましい。極端に言えば、どの交通手段かを問わず、地域公共交通が育っていき、それを使い、住民が安心して出かけられるようになることが究極の目的である。
マイカーを持つことが当たり前な地域社会に対し、マイカーがなければ生活できない状況を打破していきたい。研究を通して、公共交通を使いながら生活ができていることを身をもって示したい。
そのために、特に地方都市では、ミクロな交通の仕組みや、路線バスに接続する輸送サービスの導入等が対策として考えられる。ただし、元々、人口減少、過疎化が著しく進んでいるエリアでは、担い手不足等の課題があるため、行政や事業者との連携が必要である。
また、50年後を見据えた時、自動運転はさらに進化していると期待したいが、それでも自動運転でカバーできない地域をどうするかも考える必要があるのではないか。
●地域の暮らしの中の移動拠点整備が重要
持続可能な地域づくりやコンパクト・プラス・ネットワークを考える上で重要なのは、交通に加えて「拠点」である。拠点があって移動が生まれ、逆に言えば、移動が確保できなければ拠点まで行くことはできない。交通と拠点移動の両者が、密接に関係し合ってのコンパクト・プラス・ネットワークであると考える。
コンパクト・プラス・ネットワークの模範的な事例として、岩手県北上市の「あじさい都市」が挙げられる。アジサイの花びら一つひとつを各集落と捉えて、それぞれが独自に地域づくりを進めていくことを掲げている。各花びら(地域)が拠点をつくり、地域公共交通でつないでいくというコンパクト・プラス・ネットワークの取組みが継続的に行われている。
私が研究調査で伺った富山市における調査結果でいえば、LRT(Light Rail Transit)や路線バス、コミュニティバスだけでなく、地域の方が主体となって動かしている自主運行バスがあって、枝や葉に栄養を送ろうとしているからこそ、ネットワークが活きているのだと思う。いわば、「リ・デザイン」でいうところの、「幹」だけでなく、「枝や葉の部分」までも栄養が行き届いてこそのコンパクト・プラス・ネットワークである。