|
3 大都市の過密化
一方,第1章で述べたとおり,わが国の大郷市,すなわち東京,大阪,名古屋への人口,産業の集中は急速で,なかでも東京はすでに集中度が高い上に現在も他をはるかに上回る速度で増加をつづけている。もとより大都市へのこのような集中化傾向は世界的現象として現代の特徴となつているが,わが国においては,その集中がここ十数年間に急激に行なわれたこと,そのために都市の社会・公共部門の基礎施設の整備がこれに追随しえなかつたことが都市計画の貧困と相まつて都市の生活環境を悪化させている。
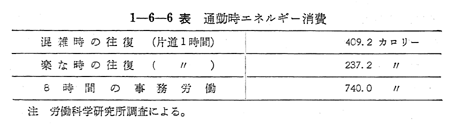
また,大都市における自動車交通量も年々増加をつづけている。自動車保有台数は昭和39年度末において,東京都109万台,愛知県52万台,大阪63万台と,30年に比較してそれぞれ4.4倍,5.2倍,4.9倍の増加となつた。このため東京都および大阪市の主要交差点においては交通渋滞が頻発しており,とくに12月および3月に激しい。39年には東京,大阪において高速有料自動車道路が供用されるにいたり,その沿道の交通混雑はかなり緩和されてきてはいるものの,道路面積の著しい不足と駐車施設の不足は自動車の利用効率を充分に発揮させるにはいたらず,大都市における問屋街や,農水産品市場の周辺等,物資の集散地における道路混雑は近代都市の形態からははるかに遠い状態にある。現在,世界の多くの都市において,都市生活を快適にすることと,自動車がますます生活に密着してくるのに対処して政府公共団体が都市の再開発を長期的計画のもとに実施しているが,わが国においても,都市の改造に着手すべき時期にきている。これは都市生活を豊かにし,交通の安全を確保することはもちろん,時間の大きな損失を防ぎ,仕事の能率を高めることにより経済を発展させることにもなる
|