|
3丂40擭搙偵峴側偭偨庡側撪峲奀塣懳嶔
丂丂慜弎偺傛偆偵撪峲慏暊検偼挊偟偄慏暊夁忚偱偁傞偺偱,塣桝戝恇偼10寧27擔奀塣憿慏崌棟壔怰媍夛偵懳偟,乽慏暊検偺嵟崅尷搙偺愝掕偺昁梫惈偺桳柍偲昁梫側応崌偵偍偗傞嵟崅尷搙検乿偵偮偄偰帎栤傪峴側偄12寧6擔偵摎怽傪偊偰,偮偓偺傛偆偵嵟崅尷搙傪愝掕偟偨丅偡側傢偪,揔惓慏暊検偲尰桳慏暊検傪斾妑偡傞偲 乲II亅(I)亅侾俆昞乴偺傛偆偵壿暔慏偵偮偄偰偼挊偟偔夁忚偱偁傝,桘憲慏傕曻抲偡傟偽挊偟偔夁忚偵側傞偍偦傟偑偁傞偑,僙儊儞僩愱梡慏偼尰桳慏暊検偑傎傏揔惓偱偁傝,廀媼娭學偐傜傒偰傕挊偟偔夁戝偵側傞偍偦傟偼側偄偺偱,壿暔慏偲桘憲慏偵偮偄偰偺傒嵟崅尷搙傪愝掕偡傞昁梫偑偁傞丅
丂丂38擭搙埲屻,撪峲榁媭晄宱嵪慏傪夝揚偟偰,嬤戙揑宱嵪慏傪寶憿偡傞偙偲偵傛傝慏暊検偺嶍尭傪恾偮偰偒偨偑,撪峲慏敃偺夁忚忬懺偼慜弎偺傛偆偵挊偟偔,偙偺傛偆側曽朄偱偼撪峲慏暊検傪挷惍偟偰宱塩偺埨掕傪恾傞偙偲偼晄壜擻偱偁傞偺偱,40擭5寧10擔撪峲奀塣嬈偺埨掕嶔偲偟偰乽撪峲奀塣懳嶔梫峧乿傪妕媍寛掕偟偨丅偙偺梫峧偺梫巪偼偮偓偺偲偍傝偱偁傞丅
丂丂撪峲奀塣懳嶔梫峧梫巪
丂I丂嬤戙揑宱嵪慏偺惍旛偲夁忚慏暊偺張棟
丂嘆丂崱屻3僇擭娫,枅擭搙13枩憤僩儞偺撪峲愱梡慏偍傛傃嬤奀廇峲慏偺寶憿傪峴側偆丅
丂嘇丂41擭搙偵夝揚偟,42擭搙傑偨偼43擭搙偵寶憿傪峴側偆幰(埲壓乽夝揚寶憿幰乿偲偄偆丅)偵懳偟,摿掕慏敃惍旛岞抍(埲壓乽岞抍乿偲偄偆丅)偼,夝揚慏偺攦擖偺偨傔偺強梫帒嬥偵偮偄偰梈帒傑偨偼嵚柋曐徹傪峴側偆丅岞抍偺梈帒偺帒嬥偼柉娫帒嬥傪妶梡偡傞偙偲偲偟,偙傟偵敽偆岞抍偺嵚柋偵懳偟,崙偼曐徹傪峴側偆丅崙偼,夝揚寶憿幰偵梈帒傪峴偨偆岞抍偍傛傃巗拞嬥梈婡娭偵懳偟棙巕曗媼傪峴側偆丅
丂嘊丂撪峲奀塣慻崌偼,嫟摨學慏傪峴側偆丅偙偺応崌岞抍偼偦偺撪峲奀塣慻崌偵梈帒傪峴側偆丅
丂丂學慏梈帒偵偮偄偰偼,撪峲奀塣慻崌偼,慻崌堳傛傝擺晅嬥傪挜廂偟,偦偺擺晅嬥傪傕偮偰曎嵪偝偣傞丅
丂II丂撪峲奀塣婇嬈偺揔惓婯柾壔
丂嘆丂撪峲奀塣婇嬈偺婇嬈婯柾偺揔惓壔傪悇恑偡傞偨傔,帠嬈傪嫋壜惂偲偡傞傕偺偲偟,崱崙夛偱強梫偺朄夵惓傪峴側偆丅
丂嘇丂塣捓偺擣壜惂偺幚巤偵偮偄偰偼,撪峲奀塣偺崌棟壔,嬤戙壔偺偨傔偺彅斒偺懱惂偺惍旛忬嫷傪姩埬偟偰寛掕偡傞丅II偺撪峲奀塣婇嬈偺揔惓婯柾壔偵偮偄偰偼嘆撪峲奀塣嬈傪嫋壜惂偲偡傞偙偲,嘇嫋壜偺婎弨偲偟偰撪峲塣憲嬈偵偮偄偰慏暊検偺婎弨傪掕傔傞偙偲,嘊嫋壜惂傊偺愗懼偼徍榓44擭3寧31擔傑偱偲偡傞偙偲摍傪撪梕偲偟偨撪峲奀塣嬈朄偺堦晹夵惓埬傪戞51夞捠忢崙夛偵採弌偟偨偑,宲懕怰媍偲側傝,戞52夞椪帪崙夛偵偍偄偰傕宲懕怰媍偲側偮偰偄傞丅
丂丂堦斒偵壍攧暔壙偼墶偽偄忬懺傪懕偗偰偄傞偑,撪峲塣捓偼壓棊孹岦傪帵偟偰偄傞丅偙偺寢壥,撪峲奀塣偺宱塩婎斦偼慜弎偺傛偆偵彏媝晄懌偑椵憹偟偰,嬌搙偵惼庛壔偟,埨慡惈偺掅偄榁媭慏偺戙懼傕偱偒偢,傑偨廋慤傕墑婜偡傞側偳偺尨場偵傛傝,彫宆峾慏偺奀擄偼憹壛偟,傑偨栘慏偼慡懝棪偑崅傑偮偰偄傞丅
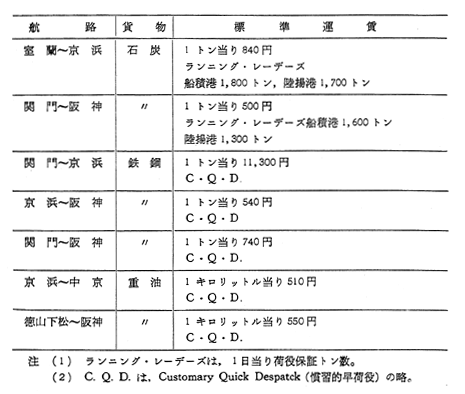
丂丂33擭埲崀掅柪偟偰偄傞撪峲塣捓巗嫷傪寶偰捈偡偨傔偵偼,昗弨昗弨塣捓傪幚岠偁傞傕偺偲偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞偑,堦曽撪峲慏暊偺挷惍偲偲傕偵壸庡嶻嬈奅偺嫤椡傪偊偰,慏敃偺壱峴棪偺岦忋傪悇恑偟,奀塣偵偍偗傞棳捠偺崌棟壔傪崱屻偲傕恑傔傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅
|