|
(2) 消費生活の充実
交通機関の発達,輸送方式の合理化による時間距離の短縮は低温流通倉庫およびその他の保管施設の整備,冷凍車両等の特殊車両の増備とあいまつて生鮮食料品等生活必需物資の大量,遠距離輸送を可能にし,市民の消費生活を豊かにしてきている。とくにコンテナ輸送を中心とした輸送方式の合理化は,遠隔輸送に伴う時間コストの増大を抑制し,かつ,大量輸送を可能にしており,大消費地である大都市への安定供給を通じて物価の安定化に好ましい影響をもたらしているといえよう。また,輸送網の拡充による市場圏の拡大は,各地の特産物を市民の日常の食卓に上らせており食生活を豊かにしている。
鉄道においては,コンテナによる地域間急行便の設定,発着基地の整備により,大幅な時間節減が可能となつた。たとえば南九州・東京間の冷蔵コンテナ特急による食肉,青果の高速輸送についてみると,従来58時間であつたものがコンテナ輸送により38時間に短縮され,さらに47年3月からは特急便の新設により29時間に短縮された。また,北海道・東京間の冷蔵コンテナによる乳製品の輸送においては,従来の61時間が38時間に短縮され,長野・東京間の高原野菜通風コンテナ輸送についても従来の15時間が10時間に短縮された。
自動車輸送についても幹線道路,高速道路の整備により,たとえば宮崎・東京間で従来の45時間が36時間に短縮されているが,生鮮食料品の輸送拡大にとつて画期的な契機となつたのは,長距離フエリー航路の開設である。たとえば細島(宮崎県)・川崎間は長距離フエリー就航により25時間で輸送できるようになり南九州の位置上の制約が大幅に緩和され生鮮食料品の輸送量は品目数量ともに拡大した。また北海道(苫小牧,釧路)と東京を30時間で結ぶ長距離フエリーの就航により,北海道産の農産物および魚介類の輸送が容易に行なわれることとなつた。
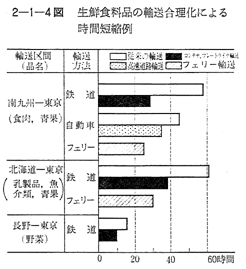
|