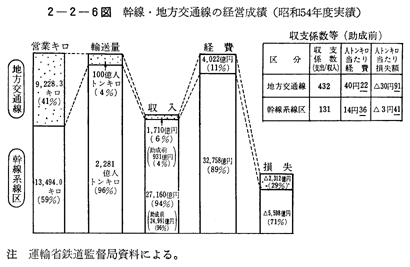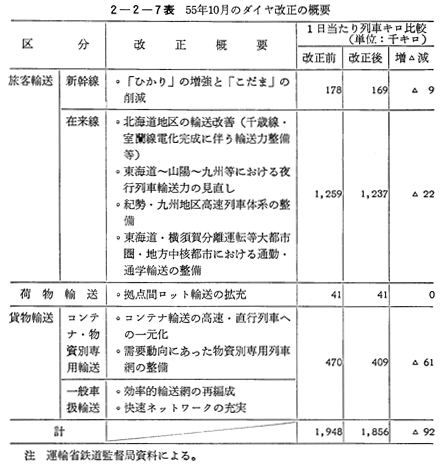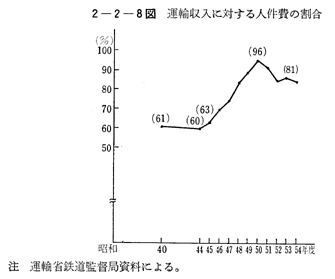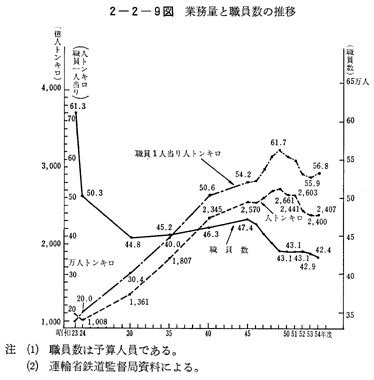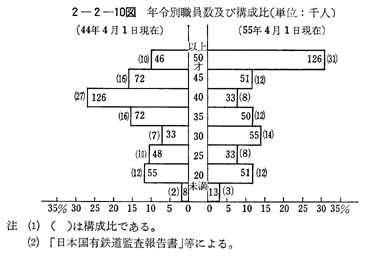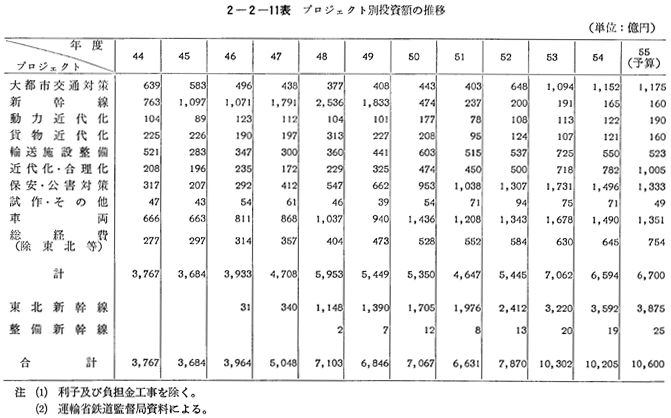|
3 国鉄の経営上の問題点
(1) 国鉄の経営分野
鉄道,航空,自動車等多様な輸送機関が相互に競争の関係にある現在においては,国鉄がその経営を適正に維持しつつ健全な発展を図るためには,鉄道の特性を発揮できる分野,すなわち,都市間旅客輸送(今後とも国鉄が重要な役割を果たす主要都市間における幹線旅客輸送),大都市圏旅客輸送(大都市圏における通勤通学旅客等大量の旅客輸送)及び大量・定型貨物輸送(国鉄の貨物輸送のうち,他の輸送機関との競争力を発揮しうるコンテナ輸送及び物資別適合輸送)に経営を重点化していく必要がある。
その他の輸送需要が少なく鉄道特性が発揮しがたい分野においては,輸送力,営業範囲の縮小等の減量化施策を講じていくことが不可欠である。
このため,旅客輸送については,輸送需要の動向に即して,列車設定キロの削減等輸送力の見直しを行うほか,駅の業務委託の推進,駅の停留所化等を推進し,貨物輸送については,輸送力の見直し,ヤード・駅の統廃合等の近代化・合理化施策を更に推進する必要がある。
特に,地方交通線については, 〔2−2−3図〕のとおり,輸送量の引き続く減少によりその経営悪化が著しく,国鉄経営の圧迫要因となっており,地域住民の足を確保するための具体的施策を講じつつバス輸送への転換を進める等,所要の措置を講ずる必要がある 〔2−2−6図〕。
なお,国鉄は,53年10月における貨物列車設定キロの削減(1日当たり7万キロの減)等を中心とするダイヤ改正に引き続き,55年10月に大幅なダイヤ改正を行い,近年の輸送需要動向に対応して旅客・貨物列車設定キロの削減等の輸送力の見直し,新幹線を含む高速列車体系の再編成等を実施した 〔2−2−7表〕。
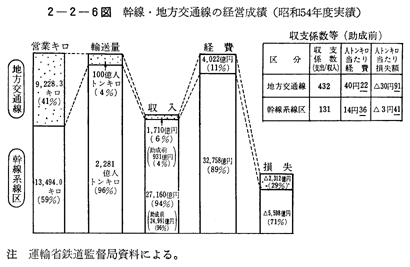
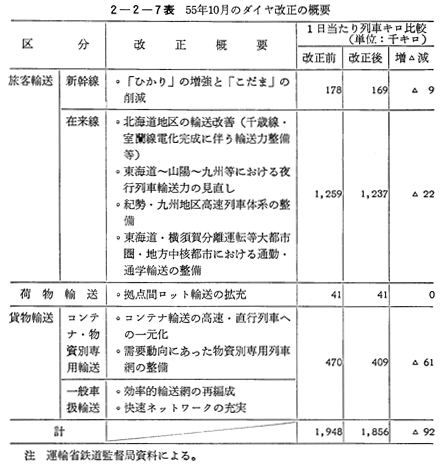
(2) 経費
ア 人件費
国鉄の要員規模は,40年代前半においては47万人程度で横ばいに推移し,以後少しずつ縮減され,54年度においては42万4,000人となっている。こうした中で,経済の高度成長を背景とした民間企業の給与上昇等の影響を受け,国鉄職員給与のベースアップ率は,40年代後半においては10%台となり,特に石油危機に端を発した諸物価・賃金の高騰のあおりを受けて49年度には25%となった。こうした事情から 〔2−2−8図〕のとおり,運輸収入に対する人件費の割合は次第に上昇し,40年代前半において60%程度であったのに対し,54年度においては85%に達している。一方,生産性の推移を職員1人当たりの人トンキロでみると 〔2−2−9図〕のとおりであり,最近,停滞傾向にある。こうしたことから経営の重点化を進めるとともに,業務運営全般の効率化,機構・組織の簡素化等を一層徹底し,要員規模の縮減を図ってゆくことが急務となっている。
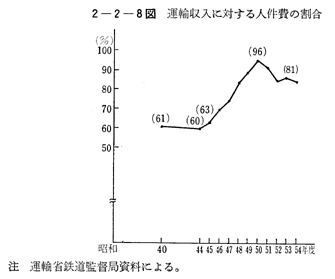
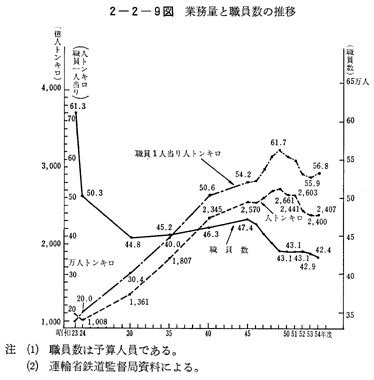
また,国鉄職員の年令構成は,戦中,戦後において大量に採用された職員の全職員の中に占める割合が高いことから,30年代,40年代において中ぶくれ型の構成であったものが,50年代に入ってきのこ型の構成となっている 〔2−2−10図〕。このため,他の公社と比較して平均給与単価が高くなっていることに加え,近年に至って,これらの職員の大量退職時代を迎えることとなり,退職手当に要する経費が急増している。この年令構成の歪みは,大量退職を通じて国鉄共済年金受給者の大幅な増加を生ずることにより,国鉄の年金負担金の増大をもたらすこととなる等国鉄財政にとって極めて大きな問題となっている。
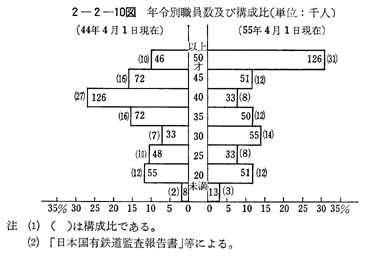
イ 設備投資
国鉄は,30年代以降,新幹線の建設,大都市交通対策を中心とする輸送力の増強,輸送の近代化・合理化,保安・公害対策等に重点を置きつつ設備投資を行っているが,その額は 〔2−2−11表〕のとおり年々増加している。このような設備投資の資金源は,30年代においては,その相当部分を自己資金によっていたが,39年度以降,経営悪化に伴いそのほとんどを外部からの借入金に依存している。このため,その金利負担が膨大なものとなっていること及び投資額の増加が売上高の増加につながっていないことが,経営の圧迫要因となっている。
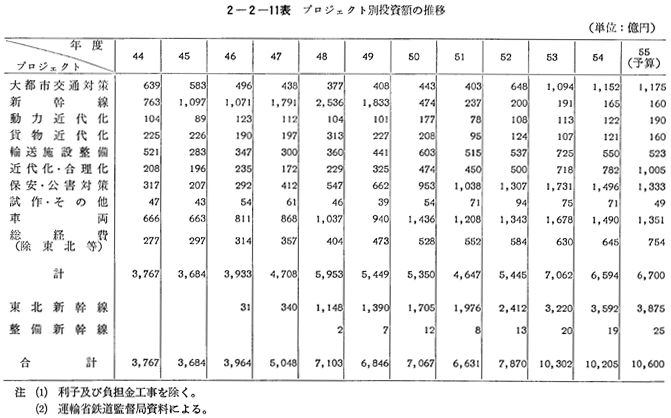
(3) 収入
ア 運賃
国鉄の基本的な運賃は,従来法律で定められていたため,経営の悪化が進んでいた40年代を通じ,適時適切な改定が行えず,それが国鉄財政を一層悪化させる原因の一つになっていた。
このような運賃決定制度上の問題を解決するため,52年12月,国有鉄道運賃法の一部改正により,当分の間,運輸大臣の認可を受けて経費の増加分の範囲内で国鉄の自主的経営判断のもとに,適時適切に改定を行うことができることとなった。
今後,運賃については,他の輸送機関との競争関係等を考慮しつつ,きめ細かな工夫を凝らし,適時適切に改定を行う必要があるが,このためには,国鉄の運賃水準が地方交通の分野においては民鉄やバスよりも相当低く,収入確保の面で不十分な状況となっていること等にかんがみ,線区別,地域別運賃の導入等従来の運賃制度を手直しする必要がある。
さらに,国鉄は,通学定期旅客運賃について平均77.3%の大幅な割引を行っているほか,身体障害者割引等のいわゆる公共割引を行っている。国鉄の経営状況が悪化の度合いを深めている現状から,これらの運賃上の公共割引から生じる国鉄の負担の軽減を図っていく必要がある。
イ 関連事業等による増収
国鉄が運輸収入以外の収入の一層の増加を図ることができるよう,52年12月に日本国有鉄道法が改正され,その投資対象事業の範囲が拡大された。今後,関連事業の新規開発と既存分野の充実を積極的に進め増収を図っていくほか,国鉄のかかえている資産の有効活用や不用資産の処分をより一層促進していく必要がある。
|