|
5 今後の輸送動向
今後の国内貨物総輸送需要の伸びは,安定成長下の経済の伸びとほぼ同程度にとどまることとなろう。しかも単調に伸びていくのではなく,55年度に見られたように,石油危機の発生など産業活動や国民生活をめぐる諸情勢の急変によって,ジグザグの成長となることも予想される。これを輸送機関別にみると,相変らず自動車,内航海運は伸長していくが,鉄道は横ばいないし減少へ向かうこととなるだろう 〔2−2−52表〕。
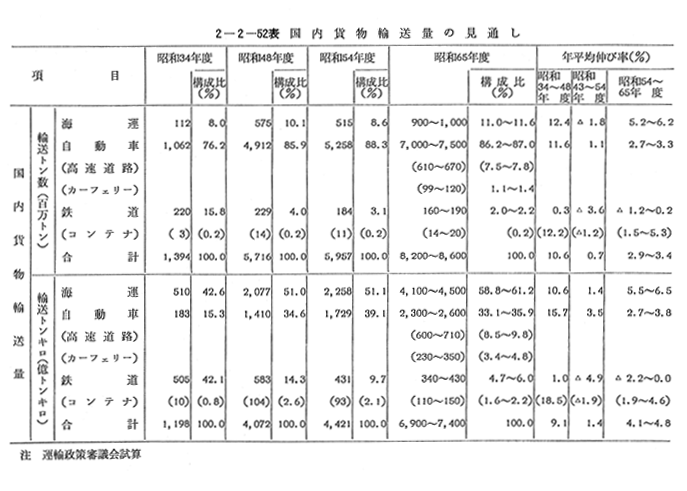
その背景としては次のようなことが指摘できる。まず第1に,実質GNPの拡大テンポは年率5.0%程度と見込まれているが,その中で第二次産業のウエイトは更に低下し,生産額1単位当たりの発生輸送量が比較的小さいサービス経済化,第三次産業化の進展が続いていく。第2に,第二次産業のうちでも,大量の輸送需要を生み出す鉄鋼金属,石油等の素材型産業よりも,情報化,システム化社会が進むにつれてエレクトロニクス化,コンピューター化等が一層進展し,比較的輸送単位が小さく高い付加価値を生み,生産額1単位当たりの発生輸送量の小さい高度な加工型産業,より知識集約型の産業が大きく伸び,そのウエイトを高めていく。第3に,財政上の制約もあり今後の公共投資の伸びも期待できない。しかも,公共投資の内容も比較的大量の貨物を誘発させる産業基盤中心の投資から,比較的誘発輸送量が小さい生活基盤整備に重点を移しつつある。また,民間設備投資も,高度経済成長期に比べその伸びが鈍化しており,その重点も能力増強投資から省エネ投資等に移りつつあり,こうした傾向は今後も続くと予想される。
|