|
5 経営基盤の確立
運輸事業の営業費用の増大の大きな要因としては,人件費や燃料費の増大などがあげられる 〔1−3−8図〕。また,運輸事業は一般に自己資本が小さく利子負担が大きい等の経営の不安定要因を有している。一方,輸送需要は,55,56年度と伸び悩んでおり,輸送原価は年々上昇している 〔1−3−9図〕。このような状況を踏まえ,輸送原価の縮減の観点から,従来より輸送手段の大型化,各種作業の合理化や機械化等による輸送の効率化,省力化など経営の全般にわたって合理化の徹底に努力してきたが,この結果,例えば乗合バスのワンマン化のように既に9割を超えるなど今後の合理化が困難な面もでてきている。しかし,依然として,企業形態別,企業別,地域別にみると経営状況には差がみられ改善の余地がないとはいえない 〔1−3−10図〕, 〔1−3−11図〕。
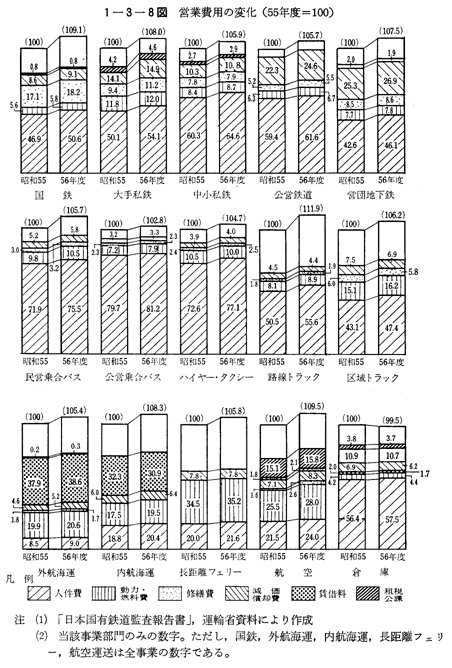
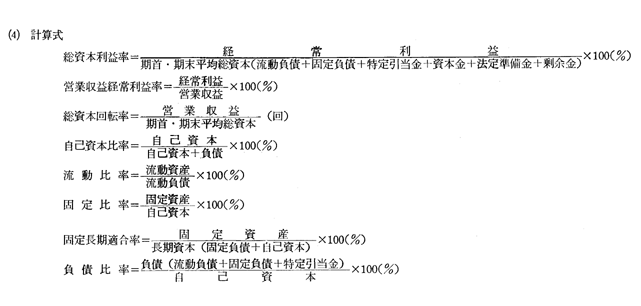
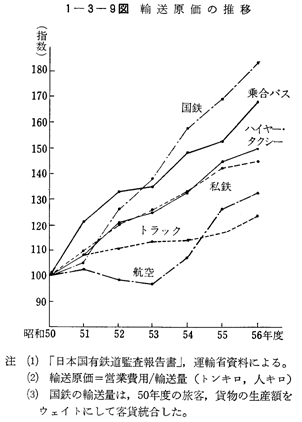
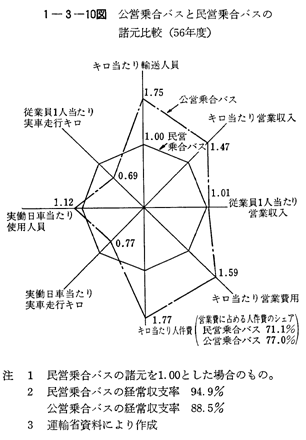
今後,収支の改善,健全な経営の確保を図る一方,各事業主体において,輸送サービスの質的充実が一層重要となり,また,輸送需要の伸びに多くを期待できないことから,輸送・事業の一層の省力化,効率化,合理化による経営体質の強化,事業基盤の充実が急務となっている。
運輸事業の経営は,能率的な経営を前提とする適正な原価に見合った運賃・料金収入により維持されることが原則となっている。したがって,各企業の合理化努力を勘案しつつ,生産性向上によりなお吸収しきれない人件費,物件費等の費用については運賃の見直しによりカバーしている。
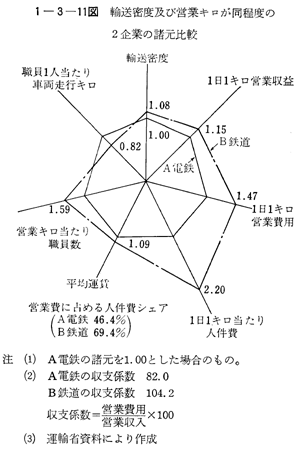
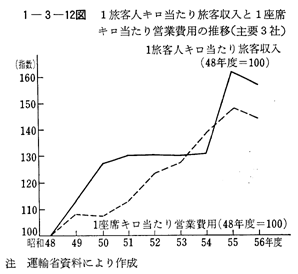
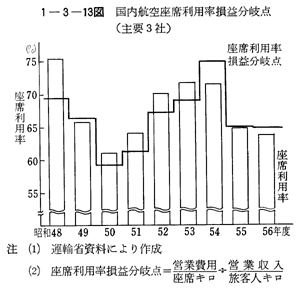
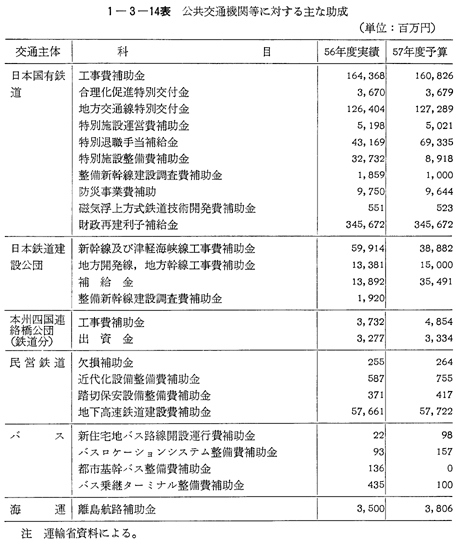
地域交通対策の推進,運輸関係社会資本の整備等の観点から,過疎地域など収益性の低い地域での輸送サービスの維持や膨大な施設建設費を要する大都市交通の整備などのため種々の助成措置が講じられている 〔1−3−16図〕。
|