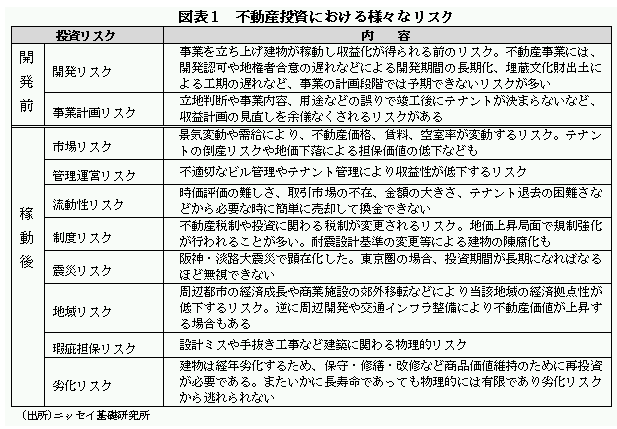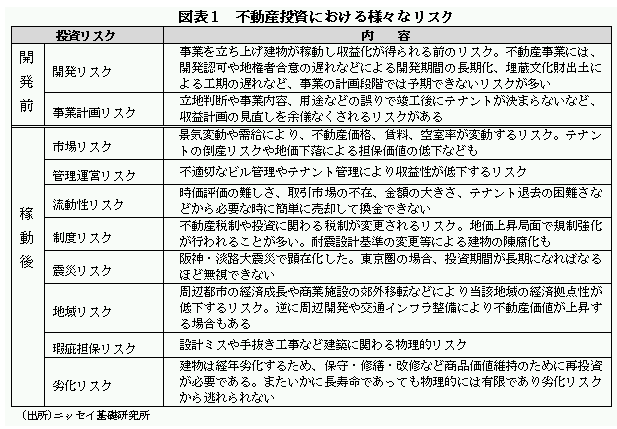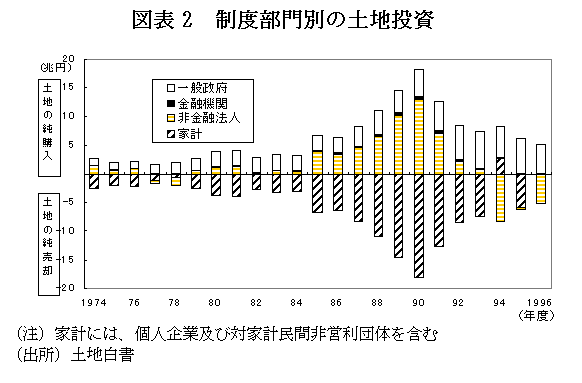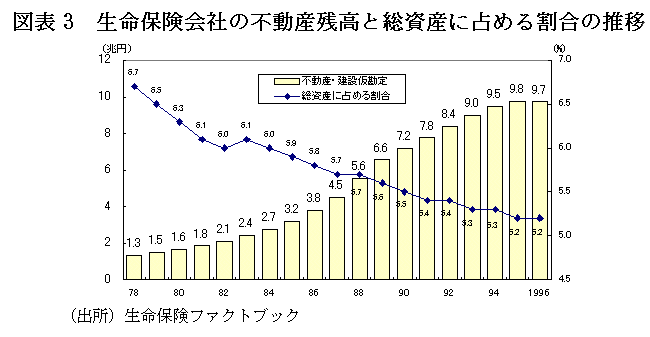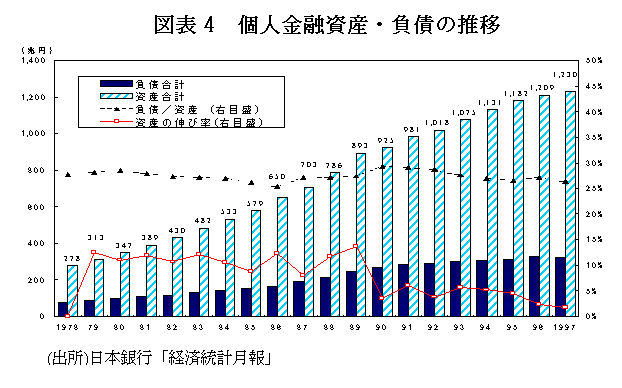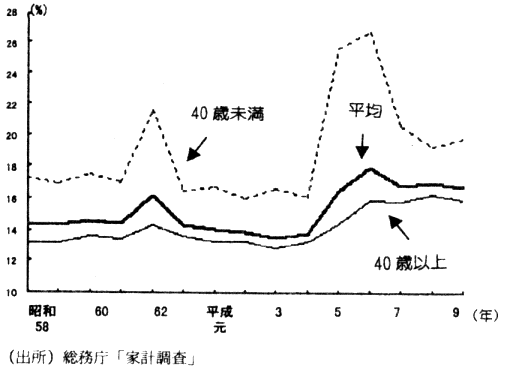| 第1章 社会経済の変化と住宅・不動産市場における経済主体の役割変化 |
1.社会経済の変化と住宅・不動産市場
- 少子・高齢化、経済の成熟化、地球規模の金融・情報ネットワーク化など、我が国の社会経済は大きく転換しつつあり、住宅・不動産市場も大きな変革期に直面している。
- 長期にわたって右肩上がりの上昇を続けてきた不動産価格は、バブル崩壊後から下落を続けている。この結果、不動産事業は開発前のリスクだけではなく、稼働後であっても市場リスク、流動性リスクなど不動産を所有することによって生じる様々なリスクに直面するようになってきた。今後の不動産投資では、他の金融商品以上にリスクとリターンを意識した投資行動への転換が求められている(図表1)。
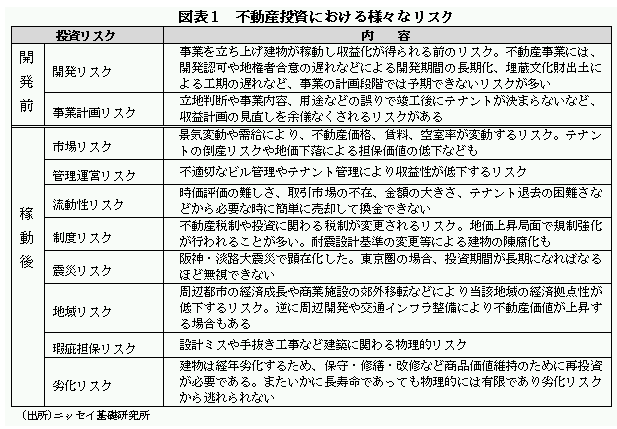
- 経済成長の持続期待によって支えられてきた「土地神話」はバブル経済の崩壊によって失われ、不動産金融の主体であった土地本位制度に基づくコーポレート・ファイナンス(ウィズ・リコース(注1))は機能不全に陥っている。これに対応して、我が国の不動産金融は、融資対象物件の資産価値のみに依存せず、物件から生み出される収益性や資産の流動性(容易な処分)等を勘案したプロジェクト・ファイナンス(ノン・リコース(注1))への転換を図ることが急務とされている。プロジェクト・ファイナンスの定着は、銀行ローンによる間接金融だけでなく、市場から投資家の資金を取り込む直接金融への発展につながるものとなる。
| (注1) |
ノンリコース条件の融資(償還請求不能融資)では、借手が返済不能に陥った場合、貸手は担保として差し出されていた不動産等の資産を処分して回収できる金額以上の返済を求めることはできない。ウィズリコース条件の融資(償還請求可能融資)の場合はこれが可能である。
|
2.キャピタル・ロスとキャッシュ・フローの枯渇による投資減退
- このように大きな転換期において、資産価値の急速な下落による巨額の不良債権を背景とした債務者及び債権者である金融機関の破綻問題などが拡大しており、資産デフレや将来に向けた雇用不安、企業の設備過剰等から個人消費、設備投資は大きく低迷している。不動産投資のための資金調達コストは増大しており、事実上新規投資は抑制されている。
- 政府による最大規模の経済対策によって景気はようやく底をつく兆しがあるが、今後の展望はなお不透明である。
3.部門別にみたストックとフローの変化:新たな主体の必要性
- 不良債権の担保物件処分が容易に進まぬ中で、住宅・不動産市場に対する投資資金の流入は低迷しており、一層のキャピタル・ロスへの懸念等から、不動産所有者は売却等を通じて所有リスクの外部化を進める傾向にある。
- これまで土地を購入・開発・売却することによって企業経営を行ってきた不動産事業者は新たな土地購入を控えており、不動産を所有せずに第三者による不動産開発や投資を支援する不動産投資顧問、プロパティー・マネジメント(注2)等の役割を今後重視していこうとする傾向がみられる。
| (注2) |
建物・設備のメンテナンスや賃料請求業務などの一般管理業務にとどまらず、合理的な賃料更改や経費削減などから物件の収益性を高めるための業務を行なう。 |
- 部門別の土地投資の推移をみると、従来土地を供給してきた家計部門は1993年に買い超しに転じ、逆に一貫して土地を購入してきた法人部門は土地を売る立場に転じている状況がある中で、一時的に政府部門が購入主体になっている状況がうかがえる(図表2)。
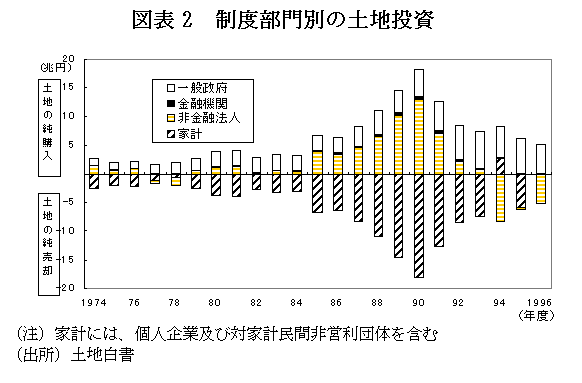
- 従来、盛んに不動産投資を行なっていた生命保険等の機関投資家のポートフォリオ(注3)に占める不動産の割合も著しく縮小しており、絶対的な投資額も1996年には取得よりも売却が進んだためマイナスに転じている(図表3)。
| (注3) |
運用資産のこと。一般にハイリスク・ハイリターンやローリスク・ローリターンなど、様々な資産に分散して投資が行なわれている。 |
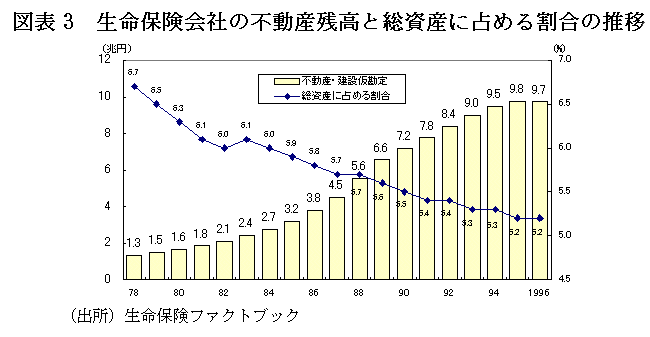
- 政府部門が土地投資を推進すること自体にもキャピタル・ロスというリスクがあり、財政的にも購入を続けることには限界がある。このように、これまで住宅・不動産市場において重要な役割を果たしてきた主体はいずれも後退しており、新たな開発・投資主体の出現が強く望まれているところである。
4.21世紀の優良なストック形成に向けた国民資産の活用
- 1200兆円と言われる国民資産もまたキャピタル・ロスに直面している上、住宅ローン債務等の増大、年金等の将来に向けた負担増などからフローの支出増大が国民資産の減少につながっていく可能性がある(図表4、5)。
- 一方、度重なる不祥事やいつでも破綻しかねない金融機関などに対する信頼の欠如もあり、外貨建預金や外資系金融機関を通じた投資機会を除くと、国民の資産を効率的に増やすための投資・運用機会はますます縮小する方向にある。このままでは膨大な国民資産は国外に流出するか有効に運用されることなく保持され縮小を続け、国内の住宅・不動産市場に対する資金供給はさらに低迷し、優良なストックの形成が進まない怖れがある。
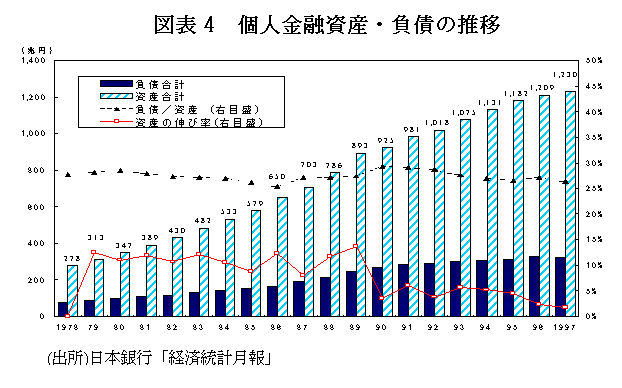
図表5 世帯主の年齢階級別可処分所得に占める住宅ローンの返済額の割合
(全国・勤労者世帯、住宅ローン返済世帯)
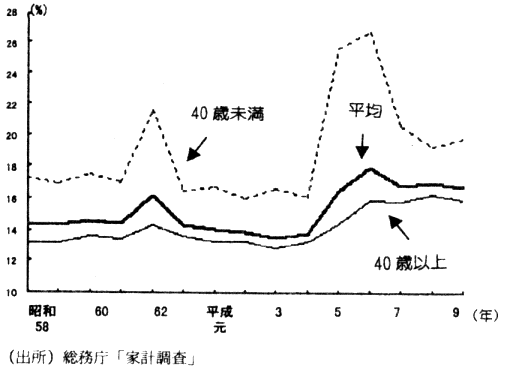
目次にもどる 前ページにもどる 次ページにすすむ