Webニューズレター新時代Vol.69 〜一緒に考えましょう、国会等の移転〜
情報化
- テレワークによるイノベーション -Work(働き方)・Life(生活)の変革からSociety(国土・社会)の構造変革へ-
-

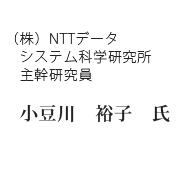
1.はじめに
テレワークは、在宅勤務、サテライトオフィス勤務やモバイルワークのように「情報通信技術(ICT)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」として、インターネットや、PC・携帯電話の高度化、無線LAN等の通信環境の発展によって、急速に普及してきた。テレワークには、企業や官公庁等団体に勤務する人が実施する「雇用型テレワーク」、SOHO2やフリーで働く、自営業者が実施する「自営型テレワーク」があり、それぞれ実施する人を雇用型テレワーカー、自営型テレワーカーと呼んでいる(図1)。
本稿では、日本におけるテレワークの普及を踏まえ、Work(働き方)・Life(生活)の変革からSociety(国土・社会)の構造変革へと、テレワークが様々な社会問題を解決する一つの手段として、改めて期待される背景や意義を考える。
図1 情報通信技術(ICT)を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方
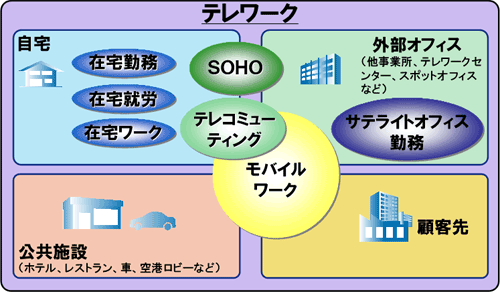
| 1イノベーション | :新しい技術や考え方によって新たな価値を創造し、社会的に大きな変化を起こすこと |
|---|---|
| 2SOHO | :Small Office Home Officeの略 主に専業性が高い仕事を行い、独立自営の度合いが高いもの |
2.日本のテレワーカー(週8時間以上実施)は1,000万人
2003年、政府のIT戦略本部の「e-Japan戦略」は、「2010年までに、適正な就業環境の下、テレワーカー(週8時間以上実施の狭義のテレワーカーを指す。以下同様)の就業人口全体に対する比率を20%とする」という目標値を設定し、本年がその節目の年となっている。
2002年時点のテレワーカーは408万人(テレワーク比率 6.1%)、2005年は674万人(同 10.4%)、そして2008年は1,000万人(同 15.2%)に到達した(注1、表1)。
また、2009年7月に策定された同本部の「i-Japan戦略2015」では、少子高齢化のセーフティネット等に資する在宅型テレワーカーを倍増し、700万人とするという新たな目標も加わった。通勤負担の軽減や育児・介護の環境づくり、交通渋滞の軽減や大気汚染対策等地球温暖化への対応、生活圏で就労することによる地域社会の課題への気づきや活動参加への期待もあり、在宅型テレワークの増加に照準を合わせる意義は大きい。
表1 日本のテレワーク人口(推計値)
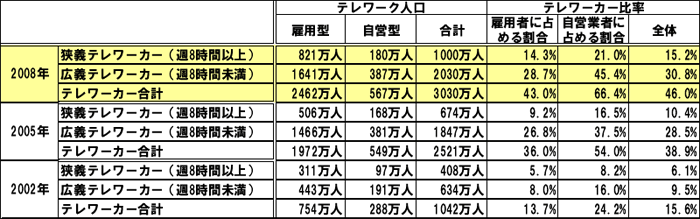
(出典)国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課(2003)「テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査」、同(2006)「平成17年度 テレワーク実態調査」報告書確定版、同(2008)「平成20年度テレワーク人口実態調査-調査結果の概要-」(http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/20telework_jittaichosa.pdf(新しいウィンドウで表示))より作成
| 注1 | :「e-Japan戦略 II 」の目標値の定義は、「雇用型テレワーク」の在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、「自営型テレワーク」のSOHO、在宅ワークなどすべてが包含されている。 |
|---|
3.地方分散策として期待されるテレワーク
三大都市圏、地方都市圏といった地域別にテレワークの状況をみると、雇用型テレワーカーのうち三大都市圏在勤者は53.9%、地方都市圏在勤者は46.1%である。雇用者全体では三大都市圏は48.7%、地方都市圏は51.3%であるので、雇用型テレワーカーについては三大都市圏の構成比が若干高くなっている。一方、自営型テレワーカーについては、三大都市圏が47.4%、地方都市圏が52.6%で、自営業者全体の同43.3%、56.7%と比べて三大都市圏の構成比が高いものの、全体では地方都市圏の占める割合が過半数を占めている(図2)。また、雇用型テレワーカーを対象に、自宅、モバイル、テレワークセンター等、他事業所といったテレワークタイプ別に構成比をみると、いずれの地域も他事業所が6割以上を占めて最も多い。三大都市圏では続いてモバイルの割合が19.3%と地方都市圏(13.9%)と比較して若干高く、地方圏では、自宅18.6%(大都市圏15.5%)、テレワークセンター6%(同3.0%)の割合がやや高くなっている(図3)。
さらに、雇用型テレワーカーについて地域別・業種別にみると、多くの業種で三大都市圏のテレワーカー比率が高く、特に「情報通信業」「不動産業、物品賃貸業」で高い。一方、「金融業、保険業」「学術研究、専門・技術サービス業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「複合サービス業」等については、地方都市圏のテレワーカー比率が若干高くなっている(図4)。
ICTの普及がはじまった1995年以降、人口、企業活動、大学など、都市部への集中が指摘されるが、テレワークという視点でみると、わずかではあるが、集中化・分散化の両方の兆しがみえるようである。
図2 地域別テレワーカーの状況
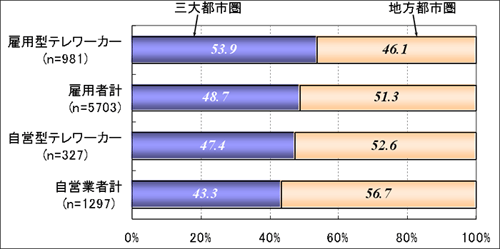
(出典)国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課(2008)
「平成20年度テレワーク推進調査(その2:テレワーク人口実態調査)」報告書
図3 地域別のテレワークタイプ:雇用型テレワーク
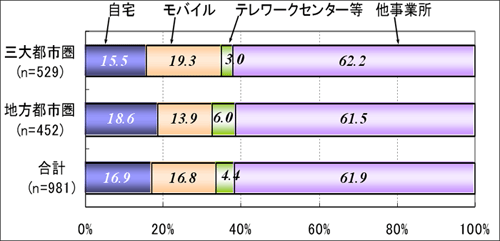
(出典)国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課(2008)
「平成20年度テレワーク推進調査(その2:テレワーク人口実態調査)」報告書
図4 地域別・業種別テレワーカーの状況
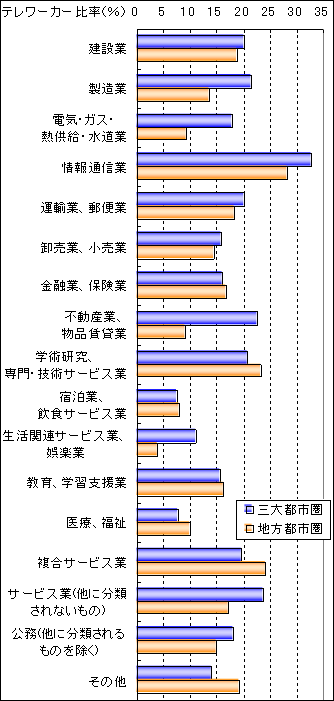
(出典)国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課(2008)
「平成20年度テレワーク推進調査(その2:テレワーク人口実態調査)」報告書
4.Life(生活).Work(働き方)の変革からSociety(国土・社会)の構造変革へ
日本テレワーク学会、Telework2.0研究部会では、2010年以降、テレワークが普及した「個人、組織、社会の未来像」に関して、経営・組織、ビジネスプロセス、人的資源管理、テクノロジー、ワークプレイス、都市・地域等の観点から検討を行ってきた。これまでの「新しいワークスタイル」という位置づけを越えて、未来を支えるテレワークの可能性を考える必要があるとの認識である。
Life(生活)面ではワークライフ・バランス3など「育児・介護ニーズを充足した豊かな生活」への効果が顕在化しつつある。情報リテラシー4を積極的に磨きながら、生活空間においては、多様な交流を通じた知性と感性の充実が促進され、異質な知との出会い、自律的な働き方を通じて「生きる力」そのものを創発していく可能性がある。
Work(働き方)面では、場所を離れた働き方は、セキュリティを確保しつつ、業務プロセスや成果の可視化を促進する。最近では、自然災害や新型インフルエンザをはじめとしたパンデミック5などに対する事業継続策としてテレワークの効果が指摘される。
Society(国土・社会)という面では、家庭内のICT環境やリテラシーの高度化が災害対策や環境課題に対しても有効に機能する可能性がある。
ネットワークによって、都市部と過疎地・地域が結ばれることにより、新たなサービス業が創造され、やや飛躍的であるが農業・漁業等の活性化によって自給率改善にも貢献できるかもしれない。「個」と、業務を可視化・標準化するノウハウを身につけた企業組織が連携することを通じて、多様でバランスがとれた国土・社会の発展に資する可能性も期待される(図5、6)。
図5 テレワークの効果
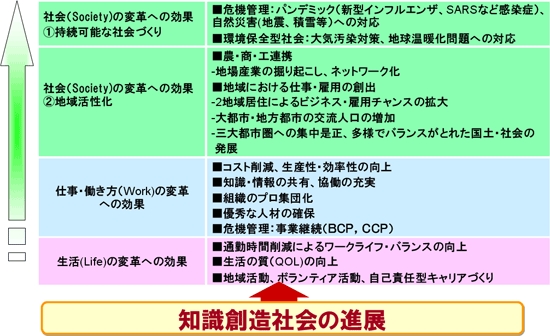
(出典)日本テレワーク学会Telework2.0研究部会を元に作成
図6 テレワークによるイノベーション
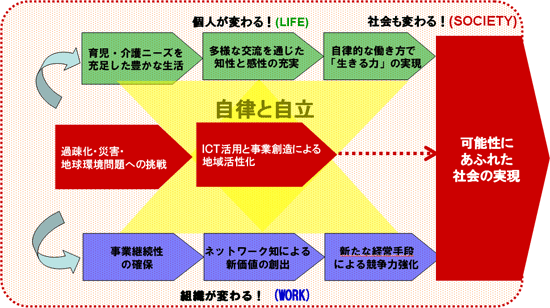
(出典)日本テレワーク学会Telework2.0研究部会
ところで、テレワーク先進国であるアメリカの連邦政府において、2008年のテレワーク実施職員数は102,900人で、このうち64%が週1日以上実施している(注2)。阻害要因としては、日本と同様に、テレワーク可能な職務範囲が限定的であることやマネジメントの抵抗などを挙げる声が大半である。しかし、経費節減や職員の処遇拡大策として普及してきた第1段階の1990年代を経て、2000年以降は第2段階として、業務継続性向上に不可欠な手段として位置づけられるようになっている。
米国で同時多発テロが発生した2001年9月11日以前よりFEMA(連邦緊急事態管理庁)は「業務継続性確保のために自宅勤務を最大活用せよ」と通達、連邦人事局がテレワーク実施の手引きを作成・公開している。2003年には「テレワークは職場が業務継続不能な状態に陥る可能性の対処に役立つ」(連邦人事局長官から連邦議会への報告書)とされ、2005年のハリケーン「カトリーナ」の大災害時には、連邦議会の下院議員がブッシュ大統領に「民間事業者に比べて政府機関の復旧が遅いのはテレワークの有無によるところが大きい」という書簡を送っている。
2006年にはFEMA(連邦緊急事態管理庁)等とOPM(人事管理局)が協力して、インフルエンザ大流行対策の実施計画やテレワークの実施手引きなどを公表し、「業務継続計画とテレワークの一体化」が急速に進んでいる。『災害によって職場が閉鎖されても、テレワークによって業務継続ができる』と回答する割合は、民間企業従業員の33%に比して、連邦政府職員は75%に上るほどになってきたのである(CDW-G社)。
工業社会から知識創造社会への移行によって、ICTによって生み出される付加価値は、これまでの個人-個人、組織-組織といった主体間のみで生み出されるものではなく、個人、組織、社会それぞれの間の相互の発信・啓発によってもたらされる傾向が強まっている。非常時の事業継続性を確保できる体制を、平時のテレワークによって確立し、「個」が生み出す知のネットワークが、組織・地域・国へのダイナミックな発展につながるシステムとして、テレワークの可能性を改めて問い直す時期がきているといえよう。
| 3ワークライフ・バランス | :仕事と生活の調和 |
|---|---|
| 4情報リテラシー | :情報を使いこなす力 |
| 5パンデミック | :ある感染症(特に伝染病)の全国的・世界的な大流行 |
| 注2 | :”Status of Telework in the Federal Government-Report to the Congress”United States Office of Personnel Management, August 2009 http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf |