Webニューズレター新時代Vol.69 〜一緒に考えましょう、国会等の移転〜
危機管理/BCP
- 金融等の手段を通じた、企業防災支援の活動について
-

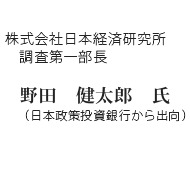
1.企業防災への関心の高まり
近時、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震、能登半島地震等、従来、地震の発生確率が低いといわれた地域でも大きな地震が発生したこともあり防災への関心が高まっている。こうした大災害に見舞われた地域においては、企業の被災が地元経済にも大きな影響を与える。さらにサプライチェーン1や情報システムで組み立てられた現代社会においては、ひとたび災害、事故が起これば、その影響はネットワークを通じて地域全体、さまざまな分野へも波及する。新潟県中越沖地震では地元中核企業の被災が地域経済にも大きな影響を与えただけでなく、同地域にあった自動車部品メーカーの被災は日本全体の自動車生産をストップさせた。こうした観点からも災害等の事態に備え地域防災力の向上、事業継続能力を高めておくことが重要となる。
防災は1つの企業だけで完結するものではなく、地域や企業同士が連携を図ることで初めて効果を発揮する部分も大きい。阪神淡路大震災や新潟県中越地震等過去の大災害から見ても、大きな災害発生時において公助が行き渡らなくなるのは明らかである。首都圏のように人口が多く、様々な中枢機能が集中している地域において事態はいっそう深刻である。自助により自らの安全確保、家族や従業員の安否が確認できた市民や企業が共助にまわれば、そのパワーは相当なものになる。特に、企業という組織化された集団は、その独自のスキルや施設を共助に転用することで、行政が行う公助と同等かそれ以上の貢献が果たせるものと期待される。そのためには、平時から地域社会や行政とネットワークを構築し、地域全体として事業継続の能力を高める施策が求められる。また、近時、事業継続計画(Business Continuity Plan :BCP)という新しいリスクマネジメント手法が導入され注目されている。首都直下地震の地震防災戦略(2006年4月)の中でも、BCPに関してほぼすべての大企業と中堅企業で50%以上の策定を掲げている等、企業防災への取り組みが進められている。
1サプライチェーン
原材料の調達から生産・販売を経て最終消費に至る、製品・サービス提供のための一連の流れ。自社だけでなく取引先等の幅広い関係を含む。
2.企業防災への取り組み状況
日本政策投資銀行が2009年6月に実施した企業の防災への取組みに関する特別調査によれば、BCPの策定済み企業の割合は全産業で13%(製造業で13%、非製造業で14%)にとどまっている。政府中央防災会議では、2005年8月に「事業継続ガイドライン」、10月に「防災に対する企業の取組み自己評価項目表」を策定・公表し、企業の防災への取り組み高度化を促す方向が打ち出された。それに続いて各業界団体等からの業種別ガイドラインは作成される動きがあるが、事業継続へ向けた取り組みは必ずしも進んでいない。さらに防災関連の計画さえもないと回答した企業が21%もあり、防災への取り組みに関して改善の余地は依然として大きいことがわかる(図表1)。
| 調査時期: | 2009年6月 |
| 調査対象: | 全国の資本金10億円以上3,402社(農業、林業、金融保険業、医療業などを除く)。 |
| 回答状況: | 回答会社数1,475社(回答率43.4%)うち、製造業611社、非製造業864社 |
図表1 企業防災への取り組み状況
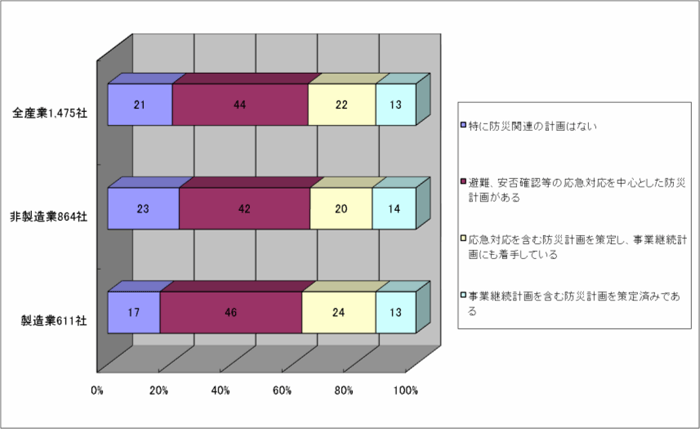
3.取り組みの促進策
防災や事業継続の取り組みにはコストがかかるものの、実際の障害が発生するまでは本当の価値を測定することが難しいことから、対策が本来必要とされる水準を下回る可能性が高い。そのため一定の促進策が必要となるが、規制、税制、補助金だけによって防災力の向上を図ることには限界がある。こうした状況を打破するためには、市場の力を利用し企業の防災への取り組みを適切に評価することで、企業が自発的・戦略的に防災力向上に努める環境を作り出す方法が有効であろう。その1つのやり方として企業の防災やBCPへの取り組みを評価し融資金利に反映させる仕組みがあり、通常の融資に対して、これらの融資を格付型の融資として分類することができる。
以下では日本政策投資銀行の防災格付融資を例にとって融資の効果について概説する(図表2)。防災格付融資は企業の防災力を評価し、融資金利に反映させる制度である。企業は防災格付融資を受けることによって、防災への取り組みをPRすることができるメリットもある。
図表2 防災格付融資制度概要
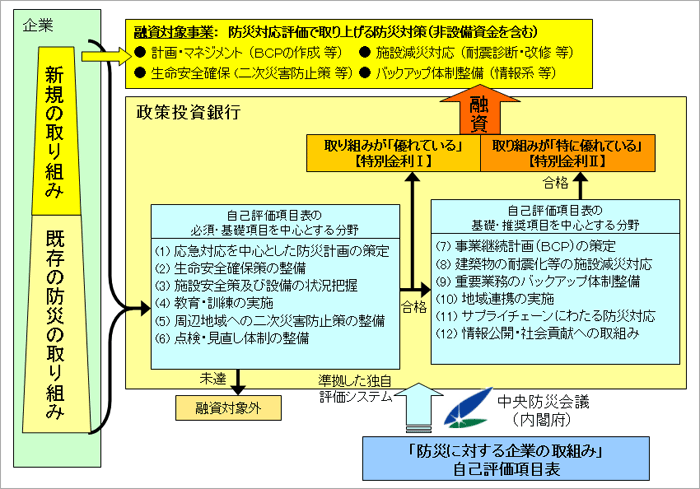
評価にあたっては、約60の項目について企業の取組水準の達成度を確認し、これをグループ分けした12の要件単位で合否を判定する。最初の4つの要件((1) 計画策定、(2) 生命安全確保、(3) 施設の状況把握、(4) 教育・訓練)では、内閣府自己評価項目表で必須と分類された項目で法令遵守等の確認を行った上、有効な対策となっているかを評価する。防災対策の基本となるこの4要件を満たした上で、(5) 二次災害防止、(6) 点検・見直し体制の整備のいずれかを満たす場合、防災対策が「十分」であるとして特別金利 I による融資を行う。
残る6つの要件は、より高度な観点から防災対策が「先進的」といえるかを評価する。(7) BCPの策定は、BCPへの取組み状況を確認する。(8) 耐震化等のハード対策、(9) バックアップ体制整備、(11) サプライチェーンの防災対応の各要件ではより具体的な対策を見ていくが、これらはBCP等の計画、訓練・点検等と有機的に一体となって効果を発揮するものと期待される。また、(10) 地域連携、(12) 情報公開・社会貢献については、CSR2的な要素を有するが、企業が社会の一員として事業を営むことを考えれば、事業継続の一部を構成すると考えることもできる。特別金利 I の要件に加えて以上の6要件中4つ以上を満たした場合には、より優遇度の高い特別金利 II が適用される。
融資の対象となる事業は、(1)〜(12)の評価対象として取り上げた防災対策に要する資金となる。ここには、耐震改修等の設備投資だけでなく、計画策定、情報システム整備のようなソフト事業を含めることが可能となる。BCPの構築に資するための対策を幅広く対象にしている。
以下で融資を受ける企業のメリットを整理すると、
- 金利優遇によって直接収益に貢献しない防災対策のコストを抑制することができる。
- 格付を通じて、防災対策に関する情報を引き出し、企業の同意を得て公表することで、企業評価を高める効果がある。さらに、先行企業の取組みが刺激となり、他企業の取り組みを促し、社会全体の防災力を高めていくことが期待される。
- 格付の評価を通じて課題の発見や業界内における位置づけを確認できるメリットもある。そして今まであまりクローズアップされることの少なかった関連セクションの貢献に対して、より積極的な評価をする機会を提供している。
加えて、本制度では評価時点で未達の項目であっても、融資対象事業など今後1年程度で確実に達成が見込まれる対策について評価に織り込むことを可能とし、インセンティブを一層高めている。防災格付融資については2008年度末までに20件、約105億円の融資が実行されている。
滋賀銀行、大垣共立銀行、京都銀行でも関連の融資制度をスタートさせている。今後、企業の防災への取り組みを評価する融資制度だけでなく、現在、環境分野に対する評価が中心であるSRI(社会責任投資)の中にも、防災、BCPに対する評価が組み込まれていくことが期待される。
2CSR (Corporate Social Responsibility)
組織の社会的責任。企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響をステークホルダー(投資家、顧客、地域等の利害関係者)に対して適切に説明を行い、信頼関係を構築すること。
4.おわりに
防災、事業継続に向けて企業が責任を果たしていくためには、企業自身のそれぞれの努力に加え、公共サイドと一体となった取り組みも必要である。企業が事業継続能力を高めることは企業価値の向上に資するとともに、社会的責任としても求められるとの認識を持ち対応を図る必要がある。一方、公共サイドは経営資源の相互融通、インフラ情報の開示を進めることで企業の取り組みとの整合性を図る。こうした動きを加速するために、金融機関には防災対策やBCPへの取り組みを融資条件に組み込むことで企業の対策を促進することが求められる。さらにその効果が一企業にとどまらないことが明らかな場合、例えば企業による自治体への災害時の物資の供給といった経営資源の提供等については、融資に対する利子補給等のさらなるインセンティブ3を付与することについて公共サイドは検討する必要があろう。
3インセンティブ
組織や個人の意思決定や行動を高める誘因