平成20年度観光の状況
第I部 観光政策の新たな展開
第2章 観光立国の実現に向けた重点課題と戦略的取組
第1節 国民の観光旅行に関する動向と課題
近年、我が国における国内宿泊観光旅行回数や海外旅行者数は伸び悩む状況にあるが、今後の少子高齢社会において活力に満ちた地域社会を実現するとともに、国際相互理解の増進や諸外国の期待に応えていくためには、我が国において、観光による交流人口を拡大していくことが重要である。
特に、平成19年度における国民の国内における旅行消費額は22.0兆円※1、その生産波及効果は49.5兆円※2であり、国民の観光旅行の促進は、現在極めて厳しい状況にある我が国経済の活性化に大きく寄与するものである。また、経済効果のみならず、地域づくりや交流人口の拡大による地域の活性化や、国際観光を通じた諸外国との草の根交流は、国家間の外交を補完・強化するとともに、国際感覚豊かな人材の育成等のソフトパワーの強化にも資するものである。
このため、国民の観光旅行の動向と旅行行動に影響を与える要因について分析を行うとともに、国民の観光旅行の促進に向けた課題の検証を行う。
1)国内宿泊観光旅行の推移
国民の国内宿泊観光旅行※3の推移を見ると、国民1人当たりの旅行回数、宿泊数ともに平成3年をピークに減少傾向にある※4。平成20年度においては、国民1人当たりの国内宿泊観光旅行回数は1.55回、国内宿泊観光旅行宿泊数は2.44泊と推計され、観光立国推進基本計画に定められた国民の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数を平成22年度までに年間4泊にするという目標に対して、約6割の水準に低迷している(図I-2-1-1)。
2)国内宿泊観光旅行回数の分析
平成15年度から平成19年度の国内宿泊観光旅行回数の推移を見ると、国民1人当たりでは平成17年度に1.77回となったものの、平成19年度には1.50回まで低下している。
年代別の国内宿泊観光旅行回数の推移を見ると、20歳代から50歳代は、平成19年度に20歳代、30歳代が国民1人当たり平均をわずかに上回ったほかは、平均より低い水準にある。60歳代は国民1人当たり平均を常に上回り、平均回数を牽引していたが、平成19年度に大きく落ち込んだことにより、国民1人当たり平均を押し下げる結果となった。
次に、男女別の国内宿泊観光旅行回数を見ると、20歳代男性は1.20回を下回る低い水準で推移しており、過去5年間を通じて年代別男女別での旅行回数が最も少なくなっている一方で、20歳代女性の旅行回数は女性1人当たり平均を上回る水準で推移しており、平成19年度の旅行回数(1.95回)は、年代別男女別で最も多くなっている。60歳代の旅行回数は男女ともに高い水準で推移していたが、平成19年度は2.00回を下回り、特に60歳代女性の落ち込みが大きくなっている(図I-2-1-2~図I-2-1-4)。
図I-2-1-1 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移

図I-2-1-2 国内宿泊観光旅行回数の推移(年代別)
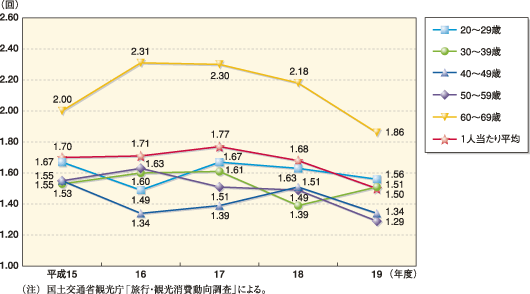
図I-2-1-3 国内宿泊観光旅行回数の推移(年代別・男性)

図I-2-1-4 国内宿泊観光旅行回数の推移(年代別・女性)

3)宿泊旅行と日帰り旅行の比較
平成15年度から平成19年度にかけての国民の国内旅行消費額の推移について、宿泊旅行、日帰り旅行それぞれを見ると、日帰り旅行の消費額は平成17年度以降3年連続で増加しているのに対し、宿泊旅行は平成15年度の16.3兆円から平成19年度の15.3兆円と1.0兆円減少している。宿泊旅行の消費額の規模は、日帰り旅行の約3倍の規模がある一方、近年の落ち込みが大きく、国内旅行消費額を押し下げていることが分かる(図I-2-1-5)。
図I-2-1-5 国内旅行消費額(宿泊・日帰り)の推移

1)全体の推移
近年の海外旅行者数の推移を見ると、平成12年に過去最高となる約1,782万人を記録した後、同時多発テロ(平成13年)、重症急性呼吸器症候群(SARS)の発生(平成15年)等により大きく落ち込んだ。平成16年からは増加に転じ、平成18年に約1,754万人を記録したものの、その後2年連続して減少している。平成20年の国民の海外旅行者数は、約1,599万人であり、観光立国推進基本計画に定められた日本人の海外旅行者数を平成22年までに2,000万人にするという目標に対して、約8割の水準にとどまっている(図I-2-1-6)。
図I-2-1-6 日本人海外旅行者数の推移

2)海外旅行者の出国率の分析
我が国における海外旅行者の出国率(人口に対する出国者の割合)の推移を年齢階層別に見ると、各年代とも平成12年までは漸増傾向にあった後、同時多発テロ(平成13年)、SARSの発生(平成15年)等により大きく落ち込んだ。平成16年からは増加に転じ、ほとんどの年代が平成12年の水準まで回復したが、20歳代は平成12年の約85%にとどまっている。
また、平成12年と平成19年の出国率を比較すると、国民総数では平成12年14.0%、平成19年13.7%とほぼ横ばいである。これを5歳刻みの年齢区分ごとに比較すると、20歳代から30歳代前半において出国率が大きく減少していることが分かる。平成12年と平成19年の20歳代の出国率を男女別に見ると、特に女性の出国率が落ち込んでいる(図I-2-1-7~図I-2-1-9)。
図I-2-1-7 年齢階層別出国率の推移

図I-2-1-8 年齢階層別出国率

図I-2-1-9 20歳代の男女別出国率

1.(1)で見たように、国内宿泊観光旅行が低迷する状況が続いていることを踏まえ、国民の国内旅行の動向に影響を与える要因を検証するため、年齢、人口規模、家族構成等により以下の対象を設定し、国内宿泊観光旅行について「平成20年度日本人の旅行行動に関する実態調査※1」等に基づき、対象ごとに現状と課題の分析を行った。
1)若年層※2
国内旅行、海外旅行双方について、男女別の傾向が異なっている層である。また、若年層は、今後は家族旅行の実施主体となるなど、その子供への影響を含め、中長期的な国内旅行の動向に大きな影響を与えると考えられる。
2)家族層※3
(財)日本交通公社「旅行者動向2008」によると、国内観光旅行に占める家族旅行の割合は、平成19年で46.2%と最も大きい。家族旅行の内訳を見ると、小学生連れ家族旅行の割合が43.7%と最も大きく、国内観光旅行全体の約2割を占めていると考えられる。また、家族旅行を通じた子供の旅行経験は、将来的な国内旅行の動向に大きな影響を与えると考えられる(図I-2-1-10)。
図I-2-1-10 国内観光旅行のマーケットセグメント別シェア(平成19年)

3)団塊世代及び60歳代(以下「団塊世代等」という)※
60歳代の平成19年度国内宿泊観光旅行回数は、年代ごとの比較で最も多い1.86回(国民1人当たり平均1.50)であり、国民1人当たりの旅行回数を牽引する層となっている。また、平成19年からは団塊世代(昭和22年から昭和24年生まれ)が順次60歳代に達しており、定年による余暇時間の増大が今後の旅行回数を押し上げることが期待される。
1)国内旅行の現状
平成15年度から平成19年度の若年層の国内宿泊観光旅行回数は、男性の旅行回数が少なく、女性の旅行回数が多いという傾向が続いている(表I-2-1-11)。平成19年度の旅行回数は、男性が1.16回、女性が1.95回であり、年代別・男女別の比較では、男性の旅行回数が最も少なく、女性の旅行回数が最も多い結果となっている。
表I-2-1-11 若年層の国内宿泊観光旅行回数の推移

「平成20年度日本人の旅行行動に関する実態調査」の調査対象となった若年層(20~29歳の「大学生」及び「社会人(子供なし)」、以下「調査対象の若年層」とする)の国内宿泊観光旅行回数を20歳代前半・後半に分けて見ると、「0回」(1年間※1に1度も国内宿泊観光旅行に行っていない)の割合は、20歳代前半で41.3%、20歳代後半で34.1%となっている。
同様に男女別の国内宿泊観光旅行回数について見ると、男性の「0回」の割合は、20歳代前半で44.2%、20歳代後半で39.4%となっている。一方、女性については、20歳代前半の「0回」の割合(37.9%)は男性と大きな違いはないものの、20歳代後半については、「0回」の割合(27.9%)が、男性及び20歳代前半の女性より10%以上小さくなっている。
また、調査対象の若年層について5年前と現在の国内宿泊観光旅行回数を比較すると、「0回」の割合は、この5年間において、20歳代前半で7.8%、20歳代後半で14.1%増加しており、回数別での増加幅が最も大きくなっている。このため、調査対象の若年層において、国内宿泊観光旅行に全く行かない層が増えることにより、旅行実施率(1年間に1回以上国内宿泊観光旅行に行った人の割合)が低下していることが分かる。このほか、20歳代後半において「4回以上」の割合の減少が目立つ(図I-2-1-12、図I-2-1-13)。
図I-2-1-12 若年層の年間国内宿泊観光旅行回数(5年前との比較)

調査対象の若年層の国内宿泊観光旅行の同行者を男女別に見ると、男性の同行者としては、「友人(学校・職場)」(50.5%)を挙げるものが最も多く、次に多い「1人で」(37.3%)は、女性(18.4%)の2倍以上の回答割合となっている。また、女性の同行者では、「家族(親)」(48.0%)を挙げるものが最も多く、その回答割合は、男性に比べ約20%も多い(図I-2-1-14)。
図I-2-1-13 若年層の年間国内宿泊観光旅行回数(男女別)

図I-2-1-14 若年層の国内宿泊観光旅行の同行者(男女別)

2)旅行行動に影響を与える要因
国内宿泊観光旅行回数の減少理由について、調査対象の若年層を「大学生」と「社会人」のグループに分けて見てみると、「お金に余裕が無くなって」という経済面での理由を挙げる回答が大学生(47.4%)、社会人(52.1%)ともに最も多くなっている。回答の詳細を見ると、「所得や仕送りが減った」ことに次いで、「貯蓄に回すようになった」という回答が多くなっており、調査対象の若年層において、消費に充てる資金の割合を減らしていることが推察される。
また、国内宿泊観光旅行回数の減少理由として、「休暇が減って」という時間面での理由を挙げる回答が、特に社会人(44.7%)に多い。社会人においては、「一緒に行っていた友達と休日が重ならなくなって」という回答も多く、休暇の減少に伴い、同行者と旅行の日程等を合わせにくくなっていることが考えられる(図I-2-1-15)。
若年層の国内旅行の実施に影響を与える一般的な理由として考えられる「就職活動」、「携帯電話やインターネットの普及」の影響について見ると、大学生・社会人ともに肯定する回答(約4割)、否定する回答(約4割)、一概には言えないとする回答(約2割)の割合に顕著な違いは見られず、国内旅行について若年層が多様な意見を持っている可能性が示唆される(図I-2-1-16、図I-2-1-17)。
図I-2-1-15 若年層の国内宿泊観光旅行の減少理由

図I-2-1-16 旅行低迷に対する意識調査(若年層:大学生)

図I-2-1-17 旅行低迷に対する意識調査(若年層:社会人)

3)国内旅行の実施動機
国内宿泊観光旅行に出かける「きっかけ」について、調査対象の若年層の上位3つの回答を見ると、大学生については、「誘いがあると」(52.5%)が最も多く、「行きたいところが見つかると」(50.7%)、「資金ができると」(43.0%)と続く。社会人については、「行きたいところが見つかると」(55.3%)が最も多く、「資金ができると」(41.6%)、「時間に余裕ができると」(39.5%)と続いている。
大学生と社会人の「きっかけ」を比較すると、大学生については、「誘いがあると」が社会人より約14%多く、他者からの誘いが国内宿泊観光旅行を実施する重要なきっかけとなっていることが分かる。一方、社会人では「日常から離れてリフレッシュしたくなると」という回答が大学生より約15%多くなっている(図I-2-1-18)。
図I-2-1-18 国内宿泊観光旅行に出かけるきっかけ(若年層)
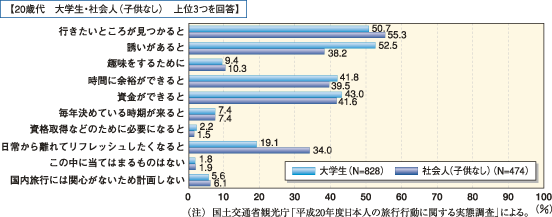
4)今後の旅行実施に対する意向
今後の国内宿泊観光旅行の実施に対する意向について見ると、旅行回数を増やしたいという回答が大学生で55.6%、社会人で62.0%を占めており、調査対象の若年層において、半数以上がもっと旅行に行きたいと考えていることが分かる。男女別では、女性の7割近くが旅行回数を増やしたいと考えているものの、旅行回数の増加意向を有する男性は49.4%と5割に満たない水準となっている。
また、国内宿泊観光旅行の回数別に見ると、最近1年間※1の国内宿泊観光旅行回数が1回以上である者については、大学生・社会人ともに旅行回数を増やしたいという回答が6割から7割程度を占めている。
一方、最近1年間※の国内宿泊観光旅行回数が0回である者については、旅行回数を増やしたいという回答が、大学生(40.1%)、社会人(48.9%)ともに5割に満たない状況となっている。特に、大学生の3割以上が旅行回数を増やしたくないと回答しており、旅行に行く層と行かない層への二極化など、将来的な国内旅行の動向に影響を及ぼす可能性がある(図I-2-1-19~図I-2-1-21)。
図I-2-1-19 若年層の旅行回数増加意向

図I-2-1-20 旅行回数の増加意向(大学生)

図I-2-1-21 旅行回数の増加意向(社会人)

5)今後の取組の方向性
前述のように、若年層については、男女間での旅行回数の差が大きく、特に20歳代男性における国内宿泊観光旅行回数の低迷が顕著であることや、旅行に全く行かない層が近年増加していることなどが明らかになっている。
しかしながら、調査対象の若年層の半数以上は、国内旅行の回数を増やしたいと考えていることから、多様な視点を持つ若年層のニーズに応じた取組を進めていくことが必要である。
例えば、若年層においては、今後の生活で重点を置きたい分野として、「所得・収入」、「資産・貯蓄」等の経済面のほか、「自己啓発・能力向上」を挙げるものが多くなっている。このような若年層のニーズに対応するため、体験型旅行等の知識や教養を高めることに効果のある旅行等を促進していくことや、物見遊山・レジャーという観光に対するイメージを、より多様なものに広げていくことが重要であると考えられる。
また、特に大学生については、他者からの誘いが旅行のきっかけとして重要であることから、大学生のグループ活動等に旅行を組み込む働きかけや若年層が魅力を感じる旅行コンテンツの開発等を通じ、若年層における国内旅行に対する潜在的な需要を喚起していくことが期待される(図I-2-1-22)。
また、社会人については国内宿泊観光旅行に出かけるきっかけとして「行きたいところが見つかると」「リフレッシュしたくなると」が上位に挙げられているが、休暇の減少、同行者と旅行の日程が合わないこと等が国内宿泊観光旅行回数の減少理由として挙げられており、有給休暇の取得を促進する環境整備を図るとともに、ニーズに合った観光地の整備が求められる。
図I-2-1-22 今後の生活の力点

1)国内旅行の現状
家族層における国内宿泊観光旅行の回数は、平成19年度で1.56回となっており、国民1人当たりの1.50回と同程度の水準となっている。
「平成20年度日本人の旅行行動に関する実態調査」の調査対象となった家族層について5年前と現在の国内宿泊観光旅行回数を比較すると、「0回」(1年間※1に一度も国内宿泊観光旅行に行っていない)の割合は28.1%と、この5年間で15.0%増加しており、旅行実施率が低下していることが分かる。また、5年前に比べ、「1回」の割合は増加しているものの、「2回」以上の割合についてはいずれも減少している(表I-2-1-23、図I-2-1-24)。
表I-2-1-23 家族層の国内宿泊観光旅行回数

図I-2-1-24 家族層の年間国内宿泊観光旅行回数(5年前との比較)

2)旅行行動に影響を与える要因
国内宿泊観光旅行回数の減少理由について見ると、若年層と同様に「お金に余裕がなくなって」(76.6%)という経済面を挙げる回答が最も多くなっている。回答の詳細を見ると、「教育費が増えた」(61.2%)という回答が最も多く、「所得が減った」(51.1%)、「家族が増えた」(42.3%)と続いている。
また、経済面以外の国内宿泊観光旅行回数の減少理由として、「子供と休日が重ならなくなって」(35.4%)という時間面を挙げる回答が多くなっており、親が休日の場合でも子供の予定との関係で国内宿泊観光旅行に行きにくくなっていることが考えられる(図I-2-1-25)。
3)今後の旅行実施に対する意向
今後の国内宿泊観光旅行の実施に対する意向について見ると、子供との旅行回数を増やしたいという回答が86.8%を占めており、調査対象の家族層において旅行回数の増加意向が非常に強いことが分かる。
また、国内宿泊観光旅行の回数別に見ると、家族層においては、最近1年間※1の国内宿泊観光旅行回数にかかわらず、8割以上が子供との家族旅行の回数を増やしたいと考えている。若年層では、年間国内宿泊観光旅行回数が少ない場合に旅行回数の増加意向が弱くなる傾向があるのに対し、家族層においては、現在の旅行の実施状況によらず、家族旅行に対する強いニーズが存在することが分かる(図I-2-1-26、図I-2-1-27)。
図I-2-1-25 家族層の国内宿泊観光旅行の減少理由

図I-2-1-26 家族層の旅行回数増加意向(子供との家族旅行)

図I-2-1-27 家族層の旅行回数増加意向(旅行回数別)

4)今後の取組の方向性
国内観光旅行市場において最大のシェアを占める家族旅行について、実施主体である家族層は、今後の旅行回数を増やしたいという意向を強く持っているが、教育費等の増加や所得の減少により国内宿泊観光旅行に行く経済的余裕を持ちにくいことや、小学生の子供と親の休日が合わせにくいこと等が、家族層における国内宿泊観光旅行の実施に影響を及ぼしていると推察される。
しかしながら、親自身の子供時代の旅行の経験・印象とその子供の旅行回数の関係について見ると、子供時代の旅行経験や印象が肯定的である程、その子供の国内宿泊観光旅行回数も増加する傾向がある。このため、子供にとって有意義な家族旅行を促進することは、将来的な家族旅行の振興のための重要な取組であると考えられる。
また、家族旅行の回数を増やすための条件として、宿泊費、交通費等の費用面以外にも、「混雑時(盆暮、ゴールデンウィーク等)を避けて旅行ができること」、「家族それぞれが楽しめること」といった課題が挙げられている。
このようなニーズに対応するため、家族層が利用しやすい価格帯の旅行商品の開発等により家族旅行に要する費用を軽減するとともに、年次有給休暇の取得の促進、学校休業の多様化・柔軟化等の取組を通じ、家族旅行をしやすい環境の整備を進めることが必要である。また、家族それぞれの旅行に対するニーズにきめ細かく対応できる観光地づくりや旅行商品の開発が期待される(図I-2-1-28、図I-2-1-29)。
図I-2-1-28 親の子供時代の旅行の経験・印象とその子供の旅行回数

図I-2-1-29 家族旅行の回数を年間に1回増やす条件

1)国内旅行の現状
60歳代の平成19年度の国内宿泊観光旅行回数は、1.86回(男性1.91回、女性1.81回)であり、国民1人当たり(1.50回)よりも0.36回多く、各年代との比較でも最も高い水準となっている。
一方、旅行回数の変化を見ると、60歳代の平成19年度の旅行回数は対前年度比較で0.33回(15.0%)減少しており、各年代の中で最も大きな減少幅となっている。
なお、参考として70歳代の国内宿泊観光旅行回数を見てみると、平成19年度は1.48回で国民1人当たりとほぼ同じであるが、対前年度比較では0.30回(16.9%)と大きく減少している(表I-2-1-30、表I-2-1-31)。
表I-2-1-30 60歳代の国内宿泊観光旅行回数の推移

表I-2-1-31 各年代の平成18年度と19年度の国内宿泊観光旅行回数の比較

2)旅行行動に影響を与える要因
団塊世代等については、退職後、これまでの退職世代よりも余暇活動を拡大することが予想され、国内旅行市場を牽引する層として期待されているが、団塊世代の一部が初めて60歳代となった平成19年度における国内宿泊観光旅行回数は、前述のとおり大きく減少している。
団塊世代等の国内宿泊観光旅行回数が期待に反して伸び悩む状況については、様々な角度からの分析が必要であるが、内閣府大臣官房政府広報室「国民生活に関する世論調査」によると、日常生活での悩みや不安を感じている人の割合は、50歳代、60歳代において他の年代と同様に増加傾向にあり、特に50歳代の割合が大きくなっている。また、50歳代、60歳代における悩みや不安の内容を見ると、「老後の生活設計」、「自分の健康」等を挙げる人の割合が大きく、団塊世代等に将来の生活や健康に対する不安が存在していることがうかがわれる。
このような将来に対する不安を背景に、国内宿泊観光旅行の実施に影響を与える経済的要因としては、団塊世代等において、貯蓄意欲が強くなる一方で消費意欲が盛り上がりにくくなっていることが考えられる。平成20年の貯蓄残高の減少理由を見ると、60歳代においては、定例的な収入の減少による貯蓄取崩しや、株式、債券価格の評価額の減少を挙げるものが多く、これらの要因が国内宿泊観光旅行の実施意欲に影響を与えている可能性がある。
また、時間的要因としては、定年延長を実施する企業の増加等により、団塊世代等の余暇時間が伸び悩んでいることが挙げられる(図I-2-1-32~図I-2-1-35、表I-2-1-36)。
図I-2-1-32 日常生活での悩みや不安

図I-2-1-33 悩みや不安の内容

図I-2-1-34 貯蓄現在高の推移・世帯主の年齢階級別

図I-2-1-35 貯蓄残高の減少理由・世帯主の年齢階級別(平成20年)

表I-2-1-36 一律定年制を定めている企業における定年年齢階級別企業数割合(平成17~20年)

3)今後の取組の方向性
一般的に定年を迎える者が多くなる60歳代は、退職後に余暇活動を拡大することが期待されているが、前述のとおり平成19年度の60歳代の国内宿泊観光旅行回数が落ち込むなど、定年の延長、景気減速による消費の手控え等を背景に、旅行回数は伸び悩む状況が続いている。
しかしながら、団塊世代等は、貯蓄現在高が高く、定年延長が行われたとしても、いずれは退職者となることから、国内旅行の主要な実施主体として旅行需要を牽引することが期待されている。
このような団塊世代等の国内旅行を促進するため、退職後は曜日にかかわらず多くの時間を余暇活動に充てることができるようになる団塊世代等の特徴を踏まえ、滞在型の旅行、平日旅行等に対応した観光地づくりに取り組むとともに、リピート需要を喚起していくため、団塊世代等の国内旅行に対する満足度を高めていくこと等が必要であると考えられる。また、定年後に増加すると考えられる夫婦旅行に対応した旅行商品の開発等が期待される。
国内旅行の主要な交通手段は自家用車であるが、団塊世代等については、加齢に伴い自家用車による旅行が困難になると考えられることから、ユニバーサルデザインの考え方に基づく交通機関の整備や旅行商品の開発など、旅行しやすい環境の整備をより一層進めていくことが必要である(図I-2-1-37)。
図I-2-1-37 旅行種別・年代別の利用交通機関(観光・レクリエーション旅行)(平成19年度)

1.(2)で見たように、国民の海外旅行について伸び悩む状況が続いていることを踏まえ、特に20歳代及び30歳代に焦点を当て、「平成20年度日本人の旅行行動に関する実態調査」、及び(社)日本旅行業協会「若者の海外旅行意識調査※」等に基づき、国民の海外旅行に関する動向と課題の分析を行った。
国民の海外旅行と国内宿泊観光旅行の実施率(1年間に1回以上旅行に行った人の割合)を比較すると、2008年の国内宿泊観光旅行の実施率が68.6%であるのに対し、2008年の海外旅行の実施率は16.8%にとどまっている(図I-2-1-38、図I-2-1-39)。
図I-2-1-38 2008年国内宿泊観光旅行回数

図I-2-1-39 2008年海外旅行回数

旅行実施率に差が生じる主な要因としては、海外旅行は、一般的に国内旅行より旅行費用が高く、旅行期間も長くなることや、言語や安心・安全面の問題等が考えられる。一方で、旅行実施の際に、国内旅行と海外旅行を比較検討するかという点については、約8割が「国内旅行と海外旅行は別のものなので比較検討しない」と考えていることから、海外旅行と国内旅行を単純に比較するのではなく、海外旅行の特性を踏まえつつ、旅行以外の余暇活動等も含めた調査・分析が必要であると考えられる。
また、「国内旅行と海外旅行は別のものなので比較検討しない」とする層について、国内旅行と海外旅行に対する志向を見ると、85.1%の回答は「今は国内旅行中心」としているが、「今後は海外旅行も考えたい」とする回答も約7割(68.8%)あることから、海外旅行に対しても強い関心が存在することが考えられる。
国内旅行と海外旅行を比較検討する場合に重視する点について見ると、「どちらが同程度の費用でより満足が得られるか」というコストパフォーマンスを重視する回答が最も多く、「単純にどちらの費用が安いか」という回答とともに経済面を重視する傾向が強い。経済面以外では、「どちらがスケジュールに合うか」という時間面を重視する回答が多い(図I-2-1-40)。
図I-2-1-40 国内旅行と海外旅行の比較検討

(社)日本旅行業協会「若者の海外旅行意識調査」においては、海外旅行の阻害要因について、「海外旅行の否定要因」、「海外旅行意向がある時の不満要因」等について分析を行っている。この分析によると、海外旅行を否定する要因として、「価値があるのかわからない」「環境の変化に対応するのが面倒」「地理・歴史・文化を知らない」等が挙げられている。
また、海外旅行に行きたいと思っている時の不満要因は、「旅行代金は高すぎる」「海外旅行の旅行代金はわかりにくい」等の旅行代金に関する要因が挙げられている(図I-2-1-41)。
図I-2-1-41 海外旅行意向に対する阻害要因

1)海外旅行の実施に影響を与える経済的要因
海外旅行の実施回数と世帯年収の関係について見ると、世帯年収が400万円未満の場合には、「海外旅行に行ったことはない」という回答が4割を超え、世帯年収400万円を境に海外旅行実施の有無に大きな違いが生じている状況が分かる。また、2回以上海外旅行を経験している者の割合は、世帯年収が高くなるほど増加している(図I-2-1-42)。
図I-2-1-42 世帯年収と海外旅行
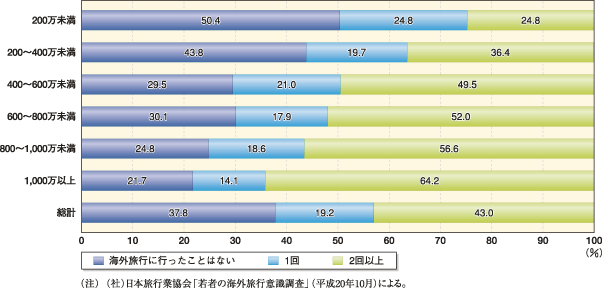
2)今後の海外旅行の実施意向
海外旅行の実施回数と今後の海外旅行の実施意向の関係について見ると、海外旅行の未経験者のうち2010年末まで海外旅行に「行く」、又は「おそらく行く」と回答した割合(17.0%)は、海外旅行の経験者の同様の回答割合(45.4%)の半分にも達しておらず、海外旅行については、経験の有無によって、海外旅行の実施意向に大きな違いが生じていることが分かる。
また、若者の海外旅行の実施に影響を与える一般的な理由として考えられる「安全や言葉に対する不安感」の影響について見ると、海外旅行の経験者においては「自分がそうだし、一般的にそのとおりだと思う」と回答した割合が、海外旅行の未経験者の半分未満となっていることから、海外旅行を経験することによって、安全や言葉に対する不安が小さくなる傾向があることがわかる(図I-2-1-43、図I-2-1-44)。
図I-2-1-43 2010年までの海外旅行の実施意向

図I-2-1-44 旅行低迷に対する意識

海外旅行を計画するきっかけについて見ると、20歳代及び30歳代前半の大学生・社会人においては、「資金ができると」という経済的要因を挙げるものが最も多く、「時間に余裕ができると」、「行きたいところが見つかると」、「誘いがあると」、「リフレッシュしたくなると」といった時間的・心理的要因が続いている。
また、「海外旅行には関心がないため計画しない」という回答が約3割を占めており、同様の回答が約5%である国内旅行に比べ、海外旅行をそもそも検討の対象として認識していない者が多いことがわかる。
前述のように、海外旅行については、その経験の有無が海外旅行の実施意向に大きな影響を与えている可能性があると考えられることから、特に20歳代から30歳代前半の男女の出国率が減少傾向にある近年の動向を念頭に置きつつ、国民の海外への関心を高めるための取組を一層進めていくことが必要である(図I-2-1-45、図I-2-1-46)。
図I-2-1-45 海外旅行に出かけるきっかけ

図I-2-1-46 国内宿泊観光旅行に出かけるきっかけ

※1 「旅行・観光消費動向調査」の国内の総旅行消費額から訪日外国人旅行の消費額を除いたもの。
※2 上記※1を基に算出。
※3 国内宿泊観光旅行は、観光・レクリエーションを主目的とするものを対象とし、出張・業務や帰省・知人訪問を主目的とするものは含まない。
※4 平成15年度から調査手法を変更し、国の承認統計として実施している「旅行・観光消費動向調査」の数値を採用しているため、それ以前との単純比較はできない。
|
※1 国土交通省観光庁「平成20年度日本人の旅行行動に関する実態調査」の概要 |
|
調査実施期間 |
:平成21年2月26~29日 |
|
調査方法 |
:インターネット調査(パネル調査) |
|
調査対象及び回収状況 |
:全国18,278名を対象に調査を実施。 |
また、対象のうち「現在の国内宿泊旅行回数」及び「5年前と比較した国内宿泊旅行回数の変化(選択肢:変わらない、かなり減った、減った、かなり増えた、増えた)」の質問に対して、「国内宿泊旅行回数が0~3回で変わらない」又は「国内宿泊旅行回数が減少した」と回答した者14,084名(全体の77.1%)の中から、「大学生」、「20~34歳社会人(子供なし)」及び「小学生の子供を持つ親」について、それぞれ1,030名(合計3,090名)を抽出し、追加調査を実施。
※2 20~29歳と設定。総務省「平成17年国勢調査」によると20~29歳の人口は約1,520万人で、全人口に占める比率は約12.1%である。
※3 小学生の子供のいる世帯と設定。
総務省「平成17年国勢調査」によると、団塊世代の人口は約674万人で全人口の約5.4%、60~69歳の人口は約1,590万人で全人口に占める割合は約12.6%である。
※ 調査を実施した平成21年2月までの1年間
※ 調査を実施した平成21年2月までの1年間
※ 調査を実施した平成21年2月までの1年間
※ 調査を実施した平成21年2月までの1年間
|
※ (社)日本旅行業協会「若者の海外旅行意識調査」 |
|
調査対象 |
:15~39歳の男女 |
|
調査実施期間 |
:平成20年7月23~25日 |
|
調査方法 |
:インターネットリサーチ |
|
有効回答数 |
:4,740サンプル(性別・年齢別(5歳毎)に各470サンプル) |
|
|