平成20年度観光の状況
第II部 平成20年度の観光の状況及び施策
第1章 観光の現状
第1節 国民の観光の動向
平成20年度における国民1人当たりの国内宿泊観光旅行回数は、1.55回と推計され、対前年度比で3.3%増となっている。また、国民1人当たりの国内宿泊観光旅行宿泊数は、2.44泊と推計され、対前年度比0.8%増となっている(図II-1-1-1)。
図II-1-1-1 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移
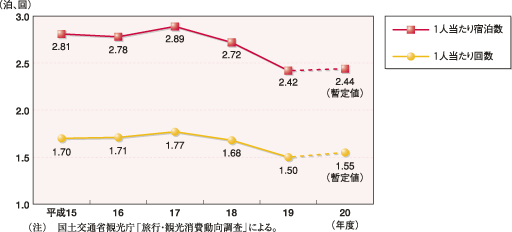
平成19年1月より1)全国統一基準により、2)すべての都道府県を対象に、3)従業者数10人以上のホテル、旅館及び簡易宿所のすべての宿泊者数等を調査する「宿泊旅行統計調査(承認統計)」を開始した。この調査結果によると、平成20年1月から12月における延べ宿泊者数は全体で3億615万人泊であり、このうち、日本人延べ宿泊者数は全体で2億8,387万人泊であった。
これを月別に見ると8月が3,117万人泊と一番多く、1月が2,067万人泊と一番少なくなっている(図II-1-1-2)。また、8月以降は、景気減速の影響を受けて対前年同月比5ヵ月連続でのマイナスとなっている。
図II-1-1-2 月別日本人延べ宿泊者数(平成20年)
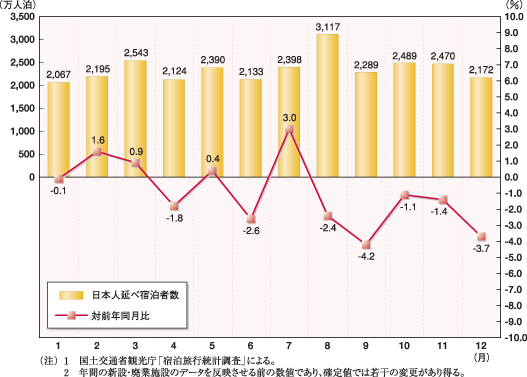
平成20年の海外旅行者数は、約1,599万人となった。燃油サーチャージの値上げや、世界的な金融危機による景気後退の影響を受けて全体的に伸び悩み、前年に比べると約131万人減少し、対前年比7.6%減であった(図II-1-1-3)。また、月別にみると、2008年は全ての月において前年同月比で減少した(図II-1-1-4)。
なお、平成18年における諸外国の海外旅行者数を比較してみると、日本の17,535千人は世界で13位となり、前年の12位より1ポイント下降した(図II-1-1-5)。
図II-1-1-3 日本人海外旅行者数の推移
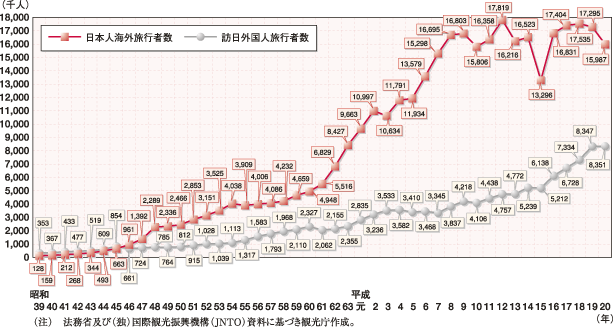
図II-1-1-4 海外旅行者数の月別推移(平成20年)
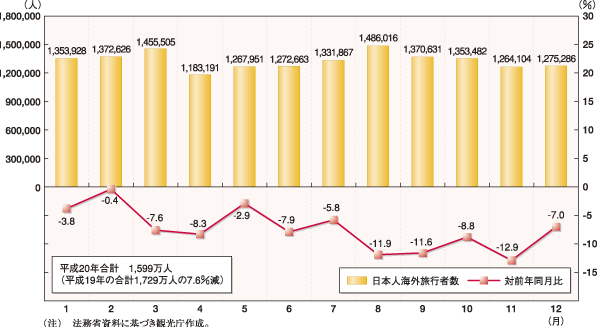
図II-1-1-5 諸外国の海外旅行者数国際ランキング(平成18年)
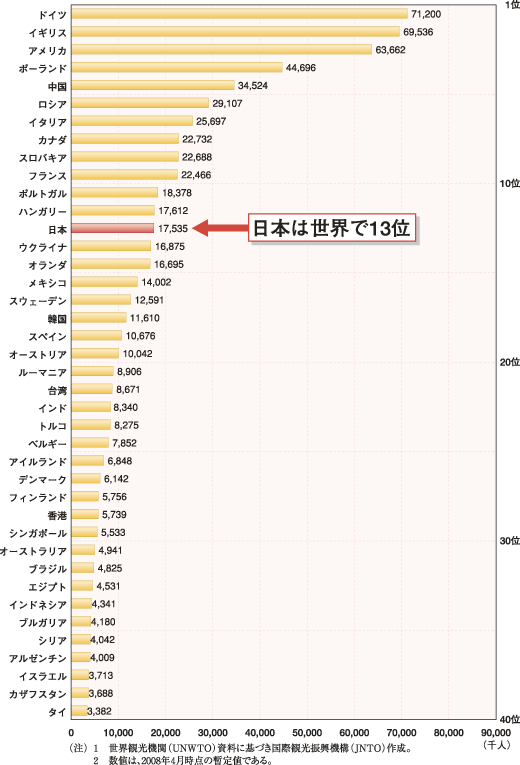
旅行日数を滞在期間6月以内の帰国日本人に関してみると、平成20年は、5日以内が60.2%、10日以内が25.4%と前年に比べ5日以内、10日以内の人の比率がわずかに減っている(図II-1-1-6)。
性別構成をみると、男性は全体の56.9%にあたる910万人、女性は全体の43.1%にあたる689万人であり、男性の比率が3年連続でわずかに増加した(図II-1-1-7)。
年齢階層別にみると、男性の場合、40歳代が全体の23.3%に当たる212万人と最も多く、次いで30歳代の同21.2%にあたる193万人の順となっているのに対し、女性の場合は20歳代が全体の23.2%にあたる160万人と最も多く、次いで30歳代が同21.0%にあたる145万人となっている(図II-1-1-8)。
図II-1-1-6 海外旅行者の滞在期間比率推移
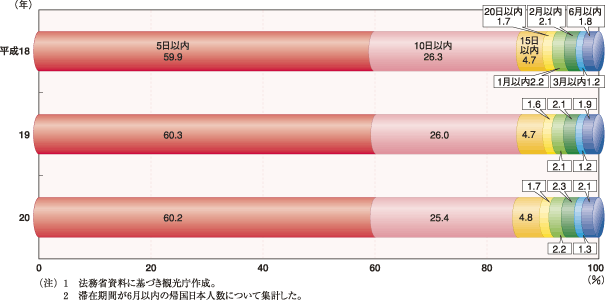
図II-1-1-7 海外旅行者の性別構成比の推移
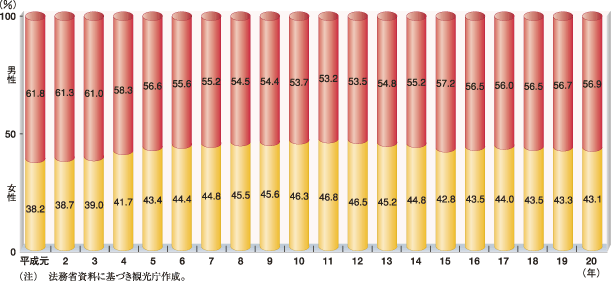
図II-1-1-8 海外旅行者の性別・年齢階層別推移
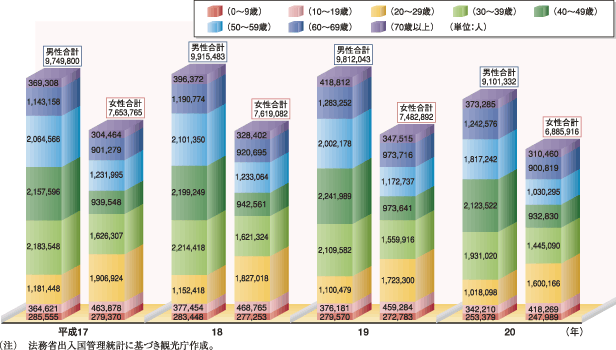
海外旅行者の出国時の輸送手段をみると、総数1,599万人のうち、全体の98.8%にあたる1,579万人が航空機を利用している。空港別利用状況では、成田国際空港利用がトップで、出国日本人全体の54.7%にあたる875万人を占め、次いで関西国際空港利用が20.9%にあたる334万人となっている。海上輸送は、20万人で、全体の1.2%となっている(図II-1-1-9)。
図II-1-1-9 出国日本人の旅客輸送の状況(平成20年)
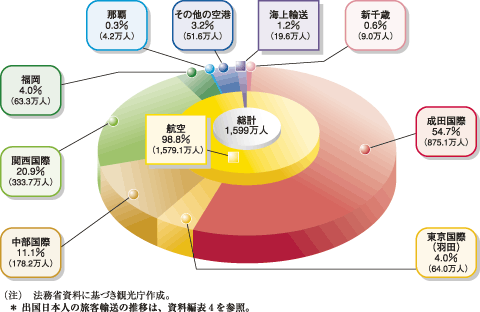
今後の生活で重点をおきたい分野は「レジャー・余暇生活」を挙げるものが34.4%と最も多いものの、近年は減少傾向にある。以下「所得・収入」、「食生活」と続いている(図II-1-1-10、図II-1-1-11)。
図II-1-1-10 今後の生活の力点
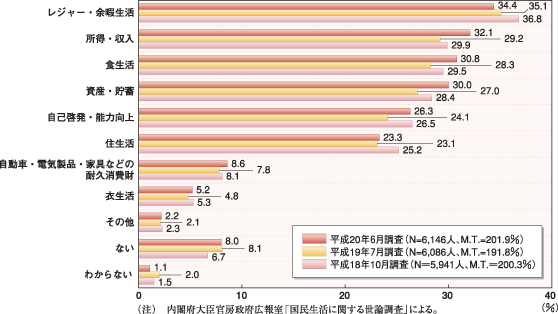
図II-1-1-11 今後の生活の力点(推移)
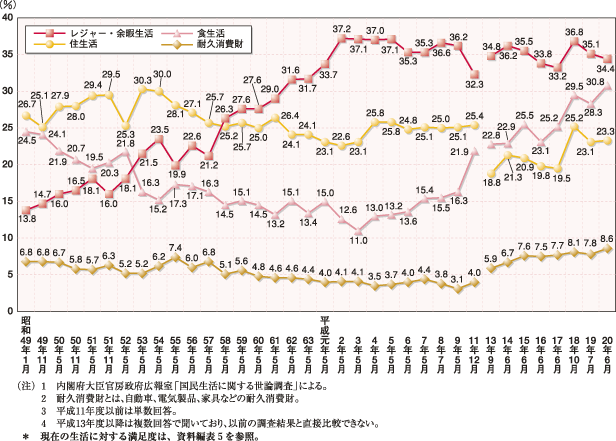
余暇活動の潜在需要を参加希望率から実際の参加率を引いた数値でみると、第1位は性・年齢を問わず「海外旅行」が最も高く、第2位が「国内観光旅行(避暑、避寒、温泉等)」となっている。
このように、観光旅行に対する潜在需要は多様な余暇活動の中で依然として高いことがうかがえる(図II-1-1-12)。
図II-1-1-12 余暇活動の潜在需要(上位10種目)
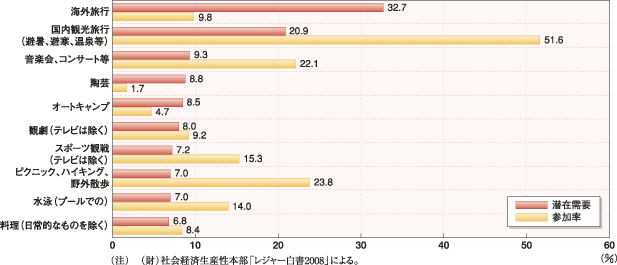
宿泊費やパック旅行等の旅行関連の支出の推移をみると、支出額及び自由時間関連支出に占める割合が、前年に比べてわずかに減少している(図II-1-1-13)。
図II-1-1-13 旅行関連の支出の自由時間関連支出等に占める割合の推移
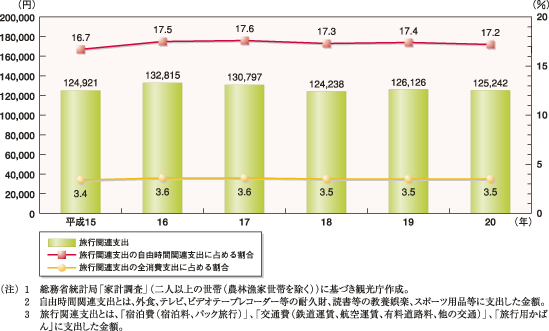
|
|