平成20年度観光の状況
第II部 平成20年度の観光の状況及び施策
第1章 観光の現状
第2節 外国人の訪日旅行の動向
「宿泊旅行統計調査」の調査結果によると、平成20年1月から12月における外国人延べ宿泊者数は全体で2,227万人泊(前年比1.7%減)であった。
また、月別外国人延べ宿泊者数を見ると4月が224万人泊と一番多い(図II-1-2-1)。対前年同月比を見ると、7月までは対前年同月比増を記録していたが、8月以降は、世界的金融危機の影響や円高の急進の影響を受け、対前年同月比減へと転じている。
国・地域別にみると、1位は韓国380万人泊(外国人延べ宿泊者数全体に占める割合17.1%)、2位は台湾371万人泊(同16.6%)、3位はアメリカ276万人泊(同12.4%)、4位は中国247万人泊(同11.1%)、5位は香港184万人泊(同8.3%)となり、これら5カ国・地域で全体の65.5%を占めた(図II-1-2-2)。
図II-1-2-1 月別外国人延べ宿泊者数(平成20年)
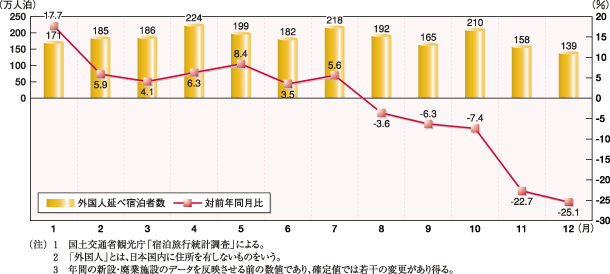
図II-1-2-2 国・地域別外国人延べ宿泊者数(平成20年)
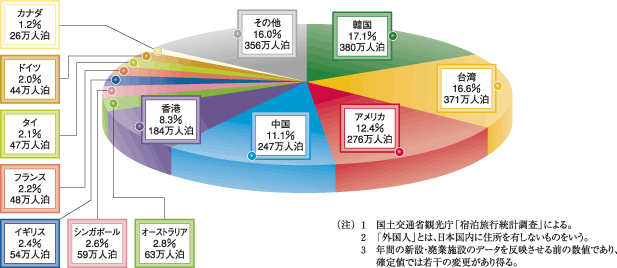
都道府県別外国人延べ宿泊者数をみると、1位の東京都が750万人泊(外国人延べ宿泊者数全体に占める割合33.7%)、2位の大阪府が256万人泊(同11.5%)、3位の北海道が213万人泊(同9.6%)で、上位3都道府県で全体の1/2以上を占めている(図II-1-2-3)。
図II-1-2-3 都道府県別外国人延べ宿泊者数(平成20年)
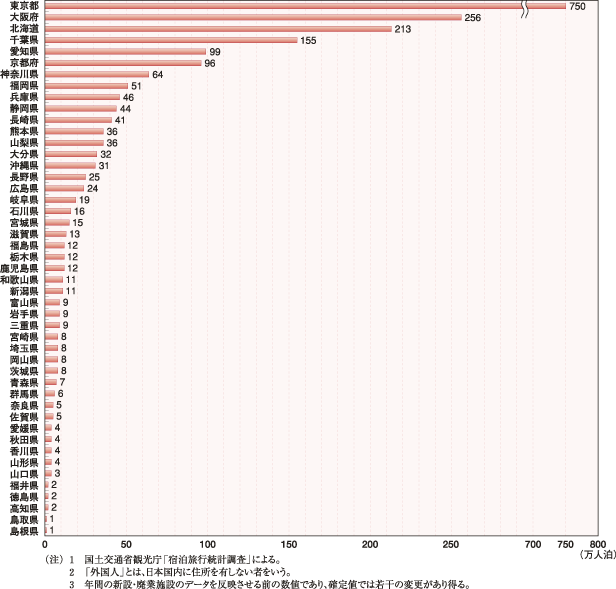
また、都道府県別外国人延べ宿泊者数を国・地域別に構成比で表すと図II-1-2-4のとおりとなり、北海道・北陸には台湾から、首都圏・京都にはアメリカから、九州には韓国からの旅行者が多数宿泊していることがうかがえる。
都道府県別延べ宿泊者数の構成比を見ると、外国人延べ宿泊者数の構成比の割合が高いのは、1位が東京都の20%、2位が大阪府の16%となった。また、県外からの日本人宿泊者数の構成比の割合が高いのは、1位の沖縄県が88%、2位が香川県の85%であった(図II-1-2-5)。
国・地域別に都道府県別に外国人の延べ宿泊者数構成比を見ると、台湾からの訪日客は北海道、他の国からの訪日客は東京都にそれぞれ最も宿泊していた(図II-1-2-6)。
図II-1-2-4 都道府県別、国・地域別外国人延べ宿泊者数構成比(平成20 年)
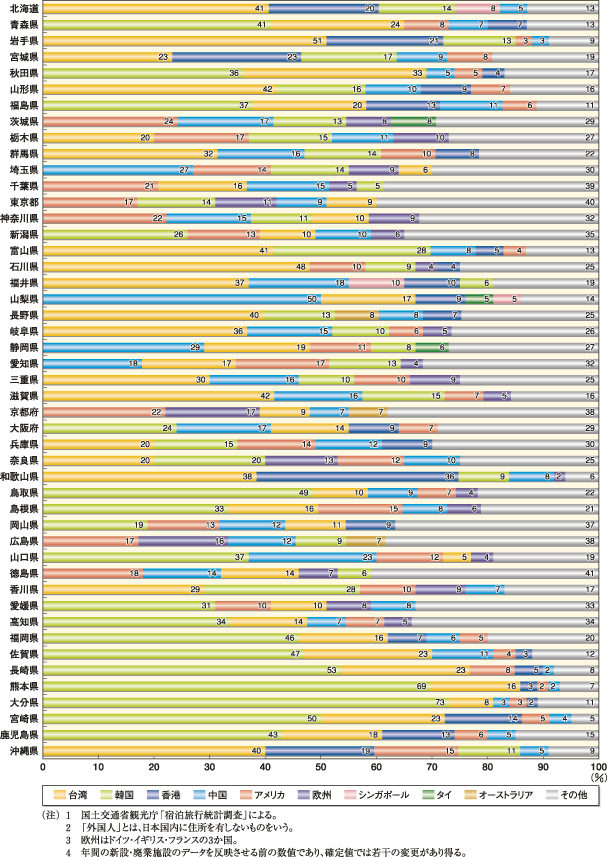
図II-1-2-5 県内・県外・外国人延べ宿泊者数構成比(平成20年)
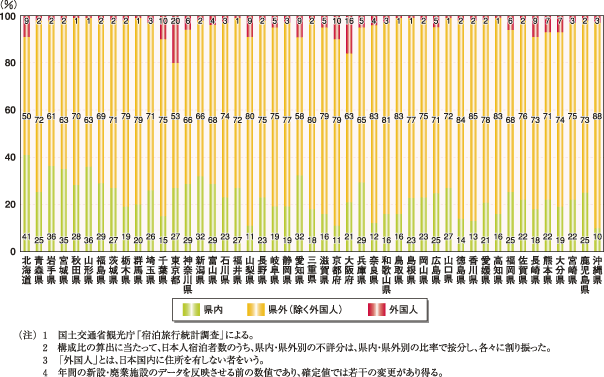
図II-1-2-6 国・地域別、都道府県別外国人延べ宿泊者数構成比(上位5都道府県)(平成20年)
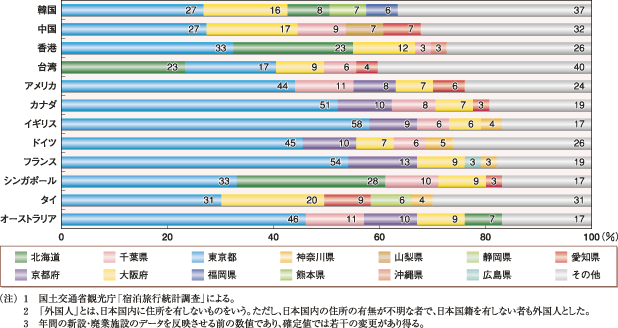
平成20年の訪日外国人旅行者数は、835万人(前年比0.05%増)となり、下半期に世界的な金融危機による景気後退や、円高の急進の影響を受けつつも、過去最高値を達成した(図II-1-2-7)。
州別にみると、アジアが615万人で全体の73.7%を占め、次いで北アメリカが97万人(11.6%)、ヨーロッパが89万人(10.6%)、オセアニアが28万人(3.3%)の順となっている(図II-1-2-8)。
図II-1-2-7 訪日外国人旅行者数の推移
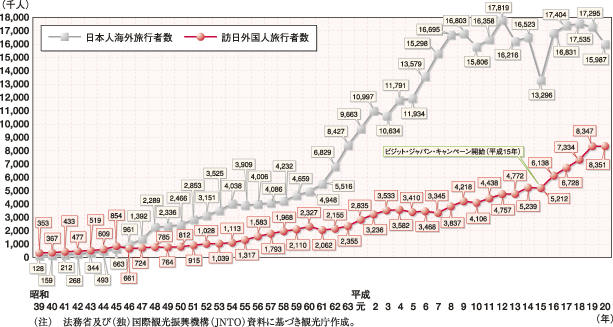
図II-1-2-8 上位12か国 州別・国・地域別訪日外国人旅行者の割合(平成20年)

国・地域別に経年変化をみると、韓国が8.4%減の238万人と大きく減少したものの、10年連続で首位となった。以下、台湾139万人(0.4%増)、中国100万人(6.2%増)、アメリカ77万人(5.8%減)、香港55万人(27.3%増)の順となっており、初の100万人を達成した中国や、香港などでは順調な伸びを示した(図II-1-2-9)。
しかし、外国人旅行者受入れ数の国際ランキングを比較できる平成19年でみると、日本の835万人は世界で28位、アジアの中でも6位となり、順調に順位を上げてきているものの、中国、香港、マレーシア、タイ、マカオといった国・地域には及ばない状況が続いている(図II-1-2-10)。
図II-1-2-9 過去10年における上位14か国・地域からの訪日外国人旅行者数の推移
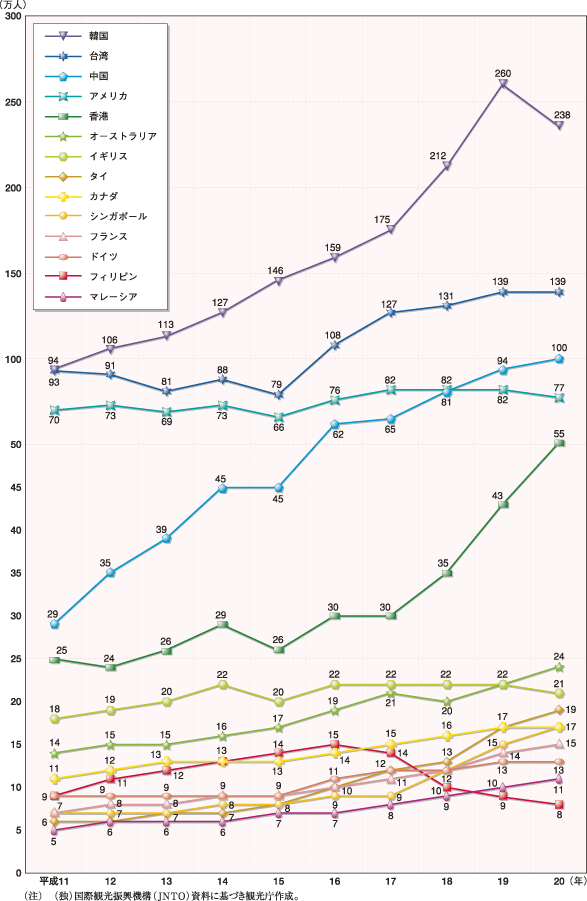
図II-1-2-10 諸外国の外国人旅行者受入れ数の国際ランキング(平成19年)
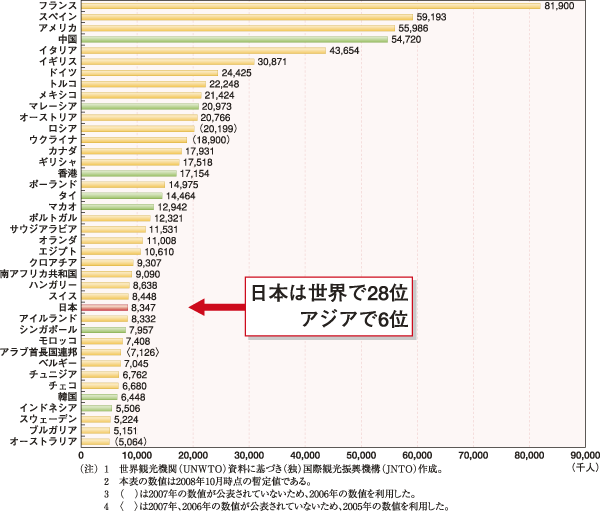
月別にみると、7月までは対前年同月比増を維持していたが、8月以降対前年同月比減に転じ、特に11月、12月には大幅な減少となった(図II-1-2-11)。
図II-1-2-11 訪日外国人旅行者の月別推移(平成20年1月~平成20年12月)
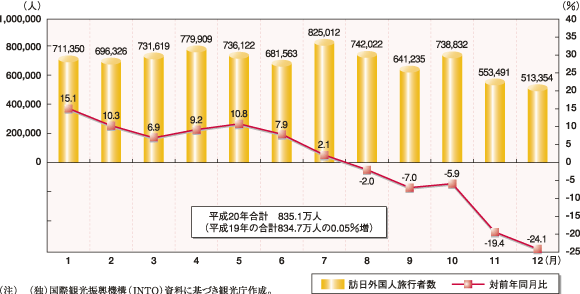
訪日外国人旅行者835万人を目的別でみると、観光目的(一時上陸客含む)は、605万人(1.6%増)、業務その他の目的が230万人(3.8%減)となり、訪日外国人旅行者全体に占める比率は、それぞれ72.4%、27.6%となった(図II-1-2-12)。
図II-1-2-12 目的別訪日外国人旅行者数(平成20年)
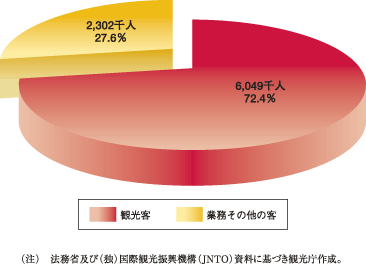
一方、(独)国際観光振興機構(JNTO)「JNTO訪日外客訪問地調査2007/2008」によれば、平成20年の訪日外国人の目的を、居住国・地域でみると、香港、台湾、韓国等で観光の比率が高く、ドイツ、アメリカ等では商用の比率が高い(図II-1-2-13)。
図II-1-2-13 国籍別訪日目的比率
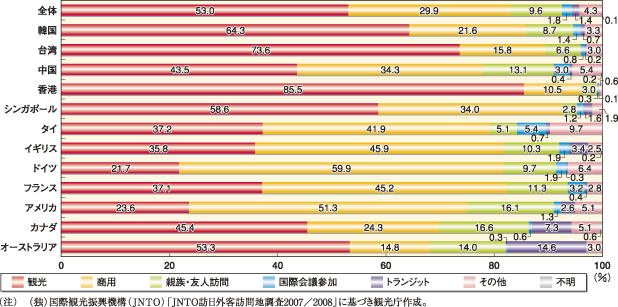
滞在期間については、平成20年は前年に比べて5日以内の比率が減り、70.7%となった。一方、10日以内、15日以内の比率については、前年に比べて増加し、17.3%、5.4%となった(図II-1-2-14)。
図II-1-2-14 訪日外国人旅行者の滞在期間比率推移
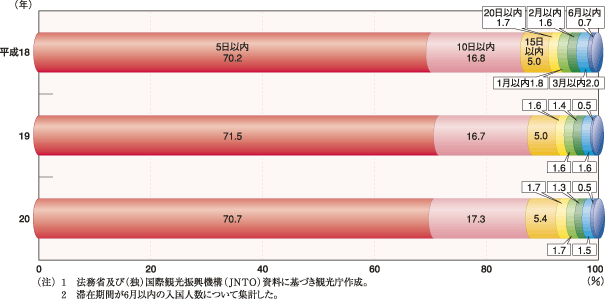
欧米ではガイド付団体ツアーの割合は非常に小さく、個人で航空券等を個別手配する割合が大きい。アジア諸国では逆にガイド付き団体ツアーの割合が高い傾向にある(図II-1-2-15)。
図II-1-2-15 国籍別旅行形態比率
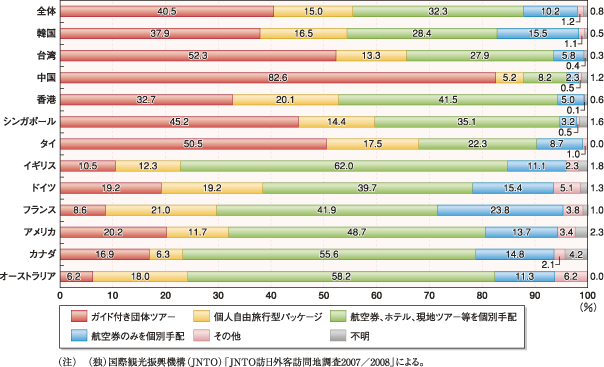
入国の際の輸送手段をみると、総数915万人※のうち、全体の92.4%にあたる845万人が航空機を利用している。空港別利用状況では、成田国際空港利用割合が減少し訪日外国人旅行者全体の46.8%となっており、次いで関西国際空港利用が17.9%となっている。また、東京国際空港(羽田空港)は、5.8%となり、前年に比べ増加している。
海上輸送は、訪日外国人旅行者全体の7.6%にあたる70万人が利用している(図II-1-2-16)。
図II-1-2-16 入国外国人の旅客輸送の状況(平成20年)
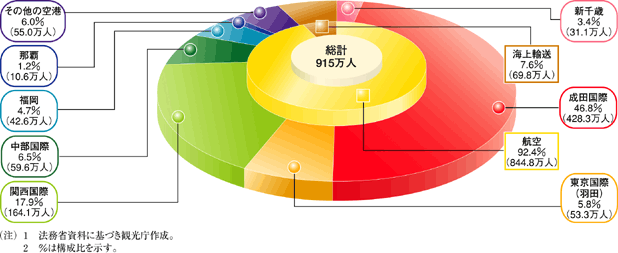
我が国における国際会議の開催件数についてみると、平成15年には247件とアジアにおいて首位であったが、平成18年には166件に減少した。しかし、平成19年には448件と大きく伸ばし、アジア2位(世界5位)となった(図II-1-2-17)。
なお、平成19年に従来の国際会議の統計基準が緩和されているが、「観光立国推進基本計画」に定められた目標値における基準に照らすと、平成19年の国際会議開催件数は216件と推計される。
図II-1-2-17 国別・国際会議開催件数の推移
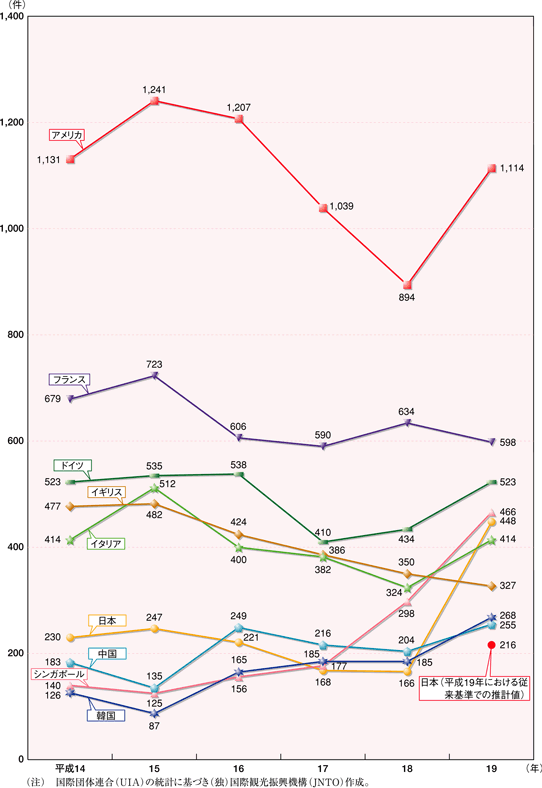
※ 訪日外国人旅行者数(平成20年:835万人)は、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者(当該国発行の旅券を所持した入国者)から日本に居住する外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者の数であるため、本図の数値とは、一致しない。
|
|