平成20年度観光の状況
第II部 平成20年度の観光の状況及び施策
第2章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成
国は、貴重な国民の財産である文化財を保護するため、「文化財保護法」に基づき、建造物、絵画、彫刻等の有形文化財を国宝、重要文化財や登録有形文化財に、演劇、音楽、工芸技術等の無形文化財を重要無形文化財に、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等の民俗文化財を重要有形・無形民俗文化財や登録有形民俗文化財に、遺跡、名勝地、動植物等を史跡、名勝、天然記念物や登録記念物に指定・登録するほか、棚田や用水路等を重要文化的景観に、歴史的な集落・町並みを重要伝統的建造物群保存地区として選定するなど、その適切な保存・活用を図っている。
特に、地域の歴史的・文化的シンボルである史跡等については、保存のための整備、建物復元・遺構の露出展示やガイダンス施設の設置といった活用のための整備を行い、その魅力を高めることで、地域の観光資源として活用されている。
また、我が国の歴史を理解する上で極めて重要な街道、水路等のうち往時のたたずまいを残しているものを「歴史の道」として選び、それに沿う地域を一体のものとして保存・整備し、活用を図っている。
そのほか、公私立の博物館や民俗資料館等において、国宝・重要文化財や地域の民俗文化財等の保存・活用を図っている。
昭和47年(1972年)に開催された第17回ユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」により、我が国では日本の文化財を世界遺産へ登録するとともに、国際的な世界遺産の保護に関する取組を進めている。
平成20年2月には国立西洋美術館(本館)を含む「ル・コルビュジエの建築と都市計画」について、日本、フランス等6か国共同で推薦書を提出した。
国立西洋美術館(本館)(C)国立西洋美術館

募金活動や寄付により歴史的価値を有する文化遺産や良好な自然環境を有する土地等を取得し、その適正な管理、保全及び活用を図るナショナルトラスト運動を行う法人に対し、寄付について税制優遇措置を講じるほか、ナショナル・トラスト活動を始めようとする団体等に向けた手引きの改訂、これまでの運動の成果及び課題の整理に関する調査等、普及啓発のための施策を講じた。今後もナショナルトラスト運動推進に関する支援を行っていくこととする。
(財)日本ナショナルトラストにおいては、旧安田楠雄邸(東京都文京区)ほか保有資産の一般公開を行った。また、平成20年5月に「地域遺産の活用に向けた今後の体制の在り方検討委員会」において取りまとめられた報告書の提言に基づき、具体的なアクションプランの策定を行ったほか、中期計画の策定について検討を行うなど、ナショナルトラスト運動を推進していくための基盤整備を図ったところであり、それを積極的に支援した。
(社)日本ナショナル・トラスト協会が主催した「第26回ナショナル・トラスト全国大会(東京)」には全国各地の関係者約150名が参加し、シンポジウム等を通じて自然環境保全活動等の一層の推進が図られた。
イベント開催による保護資産の活用(旧安田楠雄邸における「花嫁のれん展」の開催(平成20年10月))

北海道斜里町(知床100平方メートル運動)

| 2 歴史的風土に関する観光資源の保護、育成及び開発 |
| (1) 歴史的風土の保存による魅力ある国づくりの推進 |
京都市、奈良市、鎌倉市等の古都における歴史的風土を保存するため、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」等に基づき、宅地の造成等の行為を規制するとともに、「古都保存統合補助事業」により、歴史的風土特別保存地区等における地方公共団体による土地の買入れや歴史的風土の保存及び利用のための施設整備の機動的な実施を推進する。また、奈良県高市郡明日香村においては、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園飛鳥区域の整備を推進するとともに、明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金の措置による歴史的風土を創造的に活用した観光産業の育成や、観光と連携した農林業の振興を今後も引き続き実施することとしている。
| (2) 地域の観光の拠点となる都市公園の整備の推進 |
観光資源となる歴史的建造物、樹林等の地域の歴史・文化・自然的資産及び景観形成上優れた建造物を生かし、観光振興の拠点となる都市公園の整備を推進した。また、都市における樹林地の保全や湿地・干潟の再生・創出等により、多様な生物の生息生育基盤や身近な自然と触れ合う場を確保するなど、自然と共生する魅力的な都市の実現を図るため、自然再生緑地の整備を推進した。
我が国固有の優れた文化的資産の保存・活用等のため国が設置する国営公園については、平成20年度から整備着手した国営飛鳥・平城宮跡歴史公園平城宮跡区域を始め、17公園の整備を推進した。また、首里城の復元を行っている国営沖縄記念公園を始め、16公園が開園され、平成20年度は全国で約3,000万人が利用しており、これらの施策を今後も引き続き実施することとしている。
歴史上重要な幹線道路として利用され、特に重要な歴史的・文化的価値を持つ道路を対象に選定した「歴史国道」について、その保全・復元・活用を図り、併せて地域からの情報発信を行うことにより、歴史文化を軸とした魅力的な地域づくりを推進しており、平成20年度においては6箇所で歩道の整備や道路の美装化等を実施した。
重要文化財に登録予定の白岩砂防えん堤(富山県立山市 常願寺川水系)
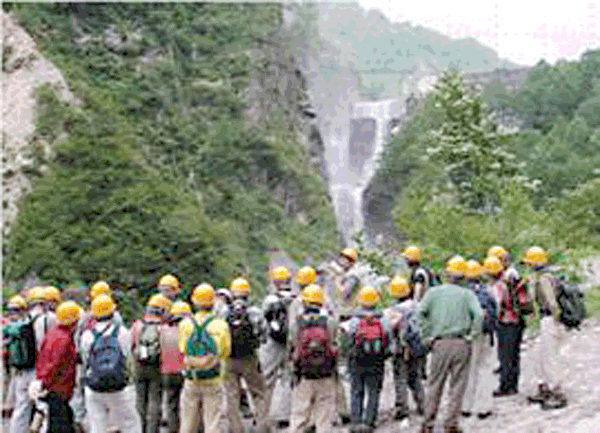
白岩砂防堰堤(富山県)など、登録有形文化財や登録記念物に登録されている歴史的価値を有する砂防関係施設について、適切な維持管理、周辺の一体的整備等を実施した。今後は、このような施設を地域の観光資源の核と位置付け、新たな交流の場の形成に資する取組を推進していく。
登録有形文化財に登録されている勝沼えん堤(山梨県甲州市)

| 3 優れた自然の風景地に関する観光資源の保護、育成及び開発 |
自然公園は、我が国の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを目的として「自然公園法」に基づき指定される公園で、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園の3種類がある。これらの公園は我が国の主要な観光地としても重要な役割を果たしている(図II-2-2-1)。
1)公園計画の見直し等
自然公園の保護及び適正な利用を図るため、公園の区域や計画を定めており、おおむね5年を目途に見直し作業を実施している。平成20年度には、鳥海国定公園及び琵琶湖国定公園において公園区域及び公園計画の見直しを行っており、今後とも全国的な見直しの作業を進めることとしている。
2)保護と管理
国立・国定公園の優れた自然の風景地のうち、特にその風致の維持を図る必要のある地域を、特別地域として指定し、各種一定の行為を規制している。
国立・国定公園の特別地域の中でも、公園の核心的な景観地については、「特別保護地区」として指定し、最も厳しい保護規制を行っている。その面積は、全国立公園面積の13.2%、全国定公園面積の4.9%である。また、我が国の周辺海域には、熱帯魚、サンゴ、海草等の海中生物を主体とする優れた海中景観が存在する。このため、海中公園地区制度が設けられ、その保護と適正な利用が図られている(表II-2-2-2、表II-2-2-3)。
国立・国定公園内で自然の風景地の保護と適正な利用を図ることを目的として、公益法人や特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という)を、その申請により公園管理団体として指定し、自然の風景地の管理、公園利用施設の維持管理、公園内の自然情報の収集・提供等に係る市民等の自発的な活動を推進している。平成20年度末までに、国立公園(知床国立公園等)で4団体を指定している。
さらに保護・管理のため以下の事業を実施した。
1)
国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、野生動植物の保護、里地里山の保全、サンゴを食害するオニヒトデの駆除等の「国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業」を行っている。
2)
8月第1日曜日の「自然公園クリーンデー」に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行うなど、関係地方公共団体等と協力し清掃活動を行った。
3)
さらに、(財)自然公園財団を始めとする関係機関により、自然公園内での歩道、便所、休憩所等の公共的施設の清掃、補修のほか、利用最盛期に集中する自動車の整理、美化清掃活動、公園施設等の維持管理、利用者に対する自然保護思想の普及啓発等の事業が行われている。
3)乗入れ規制地区の指定等
「自然公園法」により、国立公園又は国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域においては、野生動植物の生息・生育環境への被害を防止するため、スノーモービル、オフロード車あるいはモーターボート等の乗入れが規制されている。
また、国立公園内においては、「国立公園内における自動車利用適正化要綱」に基づき、地方環境事務所、地元警察署等で構成する連絡協議会において、道路交通環境に応じた規制方法を検討し、一般車両通行止め等の交通規制を行って、観光地の交通安全の確保、環境保全に努めている。
このほか、吉野熊野国立公園の西大台地区を利用調整地区に指定し、原生的な自然を有する地域を一定のルールとコントロールの下で持続的に利用するため、立入り人数の調整等を行っている。
図II-2-2-1 日本全国の国立・国定公園の配置図
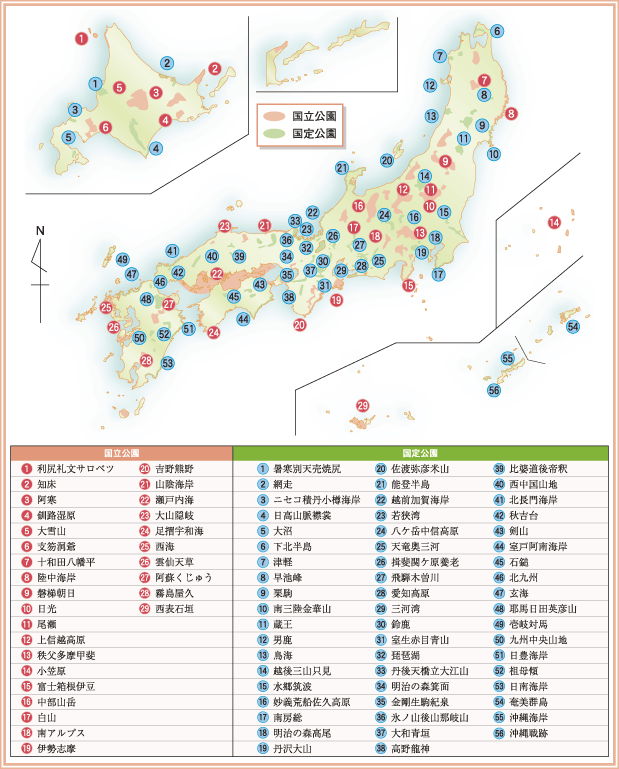
表II-2-2-2 自然公園の地域別面積
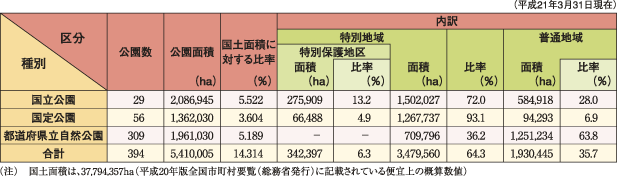
表II-2-2-3 国立・国定公園の海中公園地区
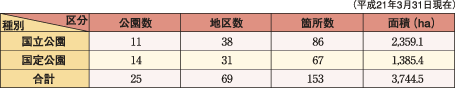
4)国立・国定公園における利用のための施設の整備
自然環境の保全に配慮しつつ、自然との触れ合いを求める国民のニーズにこたえ、安全で快適な利用を推進するため、平成20年度には全国29の国立公園において、国立公園の主要な入口における情報提供施設、山岳地域の適正な利用を推進するための登山道、利用拠点における良好な景観形成、その他利用の基幹となる施設の整備を進めるとともに、失われた自然を取り戻すための自然再生事業を実施した。
また、国定公園においては、自然との触れ合いの場の整備や自然環境の保全・再生を推進するため、平成20年度には、36都道府県に「自然環境整備交付金」を交付した。
5)長距離自然歩道の整備
自然公園や文化財を有機的に結ぶ長距離自然歩道について、平成20年度には東北、首都圏、東海、中部北陸、近畿、中国、四国、九州の長距離自然歩道において、四季を通じて安全で快適に利用できるように整備を進めた。長距離自然歩道の計画総延長は約26,000kmに及んでおり、平成19年には約6,000万人が長距離自然歩道を利用した。
6)利用者への指導等の推進、情報発信
国立・国定公園の保護と適正な利用のため、自然公園指導員約3,000名を委嘱し、利用者に自然保護思想や利用マナーの普及啓発、安全利用等に関する指導等の推進を図った。また、地方環境事務所等において約1,800名のパークボランティアの養成及びその活動に対する支援を全国25国立公園等40地区で実施した。
世界遺産条約に基づき、平成21年2月現在で、3件の世界自然遺産が登録されている(表II-2-2-4)。
表II-2-2-4 日本の世界自然遺産
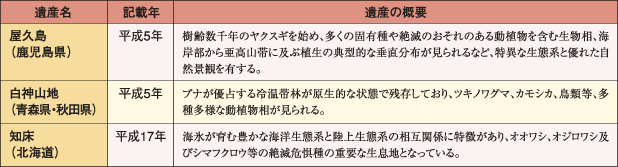
屋久島、白神山地、知床の世界自然遺産については、入山者数の調査や入山者の増加に対応した保全対策を実施するなど、保護・管理を行った。また、知床については、適正な保全の拠点施設として、調査研究、モニタリング、情報収集・管理・提供、普及啓発、人材育成等の機能を有する知床世界遺産センター等を整備した。
一方、世界遺産暫定一覧表に記載された小笠原諸島については、関係省庁・地方公共団体等が連携し、推薦登録に向けた課題である外来種対策を推進した。
| (3) 優れた自然の風景地を生かした地域づくりの推進 |
1)自然保護思想の普及
1)
「自然に親しむ運動」等を通じて、自然と触れ合う各種活動を実施したほか、「平成20年度自然公園ふれあい全国大会」を平成19年8月に新たな国立公園として指定された尾瀬国立公園において、環境省と関係4県の連携により開催した。
2)
小中学生に自然保護の大切さを学ぶ機会を提供する「子どもパークレンジャー」を実施した。
3)
「ラムサール条約湿地」を33箇所から37箇所に増やし、湿地の保全と賢明な利用を推進するとともに、水鳥湿地センター等において、普及啓発等を行った。
2)森林等の観光への活用
森林環境教育、健康づくり等の森林利用に対応した多様な森林の整備を推進するため、「森林空間総合整備事業」を実施し、教育関連施設・健康増進施設等と連携を図った森林の整備を行った。また、風景等が優れ、自然探勝、ハイキング、キャンプ等の森林レクリエーション利用に供すること等を目的とする森林については保健保安林として、名勝、旧跡の風致の保存を目的とする森林については風致保安林として、平成20年3月末現在、合わせて73万haを指定している。さらに、観光地の周辺の森林において、山崩れ、雪崩等の災害を防止するため、周辺の景観に配慮しつつ、治山事業等を実施し、安全の向上と併せて観光資源の資質向上に寄与した。
国有林野では、自然休養林等の「レクリエーションの森」を人と森林とのふれあいの場として積極的に提供した。また、国民による森づくり活動の場を提供する「ふれあいの森」、学校等による体験活動・学習活動の場を提供する「遊々の森」の設定・活用を推進した。このほか、優れた自然環境を有する森林については、保護林として設定あるいはその拡充を行い、適切な管理を行った。
木曽御岳自然休養林

3)海の観光への活用
生態系や自然景観等周辺の自然環境に配慮した海岸整備を行うエコ・コースト事業を19箇所で実施した。今後も引き続き実施することとしている。
4)生物多様性の保全と持続可能な利用
生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めた「生物多様性基本法」が平成20年5月に成立した。
5)北海道の美しい自然景観の観光への活用
北海道では地域の活動団体が主体となり、行政と連携し、「美しい景観」「活力ある地域」「魅力ある観光空間」づくりを行う「シーニックバイウェイ北海道」を推進している。平成20年度には新たに「萌える天北オロロンルート」が加わり、全道の7ルートにおいて、沿道の花植え、清掃活動、ビューポイントの整備、情報発信等様々な活動が展開されている。
「萌える天北オロロンルート(北海道苫前町)」

大規模自転車道の整備を行うとともに、川の親水施設、港湾緑地等とサイクリングロードの連携を始め、自転車と他の交通機関の連携を強化する各種施策を総合的に推進することにより、全国15箇所の「サイクルツアー推進モデル地区」においてサイクリングツアーを振興し、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図っており、今後も引き続き実施することとしている。
歩きやすさに十分配慮しつつ、周辺景観や地域の個性を生かした歩行者専用道路等を整備する「ウォーキング・トレイル事業」として、休憩施設やデザイン等を工夫した案内標識、来訪者の発着拠点となる駐車場等を整備している。
平成21年度は6箇所において、歩行者専用道路の整備及びベンチ等の休憩施設の整備等を実施しており、今後も引き続き実施することとしている。
| 4 良好な景観に関する観光資源の保護、育成及び開発 |
国際競争力の高い魅力ある観光地の形成のため、「景観形成総合支援事業」により、地域の景観上重要であって特に交流人口の拡大の効果が大きく見込まれる景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の保全活用を中心とした取組を支援している。
農村景観の保全については、景観法に基づく「景観農業振興地域整備計画」の策定を通じ、地域住民が主体となって景観と調和の取れた営農条件の確保を図るとともに、農村景観の保全の取組や、その達成に向けた措置を支援している。
また、地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないものである文化的景観について、特に重要なものとして15件の重要文化的景観の選定を行うとともに、全国各地に所在する文化的景観に関する調査、保存計画策定、整備や普及・啓発事業に対し補助を行っている。
今後も、これら取組を引き続き行うこととしている。
良好な都市環境の形成を図るため、「都市緑地法」に基づき、都市計画に特別緑地保全地区を定めている(平成20年3月末現在398地区約5,561ha(近郊緑地特別保全地区を含む))。これらの地区において、宅地の造成等の行為を規制することで自然的環境の保全を図るとともに、「緑地保全等統合補助事業」等により、地方公共団体による土地の買入れや保全利用のための施設整備の機動的な実施を支援した。
山麓斜面に市街地が近接している神戸市等において、景観に配慮した砂防関係施設等の整備を実施するとともに、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を保全・創出する取組を行っており、今後も引き続き実施することとしている。
| 5 温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発 |
平成20年3月末現在における全国の温泉ゆう出源泉数は、28,090箇所(うち自噴するもの5,097箇所、動力によるもの14,108箇所、未利用のもの8,885箇所)、ゆう出量は1日換算約403万トンに及んでいる。
また、温泉地は全国に3,139箇所あり、温泉を利用する宿泊施設数は14,907施設である。温泉の利用等に当たっては、「温泉法」に基づき温泉の枯渇を防止し、将来にわたって有効に利用し得るよう温泉の掘削、増掘又は動力装置の設置等の行為について規制を加え、その保護がなされており、都道府県等に対し今後も引き続き適切な助言を行うこととする。
さらに、温泉利用の効果が十分期待され、健全な保養地として大いに活用される温泉地を「温泉法」に基づき、「国民保養温泉地」として環境大臣が指定しており、平成21年3月末現在、91箇所が指定されている。
平成20年10月11日・12日の2日間、埼玉県さいたま市において開催された、日本各地や海外の地域伝統を集めて公演する全国規模の地域伝統芸能の祭典である「第16回地域伝統芸能全国フェスティバル」について後援を行った。
| (3) 最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への支援 |
我が国で実施される最高水準の舞台芸術公演(音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、大衆芸能の各分野延べ447件)を支援することにより、舞台芸術の創造を活性化させ、日本の文化に親しむことができる機会の増加に寄与しており、本支援事業は、今後も引き続き実施することとしている。
国立劇場(国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂・国立文楽劇場・国立劇場おきなわ)では、歌舞伎・演芸・能楽・文楽・組踊等の伝統的な芸能を、多種多様な演出や技法を尊重しながら古典伝承のままの姿で正しく維持・保存されるように努めて公開を行うとともに、新国立劇場では、国際的に比肩しうる高い水準のオペラ・バレエ・現代舞踊・演劇等の現代舞台芸術の自主制作公演を行い、国民に舞台芸術の魅力を発信する拠点として事業の充実を図っており、この取組は、今後も引き続き実施することとしている。
次世代へ伝統文化の継承・発展を図ることを目的に、都道府県が地域の個性豊かな伝統文化の一体的・総合的な保存・活用のため策定するマスタープランに基づき、伝統文化保護団体等が実施する伝承者の養成、用具等の整備、映像記録等の作成等の事業を支援する「ふるさと文化再興事業」や、次代を担う子どもたちに対し、土・日曜日等において、学校・文化施設等を拠点とし、我が国の伝統文化を計画的、継続的に体験・修得できる機会を提供する「伝統文化こども教室事業」を実施しており、今後も、引き続き施策の展開を図っていくこととしている。
霞ヶ浦(茨城県)に浮かぶ七色帆引き船

| (6) 国民の各種文化活動の発表、競演、交流の場の提供 |
日頃の国民の文化活動の取組の成果を全国規模で発表する機会を提供する国内最大級の文化の祭典である「国民文化祭」を都道府県との共催で開催することにより、地域間の交流の活発化、開催地の特色ある文化の全国発信等の成果に加え、出演者、観客等を含めた観光客の誘致に一定の成果を上げている。
平成20年度は、「第23回国民文化祭・いばらき2008」を、平成20年11月1日から9日まで茨城県内において開催し、「七色帆引き船」の運航や「西塩子の回り舞台」の開催等、茨城県の特色を生かした各種イベントを実施した。
平成21年度は静岡県で開催することとしている。
1)みなと振興交付金
知恵と工夫を凝らし、地域の活性化に寄与する「みなと」の振興を図る港湾所在市町村等の取組を支援する「みなと振興交付金」を創設し、平成20年末現在、34プロジェクト(38港湾)の「みなと振興計画」を認定しており、今後も引き続き支援することとしている。
2)住民参加型まちづくりファンド
地域の特色ある港づくりの推進を図るため、港づくり活動への助成を行う住民参加型まちづくりファンド(地方公共団体が設置する基金等)に対して、(財)民間都市開発推進機構が資金拠出による支援を行う事業を実施しており、今後も引き続き実施することとしている(図II-2-2-5)。
図II-2-2-5 支援イメージ図
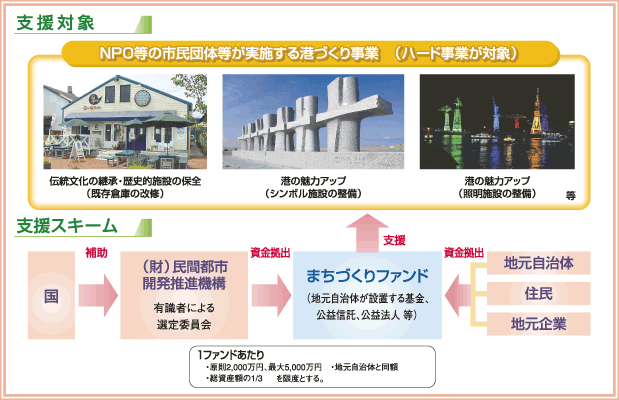
3)運河の魅力再発見プロジェクト
地域による「運河」周辺のコミュニティ基盤や観光基盤等、「運河」を核とした魅力ある地域づくりへの取組を国が支援する「運河の魅力再発見プロジェクト」を平成19年度に創設し、平成20年度末現在、10件のプロジェクトを認定している。
今後も引き続き、地域の個性を生かした水辺のにぎわい空間づくりや水上ネットワークの構築等を通じて、これらの取組を支援することとしている。
4)みなとオアシス
住民参加の下で港や海岸を活用した観光等の情報提供、産直市やフリーマーケット等の物販、各種イベントの開催等が行われる「みなとオアシス」の全国展開を推進し、港の"にぎわい・交流拠点"の形成を支援している。平成21年3月現在で55港が「みなとオアシス」に登録されている(うち9港は仮登録)(図II-2-2-6)。
図II-2-2-6 みなとオアシスの全国展開の推進
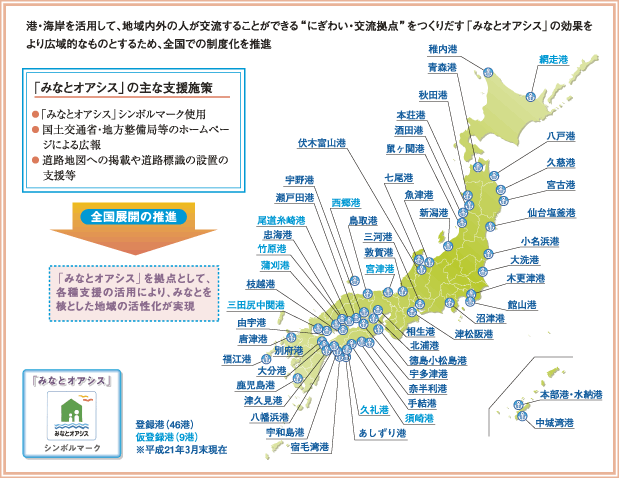
5)みなとの博物館ネットワーク・フォーラム
港に関する文物を研究、所蔵並びに展示する「みなとの博物館」が連携し、港を人々でにぎわう空間にしたり、交流の場を創出するような活動を支援し、港の歴史や文化を次世代へ継承することを目的に設立した「みなとの博物館ネットワーク・フォーラム」の活性化を促進している。
我が国の映画水準の向上、新人監督等の育成、地域の活性化等を目的とした映画製作支援(35件)を行うとともに、優れた文化記録映画作品(3件)及び永年映画界に尽力し顕著な業績を挙げた者に対する顕彰(5名)を実施した。
また、日本映画が多くの上映機会に恵まれ、海外にも市場が広がるよう、国内における上映・映画祭への支援(86件)や海外への発信支援(5箇所)を実施した。
観光交流等による離島地域経済の活性化を図ることを目的として、都市部において離島の魅力を情報発信するための大規模な交流事業「アイランダー」を開催し、離島観光情報のPRを行った。また、離島の観光振興に資するため、「島の宝100景」を公募・発表し、広く一般に周知した。さらに、離島航路事業者、旅行業者、交通事業者、地域住民等多様な主体と連携し、地域が一体となった離島地域の観光交流促進を図るための調査を実施することにより、離島地域の活性化を推進しており、引き続き、離島地域の観光交流を促進していく。
長崎県小値賀町小値賀島 「島のお母さんとの別れ」 「島の宝100景」より

大規模な交流事業「アイランダー」の様子

観光を通じた半島地域の活性化等を図るため、「半島らしい暮らし・産業創生調査」の中で半島地域ならではの資源を観光に活用した活動に取り組む団体等を育成したほか、同調査の一環として「半島地域における体験観光の促進に関する調査」を実施し、下北、能登、室津大島、宇土天草、薩摩、大隅の各地域において体験観光に関するモデル調査を行った。
また、「半島地域づくり会議in幡多」を通じて体験観光の推進や半島地域に共通する観光資源の活用に関する知見の共有や成果の普及を図っており、今後も引き続き、半島地域の観光振興を促進していく。
「豪雪地帯対策基本計画」に基づき、地域の自然や生活、文化を生かした観光を振興することとしている。冬期観光・交流の場として魅力ある地域社会の形成を図るため、冬期の道路交通の確保や、生活環境施設の整備等克雪対策を推進するとともに、雪に強い公園の整備を推進した。また、雪に親しむことをテーマに全国各地で実施した雪まつりや冬季スポーツ教室等の交流活動状況について、関係自治体に情報提供を行っており、今後、雪国と他地域との多様な交流の推進を図ることとしている。
首都圏及び近畿圏においては、関係省庁及び関係都府県が連携して、「都市環境インフラのグランドデザイン」を策定し、自然と触れ合う場の提供や観光地等の環境を構成する自然環境の保全等に関する取組を行っている。
本グランドデザインに基づき、首都圏では、「首都圏の都市環境インフラデータベース」を活用し、自然との触れ合い資源の情報や自然環境の保全等に関する取組情報等を広く首都圏住民に提供している。
また、近畿圏では、大阪府と和歌山県にまたがる和泉葛城地区において、自然との触れ合いの場や周辺居住地への良好な自然景観の提供に資する近郊緑地保全区域の区域拡大に向けた検討が進められている。
「総合保養地域整備法」に基づく基本構想を定める道府県を対象として、特定施設等の整備に関する進捗状況調査を行い、道府県で構成する全国リゾート地域連絡協議会において報告するとともに、基本構想の見直しについての意見交換を行っており、今後も引き続き実施することとしている。
1)海の環境保全
自然環境にやさしく美しい港への変革を図るため、汚泥しゅんせつや覆砂、干潟・藻場等の積極的な保全・再生・創出のほか、海浜及び緑地の整備を推進した。平成20年度は、横浜港等において緑地の整備、広島港等において干潟等の整備を実施しており、今後も引き続き緑地や干潟等の整備を実施していくこととしている。
2)港湾景観の形成
港湾が持つ景観資源を活用し、陸や海からの景観に配慮するとともに、良好な景観を享受できる緑地の整備を平成20年度は横浜港等で実施しており、今後も引き続き港湾景観の形成を図っていくこととしている。
海洋性レクリエーションの振興と公共水域の適正な利用促進を図るため、プレジャーボートの活動拠点となる小型船舶の簡易な係留・保管施設(ボートパーク)の整備を推進した。また、係留・保管場所等の情報提供サイトである「海覧版~プレジャーボート保管場所情報~」を公開し、安全、快適かつ適正なプレジャーボートの利用環境の整備を行なった。漁港においてはプレジャーボートユーザーからの利用ニーズが高いことを受け、関係機関と連携してプレジャーボートの漁港利用について検討するなど、プレジャーボート利用における適正な利用環境整備を進めている。
また、「海の駅」の更なる設置支援及びネットワーク化を推進し、利用者の利便性の向上を図った(図II-2-2-7)。
さらに、港の良好な自然環境の市民による利活用を促進し、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図るため、自治体やNPO法人等が行う自然体験・環境教育活動の場ともなる藻場・干潟等の整備を行った。また、それとともに、全国の海辺や海で活動する団体や個人により構成されるNPO法人等と連携し、海辺の自然体験・環境学習「海辺の自然学校」を開催した。今後もこれらの取組を引き続き実施することとしている。
このほか、教育関係者、海岸管理者等の連携により、世代間の交流の場、自然・体験活動の場、マリンスポーツの場として青少年が利用しやすい海岸づくりを図るため、「いきいき・海の子・浜づくり」を12箇所で実施した。
図II-2-2-7 全国「海の駅」マップ
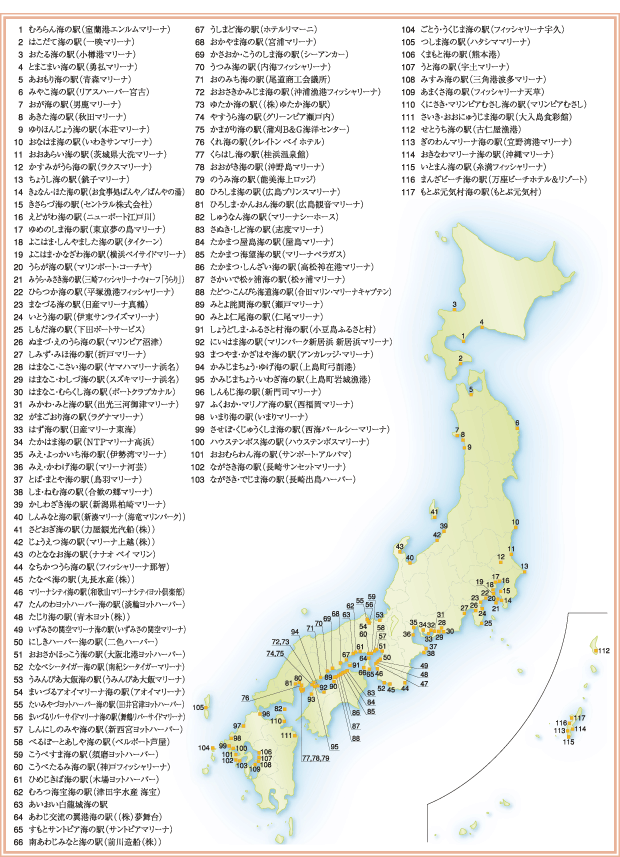
| (16) 美しい風景の撮影スポットの近傍の駐車場に関する情報提供 |
安全・快適に駐車できる駐車場と美しい風景の撮影スポットについて、当該駐車場の利用促進や国民への情報提供実施のため、平成20年度末までに約1,550箇所の駐車場を選定し、撮影スポットに係る情報を発信しており、今後も引き続き実施していくこととしている。
美しい風景の撮影スポット(和田珍味本店駐車場(島根県))

| (17) 観光資源としての河川環境の保全・創出及び活用 |
河川・湖沼を観光資源等としても活用できるよう、汚濁した底泥のしゅんせつ、浄化用水導入等の水環境改善対策を実施している。地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、生物の良好な生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観の保全・創出する多自然川づくりを実施しており、今後もこれらの取組を引き続き実施していくこととしている。
| (18) 水辺における環境学習・自然体験活動の推進 |
地域の身近な水辺における環境学習・自然体験活動を推進するため、市民団体や教育関係者、河川管理者等が連携して、子どもの水辺を登録する『「子どもの水辺」再発見プロジェクト』を推進した。また、水辺に近づきやすくする河岸の整備等を行う「水辺の楽校プロジェクト」を推進しており、これまでに269箇所が登録された(平成19年度は8箇所が登録)。
また、近年、カヌーやラフティングを始めとした水面利用や川での自然体験活動が活発化、多様化していることを踏まえ、全国の川で活動する市民団体等で構成される「NPO法人川に学ぶ体験活動協議会(RAC)」と連携し、川で安全に活動するための指導者の育成を推進しており、今後もこれらの取組を引き続き実施していくこととしている。さらに、急な増水による水難事故を防止するため、河川の安全利用に関する啓発等を推進している。
地域の生活に溶け込んでいる清澄な水や水環境の中で、特に、地域住民等による主体的かつ持続的な水環境の保全活動が行われているものを、昭和60年に選定された「名水百選」に加え、平成20年6月に「平成の名水百選」として選定し、広く紹介している。
|
|