平成20年度観光の状況
第II部 平成20年度の観光の状況及び施策
第3章 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成
第2節 観光の振興に寄与する人材の育成
| 1 観光地及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実 |
近年、観光関連の学部・学科を開設して観光人材の育成を目指す大学が増加している。平成20年4月には、和歌山大学、琉球大学、ノースアジア大学、大阪学院大学、神戸海星女子学院大学、倉敷芸術科学大学において観光関連学部・学科が開設された。これに伴い、観光関連学部・学科の入学定員は3,900人(37大学)となり、最近5年間では1,935人増加している(図II-3-2-1)。
図II-3-2-1 観光学部・学科を設置している大学の定員数の推移
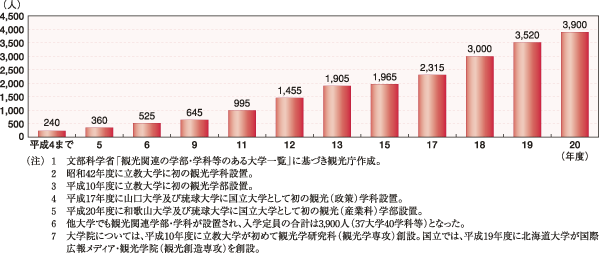
高等教育機関における観光分野の人材育成に当たっては、産業界のニーズを踏まえた教育内容の充実が必要との観点から、平成20年11月、「カリキュラムワーキンググループ」を設置し、観光経営マネジメント教育の必要性の確認や既存の観光系大学のカリキュラムの分析・検討を行い、「カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ」を公表し、課題を明らかにするとともに、「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」を作成し、産業界から求められる人材育成に必要な教育内容について提言を行った。
また、インターンシップの充実を図るため、平成20年8月より、「インターンシップ活用ワーキンググループ」を開催し、そのあり方について検討を行うほか、観光関係団体の協力の下、観光系大学を中心に6大学13名の学生の参加を得て、インターンシップ実施における企業・大学双方の受入れ内容等についての認識の共有化及び手続きの簡素化などを目的としたインターンシップモデル事業を実施した。
平成21年3月、両ワーキンググループでの議論を踏まえ、「第4回観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」を開催し、高等教育機関における観光分野の人材育成に取り組む際に参考となる情報の共有化や連携方策について検討を行った。本会議には、観光関連学部・学科を有する大学のみならず、観光に関心を持つ51大学や、幅広い民間企業等の約350名が参加した。
なお、平成20年5月現在、専門学校における旅行関係学科の生徒数は11,753人、学科数は168学科となっており、専門学校においても観光関連の人材を育成している。
第4回「産学官連携検討会議」(平成21年3月12日~13日:三田共用会議所)

ホテル、旅館等の事業経営、地域の魅力を向上させる地域経営に携わる観光・集客交流人材の育成に向けて、サービス人材の育成の観点から、産学連携によるホスピタリティ・マネジメントの生産性向上を担う経営幹部人材の育成のためのプログラム開発を支援するとともに、地域の視点から組織的に観光地を革新する観光地域経営のスキルを持つ観光地経営専門家を育成するプログラムの開発を行っており、今後とも引き続き実施していくこととしている。
また、多様化する訪日外国人旅行者のニーズへの対応と観光産業従事者の意欲の向上を図るため、旅館業従事者の人材育成に関する調査を実施し、人材育成に必要な成功要素や課題を整理するとともに、能力向上につながるような制度や仕組み等についての検討を行った。
「観光立国推進基本計画」における、平成23年度までに「ボランティアガイド」の数を47,000人とする目標に対し、ボランティアガイドの数は前年よりも約4,700人増加し、39,031人になっており、ボランティアガイド組織は全国で1,562団体となっている(平成21年3月現在)。
ガイド技術の向上、ガイド相互の情報交換の場として(社)日本観光協会が毎年1回「地域紹介・観光ボランティアガイド全国大会」を開催しており、平成20年度は、11月20日から21日に和歌山県田辺市で開催された。
「観光カリスマ」を講師として迎え、その成功手法の伝授、活動の現場体験、受講生によるワークショップ等をセミナー形式で集中的に行い、次世代の地域の観光振興を担う人材育成を目指す「観光カリスマ塾」を鹿児島県指宿市等8地区で開催しており、今後も引き続きこの取組を実施していくこととする。
地域おこし等に意欲があっても実際の行動に結びつかない女性が多い現状を改善し、同分野における女性の活躍を促進するため、地域おこし等に興味のある女性中心に、実際に活躍している女性(アドバイザー)による助言、経験交流会の開催等を行い、新たなる分野への女性のチャレンジを支援した。
各地域における自主的な観光地域づくり人材の育成を促進する観点から、各地域における観光地域づくり人材育成に取り組む団体や組織のネットワーク化を進め、地域相互間での情報共有・交換を促進するため、平成20年6月に「観光地域づくり人材育成シンポジウム」を開催するとともに、同年10月に「観光地域づくり人材育成支援メーリングリスト」を開設した。
観光地域づくり人材育成シンポジウム(平成20年6月11日:三田共用会議所)

| 3 地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進 |
| 学校における地域固有の文化、歴史等に関する教育の充実 |
学校教育では、社会科において、歴史に関する学習を行っており、例えば、小学校社会科では、古くから残る暮らしに関わる道具や地域に残る文化財や年中行事等地域の人々の生活に関する学習を行うとともに、人物や文化遺産を中心に、我が国の歴史に対する興味・関心と理解を深める学習を指導することとしている。
観光資源を有する地域の学校においては、総合的な学習の時間を活用し、地域の観光資源を紹介、案内するボランティアガイド活動が行われている事例がある。
このような活動は、将来の地域づくりの担い手の育成、旅をする心を育むなどの観点から有意義な活動であり、平成20年度においては、6月に開催した「観光地域づくり人材育成シンポジウム」において児童・生徒によるボランティアガイド活動事例の紹介を行うとともに、北海道松前町、青森県八戸市、滋賀県湖北町、鹿児島県鹿児島市の4地区でモデル事業を実施した。
また、地域の魅力や観光の意義等に関する子どもたちの理解を増進するため、宮城県、山形県、宮崎県、沖縄県が作成した観光副読本や教育関係者による観光立国教育の取組をセミナーやシンポジウムで紹介するなど、関係者との連携のもとに児童・生徒に対し観光立国についての理解促進に取り組んでいる。
体験交流施設「山の楽校」にて来館者に「南部せんべい焼き」体験を案内する中学生(八戸市)

山形観光副読本 個性と魅力ある地域づくりをめざして

|
|