平成20年度観光の状況
第II部 平成20年度の観光の状況及び施策
第5章 観光旅行の促進のための環境の整備
第4節 観光旅行の安全の確保
| 1 国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供 |
1)防災気象情報の高度化
竜巻等の突風対策に資するため、気象ドップラーレーダー等を活用した「竜巻注意情報」の提供を平成20年3月より開始しており、また、気象庁ホームページでは、竜巻注意情報や地震・津波・火山に関する情報の改善を行い、内容の充実を図った。また、併せて英文ページへの掲載内容も拡充し、外国人観光客への情報提供の充実も図った。今後も引き続き、情報の充実を図ることとしている。
2)防災情報提供センターの情報の充実
防災情報提供センターのホームページでは、国土交通省の雨量等の情報を集約して提供するとともに、「地理情報システム(GIS)」を活用し、様々な防災情報を1枚の地図に重ね合わせて利用できるようにしており、今後も引き続き、情報の充実を図ることとしている。
火山の多くは優れた自然景観や温泉等に恵まれた観光資源である一方、災害をもたらすおそれがあることから、観光客の安全確保等、災害軽減に資するため、火山活動を監視し、必要に応じて噴火警報等を発表している。さらに、避難や入山規制等の必要な防災対応を踏まえて火山活動の状況を区分した噴火警戒レベルの導入を、周辺の関係する地方自治体等と連携して進めている(平成21年3月31日現在25火山)。
また、噴火時等の的確な警戒避難体制に資するため、火山地域において異常な土砂の動き等を監視する機器等を設置し、その情報の地方自治体との共有を推進しており、今後も引き続き実施することとしている。
近年、河川での活動が多様化していることから、河川管理者、地元自治体、水面利用者が一体となって、インターネットや携帯電話による河川情報の提供等を推進している。
また、災害発生時に、観光客が適切な避難行動がとれるよう、避難場所、避難経路等を観光客にあらかじめ周知することが重要であり、このため、市町村によるハザードマップの作成・配布を促進するとともに、全国の各種ハザードマップを検索閲覧できるポータルサイトを開設しているほか、市街地には、「まるごとまちごとハザードマップ」の標識を整備し、洪水時の円滑かつ迅速な避難を可能としている。
「まるごとまちごとハザードマップ」

旅行者は、一般に地理等に不案内であるため、これらの人々に対し災害危険箇所及び避難場所・避難路等について周知徹底を図る必要がある。
そこで、地方公共団体に対し、事前に避難路や避難計画を定めるとともに、避難場所等の安全性についての点検、観光旅行者等への迅速かつ確実な情報伝達及び十分余裕をもった避難の勧告・指示等避難誘導体制全般の整備を図り、統一的な図記号等を利用した分かりやすい案内板等の設置を進めるよう要請した。また、防災関係機関との連携の下に、実践的な防災訓練を実施するよう要請した。
災害時における道路利用者の利便性の向上及び安全で円滑な道路交通の確保を目指し、道路情報板のほか、ホームページ等による道路の災害情報の提供を推進しており、今後も引き続き実施することとしている。
鉄道・自動車・海運・航空の各公共交通機関での一層の安全確保を図るため、事業者が経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制を構築・改善し、その状況を国が評価する運輸安全マネジメント制度を、保安監査と「車の両輪」で実施している。
制度導入から平成20年12月末までに、延べ1,148社(鉄道279社、自動車263社、海運567社、航空39社)に対して運輸安全マネジメント評価を実施した。
今後も運輸安全マネジメント制度の充実や保安監査の強化を行うなど公共交通機関の安全性の一層の向上を図る。
行楽地を中心に必要に応じた交通規制、交通整理及び交通指導取締りの強化に努めた。また、行楽期には、事前広報や臨時交通規制を実施するとともに、交通量の変動に対応した信号制御を行ったほか、交通渋滞情報等の提供により迂回を促すなどして、行楽車両の適切な配分誘導に努めた。
高速自動車国道等においても、交通安全施設の整備等事故防止に向けた交通安全対策を推進するとともに、道路交通情報提供装置の整備等利用者サービスの向上を推進しており、今後も引き続きこれらの施策を推進することとしている。
自然災害に対して安全で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、道路の斜面対策や災害のおそれのある区間を回避する道路の整備を行うとともに、緊急輸送道路の橋梁の耐震補強等を推進した。さらに、雪崩予防柵の設置等の防雪事業等による雪寒対策により、安定した冬期の道路交通の確保を推進した。今後も引き続き実施することとしている。
海上交通の安全確保のため、船舶への立入検査や海難防止講習会等を通じて海事関係法令の遵守、安全運航の励行等の指導並びに所要の取締りを実施した。また、ライフジャケットの常時着用、防水パックに入れた携帯電話等の連絡手段の確保、「118番」の有効活用を三つの基本とする「自己救命策確保キャンペーン」を推進した。さらに、救難体制を確保するため、民間組織の支援・指導等様々な施策を講じた。
防火セイフティマーク(防火基準点検済証、防火優良認定証)、防火自主点検済証について、積極的に広報・周知を図るとともに、消防法令違反により当該制度の適合マークが表示できない建築物に対しては、違反是正を徹底するよう消防機関に要請した。また、火災時の初動対応能力の向上、防火管理体制が手薄となる夜間の体制整備、高齢者等の災害時要援護者に対する防火安全対策等の推進を図り、旅館、ホテル等の実質的な防火安全体制の維持及び充実を促進した。
また、旅館、ホテル等で、特に既存不適格建築物について、建築物防災週間等の機会をとらえて防災査察を実施し、改善指導に努めるとともに、一定規模以上の旅館、ホテル等に対しては「建築基準法」に基づき定期的に維持・保全の状況について調査報告を求め、必要な改善指導を行い、防火・避難上の安全の確保を図っており、今後も引き続き実施することとしている。
防火基準点検済証・防火優良認定証(防火セイフティマーク) 防火対象物定期点検報告制度の点検基準に適合している施設
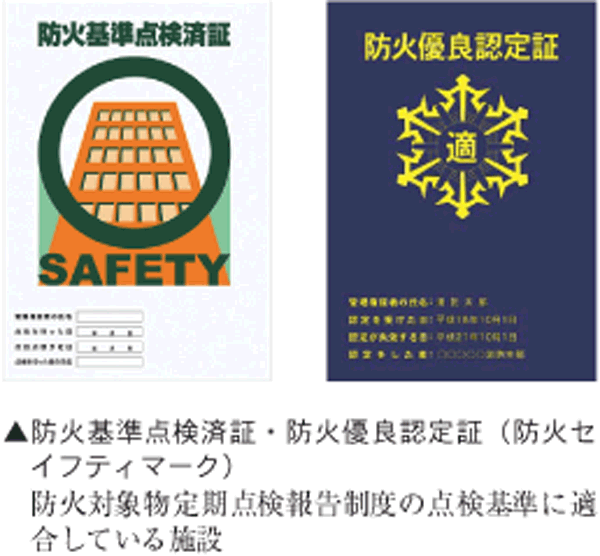
防火自主点検済証 自主点検報告表示制度の点検基準に適合している施設
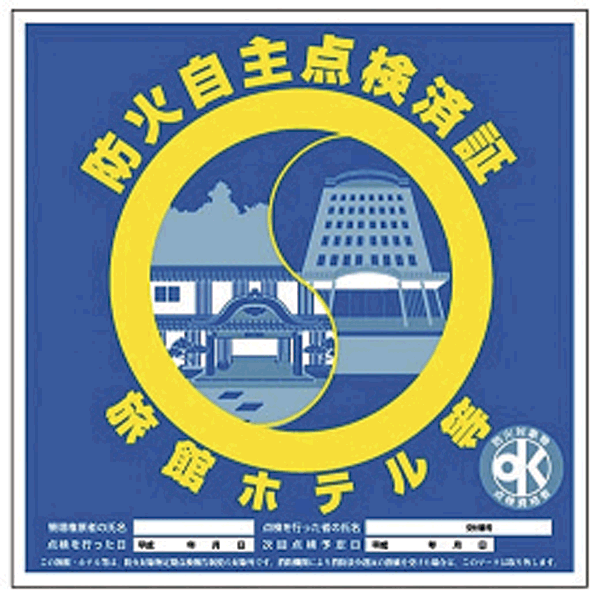
旅行者が渡航先の治安・安全情報を積極的に入手し、海外における危機及び安全対策に関する知識の向上を図るため、リーフレットを活用した周知、啓発活動を進めた。
また、旅行業者に対して、旅行者に向けた渡航先に関する渡航情報(危険情報及びスポット情報)の周知徹底や緊急連絡体制の整備を促し、海外において日本人旅行者が事件・事故に巻き込まれた際には関係省庁とも緊密な連絡を取りつつ情報収集を図った。
土砂災害の発生のおそれがある観光地について、土砂災害を防止するため砂防設備等の整備やITを活用した情報基盤の整備、「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定等のソフト対策を推進した。また、火山ごとに緊急ハード対策の施工やリアルタイムハザードマップによる危険区域の設定等を盛り込んだ「火山噴火緊急減災対策砂防計画」の策定等、ハード・ソフト一体となった対策を推進した。
さらに、浸水被害のおそれのある観光地において、雨水幹線や貯留浸透施設の整備等のハード対策、ハザードマップの公表等のソフト対策等を組み合わせた総合的な対策を推進しており、今後も引き続き実施していくこととしている。
|
|