第II部 平成23年度の観光の状況及び施策
第2章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成
3 優れた自然の風景地に関する観光資源の保護及び利用の推進
自然公園は、我が国の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを目的として「自然公園法」に基づき指定される公園で、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園の3種類がある。これらの公園は我が国の主要な観光地としても重要な役割を果たしている。
霧島屋久国立公園については、錦江湾の姶良カルデラを中心に拡張して霧島錦江湾国立公園に改めるとともに、屋久島地域を分離して新規に屋久島国立公園として指定し、我が国の国立公園の数は29から30になった。この他6の国立・国定公園について公園区域及び公園計画の見直しを行った。
また、陸中海岸国立公園などの既存の自然公園を再編し三陸復興国立公園(仮称)とし、防災上の配慮をした公園施設の再整備や長距離海岸トレイルの新規整備を行うことについて検討するとともに、農林水産業と連携したエコツーリズムの推進など各種事業を行う等の取組を推進するための検討を進めた。
国立・国定公園のうち、公園計画に基づき定められた特別地域や海域公園地区等においては、各種一定の行為を許可制度により規制することを通じて、その保護と適正な利用が図られている。
さらに、公益法人等を公園管理団体に指定し、自然の風景地の管理、公園利用施設の維持管理、公園内の自然情報の収集・提供等に関する市民等の自発的な活動を推進している。
国立公園等の貴重な自然環境を有する地域においては、野生動植物の保護、登山道の補修、外来種の駆除等の「国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業」等を行っている。
このほか、モニタリング調整会議において決定された総合モニタリング計画に基づき、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の自然公園内で公園利用者に飲用される湧水などについて放射性物質モニタリングを実施した。
国立公園内においては、関係機関・団体等で構成する協議会において交通規制を行い、適正な利用環境の確保、環境保全に努めている。
また、知床国立公園及び吉野熊野国立公園にある利用調整地区では、原生的な自然を有する地域を保全するため、立ち入り人数の調整等を実施している。
| 4) 国立・国定公園における利用のための施設の整備 |
自然環境の保全に配慮しつつ、自然とのふれあいを求める国民のニーズにこたえ、安全で快適な利用を推進するため、平成23年度には全国29の国立公園において、国立公園の主要な入口における情報提供施設、山岳地域の適正な利用を推進するための登山道、その他利用の基幹となる施設を整備した。なお、利用拠点における施設のユニバーサルデザイン化も行った。
また、国定公園においては、自然とのふれあいの場の整備や自然環境の保全・再生を推進するため、平成23年度には、34都道府県に「自然環境整備交付金」を交付した。
自然公園や文化財を有機的に結ぶ長距離自然歩道について、平成23年度には東北、首都圏、東海、中部北陸、近畿、中国、四国、九州の長距離自然歩道において、四季を通じて安全で快適に利用できるように整備を進めた。長距離自然歩道の計画総延長は約26,000kmに及んでおり、平成22年には約7,960万人が長距離自然歩道を利用した。
国立・国定公園の保護と適正な利用のため、自然公園指導員約2,800名を委嘱しており、利用者に自然保護思想や利用マナーの普及啓発、安全利用等に関する指導等の推進を図った。また、全国24国立公園等38地区の地方環境事務所等において約1,600名のパークボランティアの養成及びその活動に対する支援を実施した。
平成23年6月に開催された第35回世界遺産委員会において、新たに小笠原諸島が世界自然遺産に登録された。我が国では、世界遺産条約に基づき、平成24年3月現在で、4件の世界自然遺産が登録されている。
なお、小笠原諸島を含む各世界自然遺産地域では、世界遺産地域管理計画等に基づき、関係機関が連携して適切な保全管理を行った。また、屋久島及び白神山地については、観光利用と適正な保全管理の調和など新たな課題等に対応するため、管理計画の改定に向けた検討を行った。
世界自然遺産に登録された小笠原諸島

表II-2-2-2 日本の世界自然遺産
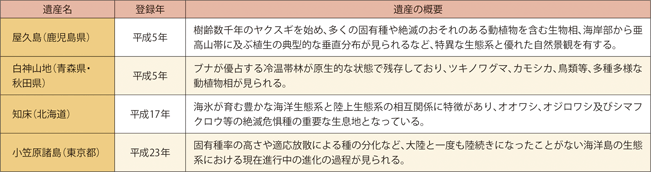
| (3) 優れた自然の風景地を生かした地域づくりの推進 |
「自然に親しむ運動」等を通じて、自然とふれあう各種活動を実施したほか、平成23年10月に新宿御苑において、「平成23年度自然公園ふれあい全国大会」を開催した。
また、小中学生に自然保護官の業務を体験してもらうなど、自然保護の大切さを学ぶ機会を提供した。
さらに、ラムサール条約事務局作成の湿地におけるサステイナブルツーリズムに係る普及啓発ツールを翻訳、配布するとともに、水鳥湿地センター等において、湿地の保全と賢明な利用について普及啓発活動を行った。
森林環境教育、健康づくり等の森林利用に対応するため、教育関連施設・健康増進施設等と連携を図った森林の整備を行い、森林の多様な利用を推進し、地域の観光資源としても活用した。また、自然探勝、ハイキング、キャンプ等の森林レクリエーション利用に供すること等を目的とする森林については保健保安林として、名所、旧跡の風致の保存を目的とする森林については風致保安林として、平成23年3月末現在、合わせて730,000haを指定している。さらに、観光地周辺の森林において、周辺の景観に配慮しつつ、治山事業等を実施し、安全の向上と併せて観光資源の資質向上に寄与した。国有林野では、自然休養林等の「レクリエーションの森」を人と森林とのふれあいの場として積極的に提供した。また、国民による森林づくり活動の場を提供する「ふれあいの森」、学校等による体験活動等の場を提供する「遊々の森」の設定・活用を推進した。
このほか、国有林野において、優れた自然環境を有する森林については、「保護林」や「緑の回廊」を設定し、適切な管理を行った。特に、大雪山・日高山脈地域では「保護林」等の大幅な拡充を行い、平成23年4月現在、両地域の保護林の面積は、合計77,000haから224,000haに増加した。また、地域住民等との協力による自然環境の保全活動のほか、グリーンサポートスタッフ(森林保護員)による清掃活動や利用者へのマナー啓発活動を推進した。さらに、陸域のほとんどを国有林野が占める世界自然遺産のほか、世界文化遺産と一体となった森林等の保全対策を推進した。平成23年6月に新たに登録が決定した小笠原諸島世界自然遺産地域においては、保護と利用の両立に向け、遺産地域の立ち入りを指定ルートに限定し、講習を受けたガイドの同行を義務付ける「利用ルール」の運用や普及啓発を図った。また、富士山等、世界遺産一覧表への記載を推薦された地域等の保全対策を講じた。
大雪山森林生態系保護地域(北海道南富良野町上川南部森林管理署管内国有林)
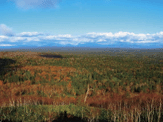
北海道では、地域の活動団体が主体となり、関係省庁をはじめとする関係者と連携し、「美しい景観」「活力ある地域」「魅力ある観光空間」づくりを行う「シーニックバイウェイ北海道」を推進している(シーニックバイウェイ北海道ホームページ:http://www.scenicbyway.jp)。
平成23年度には新たに「~十勝シーニックバイウェイ~南十勝夢街道」、「~札幌シーニックバイウェイ~藻岩山麓・定山渓ルート」が加わり、全道11ルートにおいて、沿道の花植え、景観改善、ビューポイントの整備、情報発信、観光メニューの創出等、様々な活動が展開されている。
南十勝夢街道(北海道幕別町忠類 十勝平野)

また、北海道では、自然とのかかわりの中でアイヌの人々が独自の伝統や文化を育んできており、新千歳空港における工芸品の展示や阿寒湖温泉におけるアイヌ文化の伝承・保存・普及と一体となった観光振興の取組等が行われている。
歩きやすさに十分配慮しつつ、周辺景観や地域の個性を生かした歩行者専用道路を目的としたベンチ等の休憩施設や、デザイン等を工夫した案内標識及び来訪者の発着拠点となる駐車場等の整備を支援した。
|
|