第II部 平成23年度の観光の状況及び施策
第2章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成
5 温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発
平成23年3月末現在における全国の温泉湧出源泉数は、27,671箇所(うち自噴するもの4,460箇所、動力によるもの13,476箇所、未利用のもの9,735箇所)、湧出量は1日換算約387万トンに及んでいる。また、温泉地は全国に3,185箇所あり、温泉を利用する宿泊施設数は14,052施設である。
温泉の利用等に当たっては、「温泉法」に基づき温泉の枯渇を防止し、将来にわたって有効に利用し得るよう温泉の掘削、増掘又は動力装置の設置等の行為について規制を加え、その保護がなされており、都道府県等に対し引き続き適切な助言を行うこととする。
さらに、温泉利用の効果が十分期待され、健全な保養地として大いに活用される温泉地を「温泉法」に基づき、「国民保養温泉地」として指定しており、平成22年3月末現在、91箇所が指定されている。
| (2) 最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への支援 |
我が国で実施される最高水準の舞台芸術(音楽、舞踊、伝統芸能、大衆芸能の各分野)及び、劇場・音楽堂が中心となって地域住民と芸術関係者等ともに取り組む優れた舞台芸術の制作、教育普及、人材育成等を支援することにより、舞台芸術の創造を活性化させ、日本の文化に親しむことができる機会の増加に寄与している。
定期演奏会(石川県立音楽堂)
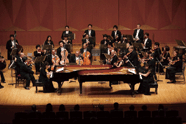
国立劇場(国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂・国立文楽劇場・国立劇場おきなわ)では、歌舞伎・文楽・能楽・大衆芸能・組踊等の伝統的な芸能を、多種多様な演出や技法を尊重しながら古典伝承のままの姿で正しく維持・保存されるように努めて公開を行っている。また、新国立劇場では、国際的水準のオペラ・バレエ・現代舞踊・演劇等の現代舞台芸術の自主制作公演を行っている。このような舞台芸術の魅力を発信する拠点としての取組を、引き続き実施することとしている。
| (4) 国民の各種文化活動の発表、競演、交流の場の提供 |
国民の文化活動の取組、成果を全国規模で発表する機会を提供する国内最大の文化の祭典である「国民文化祭」を、都道府県との共催で開催することにより、地域間の交流の活発化、開催地の特色ある文化の全国発信等に加え、出演者、観客等を含めた観光客の誘致に一定の成果を上げている。
平成23年度は、「第26回国民文化祭・京都2011」を10月29日から11月6日まで京都府内全市町村において開催した。「こころを整える~文化発心(ほっしん)」をテーマとして、70の主催事業をはじめ京都文化年イベント絵巻事業等多彩な事業を実施し、日本文化の素晴らしさを再確認する大会とした。また、東日本大震災復興の決意を広く国内外に示す大会とし、国内外から約441万人が参加者・観客として京都府を訪れた。
「第26回国民文化祭 京都2011」グランドフィナーレ

なお、平成24年度は徳島県で開催することとしている。
知恵と工夫を凝らし、地域の活性化に寄与する「みなと」の振興を図る港湾所在市町村等の取組を支援する「みなと振興交付金」を創設し、平成23年12月末現在、42プロジェクト(46港湾)の「みなと振興計画」を認定している。今後「社会資本整備総合交付金」及び「地域自主戦略交付金」により引き続き支援することとしている。
地域による「運河」周辺のコミュニティ基盤や観光基盤等、「運河」を核とした魅力ある地域づくりへの取組を国が支援する「運河の魅力再発見プロジェクト」を平成19年度に創設し、平成24年3月末現在、10件のプロジェクトを認定している。
引き続き、地域の個性を生かした水辺のにぎわい空間づくりや水上ネットワークの構築等を通じて、これらの取組を支援することとしている。
みなとや海岸の施設を住民参加の下、地域の情報発信拠点、あるいは地域の方々や観光客などの交流拠点として活用する「みなとオアシス」を全国に展開しており、港の“にぎわい・交流拠点"の形成を支援している。平成24年3月末現在で60港が登録されている。
図II-2-2-3 みなとオアシスの全国への展開状況
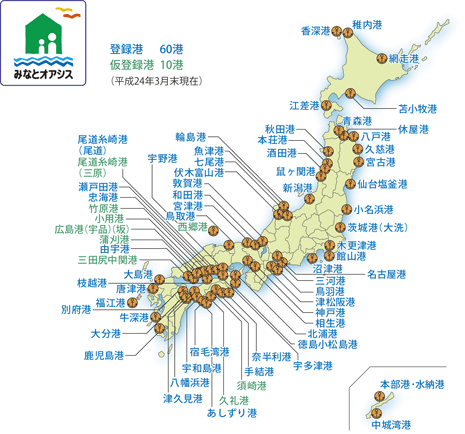
日本映画の振興を図るため、優れた日本映画の製作活動を支援するとともに、映画による国際文化交流を推進するため、国際共同製作に対する支援を実施した。また、優れた文化記録映画作品及び永年映画界に尽力し顕著な業績を挙げた者に対する顕彰や、日本映画が多くの上映機会に恵まれるよう、海外映画祭への発信支援等を実施した。
さらに、我が国のメディア芸術を一層振興するため、創作活動、普及、人材育成などに重点を置いた様々な取組を実施し、「文化庁メディア芸術祭」では平成24年2月22日~3月4日に受賞作品展を開催する等、我が国のメディア芸術を国内外に積極的に発信した。
離島地域における、交流人口拡大による自立的発展を促進する観点から、全国の離島が集まり観光・交流事業情報を都市住民に発信する交流事業「アイランダー」を開催した。また、離島地域自らの創意工夫による、先導的な地域活性化への取組の実施及びその成果を離島地域全体の取組に反映させるための「離島の活力再生支援事業」を実施した。
全国の離島が集まり観光・交流事業情報を都市住民に発信する「アイランダー」の様子
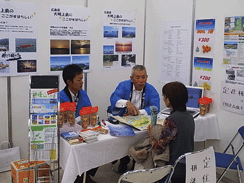
鹿児島県与論島での取組(「離島の活力再生支援事業(島食材を使った与論フードアイデンティティの確立)」で行われた観光客向け新規開発メニュー試食の様子

さらに、離島航路事業者、旅行業者、交通事業者、地域住民等多様な主体と連携し、地域が一体となった離島地域の観光交流促進を図るための調査を実施することにより、離島地域の活性化を推進している。
地域資源の活用による観光などの地域間交流等を通じた半島地域の自立的発展を図るため、地域の活動主体によるワークショップ等において、観光ボランティアの活用や複数の半島間の相互交流などの検討を行った。また、農家や企業など複数の主体による「食」をテーマとした地域活性化の取組など、幅広い主体の連携による新たな観光資源の発掘に向けた実証調査を行った。
引き続き、半島地域の観光振興を促進することとしている。
「豪雪地帯対策基本計画」に基づき、冬期の道路交通の確保や、生活環境施設の整備等克雪対策を推進するとともに、雪に強い公園の整備を推進した。また、雪に親しむことをテーマに全国各地で実施した雪まつりや冬季スポーツ教室等の交流活動状況について、関係自治体に情報提供を行っており、今後、雪国と他地域との多様な交流の推進を図ることとしている。
首都圏及び近畿圏において、自然環境の総点検を実施し、まとまりのある貴重な自然を「保全すべき自然環境」として抽出し、この「保全すべき自然環境」の保全とそれを中核とした水と緑のネットワークの形成を推進するため「都市環境インフラのグランドデザイン」を策定(首都圏平成16年、近畿圏平成18年)した。
平成23年度は、都市環境インフラのグランドデザインから得られた知見等を踏まえ、良好な都市環境を有する大都市圏の形成に向けた施策の検討を進めた。
「総合保養地域整備法」に基づく基本構想を定める道府県を対象に、特定施設等の整備に関する進捗状況調査や、基本構想の見直しについて関係省で調整を行っており、引き続き実施することとしている。
自然環境にやさしく美しい港への変革を図るため、汚泥しゅんせつや覆砂、干潟等の積極的な保全・再生・創出のほか、海浜及び緑地の整備を推進している。
港湾が持つ景観資源を活用し、陸や海からの景観に配慮するとともに、良好な景観を享受できる緑地の整備を推進し、港湾景観の形成を図っていくこととしている。
「海の駅」の更なる設置支援、ネットワーク化及び海洋教育活動を推進し、利用者の利便性の向上やマリンレジャーの振興を図った。また、プレジャーボートの漁港利用について検討するなど、地域のプレジャーボート利用における適正な利用環境整備を進めている。
図II-2-2-4 海の駅マップ
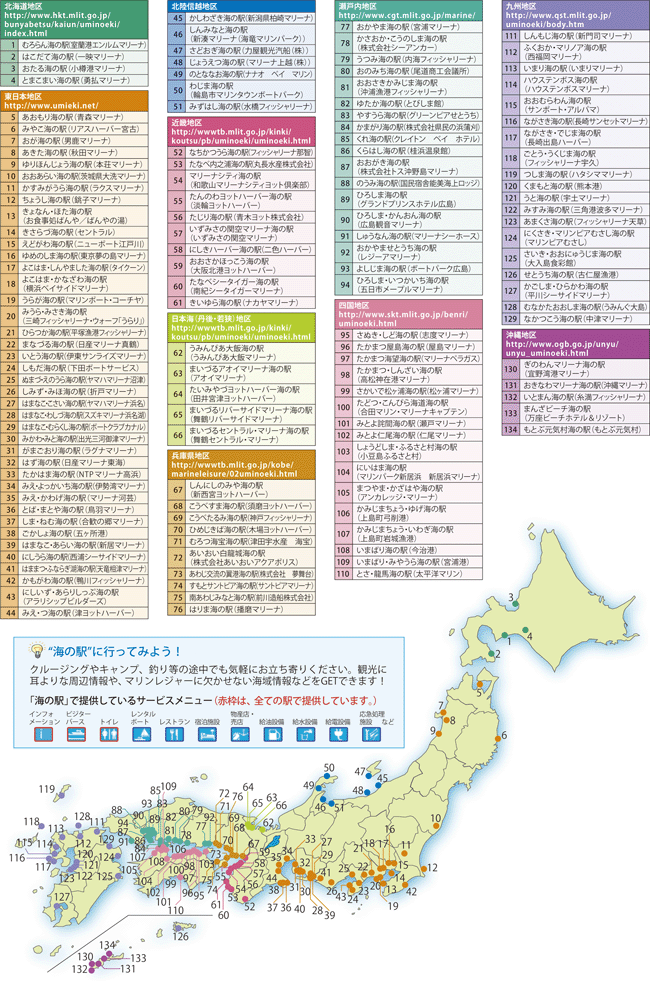
| (14) 観光資源としての河川環境の保全・創出及び活用 |
河川・湖沼を観光資源等としても活用できるよう、汚濁した底泥のしゅんせつ、浄化用水導入等の水環境改善対策を実施している。地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、生物の良好な生息・生育・繁殖環境及び良好な河川景観を保全・復元する多自然川づくりを実施しており、これらの取組を引き続き実施していくこととしている。
| (15) 水辺における環境学習・自然体験活動の推進 |
地域の身近な水辺における環境学習・自然体験活動を推進するため、市民団体や教育関係者、河川管理者等が連携して、子どもの水辺を登録する「『子どもの水辺』再発見プロジェクト」や、水辺に近づきやすくする河岸の整備等を行う「水辺の楽校プロジェクト」を推進した。
また、近年、カヌーやラフティングを始めとした水面利用や川での自然体験活動が活発化、多様化していることを踏まえ、全国の川で活動する市民団体等で構成される「特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会(RAC)」と連携し、川で安全に活動するための指導者の育成を支援している。
さらに、河川における水難事故を防止するため、河川の安全利用に関する啓発等を推進している。
地域の生活に溶け込んでいる清澄な水や水環境の中で、特に、地域住民等による主体的かつ持続的な水環境の保全活動が行われているものを、昭和60年に「名水百選」、平成20年に「平成の名水百選」として選定している。平成23年7月には、全国名水シンポジウムが、秋田県美郷町において開催された。
全国名水シンポジウムが開催された秋田県美郷町の六郷湧水群御台所清水(ろくごうゆうすいぐんおだいどころしみず)
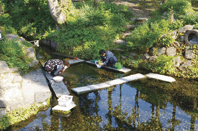
|
|