第II部 平成23年度の観光の状況及び施策
第4章 国際観光の振興
第1節 外国人観光旅客の来訪の促進
4 外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内サービスの向上 その他の外国人観光旅客の受入環境の整備等
ビザ申請人の利便性向上のため迅速かつ円滑なビザ発給に取り組んでおり、ビザは問題がない限り原則5労働日以内に発給されている。
出入国審査に要する時間の短縮を図るため、職員が常駐していない地方空海港への出入国審査を行う職員の派遣や、上陸審査における「セカンダリ審査(二次的審査)」、「事前旅客情報システム(APIS)」の効果的活用等を実施するとともに、年間入国者が多い空海港において出入国審査手続に関する案内等を行う「審査ブースコンシェルジュ」を効果的に配置した。また、平成23年10月に「訪日外国人2500万人時代の出入国管理行政検討会議」を開催し、短時間で円滑かつ厳格な審査を確実に実施できる将来の出入国審査の方法等について検討を開始した。
日本政府観光局は、外国人向け総合観光案内所であるツーリスト・インフォメーション・センター(TIC)で観光情報を提供すると同時に、地方公共団体や観光関連施設が運営する外国人旅行者への対応が可能な観光案内所(ビジット・ジャパン案内所=略称:「V」案内所)をネットワーク化し、外国人旅行者のニーズに応じた案内や情報の提供を行っている。ネットワーク参加案内所は、平成23年度に7箇所増加して、全国47都道府県、163都市・313箇所(平成24年3月末現在)に上る。
訪日外国人3,000万人プログラムの達成には、海外市場でのプロモーションと並んで、国内における受入環境の整備が重要であるところ、受入側の環境については遅れている部分が多く、対応が喫緊の課題となっている。
このため、平成23年度は、訪日外国人旅行者が安心して快適に、移動・滞在・観光することができる環境を提供することにより、訪日外国人旅行者の訪問を促進するとともに、満足度を高め、リピーターの増加を図るため、戦略拠点・地方拠点として選定された全国26地域で受入環境整備水準の評価を行った。また、先進的・モデル的な事業を実施し、地域での自立的な受入環境の整備及び他地域への普及を図るとともに、日本在住の留学生等を受入環境整備サポーターとして観光地などへ派遣することで、受入環境整備が遅れている部分を外国人目線から明確にし、改善策を提案してもらうことで、自主的な訪日外国人旅行者の受入環境整備を促進した。
「観光立国推進基本計画」における、平成23年度までに「通訳案内士」の登録者数を15,000人(「地域限定通訳案内士」を含む)とする目標に対し、平成23年4月現在の登録者数は15,371人となった。
また、一つの都道府県の範囲に限って通訳案内業務を行うことができる「地域限定通訳案内士」制度については、北海道、岩手県、栃木県、静岡県、長崎県、沖縄県の6道県において導入されている。
なお、訪日外国人3,000万人時代に対応した受入環境整備の観点から、訪日外国人の旅行ニーズの多様化や近隣アジア圏からの旅行者の急増等の環境変化に対応すべく通訳案内士以外の者による有償ガイド行為を可能とする特例措置を規定した「総合特別区域法」が平成23年8月に施行された。平成23年12月に指定された33箇所の総合特別区域のうち、「国際医療交流の拠点づくり「りんくうタウン・泉佐野市域」地域活性化総合特区」及び「和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区」の2箇所について、平成24年3月に同特例措置を盛り込んだ総合特区計画が認定された。今後、同制度を利用した地域の活性化が期待される。
また、高付加価値ガイドサービスの強化等、ガイドの質の向上に関する事業を実施した。
表II-4-1-3 通訳案内士制度の充実
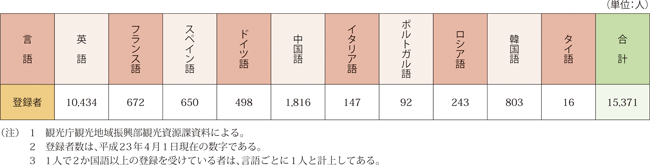
日本政府観光局では、街頭・車内等で困っている訪日外国人旅行者に通訳を行う「善意通訳(グッドウィルガイド)」の募集を、年間を通じて行っている。善意通訳登録者数は56,844人、同行ガイドや国際イベントの通訳補助等の活動を行うため、その有志が結成している「善意通訳組織(SGG)」は全国で87団体となっている(平成24年3月現在)。
| (7) 首都圏空港(羽田・成田)における国際航空機能の拡充 |
成田国際空港においては、平成23年10月から同時平行離着陸方式が開始されるとともに、年間発着枠が22万回から23.5万回に、平成24年3月には、25万回まで拡大した。なお、平成24年3月現在、91都市との間に、国際定期便が就航している。
また、羽田空港においては、平成22年10月の再拡張事業の供用開始により、32年ぶりの国際定期便就航を果たした。これにより、供用後1年間の国際線旅客数は694万人と、対前年比約2.1倍となった。なお、平成24年3月現在、14都市との間に国際定期便が就航している。
我が国を中心とする国際航空ネットワークの強化のため、「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)に基づき、首都圏空港の容量拡大に取り組みつつ、首都圏空港を含めたオープンスカイの枠組みの構築を、東アジア、ASEANの国・地域を最優先に推進してきた。これまでに米国、韓国、シンガポール、マレーシア、香港、ベトナム、マカオ、インドネシア、カナダ、オーストラリア、ブルネイ、台湾、英国、ニュージーランド及びスリランカの計15の国・地域との間でオープンスカイに合意した(平成24年3月末現在)。
| (9) 博物館・美術館等における外国人への対応の促進 |
東京、京都、奈良、九州の各国立博物館を設置する(独)国立文化財機構では、案内板の表示や展示品の説明文等を英語でも表記している。また、英語等のパンフレットを用意しているほか、所蔵している国宝、重要文化財をインターネットで閲覧できるデジタル高精細画像システムを多言語(英語、中国語、韓国語、フランス語)で発信し、対応の促進を図っている。
国立美術館では、施設案内パンフレットやホームページを英語等で作成するとともに、インフォメーションにおける英語案内を行っている。また、作品名等のキャプションの英語併記や英語による所蔵作品検索等、展示品等についての理解の促進に努めている。
国立科学博物館では、施設案内パンフレットのほか、ICTを効果的に活用した音声ガイドや展示情報端末を多言語(英語、中国語、韓国語)に対応させるなど、海外からの旅行者を始め、すべての人々が利用しやすい環境の充実に努めている。
国立劇場(国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂・国立文楽劇場・国立劇場おきなわ)では、英語等の劇場案内パンフレットを配布した。また、歌舞伎・文楽公演における英語版のイヤホンガイドの提供、公演プログラムへの英文掲載、能楽公演における各座席での英語字幕の提供等に取り組んできた。この取組は、引き続き実施することとしている。
| (11) 国立公園等における外国人観光旅行者に向けた情報提供 |
国立公園等における公園利用施設の整備にあたり、外国人に向けたインフォメーション機能の強化を図るため、ビジターセンターの展示や案内標識等の多言語表示を進めた。
また、国立公園を紹介する英語、中国語、韓国語のパンフレットを作成し、美しい日本の自然や日本の国立公園等に関する情報を発信した。
| (12) 多言語自動音声翻訳システムの実現に向けた取組 |
平成20年度から、自動音声翻訳システムの社会普及を目的とした「社会還元加速プロジェクト(言語の壁を乗り越える音声コミュニケーション技術の実現)」に取り組み、観光分野における英語、中国語、韓国語等での直接会話を可能とする自動音声翻訳システムの開発・導入を推進している。
この一環として、自動音声翻訳システムの実用化を加速するため、平成22年度からスマートフォン用の多言語音声翻訳アプリケーション“VoiceTra"を一般公開している。
これらの取組の結果、平成23年12月には、成田国際空港株式会社から、一般旅行者向けの多言語音声翻訳アプリケーション“NariTra"がリリースされるなど、観光分野での自動音声翻訳システムが実用化されている。
多言語音声翻訳アプリケーション“NariTra"

|
|