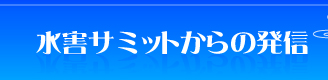トップ > こんなときどうする? > 災害時にトップがなすべきことは…
災害時にトップがなすべきことは…
- 「命を守る」ということを最優先し、避難指示を躊躇してはならない。
- 判断の遅れは命取りになる。何よりもまず、トップとして判断を早くすること。
- 「人は逃げない」ということを実感した。人は逃げないものであることを知っておくこと。人間の心には、自分に迫りくる危険を過小に評価して心の平穏を保とうとする強い働きがある。避難指示のタイミングはもちろん重要だが、危険情報を随時流し、緊迫感をもった言葉で語る等、逃げない傾向を持つ人を逃げる気にさせる技を身につけることはもっと重要である。
- ボランティアセンターをすぐに立ち上げること。ボランティアは単なる労働力ではない。ボランティアが入ってくることで、被災者も勇気づけられる、町が明るくなる。
- トップはマスコミ等を通じてできる限り住民の前に姿を見せ、「市役所も全力をあげている」ことを伝え、被災者を励ますこと。自衛隊や消防の応援隊がやってきたこと等をいち早く伝えることで住民が平静さを取り戻すこともある。
- 住民の苦しみや悲しみを理解し、トップはよく理解していることを伝えること。苦しみと悲しみの共有は被災者の心を慰めるとともに、連帯感を強め、復旧のばねになる。
- 記者会見を毎日定時に行い、情報を出し続けること。情報を隠さないこと。マスコミは時として厄介であるし、仕事の邪魔になることもあるが、情報発信は支援の獲得につながる。明るいニュースは、住民を勇気づける。
- 大量のごみが出てくる。広い仮置き場をすぐに手配すること。畳、家電製品、タイヤ等、市民に極力分別を求めること(事後の処理が早く済む)。
- お金のことは後で何とかなる。住民を救うために必要なことは果敢に実行すべきである。とりわけ災害発生直後には、職員に対して「お金のことは心配するな。市長(町村長)が何とかする。やるべきことはすべてやれ」と見えを切ることも必要。
- 忙しくても視察は嫌がらずに受け入れること。現場を見た人たちは必ず味方になってくれる。
- 応援・救援に来てくれた人々へ感謝の言葉を伝え続けること。職員も被災者である。職員とその家族への感謝も伝えること。
(水害サミット議事録から、令和3年の災害対策基本法改定を反映)