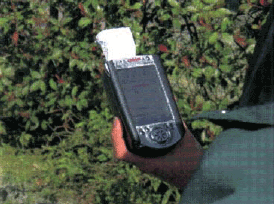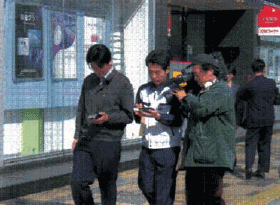地図データや位置関連コンテンツの連携利用を目指す「モバイルGIS標準」
モバイルGISは、GPS等の位置特定技術やGIS技術と携帯情報端末機器(PDA)を利用して、人や車の移動体に対して現在位置や目的地までの経路、施設情報等を提供するシステムです。また、高機能な携帯電話やPDAが開発され、いつでもどこでもインターネット等から情報を得ることが可能となり、経路案内などの地図情報を活用したGISサービスを利用できる環境が実現しつつあります。
しかし、これらのサービスは提供者毎に地図データや位置関連コンテンツを整備しているため、提供者間のデータ交換が困難で各種サービスの普及促進を阻んでいます。この問題を解決するため、2001年5月にITS標準化委員会にモバイルGISビジネスチームが設置され、異なる整備主体が作成した地図データや位置関連コンテンツを連携利用するための「モバイルGIS標準」の検討が進められています。
モバイルGIS標準によって、次のサービスの提供が可能になります。
- 異なる主体・縮尺の地図データの連携機能
- 異なる主体の情報コンテンツの連携機能
久留米でモニターによる実験を実施
モバイルGIS標準案に基づいたサービスイメージや機能・性能について確認することを目的に、福岡国道工事事務所は管内の久留米地区で実験を実施。久留米地区にて入手可能な地図データおよび位置関連コンテンツをモバイルGIS標準に準拠したデータ形式となるように予め編集したものを利用しました。システムは、モニターが携帯するGPS受信機とPHS内蔵のPDA、PDAからの問い合わせに回答する地図サーバから構成されています。
実験は、1)タウン情報とバリアフリー情報の連携、2)マルチモーダルな経路案内のサービスを想定し、久留米市の国道209号(通称・明治通り)周辺にて実施。モニターは、モバイルGIS機能が組み込まれた携帯情報端末を持って、予め指定された歩行経路を歩きました。この実験によって、地図データやコンテンツの連携利用やインターフェースに関する評価データを収集できました。
携帯端末の外観
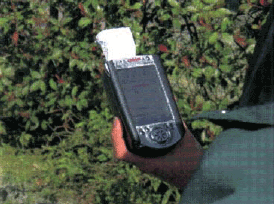
実験風景
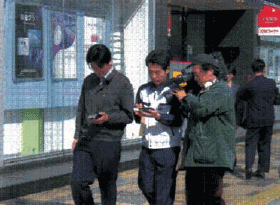
 モバイルGIS
モバイルGIS
 モバイルGIS
モバイルGIS