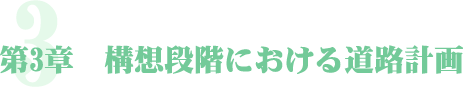
構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン
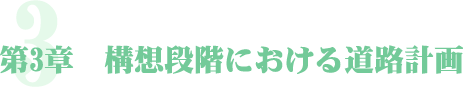
| 構想段階とは、路線別計画のうち、道路管理者が、道路の概ねの位置や構造等の基本的な事項(概略計画)を決定する段階をいう。 構想段階においては、当該道路計画の目的等を明確化した上で、目的の達成に資する幅広い比較案から最も優位な概略計画案の選定を行い(計画検討プロセス)、道路管理者は、この概略計画案をもとに、概略計画を決定する。 計画検討プロセスは、政策的、技術的観点の情報に加え、市民等との一連のコミュニケーション(市民参画プロセス:第5章参照)を通して得られた情報も考慮しつつ進めるものとする。 |
構想段階における計画の体系、計画検討プロセス、市民参画プロセスの関係は以下のように整理できます。
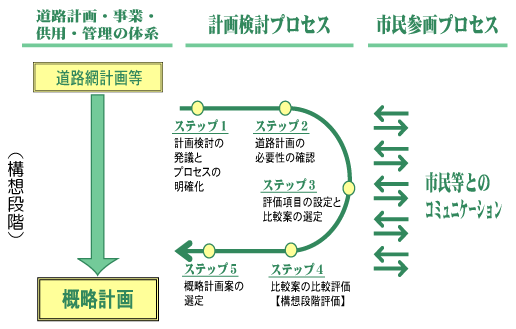
| (1)概略計画の決定 道路管理者が概略計画を決定するにあたっては、概略計画案をもとに次に掲げる観点を総合的に検討して判断するものとする。
道路管理者は概略計画として基本的には次の事項を定める。
道路管理者は、概略計画を決定した場合には、これを公表するものとする。 なお、概略計画を決定した区間が都市計画区域内にある場合には、必要に応じ、都市計画決定権者と連携して、それぞれの都市計画区域における整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)に位置づける等の措置を講じる。 (4) 概略計画の効力 概略計画の内容は、詳しい計画精度には至っていないため、その決定をもって私権を制限するような効力(建築の規制等)が生じるものではない。しかし、概略計画は、当該道路計画の必要性や比較案の比較検討等について適切なプロセスを経て意思決定されたものであり、その決定をもって次の段階(図1に示す計画段階)へ進むことが適当であるとの評価がなされたとみなすことができる。 |
概略計画の決定は、適切なプロセスを経て選定された概略計画案をもとに、道路管理者が行います。市民参画プロセスを実施するということは、必ずしも「市民参画で得られた結論をそのまま概略計画にする」ということではなく、「市民参画で得られた情報を、意思決定にあたって考慮する重要な要素にする」ということであることに注意が必要です。
また、「計画検討プロセスの適切性及び市民参画プロセスの妥当性」については、本ガイドラインに示す標準的なプロセスが適切に実施されている場合には、この要件を満たしているものと解してよいものと考えます。
概略計画において決定する事項は基本的に以下の内容とします。なお、その一部について概略計画の段階では定めることが困難な場合には、その旨を記載するものとします。
| ①起終点 | : | 当該路線の起点及び終点の所在地の市町村名を記載します。 |
| ②道路種別 | : | 計画する道路の種別が道路法第三条に規定されている高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のいずれに該当するかを記載します。 |
| ③計画諸元 | : | 計画する道路の標準車線数及び設計速度(単位:km/h)を記載します。 |
| ④構想ルート帯 | : | 概ね1/25,000~1/50,000の縮尺の図を用い、計画する路線の位置を概ね250m~1km程度の幅を持つルート帯で図示します。なお、検討の結果、より広い幅でルート帯を決定し、計画段階以降のより詳細な検討を踏まえて具体的に絞り込んでいくことも考えられます。 |
| ⑤主な連結する道路 | : | 当該計画道路に連結する、あるいは連結する予定のある主な道路について、その連結位置が所在する予定の市町村名及び連結する道路の名称を記載し、ルート帯上に図示します。 |
| ⑥主たる構造 | : | 計画する道路の構造を盛土、切土、トンネル、橋若しくは効果、その他の構造の別に区別して記載します。なお、区間により、構造が異なる場合には、一定延長の区間毎(区間の起終点を市町村名で記載)に構造を記載し、必要に応じルート帯上に図示します。 |
| ⑦その他必要な事項 | : | 計画段階において考慮すべき事項(例:接道条件や、交通管理等)がある場合には、その旨を記載します。 |
なお、必要に応じて、①~⑥のような道路の諸元のほかに、道路計画の目的や計画決定の判断根拠(コントロールポイント等も含む)も含めて概略計画の内容として決定し、公表することもできます。
道路管理者は、決定した概略計画が広く市民等に認知されるよう努める必要があります。その際の公表等の方法には、広報誌、ホームページ、マスメディアを通じた情報発信等があります。
概略計画は、環境影響評価手続の前提となる計画で、方法書に記載する事業内容とすることができます。
道路計画と都市計画の方針との整合を図るため、構想段階から都市計画決定権者と連携を図り、決定した概略計画を都市計画区域における整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)に位置づけ、沿線地域の将来像との調和が図られるようにしておくことが望ましいと考えられます。
概略計画は、次の計画段階(都市計画決定手続等)における検討の基本となるものであり、都市計画手続に諮る計画案について基本的な事項を決定するものです。
概略計画の検討過程において市民参画プロセスが適切に実施されることにより、「公益性の観点から、より詳細な計画の段階(次の計画段階)に進めて検討することが適当と認められた案を得た」と考えることができます。
概略計画は、概略設計の前提となる基本的事項(起終点やルート帯等)程度の精度で決定されます。概略計画における精度をこの程度とする理由は、構想段階において議論すべき公益的な視点に留まらず、計画段階で議論すべきこと(地域的な利害調整等)までが構想段階で論点となり議論が混乱することを避けるためです。
構想段階においては、以下の段階的な手順(計画検討プロセス)に沿って計画検討を進めることを標準とする。
|
ステップ5で概略計画案の正当性を示すためには、ステップ4で対策をしない案(比較評価のベースラインとする)も含めて現実的で合理的な複数の比較案を比較評価して比較優位性を示すことが必要ですが、比較優位性を検証するためには、ステップ3で選定・設定される比較案や評価項目が適切であることが求められます。
また、評価項目の適切さを示すためには、ステップ2で道路計画の目的やその背景にある課題を明らかにしておく必要があります。
このような手順を踏まずに検討を進めると、概略計画の決定に際して、当初の課題や目的の設定に問題がある等の指摘を受ける可能性もあります。このためステップを区切りつつ段階的に検討を進めることが重要です。
ステップ3~5については、道路計画の内容や検討対象となる地域の状況に応じて、様々な工夫が考えられます。
例えば、ルート位置について複数の比較案を提示する代わりに、道路整備が考えられるエリア全体を覆うような幅広のルート帯を示し、その後の検討でルートとすることが望ましくない範囲を削っていくことによって最終的なルート帯を確定する方法をとった事例もあります。
このように、計画検討プロセスの合理性を確保できるのであれば、個別案件の状況に応じて本ガイドラインと異なるプロセスで検討を進めることも可能です。
計画検討プロセスは、基本的には次のような流れで実施されます。
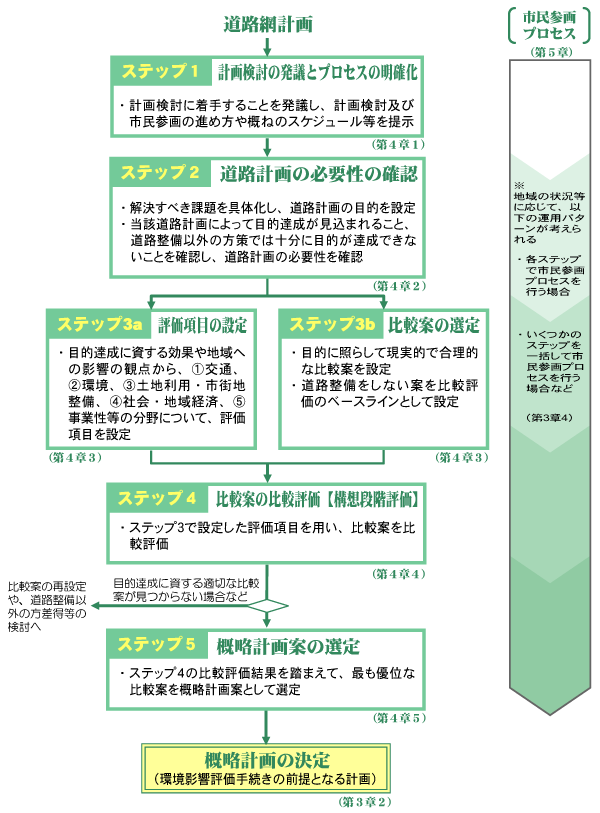
図 計画検討プロセスの流れ
※各ステップの詳細は第4章を参照
| 構想段階において計画検討プロセスを進める際には、市民等とのコミュニケーション活動(市民参画プロセス)を行い、積極的な情報提供を行うとともに、計画検討に生かすべき情報の入手に努めるものとする。 市民参画プロセスは、計画検討プロセスのステップ毎に実施することが望ましいが、前後するステップについて一括して実施する等、状況に応じて適切に実施方針を選択することができる。なお、複数ステップについて一括実施する場合にも、プロセス全体を通じた全ての内容について市民参画プロセスを行うことが必要である。 |
市民参画プロセスは、計画検討プロセスのステップ毎に実施することを標準としますが、地域の状況やこれまでの経緯等を踏まえて、実施のタイミングを決めることが重要です。
例えば、道路計画に考慮すべき要素や関係者があまり多くない場合には、前後するステップを一括して市民参画プロセスを実施したり、逆に複雑な利害関係が伴う計画の場合には、ステップを細かく区分してそれぞれ市民参画プロセスを実施したりする場合等が考えられます。
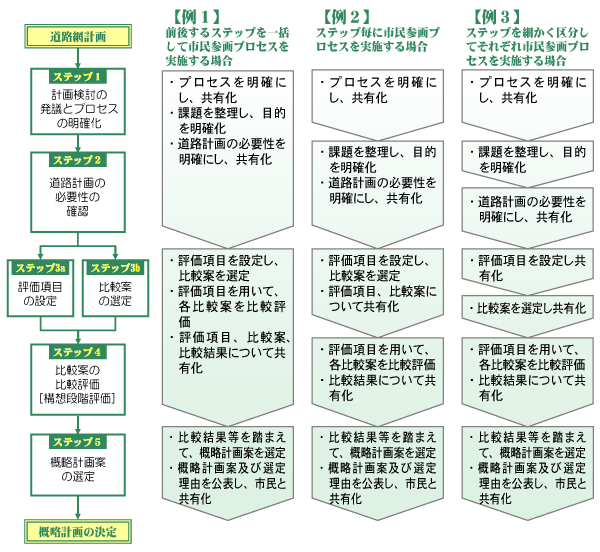
図 市民参画プロセスの運用例
| 構想段階における検討を効率的に進めるために時間管理概念の導入が有効である。そのため、構想段階の検討着手時に計画検討及び市民参画に関わる実施方針(具体的な進め方や概ねのスケジュール等)を計画するものとする。計画検討プロセスに要する期間は、計画の規模や複雑さ、経緯等を勘案して適切に定めるとともに、ステップ1に関する市民参画プロセスにおいて、市民等とのコミュニケーションを十分に行い、プロセスの進め方を明確にしておくことが必要である。 |
構想段階における検討を効果的に進めるためには、予め定めたスケジュールを市民等と共有し、そのスケジュールに基づいてプロセスの進行を管理することが重要です。期限までに結論がでなかった場合には、その時点までの決定事項を一度とりまとめた上で、改めてスケジュールを設定し直す等の工夫が必要です。
なお、市民参画プロセスに要する期間は市民参画プロセスの進め方等により異なると考えられますが、過去の事例では、計画検討の発議をしてから概略計画の案を選定するまでに、6ヶ月~18ヶ月程度をかけている例が多く見られます。