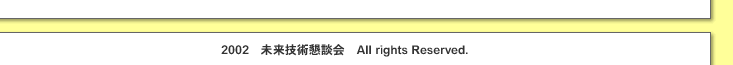|
|
| 技術論として、セメントを使ったコンクリートが20世紀の建設技術を支えた大きな建設資材であったことは確かで、都市の空間でもコンクリートにより鉄骨を支えながら、1つの工事を進めてきたことは確かである。しかし、果たしてコンクリートに未来性があるかというと、断定的になるがコンクリートには未来がない。 建築学会でもお話ししたが、コンクリートを使わない21世紀、22世紀というのが建設技術の最大のテーマになるのではないか。コンクリートが花を咲かせたのは20世紀であり、歴史が変化して行く必要があるのではないか、ということである。 構造物が非常に軽量化することや、施工が容易になるというプラス面も含めながら、コンクリートではない新しい建設資材について語り合うことができたら良い。その際に、あなたは何を予想しているのかと聞かれるので、私の考えというよりも、答えないと提案が虚しくなるということで、「シートや幕を使うことをもっと徹底するべきではないか」と、あえて提案している。 建造物でも、コンクリートをやめて鉄と布で建物ができないだろうか、道路の舗装も、アスファルトという時代ではなくシートによって舗装したらどうか、車道についても将来は広がっていくのではないか、河川工事においてもコンクリートを一切やめてシートで覆うことでコントロールすることを開発できないだろうかと考える。 そのシートは今、アメリカを中心にロシアも加わって、人工衛星の幕ということが大テーマであり、NASAが月ロケットを打ち上げ、月の路上を兵隊が宇宙服を着て歩いた実績ができた。その宇宙服の布はどのような技術でできているのか興味があり、地球上でも宇宙ロケットで兵隊が着た洋服を着て、あるいは都市がその布で覆われていれば、環境やリスクに対して、非常に対応し得るのではないかと考えた。 その幕は、水分や温度や気象に対応することが非常に上手くできており、一方に向かって透浸性がある。逆の透浸性がない幕を見た時は感動し、これが人間の建設資材になる日はいつ来るだろうかと考えた。セメント工場が滅び、繊維産業が建設資材の提供者になると言うと、関西のある大きな繊維業者の方が、「繊維産業の将来性が極めて暗いので、今日は良い話を聞いた」と言った。人間の生活空間全てを繊維産業で供給して行くことはとても良いことである。 耐震分野の一番大きな技術的問題は重量に耐えることであり、コンクリートと鉄でつくられたビルは、重量に非常に弱体である。状況によってはニューヨークのようになる訳であり、それは重量が過重であることに起因するので、ものすごい軽量化が進み、非常に軽量なビルであれば全く問題が違うというようなことを議論した。 徐々にITという形が進み、単なるITが通信技術を進歩させることにとどまらず、建設技術のロボット化にどのような役割を果たすのか、非常に興味のある問題である。デジタル技術が最近異常なほど進歩し、この非常に高い技術を何にどのように利用したら良いのかということを技術屋達は悩んでおり、私を呼んで、「建設畑で自分達の技術を利用する広場が広がらないか」と言う。デジタル技術の研究会としては、自分達の開発した技術の利用の仕方というところへ、既に問題が移っている。 技術の進歩は毎日進み、今できた技術や研究費を得るために売っていくことと並行して動いていくので、技術が進歩してまた売って、また売ったら技術が進歩してということの繰り返しになることは言うまでもない。 しかも、沢山の技術者が個人的な能力でその開発をしており、大会社といえどもチームを組んではいるが、個人的なレベルの技術開発が中心になっており、小さなグループでもそれが可能になる。現在のシリコンバレーのようなことが動いている訳で、日本もここへ来て、小グループあるいは個人が技術開発を進めていくために、非常に快適な環境を持ったシリコンバレーをつくる必要がどうしてもあるのではないか。 シリコンバレーはどのような形でつくったら良いかと考え、アメリカや世界に広がってきたシリコンバレーの形を少し聞いたりすると、なかなかおもしろい宿題が多く、少なくとも日本でシリコンバレーをつくるとしたらどういうことが問題になるか、皆さん方の間でも議論にしていただくことが必要ではないかと思う。 どの国のシリコンバレーも、成功しているインフラストラクチャーとしては、むしろ大学というものがテーマであり、シリコンバレーにつながり得る能力を持った大学ということが成功のカギになっているということは明らかである。その大学とは、国際的に開かれており、国籍を問わない教授陣であり、しかも、ある程度の研究費を用意されているけれども、企業に研究費を頼っているという形が多い。これは、中国でも台湾でもインドでも、どんどん進んできている点である。日本ではシリコンバレーに適した大学が建設できるかどうかということの方が、シリコンバレーそのものよりもなかなか難しい問題になるであろうということで、私は乱暴ではあるが、日本のシリコンバレーは日本の大学でない方が良いと思う。 どこの国でも、開放された国の大学が、日本のシリコンバレーに立地することを特例的に認めてもらったらどうだろうかと思うほど、大学というのは重要である。技術が大学とドッキングして、シリコンバレーで現実につくられて、それを利用する企業群がそのシリコンバレーに立地するという姿がおもしろい。このようなものを国土交通省や国土技術研究センターなどで徹底的に企画を立案すれば、非常におもしろいことになると考えている。 次に、実際の生活空間における環境問題の基本である車の問題、電力の問題やゴミの問題ついて述べる。 車社会をどのようにつくるのか。車自体を根本的に変えてしまうということもある。電力についても、水力、火力、原子力というような系列で良いのかどうか、安全が確保できるのか。同時に、風力発電についてもっと徹底した方が良いのではないか。 アメリカの中には、アメリカの電力の半分が風力発電になると言う人もいる。日本列島の風力は、どの位の蓄積を持っていると見たら良いかということも議論である。 そしてゴミについては、生活廃棄物から産業廃棄物に至るまで国土に捨てられており、処理するといっても、液体、固体、気体という空回りをしているだけである。何らかの形でポリウレタンを捨てていくということは、時間が蓄積すると大変なことになる。日本は海に恵まれているため、固体化して海に捨てるということが今までできていたために何とかなっているが、これから海に固体のゴミを捨てることをやめようということになった途端に一体どうなるのか。その時にはゼロエミッションで、ゴミがでない社会を創作しようという意見まで出てきているのが現状である。 しかし現在では、既に環境ホルモンによる人体やあるいは自然への被害が現実のものとなっており、しかも被害が非常に微小であるということで、そのままに放置されている。時間が経って子供や孫や曾孫という代を経た時に、環境ホルモンがどのような影響を持って現れてくるかということは、想像するのも嫌な位怖い話である。今から生まれてくる人達は、少し容易ならざる社会に真正面からぶつかることになると思う。 最後に、そのような環境ホルモンの議論が出る前提には、日本列島に住んでいる人間が食べ物をつくらないで7割方輸入に頼っており、輸入の農産物は全部有害であるということがある。この有害な輸入農産物を食べ続けていると一体どういうことになるのか、もっと真剣に議論すべきではないか。薬に頼ろうというロシア型の意見もあるが、薬になれば副作用の心配がある。 それでは、一体どのような農業を行えば良いのか。日本が日本の国土条件の中で、どのような農作技術をつくり上げれば良いのかという意味では、農産物に対する技術も国土技術の一環ではないか。特に土壌との関係では、農業は非常に大きな影響を受けることになるので、日本の国土技術ということを言う限りは、日本全国の土壌の条件を知り尽くさなければできないだろうということになる。 最後に、今日お話しした全てのことを総括する意味では、やはり人口に関する国勢調査が政策の決定に大きな影響を与えており、これから人口が激減していくことも、国勢調査によって明らかになってきている。国勢調査が人口であるならば、国土というものの調査を国勢調査としてやるべきではないだろうか。 環境庁が、緑の国勢調査を少しだけ行っているが、やはり人間の情報、土壌の条件も含めて、自然環境とともに国土の情報を国勢調査レベルで5年毎にきちんとできないだろうか。この情報マップができれば、国土管理も、もう少し科学的な根拠を持ってできるのではないか。 私の時代は、声の大きい人の意見を作文で綴り合わすという低いレベルであるが、いろいろな人の意見を聞くとともに、国勢調査のデータが完成し、それをコンピューターが完全に処理してくれることから科学的な22世紀の国土計画ができる、そこまで行ってほしいと考えている。 |
| ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |