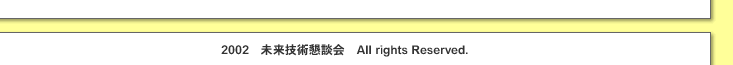|
【冨岡委員】
 下河辺顧問がお話しされた、これからの国土技術のロボット化、生産性向上や工期短縮の技術によるCD技術は、建設業に携わる我々の課題として取り組んでいる。今まで建設に使った材料は、鉄やコンクリートにしても、その内容を「より強くより軽く」という目標でいろいろ行ってきたと思う。今後それに加えて、より簡単にであるとか、より長くであるとか、再利用可能などがキーワードになると思い、コンクリートに変わる新材料は何かと、私達は大変興味を持っていた。 下河辺顧問がお話しされた、これからの国土技術のロボット化、生産性向上や工期短縮の技術によるCD技術は、建設業に携わる我々の課題として取り組んでいる。今まで建設に使った材料は、鉄やコンクリートにしても、その内容を「より強くより軽く」という目標でいろいろ行ってきたと思う。今後それに加えて、より簡単にであるとか、より長くであるとか、再利用可能などがキーワードになると思い、コンクリートに変わる新材料は何かと、私達は大変興味を持っていた。
1つには、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーの進歩により、新材料が多少生まれるのかという感じはした。今日、下河辺顧問が幕、シートというお話をされたが、シートとは、今までも東京ドームに使用しているようなシートのことを指しているのか、どのようなシートについて述べられているのかお教えいただきたい。
【下河辺氏】
私は、アメリカの人工衛星の開発をしている人達に使用しているシートのことを聞いた時に一番興味を持った。それは国家の力で技術開発しているのだが、成功すれば、このシートは一般の市民が使う材料にまで展開するだろうと思った時に楽しくなったということが出発点である。
縦割りが問題であるとか、各省の意見がバラバラで連絡もないであるとか、そのようなことが新しい技術開発にとって問題だという指摘があるが、私はそれに全面的に反対である。縦割りが極度に闘わなければ行政も企業の組織も成長はないと思っている。今は官庁でも企業でも同じで、縦割りがいけなくて連絡しなくてはいけないと言っているが、忙しくて本質的なことは何もしていない。
社長は、リーダーシップより、和やかな会社をつくる努力が最大限の仕事になっている。それでは日本は駄目だろう。私の役所に対する一番の期待感は、ますます縄張り争いをし、そこから何が生まれるかということである。畑村委員がお話しされたたように、大部分は失敗に終わっていくので、それで良いのだと役人が覚悟する方が良いと思う。成功した場合は、不思議なことが起きたと思えば良い。
【谷村技術総括審議官】
畑村委員は「失敗を生かすために失敗を立体的に捉え、その中で、原因究明と責任追及を分離しよう」とおっしゃられたが、その点について少し解説をお願いしたい。
自分が考えている問題意識を事例でお話しさせていただく。私は、製造業、造船業が専門であり、ナホトカ号の事故当時、原因究明担当責任者であった。あの時に分析をしていただいた結果、「あの波浪条件の中で耐えられる板圧になっていなかった」と日本は結論づけたが、ロシア側はそのような分析をしなかった。きちっとした手続を踏んだ上で、「未知との遭遇」があって沈んだと結論づけたのである。
その裏側には、保険に対する付保の問題や、リスクに対するマネジメントの議論があった。それで、これは水掛け論のまま、最終的に上手くいかないだろうと思った。原因究明をしないと再発防止ができない。ある時から再発防止と原因究明とを分離し、再発防止だけはロシアと日本と共同提案で、国連の専門機関に出して対策をつくった。その際、原因究明とそれを妨げる様々な制度とが現実的には混在しているように感じたが、これが疑問である。
もう1つ似たような話がある。原子力関係で少し語弊があるかもしれないが、担当していた時に、原子力使用済み燃料を運ぶ輸送容器とつくりかけの輸送容器の改ざん問題があった。その際、もう一度手続きを原点に戻し、最初から再度チェックを行った。
運輸省に与えられた担務事項とは、純粋に科学的、技術的にイエス・オア・ノー、あるいは正しいか、正しくないかの判断をしていくことだと理解していたので、もう一度最初に戻ってやり直せば、改ざんをした容器ももう一度使えるという判断で、繰り返しをして行った。
国会でこのことについて、女性の議員の方から50分位問答を受けた。その時に述べられた中で気になることが1つだけあり、それは、再発防止をするためには、もう一度仕組みをきちんと考え直していかなければいけないということである。このような場合、科学的、技術的事項以外の事項として、罰則であるとか、ディスアドバンテージを与える措置をとる必要があるのではないか。ここの部分は、私達に与えられている担務事項、つまり、法律で決められた担務事項とは全くかけ離れた社会的責任を追及する、社会的制裁を加えるというような話である。
例えば、失敗や改ざんした容器はそのまま捨て、新しい容器ももう一度再投資をしてつくり直す程度のディスアドバンテージを与えなければ、再発防止にはつながらないであろう。そこは何となく釈然としないまま終わったが、この2つの事例を見ると、失敗を立体的階層で考えるという話は非常に興味がある。
その中でもう1つ、原因究明と責任追及とを分離する話があるが、私は、そうはならないのではないかと感じている。この点について解説をお願いしたい。
【畑村委員】
日本中のメンタリティーが、今述べられた中に全部抜けていて、しかし、ひそかに皆が期待しているのが、溜飲を下げるということである。何か実行した人が責任をとり、その人が困った状態になると皆がスーッとする。非常に人間のいやらしい部分であり、日本には理屈で動かなくてはいけない部分と、溜飲を下げる部分とが混在しており、それがいろいろなところに顔を出すような気がする。
例えばペナルティーを与えるのであれば、実物が本当に使えるものであれば再度使い、ペナルティーとして与えようとする金額分だけ払わせれば良いと思う。何も無駄にすることはない。私は、それを捨てないと皆が納得しないのは、ほとんど情緒の世界だと思う。
それで、政治が情緒の世界の中で動きやすい。すると、皆マスコミがおかしいから、何がおかしいからと言う。日本人の考え方の中に、溜飲を下げることを期待するところがあり、そのことが原因究明と責任追及とを混同し、分離ができないでいる理由であると思う。
法律に携わる人達と議論しても日本の法体系では無理だと言うが、先進国で行わないのは日本だけである。法律に携わる人達が怠慢だからである。日本の法体系を変える時期が来ているのに実行せずに、まだ法律的に見た時にその方が良いと言うのは、怠慢だと思う。
本当に変えないと、失敗の取り扱いがきちんとできないために、日本の国力がどんどん落ちていくのではないか。とにかく、物の見方をきちんと変える分だけ変え、議論すべきものを議論し、これでやろうか、としなければならない。責任追及と原因究明とを分離しないために同じことが繰り返され、だれも本当のことを話せない。
今、残念なのは、技術者が正当な扱いを受けていないことである。技術者は、なぜ理科離れが起きているか言わないが、子供達は、お父さんが社会から尊敬を受けないで不当な扱いを受けていると見ている。故に理科離れが起こる。
社会の中でより一層理科を扱い、真に技術者が尊敬を受けるような社会運営をしない限り、日本中がツケを払うことになると思う。真の意味の尊敬を受けるとは何か。例えば賭けをし、その賭けが上手く行く。上手く行かないという時には、仮に上手く行かなかったとしても当たり前ではないか。日本の社会は賭けをできるだけすばらしいと考えなければならないと思う。
典型的な例がロケットの開発である。小さなことを失敗し、皆で溜飲を下げているやり方は、日本を本当に駄目にすると思う。もっとおおらかにすべきである。原因究明と責任追及とを分けると、その時からいろいろなものが変わるのではないか。
|