|
|
���z��@�ɂ�����s�s�v�搧�x�̌��������Ɋ֘A�����ۑ�
�ւ̑Ή��ɂ��� |
 
|
�����P�Q�N�Q���W���@
���z��@�ɂ�����s�s�v�搧
�x�̌��������Ɋ֘A�����ۑ�ւ̑Ή��ɂ���
���z�R�c��z�s������
�s�X�n�����ȉ�
�@���z�R�c��ł́A���ݑ�b���畽���V�N�P�P���W���t�����ݏȏZ�w����R�U�T���y�ь��ݏȉc�ǔ���U�P�Q���������Č��z�R�c��Ɏ���̂������u��\�ꐢ�I
��W�]���A�o�ώЉ�̕ω��ɑΉ������V���Ȍ��z�s���݂̍���ɂ��āv�����R�c���s���A�����X�N�R���Q�S���Ɂu��\�ꐢ�I��W�]���A�o�ώЉ�̕ω��ɑΉ�
�����V���Ȍ��z�s���݂̍���Ɋւ��铚�\�v���s�����B
�@�����\�Ɋ�Â��A�����X�N�ɋ����Z��̘L���A�K�i�ɌW��e�ϗ��s�Z�����x������e�Ƃ���s�s�v��@�y�ь��z��@�̈ꕔ�������A�����P�O�N�Ɍ��z�m�F�E
�����̖��ԊJ���A���z��̐��\�K�艻���̂�����P�̋K��̊�̌n�̌������A������A�S���z���v���x�̓����A���Ԍ����̓����A�m�F�������Ɋւ���
�}���̉{��������e�Ƃ��錚�z��@�̈ꕔ�������A�����P�P�N�ɏZ��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@���̐��肪�Ȃ��ꂽ�Ƃ���ł���B
�@���̓��\�ɍۂ��āA���z��@�̏W�c�K��ɂ��Ă͈�������������i�߂邱�ƂƂ��ꂽ���Ƃ���A�����P�P�N�X���ɁA�s�X�n�����ȉ���ĊJ���A�W�c�K��
�̊e��`�Ԑ������ɂ��Ă̑��_�������������i�߂邽�ߊ�E���x���ψ����ݒu�����B���̒��ŁA���}�ɑΉ����ׂ��d�v�ȉۑ�Ƃ��āA�s�s�v�撆���R�c��
�ɂ�����s�s�v�搧�x�̌������Ɋ֘A�����W�c�K��y�і��W�s�X�n���ɂ����錚���������̎戵���ɂ��āA�d�_�I�ɒ����R�c���s���Ă����B
�@�{�́A������Ƃ�܂Ƃ߂����̂ł���A�R�c�ɎQ�������ψ��͎��̂Ƃ���ł���B
|
| ��
�@�@�� |
��
�яd�h�i�s�X�n�����ȉ�@��E���x���ψ���卸�j�A
�H�{�@�q���A�L�g�@�F��A���@�������A��
�R�@�ǎq�A�����@���A
�ЎR�@���v�A��
��@�K�Y�A�S
���@���A��c�@�}���q�A�G
�@�����A
�K���@�ΐl�A��
�J�@���A��
�c�@�B�v�A���{�@�����A��
�{�@�P�Y�A
�X�@�� |
| ��
��ψ� |
��
���@����Y�A�勴�@�m���A��
���@�����A����@���A���
�@���p�A
�����@�ǎO�A��
�������A
�@����@�G�v�A����@�� |
| �I
�u�U�[�o�[ |
��
���@���Y�i���z�s������j�A�{�V�@���q�Y�i���z�s������㗝�j |
|
|
�@�Ȃ��A���@������A���@�K�Y�A�S���@���A�K���@�ΐl�̊e���͕��ȉ�ψ��ł��������A�r���A�C�������ɔ����ޔC�����B
|
|
 |
 |
 |
|
|
 
|
�@���z��@�́A���z���̕~�n�A�\���A�ݔ�
�y�їp�r�Ɋւ���Œ�̊���߂Ă���A���̂����W�c�K��́A�~�n�̐ړ����̓��H�W�K��A�p�r�����A�e�ϗ������A�����������A�ΐ������A���e�K���A
�n��v��Ȃǂ���\������Ă���B
�@�W�c�K��̊e��`�Ԑ������̑��_�����s����ŁA�W�c�K��������v�ȉۑ�Ƃ��ẮA
�@�@�@����̕ω��ɑΉ������������̂��鐧�x�ƂȂ��Ă��邩
�@�A�@���L���Ȏs�X�n���̌`���ւ̃j�[�Y�ɏ_��ɑΉ����Ă��邩
�@�B�@�s�K�i���z����h�Џ�̖��ȂǂɓI�m�ɑΉ����Ă��邩
����������B
�@�܂��A�s�s�v�撆���R�c��ɂ����ẮA�s�s�v��@�����R�O�N���o�߂��ēs�s�I�����Ɠs�s�I�������߂���Љ�o�ϊ��̗l������ς��Ă��邱�Ƃ���A��
�s�̓s�s�v�搧�x�̑S�ʂɂ킽���Ă̌��������s���A�u�o�ώЉ�̕ω��܂����V���ȓs�s�v�搧�x�̂�����ɂ��āv�̓��\���s��ꂽ�Ƃ���ł���B��
�̒��ŁA���z��@�W�c�K��Ɋ֘A�������̂Ƃ��ẮA
�@�@�@���������x�y�ъJ�������x�̒n��̎���ɉ������_��̊m��
�@�A�@�����s�X�n�Đ����̂��߂̐V���Ȑ��x�̓���
�@�B�@���R�I����i�ςȂǓs�s���̕ۑS�̂��߂̐��x�̏[��
�@�C�@�s�s�v����O�ɂ�����J���s�y�ь��z�s�ׂɑ���K���̑n��
����������B
�@�{���ȉ�ɂ����ẮA�e��`�Ԑ������̑��_����i�߂钆�ŁA�����̓s�s�v�搧�x�̌������ɂ������ۑ�ƁA���W�s�X�n���̍X�V�𑣂������������̍�
�����ɂ��āA���}�Ɍ�����i�߂�ׂ��ۑ�ƈʒu�Â��A�s�s�v�撆���R�c���{��������v�搧�x���ψ���ł̐R�c�Ƃ��A�g��}��A�R�c���s���Ă����B
�@�{�́A�����ɂ��āA���z�R�c��z�s������s�X�n�����ȉ�Ƃ��Ă̊�{�I�l�������Ƃ�܂Ƃ߂����̂ł���B
|
|
 |
 |
|
|
 
| �i�P�j�s�s�v������̗p�r�n��̎w��̂Ȃ���� |
|
�@���݂̓s�s�v��@�ł́A�s�s�v������s
�X�����Ǝs�X���������ɋ敪�i�������j���邱�Ƃ��{���Ƃ���Ă���A����ɂ��v��I�Ȏs�X
�n������}�邱�ƂƂ��Ă���B���̏ꍇ�A�s�X����}�����ׂ����ł���s�X���������ɂ����ẮA�J�������x�ɂ�薳�����Ȏs�X����}������ƂƂ��ɁA
�����Ƃ��ėp�r�n��͒�߂Ȃ����ƂƂ���Ă���B�������Ȃ���A�s�X���������ɂ�����J���̗}�����n��̊������̑j�Q�v���ɂȂ��Ă���Ƃ����c�_������
���Ƃ���A�s�s�v�撆���R�c��\�ŁA���������邱�Ƃ�{���Ƃ��鐧�x�����߁A�s�s�v���悲�Ƃɐ����������邩�ۂ���s���{���̔��f�Ɉς˂�����Ƃ���
���Ƃ����ꂽ�B���̏ꍇ�A�����������Ȃ��i��������j�s�s�v������̗p�r�n��̎w��̂Ȃ����ł́A�s�X����}�����ׂ����ł���s�X��������悪
��߂�ꂸ�A�J�����̂����闧�n����K�p����Ȃ����߁A�y�n���p�̍����������錜�O������B
�@���ɁA�p�r�n��̎w��̂Ȃ����ł́A��ʓI�ɂ͎s�X���̈��͂��Ⴂ���Ƃ����r�I�����e�ϗ������i�����S�O�O���j�A�����������i�����V�O���j���K�p
����Ă��邪�A���̂܂܂ł͍��e�ς̌��z�������z����邱�Ƃɂ����Ɠ��̑��W��̖��A��ʂ̋Ǐ��I�����Ȃǂ����������ꂪ�����Ȃ邱�ƁA�܂��A�p
�r�n�悪�w�肳�ꂽ���ł͂T�O���̗e�ϗ��������K�p�\�i��w�Z����p�n��̏ꍇ�j�ł��邪�A�p�r�n��̎w��̂Ȃ����ł͌��݂P�O�O���̗e�ϗ�������
�ł����K�p�ł��Ȃ��ȂǑI�����������Ă��邱�Ƃ���A�����I�ɗp�r�n����w�肷��ۂɌ��z�K����̕s�ύt�������邨���ꂪ����B
�@����ɁA�p�r�n��̎w��̂Ȃ����ł́A�p�r�������K�p����Ȃ����Ƃ���A�X�܁A�z�e���A���W���[�{�݁A�H��A�q�ɓ��̌��z�������z�����\������
��A���ӂ̐������ւ̈��e�����ʍ��G���̖�肪�����邨���ꂪ����B�@
|
| �i�Q�j�����s�X�n |
|
�@�s�s�̌��S�Ȕ��W�ƒ������鐮����}����
�������߂ɂ́A���Ɋ����s�X�n�ɂ����ēy�n�̗L�����x���p��i�߂Ă������Ƃ��d�v�ł���B���̂�
���A�s�S�����̏��ƒn��ł́A���Z���̊m�ۂ̊ϓ_�������ƁE�Ɩ��{�݂̏W�ς�}��ϓ_����A��Վ{�݂ɑ��镉�ׂ����Ă��A���x���p�����������
�悤�����e�ϗ����w�肳��Ă���A���e�K�����K�p����Ȃ��B�������Ȃ���A���x���p�̏����������Ă�������s�X�n�ɂ����Ă��A�ʂ̕~�n�P�ʂŌ���A��
�j�I���z���⌀��Ȃǂ̌��z���̓����A�w�Z�ɗאڂ���~�n�Ȃǂ̒n��̏��ɂ��A�w�肳�ꂽ�e�ϗ��̌��x�܂ŗ��p���邱�Ƃ�����͕s�K�Ȃ��̂���
��A�n��S�̂Ƃ��ēy�n�̗L�����x���p���\���ɐ}���Ă��Ȃ��ꍇ������B
|
| �i�R�j�s�s�v����O |
|
�@�s�s�v����́A��̂̓s�s�Ƃ��đ����I
�ɐ������A�J�����A�y�ѕۑS����K�v��������Ɏw�肷�邱�ƂƂ���Ă���B���̂��߁A���̏�
���������s�����̋��ɂ��ēs�s�v������w�肵�A�s�s�{�݂̐�����s�X�n�J�����Ƃ��s���ƂƂ��ɁA���̊J���s�y�ь��z�s�ׂ��K�����Ă���B
�@�������Ȃ���A�s�s�v����ȊO�̋��ɂ����Ă��A�����W�����ӂ⊲�����H�̉����A�������H�̃C���^�[�`�F���W���ӓ��𒆐S�ɁA�X�|�b�g�I�ɑ�K�͂ȊJ
���s�ׂ⌚�z�s�ׂ��W�ς��A���ӂł̌�ʏa�̔����A�p�r�̖������ȍ��ݓ��̖�肪�����Ă���B�����������ɑΏ����邽�߁A�s�s�v�撆���R�c��\�ɂ�
���ẮA�y�n���p�K���݂̂��s���d�g�݂Ƃ��Ďs���������s�s�v����i���́j���w�肷�鐧�x�̑n�݂���Ă���B
�@�Ȃ��A���z��@�ɂ����ẮA�s�s�v����O�ɂ������K�͂ȃ��]�[�g�}���V�������̌��݂ɔ������ւ̑Ή���}�邽�߁A�����S�N�̉����ɂ��A����
�s�s�v����O�ł����z���̌`�Ԑ������s�����Ƃ��ł��邱�ƂƂ��ꂽ���A���z���̗p�r�ɂ��Ă͐������Ă��Ȃ��B
|
| �i�S�j���W�s�X�n�� |
|
�@��s�s�𒆐S�ɍL�����݂��Ă���h�Џ�댯�Ȗ��W�s�X�n�ɂ����ẮA�ЊQ�ɋ�
���܂��Â���𑁋}�ɐ��i���Ă������Ƃ����߂��Ă���B�����̎s�X�n�́A��ʓI�ɏZ���n�p�r�n��⏀�H�ƒn�悪�w�肳��A���������U�O���ɐ�������
�Ă���A���ɋ����ȕ~�n�ł́A���đւ����Ƃ��Ă����z�v�悪����������邱�Ƃ���V�����z���̍X�V���i��ł��Ȃ��B���̂��߁A���H���̌����{�݂̐���
��s�X�n�ĊJ�����Ɠ��ɂ��ʓI�Ȑ��������������i�߂�ƂƂ��ɁA�X�̌��z���ɂ��Ă����̑ωΐ��\��L������̂ւ̋����I�ȍX�V�𑣂����Ƃɂ��A
�n��S�̖̂h�ΐ�����S���̌����}��K�v������B
|
|
 |
 |
|
|
 
�i�P�j�s�s�v��
�����̗p�r�n��̎w��̂Ȃ����
|
|
�@�@�`�Ԑ����̌�����
�@�s�s�v������̗p�r�n��̎w��̂Ȃ����ɂ����ẮA���݁A�e�ϗ������S�O�O���A�����������V�O���������Ƃ��A����s�������w�肵��������
�́A���ꂼ��P�O�O���A�T�O���܂Ő������������邱�Ƃ��ł���B���̎d�g�݂����߁A�y�n���p�̎��Ԃɑ������K�����K�p�����悤�A����s����������K���l
��I������d�g�݂Ƃ���ƂƂ��ɁA�����w�Z����p�n����݂̗e�ϗ������T�O���A�����������R�O���܂œK�p�\�ƂȂ�悤�K���l��lj����邱�Ƃ��K�v
�ł���B�܂��A�e�ϗ������A�����������Ƃ����܂��Č��ʓI�Ȑ����ƂȂ�悤�ΐ���������e�����ɂ��Ă�������}����������s�����Ƃ��K�v�ł���B
�A�@����̗p�r�̌��z���̌��z�̐���
�@��������s�s�v����̂����p�r�n��̎w��̂Ȃ����ɂ��ẮA�J�������x�̂����闧�n����K�p���ꂸ�A�y�n���p�̍��������O����邽�߁A�y�n
���p�K����@�̏[�����K�v�ł���B��̓I�ɂ́A�n�������c�̂��A�������ׂ����z���̗p�r�̊T�v���߂����p�r�����n��i���́j��s�s�v��Œ�߁A���Y�n
��̗ǍD�Ȋ��̌`�����͕ێ���}�邽�߂ɁA���z��@�Ɋ�Â����Ō��z���𐧌����A���z�m�F�ŒS�ۂł���悤�ɂ��ׂ��ł���B
|
|
|
�i�Q�j�����s�X
�n
|
|
�@�n��S�̂̍��x���p�̂��߂̏�����������
����ɂ�������炸�A���x���p���\���Ɏ�������Ă��Ȃ��ꍇ�ɁA����𑣂��d�g�݂��[������K�v������B���̂��߁A��s�s�̓s�S�����̏��ƒn��̂����A��
�H�A�S���A���������̊�Վ{�݂��\���ɐ������ꂽ���ŁA���A���ʂ̊�Վ{�݂Ɏx�����Ă���n��ɂ��āA�n��S�̂̓y�n�̍��x���p��}��ׂ�����
�s�s�v��Œ�߁A���Y�����ɂ����ẮA����s�������A�n��̎���ɂ����������I���K���ȓy�n���p��}�邽�ߕK�v�Ɣ��f����ƂƂ��ɁA��ʏ�A���S��A
�h�Ώ�y�щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�肷�邱�Ƃɂ��A�Q�ȏ�̕~�n�̌��z���ɂ��ĕ~�n�ʐϋy�щ��זʐς����ꂼ�ꍇ�Z���ėe�ϗ�������K�p���A�����p�e��
�������p�ł���悤���ׂ��ł���B
�@���̍ہA���j�I���z���̕ۑS���n�̑n�o���̎s�X�n���̈ێ������}�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���ƂƂ��ɁA���炩���ߓ���s���������f�E�F�����
�߁A���\���ׂ��ł���B
�@�܂��A���̐��x�̎��{�ɓ������ẮA��c�n�̑����I�v���x�y�јA�S���z���v���x�Ɠ��l�ɁA���̎����������A�c�����铙�F��ɌW��y�n�ɂ��Ă̎�
���̈��S�����m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B
|
|
|
�i�R�j�s�s�v��
���O
|
|
�@�s�s�v�撆���R�c��\�Œ��ꂽ���s
�s�v����i���́j�́A�s�s�v����O�̋��̂����A���z���̌��z���͂��̕~�n�̑��������ɍs���A���͍s����ƌ����܂�A���z���̗p�r�̐�����i�ς�
�ێ�����}��K�v���������ƔF�߂�����ɂ��āA�s�������w�肷����̂ł���B�܂��A���̋��Ɍ���ł���s�s�v��́A�p�r�n��A����p�r�����n��
�i���́j�A���v�n�擙���z���̗p�r������i�ς̈ێ����ɌW��n��n��y�ђn��v��Ƃ���Ă���A�J�������x��3,000�u�ȏ�̊J���s�ׂ�ΏۂɋZ�p��
����K�p���邱�ƂƂ��Ă���B
�@���̂悤�ȏ��s�s�v����i���́j���n�݂��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�s�s�v��ɂ���߂�ꂽ�p�r�A�e�ϗ��A���������̐����̎��������m�ۂ��邽�߁A�s�s�v���
��Ɠ��l�ɁA�ړ����̌��z��@�W�c�K���K�p���邱�Ƃ��K���ł���B
�@�Ȃ��A���z��@��U�W���̂X�Ɋ�Â����ɂ��ẮA�s�s�v����y�я��s�s�v����i���́j�ȊO�̋��ɂ����āA���z���̕~�n���͍\���Ɋւ���K�v
�ȋK�����s�����x�Ƃ��āA������������������ׂ��ł���B
|
�i�S�j���W�s�X
�n��
|
|
�@�V�����z���̌��ւ����i��ł��Ȃ����W�s
�X�n���̂����A���H������̐������i�߂��Ă��邱�ƂȂǂɂ����h�����Ɏx�Ⴊ�Ȃ��n�擙�ɂ����ẮA�Z���̈ӌ��܂��A��������n���m�ۂ���Ȃǒn
��S�̂̋��Z���̌����}�錚�z���[������߂�ꂽ�ꍇ�ɁA�����������̊ɘa�ɂ��X�̘V�����z���̋����I�Ȍ��ւ��𑣐i����d�g�݂�݂��邱�Ƃ�
�K�v�ł���B
�@��̓I�ɂ́A�גn���Ɍ��z��@��S�U���Ɋ�Â��ǖʐ��̎w���n��v��ɂ��ǖʂ̈ʒu�̐������Ȃ���A�w������ɉ����ĘA���I�ȋ�n���m�ۂ���邱
�Ƃɂ��A���H���̋�n�ƕ����āA��ʂ���̍̌���ʕ����m�ۂł���ꍇ�ɂ́A���ωΌ��z�����Ƃ��邱�Ƃɂ��ωΐ��\�̊m�ۂ�A�גn���̊J�������𐧌�
���邱�Ƃɂ�鉄�Ėh�~���ʂ��X�ɕ]�����邱�Ƃɂ��A�ʂɌ������������ɘa�ł���悤�Ȏd�g�݂�݂���ׂ��ł���B
|
|
 |
|
|
|

|
�@����A���z��@�W�c�K��ɂ��āA���z
��@�����z���̕~�n�A�\���A�ݔ��y�їp�r�Ɋւ���Œ�̊���߂���̂ł��邱�ƂƂ̊W���܂߂āA���_����i�߂Ă����K�v������B
�@���̏ꍇ�A���z��@�W�c�K�肪�A����̕ω��ɑΉ������������̂��鐧�x�ƂȂ��Ă��邩�A���L���Ȏs�X�n���̌`���ւ̃j�[�Y�ɏ_��ɑΉ����Ă���
���A�s�K�i���z����h�Џ�̖��ȂǂɓI�m�ɑΉ����Ă��邩�Ƃ������ϓ_����_�_�����A�Ⴆ�A���ɓK�p����Ă���K���ɂ��ċ��E�F���@���܂�
�č������ł�����͍̂��������A���s���x�őΉ��ł��Ȃ����̂ɂ��Ă͕K�v�ȋK�����s������悤���x���[�����邱�Ƃ�A�n��̎���ɉ����Ēn�������c�̂�
�K����I�����ēK�p�ł���悤���x���[�����邱�ƁA����ɏZ���Q���Ɍ����Đ��x�̃A�J�E���^�r���e�B�����߂邱�ƂȂǂɂ��Č������ׂ��ł���B
�@�܂��A�K���ړI��K�����e�̖��m���A�s�X�n�̉ۑ�̉����Ɍ������K���̂�����A�n�������̗���̒��ł̋K���̂�����Ƃ��������_����R�c��i�߂Ă�����
�Ƃ��K�v�ł���B
|
|
 |
|
|
|

|
|
|
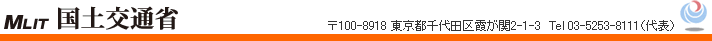 |
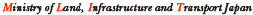 |
Copyright© 2000
MLIT Japan. All Rights Reserved. |
 |
|


















