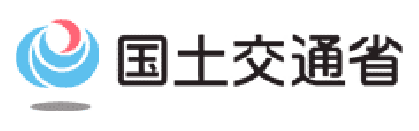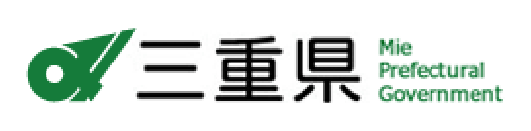開催地の紹介
開催地の紹介

三重の魅力
日本のほぼ真ん中に位置する三重県には、日本人の心のふるさととして親しまれる「伊勢神宮」や世界遺産「熊野古道」、伊賀忍者発祥の地、リアス海岸など、美しい自然や名所旧跡が数多く存在します。 三重は、そうした自然と文化、海山の幸に恵まれていることから、美し国(うましくに)といわれてきました。

英虞湾
志摩半島南部に位置する一番大きな入海。リアス海岸の特徴をもち、伊勢志摩サミットの会場となった賢島をはじめ無数に浮かぶ大小さまざまの島影が印象深く、真珠の養殖で有名です。 登茂山や横山といった展望台からの景色は写真撮影スポットとして知られ、特に美しいものがあります。

真珠
御木本幸吉翁が、世界で初めて真珠養殖に成功してからおよそ130年。手作業で行われる核入れをはじめ、卓越した技術によって育まれる一粒一粒。 先人のたゆまぬ努力、人と自然の力が生んだ神秘の輝きが、世界中の人々を魅了しています。

海女文化
鳥羽・志摩に伝承される、女性たちによる素潜り漁の技術です。海女漁は、古来より継承されてきたと考えられ、「万葉集」でも海女のことがうたわれています。 この素潜り漁の技術は現代まで引き継がれ、現在、鳥羽・志摩の海女の数は全国で一番多く、伝統ある海女漁の技術を守り続けています。

海の幸
海の幸の王様「伊勢えび」。ほのかな甘みを感じる活造り、プリプリの食感がたまらない炭火焼、豪勢なお味噌汁など、さまざまな食べ方で堪能できます。
食通も絶賛する高級ブランド「的矢かき」。豊かな海でふっくらと育ち、甘みのある味わいはまさに海のミルク。特許取得の紫外線を利用したシステムを用いた安全安心な牡蠣としても有名であり、生食ならではの濃い旨味をご堪能ください。
「あのりふぐ」は、10月1日~2月末に安乗漁港を中心に水揚げされる700g以上の天然トラフグ。引き締まった身が生み出すしっかりとした食感が特徴で、ふぐ刺し、ふぐ鍋、から揚げ、白子、ヒレ酒と一匹すべてを存分に味わうことができます。

伊勢神宮
伝承では2000年の歴史を有し、日本人の「心のふるさと」と称される伊勢神宮。
正式には神宮といい、天照大御神をお祀りする皇大神宮(内宮)と、衣食住を始め産業の守り神である豊受大御神をお祀りする豊受大神宮(外宮)を始め、125の宮社全てを指します。
社殿などを20年に一度造り替える「式年遷宮」は、1300年にわたり繰り返され、次回は令和15年に行われます。

伊勢茶
三重県は、全国第3位のお茶どころ。三重県で作られるお茶は、江戸時代から「伊勢茶」の名称で親しまれています。 南北に長い三重県では、地域の風土を活かして、旨みの強いまろやかな味わいの「かぶせ茶」や、お茶の色が濃く濃厚な味わいの「深蒸し煎茶」など、地域ごとに特色のあるお茶が作られています。

松阪牛
和牛の最高級ブランドとして「肉の芸術品」とも評される松阪牛。匠の技を伝承する生産者や松阪牛を扱う食肉業者の弛まぬ努力により、脂の融点が低く、とろけるようなその極上の味わいが、国内外から大きな賞賛を受けています。

斎宮跡
斎宮は「いつきのみや」とも呼ばれ、斎王の宮殿と斎宮寮(さいくうりょう)という役所のこと。斎王は、天皇に代わって伊勢神宮に仕えるため、天皇の代替りごとに皇族女性の中から選ばれて、都から伊勢に派遣されました。 その遺跡である斎宮跡では、往時を彷彿とさせる「斎王まつり」が毎年6月に開催され、賑わいを見せています。

忍者
忍者とは、日本特有の兵法として発達した忍術の使い手のことです。 「伊賀流忍者博物館」では、忍術実演ショーが行われ、忍者の姿に思いを馳せることができます。

熊野古道
伊勢路
熊野古道とは、伊勢や大阪・和歌山、高野から紀伊半島南部にある熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の総称)までを結ぶ古い参詣道の総称であり、ユネスコの世界遺産にも登録されています。
三重県には、伊勢神宮と熊野三山を結ぶ「熊野古道伊勢路」があり、江戸時代には、お伊勢参りの後に伊勢路を通って熊野三山へ向かう巡礼が盛んになりました。美しい石畳や竹林、熊野灘など多彩な風景を楽しめるのが特徴です。