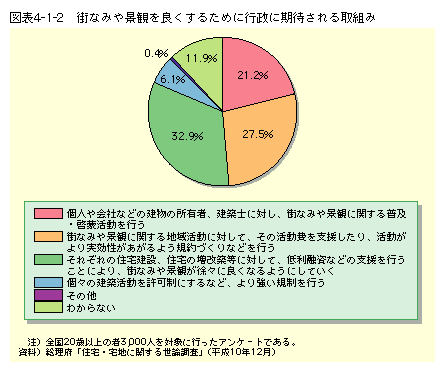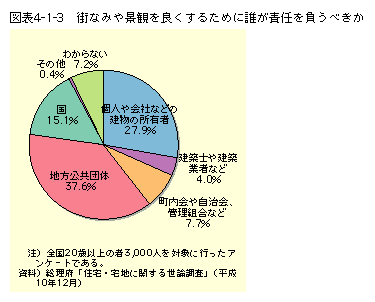第4章 美しい景観のまちを育むために
「美しい景観のまち」は人々の生活に快適さ、豊かさ、ゆとりを与えることで、人々のまちに対する新たなニーズに応えるばかりではなく、美しい景観に魅了された人々を引き付け、まちに活気を呼び起こすことにより、まちの国際競争力の源泉となるソフトパワーを持つ。
しかし、これまでの我が国の都市景観を振り返ると、必ずしも賞賛されるべきものばかりではなく、反省すべき点が多い。総理府の実施した世論調査「住宅・宅地に関する世論調査(平成10年12月)」においても、我が国の景観については、否定的な評価を持つ人が多いことが分かる(図表4−1−1)。
景観のよいまちを形成することについては、「総論」としては「賛成」される場合が多いであろう。行政としても、良好なまちなみ・景観を形成するための手法としては、都市計画法、建築基準法等の法律や、都道府県・市町村の条例等などにより、まちづくりの基本的な方針や規制誘導策を示している。しかし、「各論」に入ると、各地で「合意形成のプロセスの失敗」と「守るべき資産や景観の喪失」が起こっている。「住宅・宅地に関する世論調査」においても、規制による良好な景観づくりは望まれておらず、むしろ、個人や会社など不動産の所有者が景観に関する認識をもち、自主的に規約を結ぶことで景観を担保する、という方向性が望まれていることが分かる(図表4−1−2)。
このように、良好な景観を形成するための施策を推進するためには、住民とのコミュニケーションの下で、地域のあるべき姿をビジョンとして分かりやすく定め、住民・行政等がコンセンサスを形成していくプロセスが大切である。この場合、全国一律の手法による景観の形成を目指すのではなく、地元市町村と地元住民が、地域の歴史・風土が生み出す個性や地元のニーズに応じて弾力的な対応ができるよう、公共施設の整備と一体となった景観形成のための事業実施を含め、自主性を発揮できるためのツールが多く備えられていることが必要である。「住宅・宅地に関する世論調査」においても、街なみや景観を良くする責任の所在について、地方公共団体のほか、建物の所有者や住民グループに期待が寄せられており(図表4−1−3)、また、まちづくりNPOへの参加に関して前向きな姿勢が見られており、今後、このような住民の活動が景観づくりに積極的に関わってくることが期待される(図表4−1−4)。
人々が愛着をもち、地域のアイデンティティとする景観は、他者から押し付けられたものではなく、住民等関係者により生み出され、支えられ育まれるものでなくてはならない。このため、建築協定等住民同士の自主的な取り決めによって景観を守る手法や、NPO活動や直接の資金提供等による住民の自主的な活動を通じて良好な景観が形成されていくことが大切である。また、住民一人一人がまちづくりの主役であり、地域社会の共有財産であるまちの美しさを共同で作る、という意識を育て、共有することが大切である。ただし、景観は人々によって生まれるものであるから、景観問題を見かけ、外見の問題として捉えるのではなく、人々がまちでどのような活動をして、どのようにまちと関わっているのかが、景観を形成するうえで反映される重要な要素となる。受動的ではなく、主体性と責任感をもってまちと関わっているかどうか、住民同士を結ぶコミュニティが生き生きしているかどうか、また、行政の側でも、住民とのパートナーシップを築き、一緒に良好な景観を目指す協働作業を行っているかどうか、というまちづくりと表裏一体の問題として捉えることが大切である。
よい景観を形成するためには次のような5つの要素がある。
1)どのような景観のまちをつくるのか、というビジョンの作成
建設省の行った市町村アンケートによれば、景観形成に対して前向きな姿勢で取組んでいる市町村は多く、その際、必要となる取組みとしては、まずはまちづくりや景観に関する長期的な展望をビジョンとして分かりやすく示すとともに、それを地域の住民と共有して、住民と一体となって良好な景観形成に努めて行くことの必要性が認識されている。このため、都市計画法や建築基準法では、都道府県や市町村が都市計画マスタープラン、地区計画制度、まちづくり・景観条例等を用いて、住民の意見を十分反映したビジョンを策定し、またそれに基づいての規制誘導策を施すためのツールを用意している。
2)リーダー・専門家
まちづくりにおいては、「景観をよくしたい」「きれいなまちに住みたい」という住民の思い入れや意識が基礎として大切になる一方で、それを実現するためには、都市計画や景観について専門的な知識や実務経験を有する専門家がリーダーとして住民を先導し、またアドバイザーとして住民の活動を支援していくことが必要である。
また、地方自治を担う行政の側においても、地方分権の推進の流れの中で、市町村のまちづくりにおける役割が増大することを認識しなければならない。このため、長い目で、景観設計に配慮し、事業の設計、施工から維持管理に至るまでの一連のプロセスに習熟した専門家を育てることが必要である。また、住民との関係においても、意欲的にまちづくりについて提案し、自主的な活動を繰り広げる住民とコミュニケーションを図り、住民の「やる気」をまちづくりの実践に結び付けていく「コーディネーター」としての機能を発揮することも期待される。
3)住民のコンセンサス
住民が目指すべきまちや景観について、コンセンサスを形成させておくことが必要である。このため、景観形成の意義を数値化することや、模型を作成して示すなど、分かりやすい手法により、そのまちのあるべき姿を言語化し、客観的にその合理性が説明できる方法を開発するべきである。また、まちづくりに関するボランティア活動などを通じてコミュニティ意識を形成することや、コミュニケーション型行政の推進により、まちづくりに市民が関わることにより、公共心を育成することなどが必要となってくる。
4)住民の主体的な活動
これまでも、住民の主体的な活動がまちづくりを支えてきており、町内会、自治会等の地域に根ざした団体のきめ細やかな活動により、その区域の住民相互の意志を調整し、良好な地域社会の維持・形成のためのコンセンサスの形成や様々な町内美化の活動等が進められ、地域の核として活躍されてきた経緯がある。近年では、NPO(民間非営利団体)の活動、住民・行政・企業が一体となったパートナーシップによるまちづくり活動、都市緑地保全法に基づく緑地管理機構による緑地保全のための活動、シビック・トラスト活動、公物管理におけるボランティア活用(「養子縁組制度(アドプト・システム)」など)が見られ、このような住民の主体的な活動が今後のまちづくり・景観づくりにおいて活躍されることを期待する。
5)公共施設の整備との一体化
まちにおける良好な景観は、景観形成に配慮した公共施設の整備と建築物とが一体となって、はじめて形成されるものである。このため、良好な景観を形成することは、物質的豊かさから精神的豊かさを重視する方向へ国民の意識が変化し、ライフスタイルや価値観の多様化が進む中で、地域の主体性・自主性を最大限尊重しつつ、地域固有の歴史や伝統に立脚したまちづくりの重要な達成目標の一つである。建設省においては、地方公共団体が景観に配慮したまちづくりを実施するための事業を推進する補助制度を充実させ、地方公共団体の活動を支援している。
景観をテーマとしてまちづくりに住民が「参加」し、議論を尽くしてコンセンサスを得た上で、行政と住民が各施策を統合してそれぞれの役割を実践(統合化・総合化)していく「造景」の仕組みづくりこそが、環境と共生した美しい景観のみならず、地域の文化や個性を生み育てる住民の誇りや愛着、地域への一体感(アイデンティティ)や公共心などを醸成させ、魅力ある地域社会(コミュニティ)を再生する原動力になると期待している。