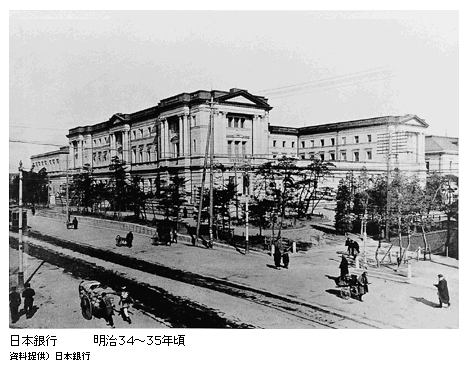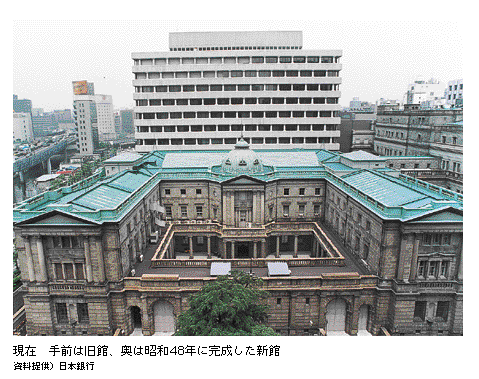(建設人材革命の時代)
幕末から明治維新を経て明治の初期、我が国の建設分野に西洋の近代建築、近代土木の学問と技術が入ってきた。当時は日本人の建築家が未だ養成されず、江戸幕府や明治政府は外国人技術者を招き、主要な建築物の設計に当たらせた。こうした建築物の施工や当時の多くの木造漆喰の建築物の設計・施工には宮大工をはじめ日本人の棟梁・職人が当たった。この時期の棟梁や職人の中には、当時の横浜のような外国人居留地のある国際都市などに出向いて西洋建築を学び、現地や東京などの大都市、さらには故郷で伝統的な地場の資材を活用したり地域の文化・風土に配慮しつつ、和風木造建築に洋風の建築を融合させた和洋折衷の擬洋風を生み出すとともに、さらに進んで純粋な洋風建築に果敢に挑戦した腕の良い大工の棟梁や建築職人がいた。
建築物が木造から煉瓦造建築の時代となる頃、日本人の大卒建築家が輩出し、棟梁・職人は施工のみを手掛け、さらに明治22年(1889年)、官庁工事における競争入札制度が導入されると、職人の大きな変革をもたらした。大工の棟梁や石工等の一部の者は近代建築・土木工事を請け負う請負業(元請)となり、その下請に入る者、町場の親方職人となる者などに再編されたといわれる。この時代においても、建築の様式や工法、雇用形態の変化やコスト競争の激化に伴って、卓越した技能・技量をもつ職人よりは、一定の仕事を効率よく行う職人が一般の工事には求められ、また、左官や瓦工事から煉瓦工事、さらにタイル工事が生まれるなど業種の分化も始まった。また、請負業には、自身は技術・技能をもたないが、労働・資材の調達管理能力等経営力のある店主も出現するなど、今日の総合工事業と専門工事業発展の基礎が築かれた。一方、施工能力のない不良業者の存在が、この時期請負人全体の社会的評価を下げたとも指摘され、こうした者の排除は今日もなお求められる行政の課題である。
明治期に来日したアメリカ人の動物学者で東京・大森貝塚の発見者でもあるエドワード・モース(1838〜1925年)は、明治初期の大工について、「日本の大工は、その仕事じたいがすぐれているばかりか、あたらしいものを創造する能力においても、アメリカの大工よりすぐれている。日本の大工…は、平面図をみて、それが、あたらしい、みなれない方法でえがかれていたり、対象自身がまったく未経験のものであったとしても、辛抱づよくこれに対処し、けっきょく、うまくしあげてしまうのである。」(エドワード・S・モース著「日本のすまい・内と外」(鹿島出版会))としているが、新文明、新技術による経営や技術の大変革の時代に、未だ手掛けたことのない西洋建築物の平面の設計図と建築資材を前にして、頭に完成後の立体的な姿を予想しながら、図面(頭脳)と現場(技・腕)を結びつけ、実に創造的な施工・管理により問題解決に挑戦した先人の気概が伝わってくる。
それから100年余り、建設産業は今厳しい環境の変化に直面している。コストダウンとともに新工法の開発、品質の向上、提案力の強化などの差別化、高付加価値化による競争力強化を求められている。経営革新や経営力・施工力強化の意欲を有する企業が、技術革新による新技術・新工法や優秀で創造的な人材の能力の発揮による現場労働生産性の向上を通じて、適切な利益を確保し、高品質と低コストを満たす建設生産システムを実現できる建設市場の整備が必要となっている。
なお、詳細については、「第3 建設活動の動向、建設産業と不動産業」の「
II 建設産業の動向と施策」を参照されたい。