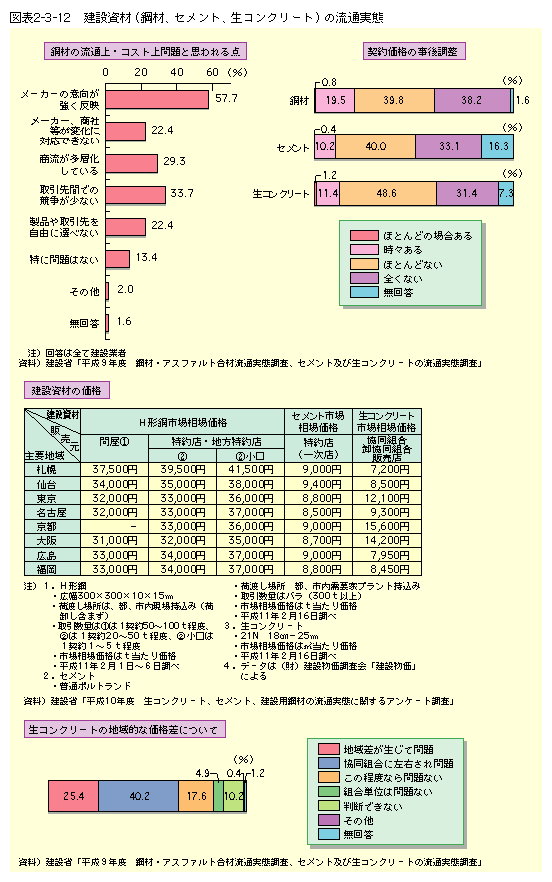(建設産業におけるIT革命の方向)
建設業においては、基本的に単品受注・屋外現場生産などの産業としての性格上、従来からの生産の基本的な仕組み自体はITの時代になっても変わらないものと考えられ、またIT導入の現状や将来の活用方向について、現段階では企業によりその考え方や取組みに格差もみられる。
しかしながら、建設投資の減少傾向と厳しいコスト競争の中では、中長期的に見ても、IT活用による「情報の共有」と「情報の交換」による生産システムの効率化が現場コスト、トータルコスト、経営コストの軽減を通じて、コスト競争にも、品質競争にも、さらに顧客満足度の向上にも好影響を与えることは確実である。このため、ビジネス・チャンスの拡大を図るためにも、社内・企業グループ内・調達・生産・メンテナンス、元請と協力会社(関連下請)のように、企業、業界の枠を超えたIT活用の動きが出てくるものと思われる。現場の人材でいえば置かれる監理技術者、主任技術者、さらに基幹技能者には、従来の「ひと・もの・かね」に「各種情報の分析・統合・活用」を加えて優良な生産物を生み出す真のマネジメント能力が必要となる。
このため、建設産業におけるIT革命のもたらす大きな方向性について、概観してみたい。
(1)生産性向上による建設生産システム全体の改革をもたらす
現在の生産の仕組みは、基本的に、営業から設計、施工へと各段階ごとの仕事の順送りであり、各段階は一企業にとどまらず、異なる企業であることも多い。このため、各段階ごとの情報共有が進みにくく、ひとたび工程の中の一部門でトラブルが生じると、川上部門に向かって部門を越えた「手戻り」があり、その修正と調整に費やす時間とコストは膨大である。ITの活用により、現場施工を担う部門から、営業、設計、財務管理、資材調達を担う部門まで、全部門が共通の問題意識をもち、情報共有を進めることにより、例えば現場で生じた問題をリアルタイムで設計部門においても把握して現場と同時進行型で解決策の提案ができ、また現場においても設計部門の指示を待たずとも設計情報をもとに暫定的な問題解決が可能となるなど、生産プロセス全体に変化が起こるものと考えられる。
このように店社から現場までのパソコンやモバイルによるIT装備により、営業、設計段階から元請・設計(意匠、構造、監理等)・下請など関係者が情報を共有・交換することで、生産プロセスの全段階を通じて互いに問題点を先取りし、解決のため知恵(施工技術やノウハウ)と情報を交換しながら、同時にそれぞれの作業が進められる「コンカレント・エンジニアリング(
注1)(Concurrent Engineering)」の物理的条件が整うことになる。これにより、建設プロセスの川上部門に作業部隊を集め生産プロセス全体を最適生産に向けマネジメントできるため、元請技術者による工事全体の総合的な管理のみならず、各専門工事においても後戻りなく責任施工ができるようになり、特に現場での「待ち時間」が大幅に短縮でき、最終的にコスト縮減・時間短縮・品質向上につながる。また、生産プロセスの各段階で、総合工事業、専門工事業さらにはメーカー等関係者が一体となり協力して作業を進める「コラボレーション・ワーク(
注2)(Collaboration Work)」を組み合わせることで、営業、設計から現場、資機材を含めた生産プロセス全体の生産性が上がる。
実際には、IT投資は初期段階では多大な出費を伴うが、長期的には元請・下請・設計など生産プロセス全体の生産性向上によって生じた余裕(時間・コストの節減から生まれるキャッシュ・フロー)を建設生産物の一層の品質確保のための投資努力(技術開発、労働報酬など)に回すことで、元請・下請による従来の建設生産システム改革につながることが期待される。こうした努力を通じて得た独自のコア・コンピタンス(
注3)(Core Competence)を持った建設業者をはじめ関係企業が提携して、付加価値の高い仕事を創造できる時代が到来すると期待される。
(2)『ストック・メンテナンスの世紀』への対応
今後、建設生産物のストックの大量な蓄積によって、個々の建築物のライフサイクルコストの管理が大きな課題となる。リフォーム(維持・補修・改修)市場の拡大に伴い、各企業とも過去に施工した建築物などの基本的な数値データ、クレーム情報と対応記録、定期的な診断結果などを電子情報化した履歴情報の有無が、受注の際の大きな武器になり、企業対消費者(B to C)の取引が拡大し、将来の大きなビジネス・チャンスを生むと考えられる(「リフォーム市場等の動向」については、
第1章第4節参照)。
特に、現在も小規模な診断サービス程度のものは、随時行われる顧客への無料サービスとして企業の一般管理費に吸収されている場合があるが、施工時期、施工者、施工内容等に関する記録、瑕疵担保期間以降の診断体制等施主の多様な要望に応えられる情報の整備は、将来大規模なサービス産業に成長する可能性があると考えられる。リフォーム・メンテナンスに関し顧客より提示された経営資源の中から、顧客満足度の最も高い最適サービス計画を提供する建築ストックの「ケア・マネジメント(
注4)」サービスとして、付加価値の高いフィー・ビジネスに発展すると思われる。
(3)電子商取引等による建設資材の商流・流通システムの改革を促す
アメリカでは、製造業などでITを活用した生産管理、部品調達などのサプライ・チェーン・マネジメント(Supply Chain Management(SCM))を採用し、多大の効果を生んでいる。我が国でも同様に、製造業の分野でインターネットによる部品調達が本格化し、調達部門の雇用削減・配置転換、調達コストの削減に効果を上げはじめている。
建設産業においても、公共工事のコスト縮減などの観点から、電子商取引による資材調達の合理化が将来期待されるが、オンラインで商品の売買や取引の決済まで行える金融業等とは違い物流が伴うことや、現場の単品受注生産という産業特性もあり、その成長性は未知数である。
建設業者と直接取引関係のある資材業者との間の取引における商慣行も複雑である。代表的な建設資材として、鋼材、セメント、生コンクリートについて見ても、商流も多層化しており、資材購入時における契約価格の後決め(事後調整)など共通する商慣行が一部にあるが、これが電子商取引の導入によりどのように変化するかは分からない。また、建設の現場もジャスト・イン・タイムの搬入を進めているため、遠方からの調達は物流面で納期等に不安も残り、結果として業者が限定されてしまうため、インターネットの利点が生かされ難いこともある。特に、生コンクリートのように、製品の性質上調達地域が限定(ミキサー車で概ね90分以内)され、また協同組合(生コン)の組織率により市場価格が左右されるといわれる市場ではIT導入に関する誘引が湧きにくいものと考えられる(図表2-3-12)。
このため、相場より条件の良い複数の業者を選んだ上で具体的な価格を実地に交渉しながら適正価格に近づけていく動きや、大理石など特殊な部材を海外から調達するようなケースでの電子商取引の動きなども進むものと見込まれる。
(4)専門工事業を含む中小建設業においても共通して進むと考えられる取組み
1) 社内(本社、支社、現場等)における情報の電子化による双方向の情報交換や情報共有の円滑化
2) 顧客情報や発注情報のデータベース化による管理
3) 関係企業相互間における業務効率化のための、見積もり、図面などの電子情報化による交換
などの取組みが始まると考えられる。
いずれにしても、各企業は、ITを活用できなければ、現下の厳しいコスト競争の中で、生産性の向上を通じたコスト縮減は不可能になりつつあることから、取引業務や施工現場でITを有効に活用し得る人材を育成、確保していくことが新たな課題として掲げられ、それができなければ、競争に取り残されざるを得ないと考えられる。
(注1)「同時性技術方式」という。各部門の分業体制の枠にとらわれず、製品生産という最終目的に対して、コンピュータ・ネットワークに支えられた各部門間の情報共有を円滑に行い、最適な生産体制を柔軟に構築していくこと。
(注2)さまざまな背景・分野を持った人間がある共通の目標に向かって協力し、新しいアイデアを創発すること。個々の分野の人間の発想が互いに補完するという効果だけでなく、異なる視点を交錯させることで新しい視点を見出そうとする。
(注3)企業の競争力の中核となる、他の企業に絶対的に優位に立てる要因。独自に開発した技術力、ブランド力、顧客情報量等がコア・コンピタンスになると考えられる。また、コア・コンピタンスを軸に企業経営戦略を組み立てることを経営学上、「コア・コンピタンス経営」という。
(注4)利用者が、自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することを基本とした上で、各分野の専門家が連携して、それを支援していくという考え方。例えば、介護保険制度においては、利用者の在宅介護サービスの支援メニュー(訪問介護、住宅改修など)に関し、福祉や保健医療の専門職が行う(サービス計画の作成)→(アセスメント)→(サービスの提供)→(実施後のサービスのモニタリング)及び(ニーズの再評価)といった一連の流れ〈介護報酬の対象となる〉を指す。