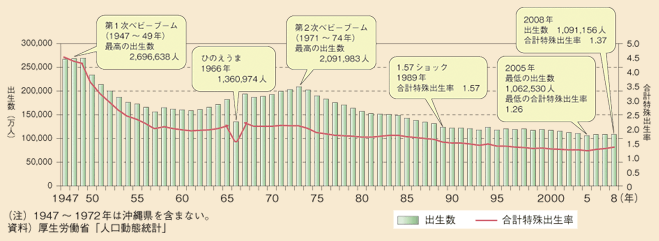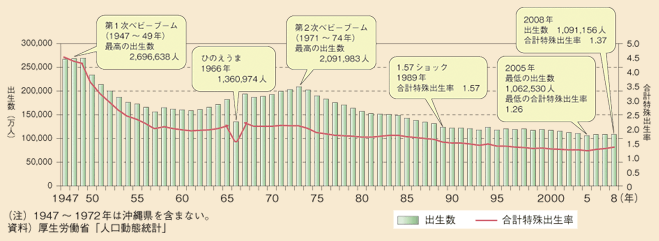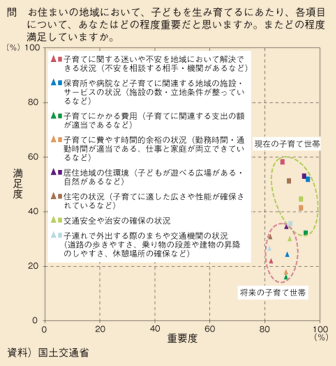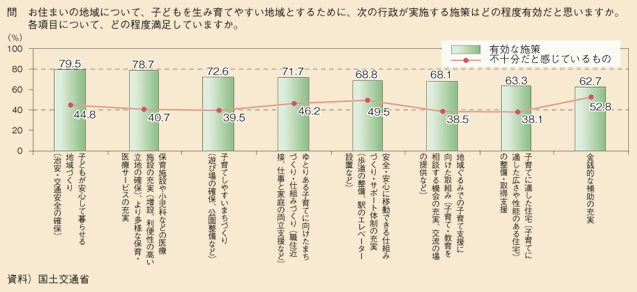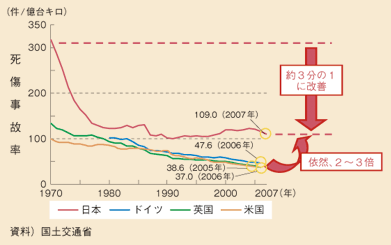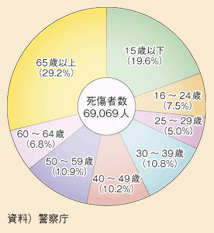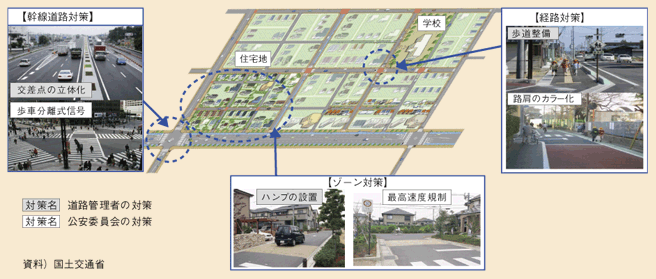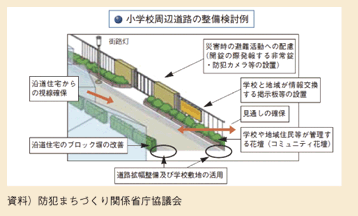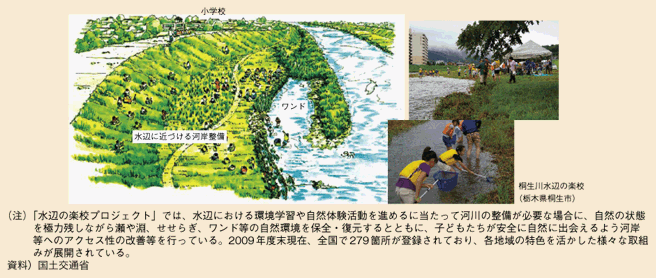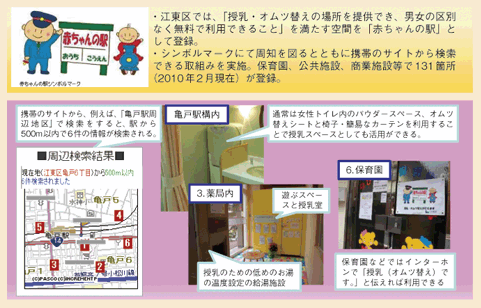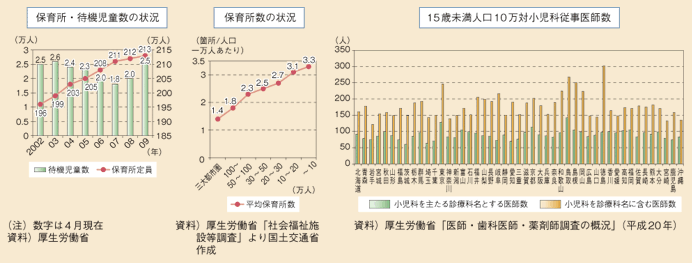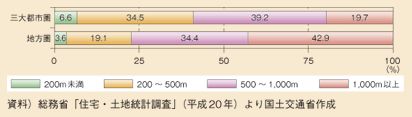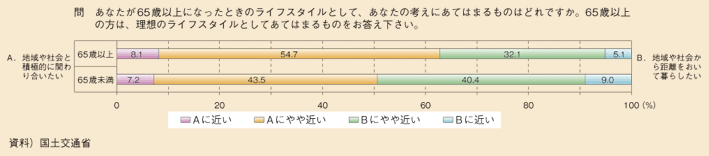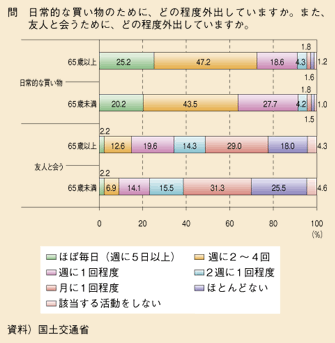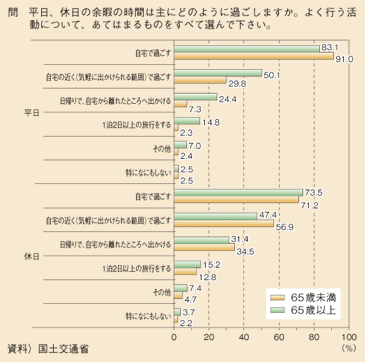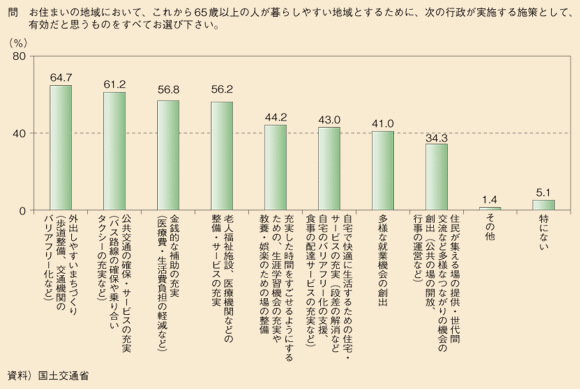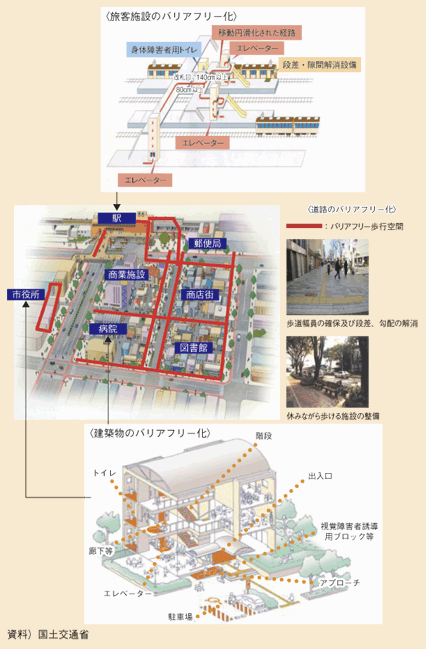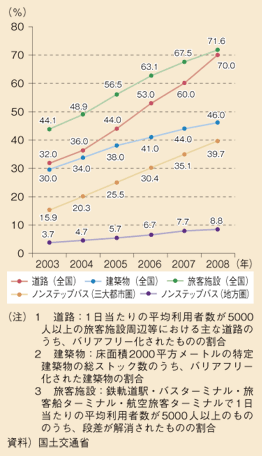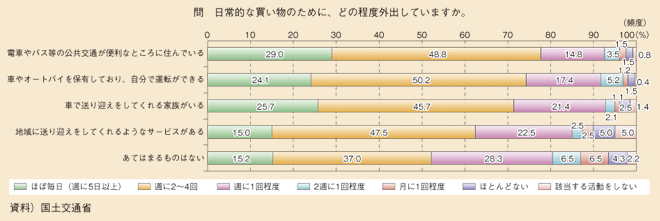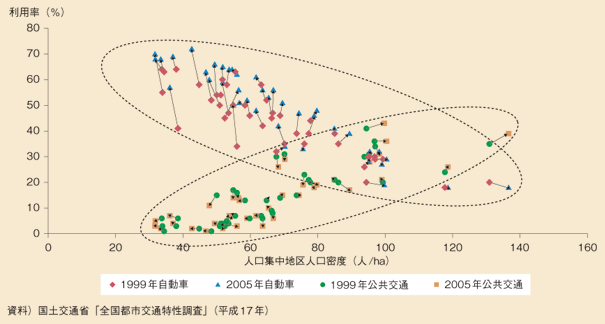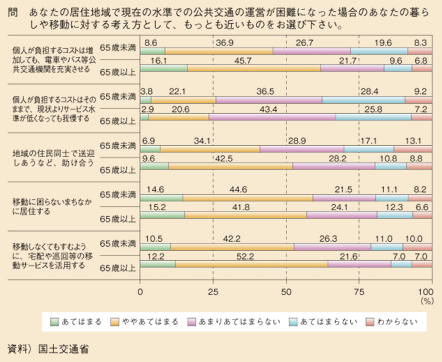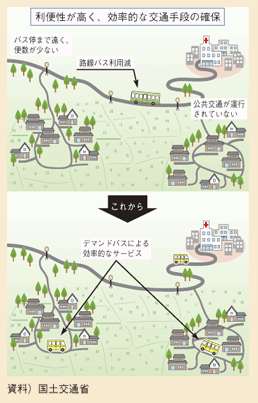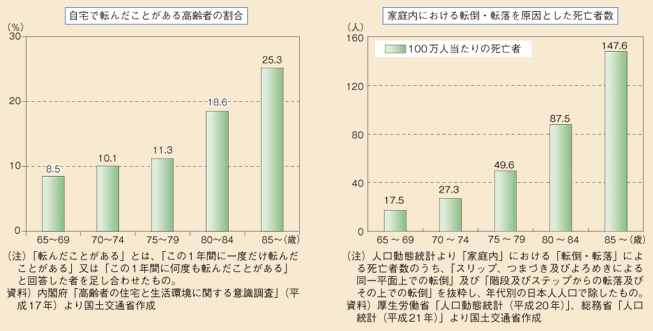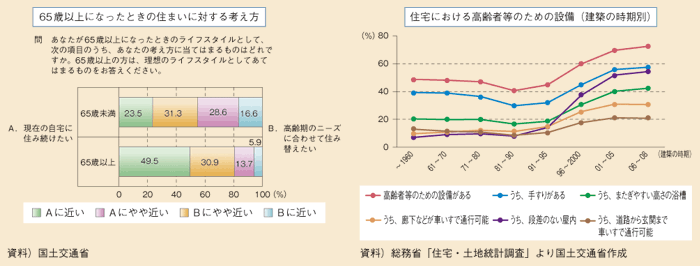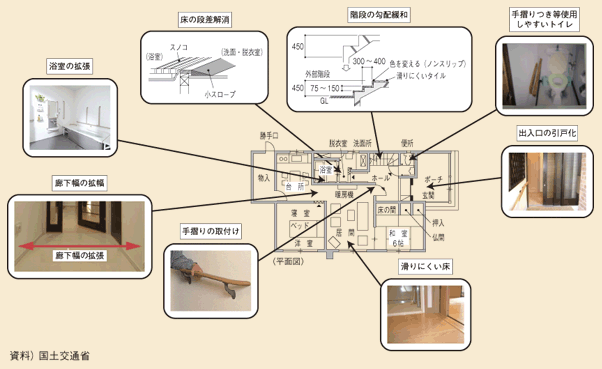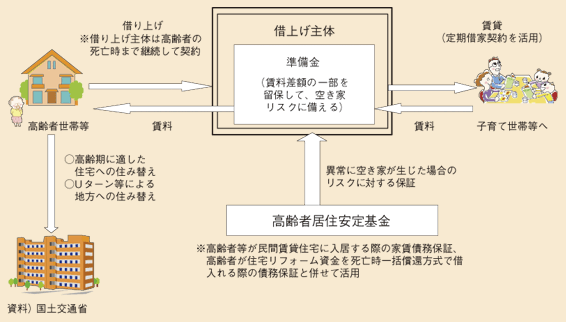1 子育て・高齢期を安心してより豊かに過ごすために
(1)子育てニーズに応える環境整備
ここでは、少子化が進展している中で、子育てを行う人々の視点から、地域・社会における子育て環境の状況や今後求められるものを考える。
図表71 出生数と合計特殊出生率の推移
1)子育て環境に関するニーズの高さ
国土交通省の調査では、子育て環境に関するニーズの高さが改めて確認された。
現在の子育て世帯と将来の子育て世帯(注1)に、地域の子育て環境の重要性を尋ねたところ、子育ての相談体制等ソフト面のみならず、まちの子どもを連れての歩きやすさなどハード面についても、それぞれ8割以上の人々が重要であると答えている。他方で、これらの子育て環境が地域に整っているとの認識は6割未満となっている。さらに詳細にみると、将来の子育て世帯の方が、現在の子育て世帯より、子育て環境への満足度が低くなっている。
子育て支援の観点のみならず、将来の子育て世帯の不安要素を軽減するといった少子化対策という観点でも、地域の子育て環境を整えていくことが求められる。
図表72 地域の子育て環境に関するニーズ(重要度と満足度の分布)
2)子育てニーズに応える環境整備
国土交通省の調査では、子育て環境をより整えるための行政の各施策に6割から8割程度の人々が期待を寄せていることがわかった。
特に、子どもが安心して暮らせる地域づくり、保育所など子育てに必要な施設・サービスの充実、子育てしやすいまちづくり・仕組みづくりといった分野については、7割超の人々が行政の施策が有効であると答えている。
図表73 地域の子育て環境を整えるために実施する行政の施策の有効度
以下、地域における子育て環境について、特に、行政へ高い期待が寄せられている分野を中心に、みてみる。
(子どもが安心して暮らせる地域づくり)
図表74は、交通事故の死傷事故率について国際比較したものである。我が国における交通事故の死傷事故率は、減少傾向にあるものの依然として諸外国より高い。図表75は、年齢層別に歩行中の死傷者数をみたものである。全体の約2割が15歳以下であり、子どもが歩行中に交通事故に巻き込まれ死傷する数は、高齢者に次いで他の年齢層より多くなっている(注2)。
図表74 交通事故(死傷事故率)の推移(国別)
図表75 歩行中の年齢層別死者及び負傷者数(2009年)
子育て世帯にとっては、日常利用する道路における交通安全対策や防犯対策について、交通規制や防犯パトロールなどソフト面の対策のみならず、交通安全施設や防犯設備の整備などハード面の対策が大切である(注3)。
交通安全対策として、特に子どもがより多く通ると考えられる通学路等において重点的に歩道の整備に取り組むとともに、歩道と車道を容易に見分けられるよう歩道のカラー舗装にも取り組むことが重要である。広域的な観点からは、住宅地内においてハンプの設置・速度規制等により車両の速度を制限したり通過交通が流入しないよう誘導したりするなど、生活道路を面的な空間ととらえ、対策を進めることが大切である。
図表76 安心して歩行できる空間の整備
防犯対策として、人の目を確保する地域づくりも有効である。
道路、公園等の植栽等について周囲からの見通しを確保するよう配慮したり、学校、駐車場等の外周の柵等を見通しのよいものにするなど、犯罪を未然に防ぐよう取り組むことが大切である。また、住宅地における通過交通の抑制は、交通安全のみならず、不審者が流入しにくくなるほか、住民の屋外活動が活発になる環境が整うなど治安面でも有効であると考えられる。
今後とも、子どもが安心して暮らせる地域づくりが求められる。
図表77 防犯対策としての地域づくり(小学校周辺道路の整備検討例)
(子育てしやすいまちづくり)
子育てのしやすいまちづくりとして、子どもの遊び場が必要である。
遊び場の確保に当たっては、身近な都市公園の整備を推進するとともに、老朽化した遊具等の点検・修繕など安全性の維持・確保も必要である。水辺空間は、川辺の生物や草木といった自然に親しみながら子どもが遊べる場であり、安全性を備えた親水空間を確保することも求められる。
図表78 子どもが親しむことのできる水辺空間
子どもを連れて外出しやすいまちづくりを進めることも重要である。
特に乳幼児は、外出中にケアが必要となる場面もあり(注4)、これに配慮した環境づくりが求められる。例えば、まちなかや駅ナカ・周辺など子育て世帯が頻繁に出向くところに、公共施設や商業施設など地域の既存施設を活用して子育てしやすい空間づくりを行うなどの取組みが大切である(注5)。
図表79 子育て支援拠点を創出するまちづくり(江東区における例)
(子育てに必要な施設の立地、アクセスの確保)
図表80は、子育てに必要な施設についてみたものである。保育所定員は近年着実に伸びているものの、待機児童数は依然として2.5万人程度となっている。人口当たりの保育所数は人口規模が大きくなるほど少なく、待機児童率は三大都市圏において高くなっている(注6)。小児科医療サービスについても、地域によって差異があることがうかがえる。
図表80 子育てに必要な施設の状況
これらの施設については、量的拡大のみならず立地やアクセスもみる必要がある。
自宅から最寄りの保育所への距離は、地方圏において三大都市圏より長くなっており、三大都市圏においてもその距離が500m未満である世帯は4割程度となっている(注7)。
図表81 最寄りの保育所までの距離別世帯比率
また、子どもを預かる施設や病院への“通いやすさ”は、子育て世帯の住環境を向上させる上で大切である
(注8)。保育所や病院など子育てに必要な施設については、その量的拡大やサービスの充実のみならず、子育てをする人々が利用しやすい立地やアクセスの確保を図ることが重要である。利用する人々にとっては、自宅と職場の往復といった日々の生活における動線に子育てに必要な施設があることが望ましい
(注9)。近年、駅ビルに保育所や病院を設ける鉄道事業者や、社内保育所を設ける企業等が増えつつあるが、子育て世帯の共働き率が増える中、今後とも子育てに必要な施設の利便性の高い立地の確保について十分配慮していくことが必要である。
(子育てしやすい仕組みづくり)
子育てのための時間的ゆとりの確保に向けた取組みも大切である。
1日当たりの労働時間・通勤時間が長いほど、家族と過ごす時間は少なくなる傾向にある
(注10)。時差通勤や職住近接、テレワーク等の促進により、通勤時間など仕事に関連する時間を軽減したり、より柔軟な働き方を可能としたりする環境を整えることも重要である。また、輸送機関における通勤混雑率は改善されてきているものの、特に大都市部において依然として高い状況にあり
(注11)、子どもを連れての通勤等に対応する観点からも更なる混雑率緩和の取組みが期待される。
(2)高齢期ニーズに応える環境整備
序章・
第1章でみたように、我が国では高齢化が急速に進展している。ここでは、私たち一人ひとりの立場から65歳以上の高齢者として過ごすことに焦点を当て、今後求められるものを考える。
1)外出意向と取り巻く環境
(65歳からの暮らしぶり)
国土交通省の調査において、65歳からの暮らし方について考え方を尋ねたところ、現在65歳未満の人々より65歳以上である高齢者の方が、地域や社会と積極的に関わり合いたいと考えている人が多かった。
図表82 65歳以上になったときの地域や社会との関わり合いに対する考え方
また、現在の日々の暮らしぶりについて、買い物や友人と会うための外出頻度を尋ねたところ、現在65歳未満の人々より高齢者の方が、頻度が高くなっている。さらに、自由時間の過ごし方を尋ねたところ、65歳未満の人々は平日に比べて休日に旅行したり日帰りで遠出したりしている一方で、高齢者は平日も休日も大差なく旅行したり日帰りで遠出したりしていることがわかる。
図表83 年齢別外出頻度
図表84 年齢別平日と休日の余暇の過ごし方
国土交通省の調査では、65歳以上の人々が暮らしやすい地域とするために行政が実施する施策として、特に「外出しやすいまちづくり」、「公共交通の確保・サービスの充実」について有効であると考えていることがわかった。
図表85 65歳以上の人々が暮らしやすい地域とするために行政が実施する施策の有効度
65歳からの暮らしぶりについては、外出を支える環境づくりに対する行政への期待がうかがえる。高齢者の外出を取り巻く環境は、現在、地域・社会においてどの程度整っているのか、以下みる。
(外出しやすいまちづくり)
安全で快適に外出できる生活環境は、暮らしの根幹である。特に高齢者にとっては、自宅を一歩出てから目的地で用事を済ませ、再び自宅に戻るまでの間、階段等があると負担になったり、少々の段差でも転倒への不安要素になったりすることが考えられる。誰もが安心して社会参加ができ快適に暮らせるような環境を整えるため、外出しやすいまちづくりの更なる推進が必要である。まちなかを安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差、勾配の改善を行ったり、ベンチ等を設置し休憩できるようにしたり、駅やバスターミナルなど旅客施設にエレベーターを設置するなどの対応が求められる。バリアフリー化の進捗状況については、歩道の段差解消、旅客施設における取組み(注12)、建築物のバリアフリー化等、着実に整備されつつある。他方で、例えばノンステップバスの導入率は、三大都市圏に比べて地方圏は低い状況が続いているなど、地域差がある状況にある。
誰もが安心して社会参加ができ快適に暮らせるような取組みが今後とも求められる。
図表86 外出しやすいまちづくり
図表87 バリアフリー化の状況
(地域の足の確保)
高齢者が外出するに当たっては、その手段をどう確保するかも課題となる。積極的な外出意向があっても、地域の公共交通機関の状況などおかれた環境により外出の可否が制限されることは望ましくない。
国土交通省の調査において、高齢者の移動を取り巻く環境と外出の頻度の関係をみたところ、両者は関連性があることがうかがえた。公共交通が便利なところに住んでいる高齢者の方が、多頻度にて日常的な買い物のために外出している。
図表88 高齢者の移動を取り巻く環境と外出頻度
一方で、公共交通の利用率には地域差がある。
図表89は、人々の主な移動手段の利用状況をみたものであるが、人口密度が低い地域において、公共交通の利用率が低い水準にあるとともに、自動車の利用率は近年高まっている。また、特に地方圏において、移動を取り巻く環境として公共交通の利便性が確保されていない状況がうかがえる(注13)。
図表89 公共交通の利用率と自動車の利用率
今後、自動車に過度に依存する傾向が続くと、高齢化が進展する中、自動車を利用できなくなった場合に外出できないといった懸念も生じる。誰もが安心して暮らすことができるよう、地域における移動手段の確保に向けた取組みが求められる。
国土交通省の調査において、移動等に対する人々の考え方を尋ねたところ、「個人が負担するコストは増加しても電車やバス等公共交通機関を充実させる」との考え方が、「個人が負担するコストはそのままで現状よりサービス水準が低くなっても我慢する」との考え方を上回った。この傾向は、特に高齢者において強い。公共交通の再生が求められる(注14)。また、地域の足を確保する観点では、最近では、デマンド交通も普及しつつあるが、これは自宅と目的地を柔軟かつニーズに沿った時間設定でつなぐものであり、地域特性や人々の需要にきめ細やかに対応することが期待される。さらに、地域の住民同士で送迎し合うことも方策の一つである。自動車への依存度が高い地域において、自動車が利用できなかったり、送り迎えをしてくれる家族がいなかったりする人々に対して、助け合いの視点により地域全体で人々の移動を支えていく観点も重要である。
他方で、移動に困らないまちなかに居住したり、宅配等のサービスを利用したりすることも考えられ、総合的な取組みが必要である。
図表90 暮らしや移動に対する考え方
図表91 デマンド交通
2)安全に暮らせる住まいの重要性
(65歳からの生活における危険)
前述の通り、65歳以上でも積極的な外出意向があるなど“元気な高齢者像”がうかがえたが、一方で、高齢期は一括りに捉えることはできない。
例えば、自宅で転倒したことのある高齢者は、65歳以上69歳以下では約9%であるが、85歳以上では4人に1人にまで増加している。さらに、家庭内における転倒・転落を原因とした死亡事故についても、65歳以上69歳以下と、75歳以上79歳以下では、2倍以上もの差がある。住み慣れた我が家にも、歳を重ねるにつれて危険な要素がでてくることがうかがえる。
図表92 住まいの危険
また、国土交通省の調査において、65歳からの暮らし方について考え方を尋ねたところ、現在65歳以上である高齢者は自宅に住み続けたいとの意向が強いことがわかった。一方で、住宅における高齢者のための設備については、築年数の古い家では半分も整っていない。
図表93 自宅に住み続けたい意向と住まいの設備
(安全に暮らせる住まいの確保に向けて)
高齢期に向けて、安全な住まいを確保することは重要である。住み慣れた我が家で暮らし続けるため、バリアフリー化など高齢期ニーズへの対応が必要となる。
図表94 バリアフリー化
また、高齢期ニーズに対応した住宅に住み替えることも考えられる。住み替えについては、例えば、子育て世代は広さを求める一方で、高齢者世代は広さよりバリアフリー化を必要とするなど、住宅へのニーズが世代によって異なるという側面をとらえてマッチングを図ることにより、既存の住宅ストックを有効活用する視点も大切である。
図表95 高齢者世帯と子育て世帯の住み替え需要マッチング
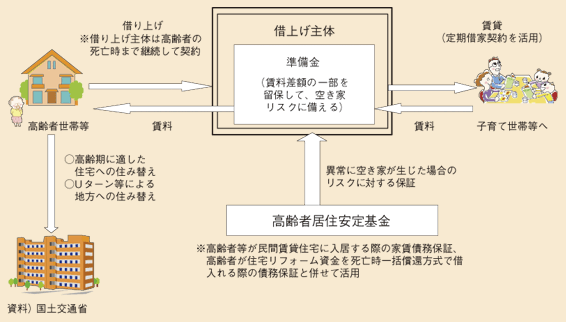
(注1)ここで、「現在の子育て世帯」とは、国土交通省の調査において未就学児(0歳から7歳未満)をもつと答えた人々であり、「将来の子育て世帯」とは、子どもの誕生の予定がある、または、子どもをいつかもちたいと答えた人々である。
(注2)人口1,000人当たりの歩行中の死傷者数を年齢層別にみると、65歳以上は0.76人、15歳以下は0.74人であり、他の年齢層より高くなっている。
(注3)子育て世帯の安全・安心に対する満足度を高める上で、交通安全対策や防犯対策は重要な要素であること、また、交通安全施設や防犯設備の整備などハード面の対策がより有効であるといった検証がある(国土交通政策研究所「子育てに適した居住環境に関する研究」)。
(注4)乳幼児は、移動においてベビーカーが必要であったり、食事については授乳施設や給湯施設が必要になったりするなど、まちづくりの観点でのニーズがある。なお、ベビーカーでの外出しやすいまちづくりとして、バリアフリー化の状況については、
第2章第2節図表87「バリアフリー化の状況」参照。
(注5)国土交通省「安心して子育てができる環境整備のあり方に関する調査研究」(平成22年)。
(注6)
第1章第2節図表40「都道府県別生活の諸条件」参照。
(注7)子どもを預かる施設までの距離について5分ごとに人々の効用をみた場合、自宅から5分であれば効用は高いが、その距離が10分、15分となると効用が大きく落ち込むといった検証がある(国土交通政策研究所「子育てに適した居住環境に関する研究」)。
(注8)住環境の各要素のうち、保育、教育、医療に関する住環境の総合的な満足度を高める効果があるものとして、「子どもがかかりつけの病院または診療所の通いやすさ」、「子どもを預かる施設の通いやすさ」は、「保育園などの子どもを預かるサービス・制度」より効果が大きいといった検証がある(国土交通政策研究所「子育てに適した居住環境に関する研究」)。
(注9)例えば、東京都における認証保育所(計493箇所、2010年3月現在)の最寄り駅からの距離は、駅から徒歩3分以下は35.7%、3分〜5分以下は36.9%、5分〜10分以下は16.6%、10分〜15分以下は7.3%、15分〜は3.4%となっている(東京都資料)。
(注10)総務省「社会生活基本調査」特別集計によると、例えば労働時間と通勤時間の合計時間が8時間から10時間未満である男性雇用者について、家族と過ごす時間が2時間未満である割合は約25%である一方、合計時間が14時間以上では約55%となっている(内閣府「国民生活白書」(平成19年))。
(注11)混雑率は、最混雑時間帯1時間の平均であり、首都圏は171%、中京圏は146%、近畿圏は133%となっている(2007年、「大都市交通センサス」)。ここで、首都圏、中京圏、近畿圏とは、東京駅、名古屋駅、大阪駅までの鉄道所要時間が2時間以内(中京圏は1時間30分)の地域であり、かつ、首都圏は東京都23区、中京圏は名古屋市、近畿圏は大阪市への通勤・通学者比率が3%以上かつ500人以上を満たすような市町村(これらの行政区と連担する行政区を含む。)である。なお、混雑率180%は、折りたたむなど無理をしなければ新聞を読めない状況で、150%は、拡げて新聞が読める状況である。
(注12)駅のバリアフリー化により、子育て世代・高齢者の2割近くが駅周辺の商店街での買い物の機会が増えていること、また、駅の乗降客数(定期外)が4〜7%増加するといった効果が検証されている事例もみられる(国土交通政策研究所「三世代共生ユニバーサル社会の構築に向けた調査研究」)。
(注13)国土交通省の調査において、移動をとりまく環境について尋ねたところ、「電車やバス等の公共交通が便利なところに住んでいる」と答えた人は、三大都市圏で71.7%、地方圏で39.9%となっており、「車やオートバイを保有しており、自分で運転ができる」と答えた人は、三大都市圏で54.4%、地方圏で70.9%となっている。
(注14)国土交通省が2008年11月に実施した調査によると、公共交通が整備されていることについての重要度は、公共交通の利用頻度にかかわらず高くなっており、公共交通サービスの確保がセーフティーネットとして位置づけられ、安心感の醸成につながっていることがうかがわれる。