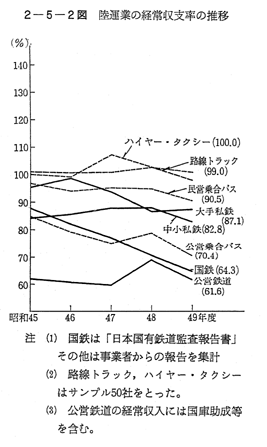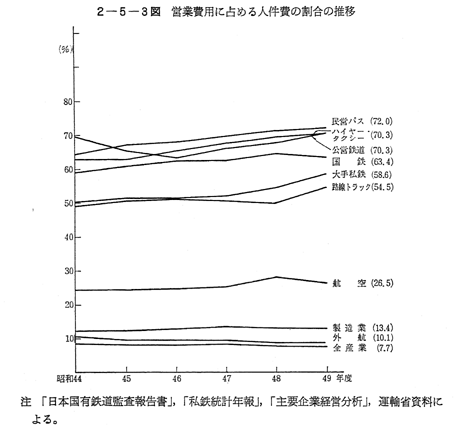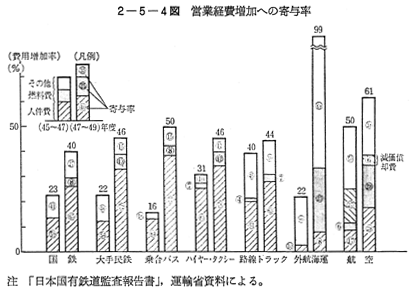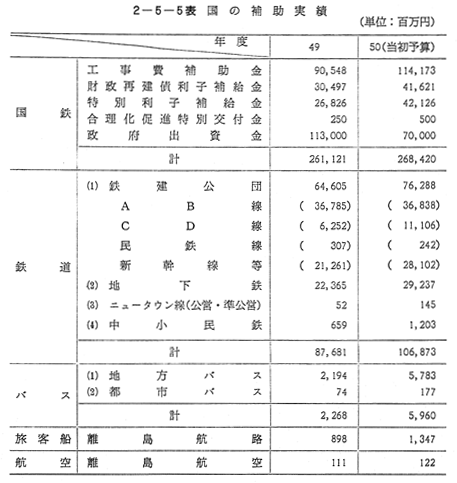|
1 陸運
国鉄を始めとする鉄道,バス等の陸運事業部門の49年度の経営状況は,人件費,燃料費等経費の大幅増のため,49年に運賃改定が実施されたが経費増を賄うに至らず経常損益は一段と悪化し,これらの業種の経常収支率は 〔2−5−2図〕にみるとおり,いずれも100%を割り込んでいる。
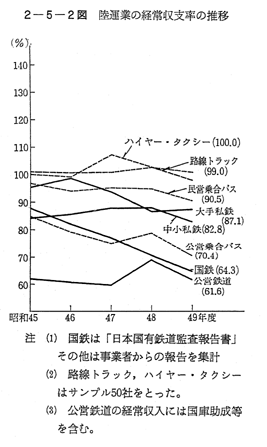
49年度にあっては,石油危機を契機として人件費,燃料費,物件費等が一斉に高騰することとなった。鉄道,バス,トラック等の陸運業はいずれも労働集約性が極めて高いことから, 〔2−5−3図〕にみられるとおり,営業費用中に占める人件費の比率が,全産業平均の7.7%あるいは製造業平均の13.4%に対し,50〜70%の高率となっており,47年度から49年度の間の営業経費の増加に対する人件費の寄与率も 〔2−5−4図〕のとおりいずれも60%以上を示している。従来,陸運業については,各業種とも省力化を中心として輸送の効率化を図った結果,第3章において述べたとおり,その物的労働生産性は 〔2−3−4図〕のように年々向上してきたが,陸運業の性格からみて経費の上昇を企業の合理化努力のみで吸収することは極めて困難な状況にある。
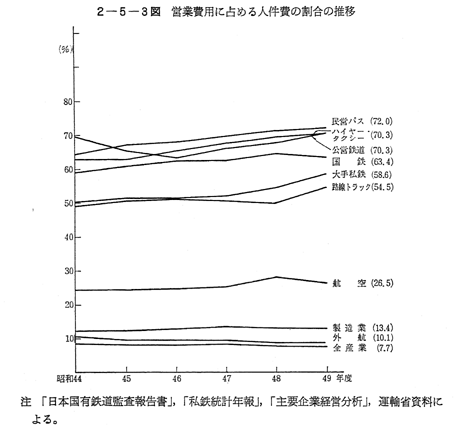
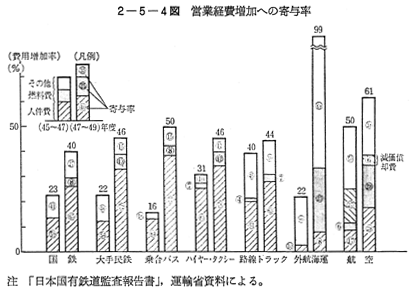
さらに,鉄道等にあっては,輸送需要の増加に対処するとともにサービスの改善,安全の確保等を図るための施設整備が要請されているが,高架化又は地下化等非常にコストの高い施設整備が多くなっているほか,混雑緩和,サービス改善,安全公害対策等直接収益の向上に結びつかない投資が増加しており,一般的な用地費,建設費の高騰ともあいまって事業経営にとって大きな負担となわ経営収支を圧迫している。
次に需要面からみると,すでに述べたとおり陸運業は,高度成長期を通じて過密過疎化とモータリゼーションの直接的な影響を受け,地方にあっては鉄道,バス等の輸送量が減少しつつあり,また都市にあっては道路混雑に加え鉄道網の整備もあり,バス,タクシーの需要が減退し収入が伸び悩んでいる。このほか,49年度には経済不況による荷動きの停滞から鉄道(貨物),道路貨物運送事業,通運業等においてその輸送量(取扱量)が大幅に減少し十分な収入の確保ができなかった。
以上述べたように隆運業の経営状況は全般的に悪化傾向にあることから,企業の合理化努力,コストの上昇を勘案しつつ,施設の整備,サービスの改善等を図るため運賃改定を実施してきたが,公共料金の抑制の一環として運賃料金の改定は必ずしも適時適切に実施されなかった。
陸運業は一般に労働隻約的な産業でコストに占める人件費の比率が高く,また製造業等他部門に比し生産性の向上が困難であるため,賃金の上昇を生産性海上により吸収することは難しく, 〔2−6−5図〕の国鉄運賃にみるような消費者物価指数の上昇率をもはるかに下まわる運賃水準は,その経営危機を招く大きな要因となっている。
運賃料金等公共料金の抑制は,物価安定のための緊急措置としては一応の効果を期待できるものではあるが,その定常化は鉄道,バス等の公共輸送機関に大きな犠牲を強いることになる。特に,国鉄あるいは公営企業にあっては,物価抑制等の要請によう運賃改定が延期,修正され,運賃が低水準となる傾向が顕著であり,運輸業全般の運賃体系の適正化をも困難としてきた。その結果,鉄道等の公共輸送機関では,採算性の悪化から投資の停滞,サービス水準の低下を招いており,効率性,低公害性,安全性についての高い評価にもかかわらず,その機能を十分に発揮できなくなるおそれがある。
運賃料金は,今後その比重が増大することが予想される安全公害対策のためのコストをも含め,輸送サービスの提供に要する原価を回収することはもちろん,サービスの拡大再生産,すなわち施設の拡充整備に要する資金の調達を容易にするような水準のものであることが必要であり,また費用負担を適正にするものでなければならず,このような観点から今後適時適切な運賃改定が行われることが望まれる。
また,運賃料金については,通勤通学割引,貨物政策割引等の各種の割引を行っているが,通勤割引の場合は,通勤費の事業所負担が一般化している現在においてはその可否が問題となろう。
以上述べたように原則的には受益者負担が徹底されるべきであるが,その所要経費のすべてを運賃収入のみで賄うことが現実的に困難となるものについては,その範囲を明確にしてその費用の一部を国又は地方公共団体が負担する必要があろう。
このような観点から,まず第1に,都市鉄道のようにその資本的経費が過大となっているものについては,その負担を軽減することを目的として 〔2−5−5表〕のとおり,国鉄に対する工事費助成,日本鉄道建設公団による鉄道整備,地下鉄建設費補助を行うとともに,これに財政融資をも加え年々その拡充を図ってきている。
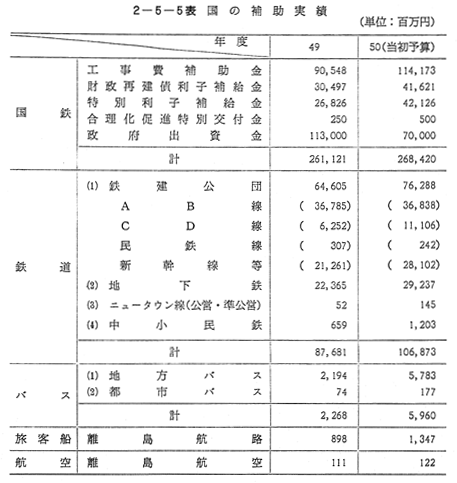
第2に,大都市周辺部に大規模な団地が次々と建設されており,この場合団地住民の足の確保のため鉄道あるいはバスの先行的な整備が必要となるが,その採算性を確保することは困難である。このため,公営又は準公営によるニュータウン鉄道の整備に対する助成及び新住宅市街地バス路線開設費補助を行うとともに開発者負担制度の導入,開発計画との調整等を進めている。
第3に,地方バス,ローカル鉄道等需要の減退から経営が困難となっている地方交通についてはその運行を確保するため,地方バス路線運行費等助成及び地方鉄道軌道整備費補助を実施してきている。
いずれにしても,これら陸運業においては,合理化努力にもかかわらず今後ある程度のコストの上昇は避けられない情勢にあり,また,国及び地方公共団体の財政事情も厳しい局面を迎えていることから,一段と悪化している経営危機を克服するためには,公共料金抑制策の評価をも含めて運賃制度の全般について抜本的に見直していくことが必要となろう。
|