ホーム > 海難ものしり帖 >海の交通法規 >海の交通法規入門
海の交通法規入門
昼間の航海 船の形象物(その2)
各種船舶間の航法でも説明しましたが、海の上では、動きやすい船が動きにくい船を避けるという原則があります。
おさらいをしてみると、その動きやすさは以下のとおり決められており、航行中の動力船が帆船や漁ろうに従事する船舶などを、帆船が漁ろうに従事する船舶
や運転不自由船などを避けることになります。
| ◎動力船 | : エンジン(機関)で走る普通の船 |
| ○帆船 | : ヨットなどセール(帆)のみで走る船 |
| △漁ろうに従事する船舶 | : 操業中で操縦が制限された漁船 |
| ×運転不自由船 | : 故障その他で他の船を避けることができない船 |
| ×操縦性能制限船 | : しゅんせつ等の作業中で他の船を避けることができない船 |
| □喫水制限船 | : 喫水と水深の関係で進路が制限された船 |
各種船舶間においては「避ける船」が決められているものの、相手船が漁ろうに従事する船舶や、運転不自由船であることがわからなければ、避けなけ
ればいけないことに気づくことができません。
そこで各種船舶は、その状況を周囲に伝えられるよう、それぞれ掲げるべき形象物が定められています。
1 帆船の形象物
帆船が帆走している場合、そのマストや帆自体が大きな形象物となっているため、特に掲げるべき形象物は定められていません。
ところが、海上衝突予防法で言う「帆船」は、帆のみを用いて推進している船舶のことを言いますので、帆を張りながらエンジンも使用して航行している場合
は◎動力船となり、○帆
船ではありません。
そこで、帆船が帆及び機関を用いている場合、前部のもっとも見えやすい場所に円すい形形象物![]() 1個を頂点を下に向けて表示します。この形象物は、大型の帆船も、小型のヨットも同様です。
1個を頂点を下に向けて表示します。この形象物は、大型の帆船も、小型のヨットも同様です。
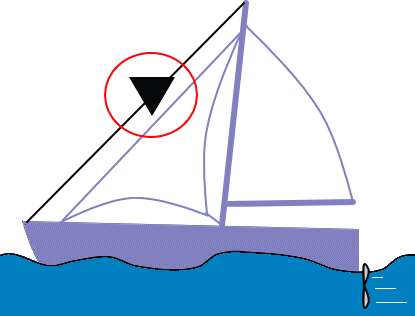
機関及び帆を同時に用いて推進している場合の形象物
(前部に円すい形形象物1個を頂点を下に向けて表示)
2 漁ろうに従事している船舶の形象物
海上衝突予防法では「漁ろうに従事している船舶」とは、船舶の操縦性能を制限する網や縄などの漁具を用いて漁ろうをしている船舶のことを言います。
例えば、底びき網、はえ縄、トロールなどがあげられ、すぐには針路、速力の変更ができない場合などが該当します。
このため、一本釣り漁など、漁具が小さく、船自体の操縦性能が制限されないものは◎動力船と
なります。
また、錨泊しながら漁ろうに従事している船舶は、「錨泊中![]() 」の形象物は掲げないで、「漁ろう中
」の形象物は掲げないで、「漁ろう中![]() 」の形象物のみを掲げます。
」の形象物のみを掲げます。
漁ろうに従事している船舶は、トロール(けた網その他の漁具を水中で引くことをいう。)により漁ろうに従事している場合と、それ以外の漁法により漁ろうに従事して
いる場合とで掲げる形象物が違います。
トロールにより漁ろうに従事している場合は、鼓形![]() (2個の同形の円すいを頂点で結合したもの)の形象物を掲げます。
(2個の同形の円すいを頂点で結合したもの)の形象物を掲げます。
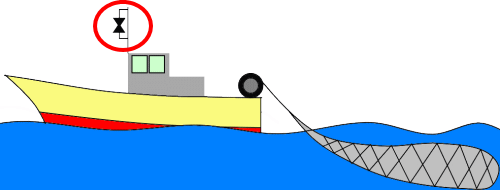
トロールにより漁ろうに従事している場合の形象物
(鼓形形象物1個)
トロール以外の漁法(はえ縄等)により漁ろうに従事している場合は、その漁具の水平距離が150mを超える場合、鼓形の形象物![]() に加えて、漁具を出している方向に円すい形形象物
に加えて、漁具を出している方向に円すい形形象物![]() 1個を頂点を上にして表示します。
1個を頂点を上にして表示します。
漁具の水平距離が150mを超えない場合は円すい形形象物は表示しなくてよいことになりますので、トロールによる場合と同じ鼓形形象物![]() 1個の表示になります。
1個の表示になります。
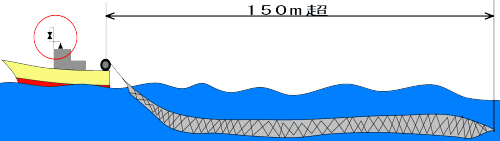
トロール以外の漁法により漁ろうに従事している場合の形象物
(鼓形形象物1個、漁具の水平距離が150mを超える場合は漁具を出している方向に頂点を上にした円すい形形象物1個を表示)
3 運転不自由船の形象物
舵や機関の故障など、船の異常事態により操縦性能が制限された場合、「運転不自由船」としてもっとも見えやすい場所に球形形象物![]() 2個を垂直線上に掲げます。
2個を垂直線上に掲げます。
また、12m未満の船舶については、表示義務はありません。
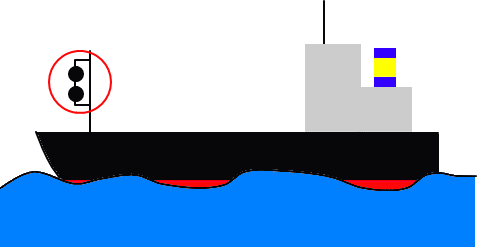
運転不自由船の形象物(球形形象物を垂直線上に2個)
4 操縦性能制限船の形象物
工事や作業のため、他船の進路を避けることができない操縦性能制限船は、垂直線上に球形![]() 、ひし形
、ひし形![]() 、球形
、球形![]() の3個を掲げ
ます。
の3個を掲げ
ます。
操縦性能制限船の場合、その作業内容は様々ですので、球、ひし形、球のほか、錨泊中であれば錨泊中の形象物(球形形象物![]() )を、えい航中であればえい航中の形象物(ひし形形象
物
)を、えい航中であればえい航中の形象物(ひし形形象
物![]() )をこれに加えて表示しなければいけませ
ん。
)をこれに加えて表示しなければいけませ
ん。
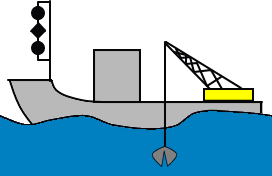
操縦性能制限船の形象物(ひし形形象物1個、その上方と下方に球形形象物を1個ずつ)
また、しゅんせつなどの水中作業を行っている場合、その作業を行っている舷側は他の船舶が通航できなくなるため、その作業を行っている舷側を伝え
る必要があります。
この場合、作業を行っている通航不能な舷側に球形2個を、作業を行っていない通航可能な舷側にひし形2個を表示します。
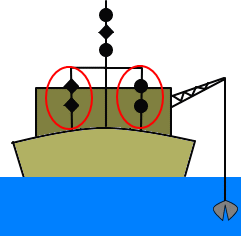
しゅんせつその他の水中作業に従事している船舶の形象物
(作業を行っている舷に球形2個、反対舷にひし形2個)
そのほか、操縦性能制限船では潜水夫による作業を行っている場合(国際A旗)や掃海作業を行っている場合(球形3個、1個は前部マスト頂、2個は
前部マストヤード両端)なども定められています。
また、動力船であっても、水先船や喫水制限船などにも掲げるべき形象物があります。
| ◎ もう少し詳しく知りたい場合は |
| 航行中の帆船等 海上衝突予防法 → 第25条 |
| 漁ろうに従事している船舶 海上衝突予防法 → 第26条 |
| 運 転不自由船及び操縦性能制限船 海上衝突予防法 → 第27条 |
| 喫水制限船 海上衝突予防 法 → 第28条 |
各種船舶間の航法を適用するには、誰が見ても容易にどのような状態の船舶なのかがわかる必要があります。
形象物はそのための大事な伝達手段です。形象物を掲げた船を見つけたときには、その状態がすぐにわかるようにしましょう。