Webニューズレター新時代Vol.68 〜一緒に考えましょう、国会等の移転〜
危機管理
- 首都中枢機能の危機管理と事業継続計画
-

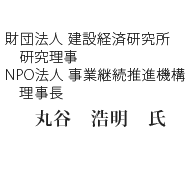
1.首都中枢機能と事業継続計画
今日、首都東京が担う中枢機能に対して懸念されている脅威には、首都直下地震、新型インフルエンザ(強毒型)、大規模テロ・攻撃などがある。これらに対応するため、首都の中枢機能を別地域に分散させた方がよいとの意見がある。一方、これら脅威に対する現状の対応として、行政には業務継続計画、民間企業には事業継続計画(いずれもBCP:Business Continuity Plan)の策定が求められている(図表1)。
BCPの主な方法論は、重要業務を絞り込み、重要業務の継続・実施に不可欠なヒト、モノ、カネ、情報、システムといった各種リソースについて、受ける被害を想定し、そのリソースの代替を確保し、あるいは被害軽減の補強をすることである。そこで、首都機能の継続のため、重要業務に不可欠な各種リソースが受ける被害状況と、その代替や補強をどのように行えるかを現実に即して綿密に考えることが求められることになる。
図表1 首都直下地震の地震防災戦略(経済被害)
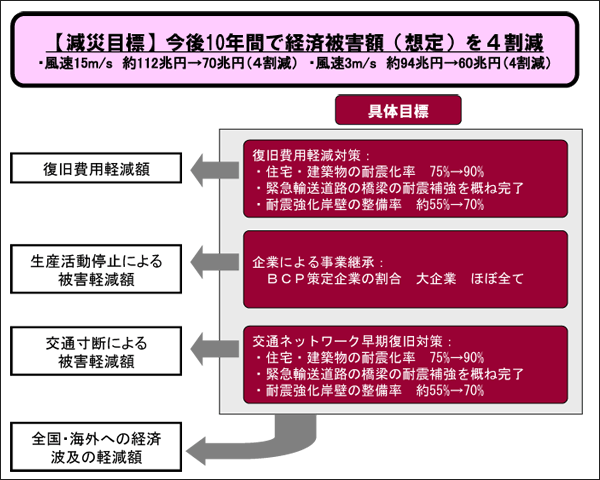
出典:内閣府(防災担当)資料
2.首都直下地震と事業継続
現在、発生が懸念されているマグニチュード7クラスの首都直下地震(注)では、震度想定が発表されているいずれのタイプでも、震度6レベルの地域はさほど広くない(図表2)。一方、首都圏の大きさをみると、東京都心、横浜市、さいたま市、千葉市及び立川市(政府中枢の代替拠点が存在)の距離は思いのほかあり、これらの都市すべてが震度6弱以上(大きな被害が出る震度)となることは想定されていない。もちろん、震源地に近い地区の被害は甚大で、耐震性不足のビルの一部は倒壊し、多くが継続使用できなくなる。人的にもかなりの被害が生じ、家を失った住民の住宅確保も困難となろう。しかし、行政や企業の重要拠点の建物・施設には耐震性があるものが多いほか、首都圏の拠点的都市のいずれかにはさほど大きな被害が出ない都市が残るため、行政や企業が首都圏に残りたいと考えれば、それは可能だと思われる。
著者の直感的な予想では、政府の中枢機関は、首都圏の復旧・復興が最大課題となるので、陣頭指揮を志向して、東京都心部から撤退したとしても、横浜、さいたま、千葉、立川などの首都圏内の都市のどこかとどまるのではないか。これらの都市に関東地方の支分局を持つ組織も多い。企業も、首都圏に本拠を置き続けることが有利なところは政府と同様な動きをすると考えられる。例えば、復旧・復興投資に関係する業種などである。それ以外の企業は、被災程度に応じ本社機能を大阪、名古屋などの大規模支店に移すところも多いであろう。
そこで、筆者は、大阪、名古屋等の首都圏以外の主要都市が、あらかじめ企業の中枢部門機能の一部を受け入れる準備をする意義を認めるものの、同時に、首都圏の各都市も代替拠点の候補として検討されるべきと考えている。
図表2 東京湾北部地震(M7.3)の震度分布
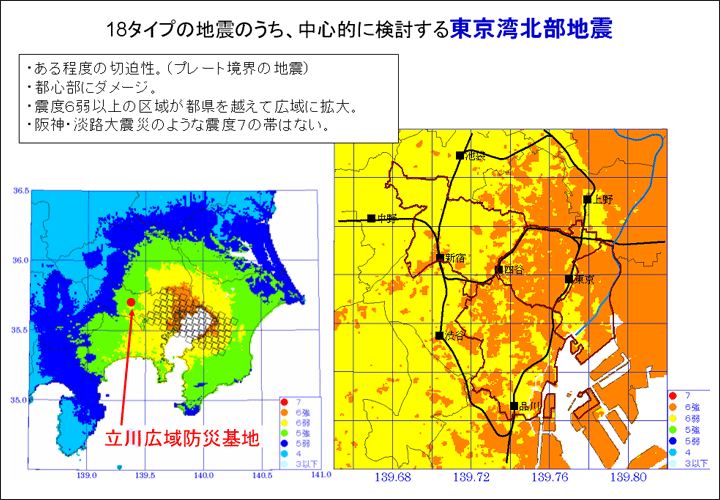
出典:内閣府(防災担当)資料
(注)内閣府は18タイプの地震動を想定。なお、関東大震災に匹敵するマグニチュード8クラスの規模の地震の発生は200〜300年間隔と考えられているので、今世紀中には発生しないと見られている。
3.感染症蔓延と事業継続
感染が続く弱毒性の新型インフルエンザA(H1N1)とは別に、トリ由来の強毒性の新型インフルエンザが蔓延すれば、政府想定では、最大で国民の25%が感染し、そのうちの2%が死亡するとされる。死亡率は高めに振れる可能性もあり、重要な官民の活動の業務継続・事業継続の備えが不可欠である。
感染症は人が密集する地域でより深刻な被害が懸念されるため、最大の人口密集地である東京・首都圏での蔓延対策は他地域にも増して急がれる。しかし、新型インフルエンザのような感染症への備えに首都機能の分散が有効かといえば、確実な保証にはならない。すなわち、分散先との間に人の行き来がある限り、東京・首都圏との同時感染を避けることが相当難しいからである。地理的に離れた代替拠点の効果は、地震などに比べて限定的なのである。
新型インフルエンザの事業継続対策では、組織全体に感染が広がらないようにするスプリット・チーム制(図表3)が有効とされるが、この場合の離れる距離の効果は、人と人とが近接しない範囲を超えれば、それ以上遠くにしても交流が多い限りあまり変わらない。
図表3 スプリット・チーム制の種類
- 1.自宅勤務を使用するスプリットチーム
- 2チーム以上に別れ、自宅勤務と出勤とにチームを分ける。出勤チームに感染者が出た場合には、出勤と自宅勤務を交代する。
- 2.泊り込み勤務を使用するスプリットチーム
- 職場やその近隣での泊まり込みにおいて、泊まり込みチーム内での集団感染にも備えるため、通常の勤務体制(又は自宅待機)の別チームを設けて、適宜交代する。
- 3.相互に行き来のない場所で並行して業務をするスプリット・チーム
- 離れた場所で2チーム(以上)が並行して同様の業務を行う。双方は電話、メール等で十分に連絡調整を行うことは可だが、食堂やエレベータを含め、相互の接触は一切絶つ。
- 4.時差勤務を利用するスプリットチーム
- 2チーム以上に別れ、同じ職場で時差勤務を行う。接触感染を防ぐために交代時に時間の幅を取り、その間でしっかりと職場の消毒、掃除をする。チーム間の飛沫感染を効果的に防ぐことは可能。
出典:筆者作成資料
4.大規模テロ・攻撃と事業継続
テロや戦争のような攻撃については、物理的・化学的・生物学的などの種類、被害の範囲や程度などが様々に考えられるため、首都機能の分散による対策を実施する費用対効果を一律に評価することは難しい。ただし、この場合も上記2で議論した「首都圏の大きさ」はまず認識しておくべきである。
米国政府の業務継続計画はCOOPと呼ばれ、詳細は秘匿されているが、平常時の10分の1程度の業務を秘密の代替場所で継続することが主旨となっている。大規模テロ等を強く意識していると考えられ、日本では同趣旨の業務継続計画の検討は未着手と筆者は認識しているが、今後、検討すべきものである。
このような業務継続では、機能分散先の場所が公表されてしまうとそこを同時に攻撃されることが懸念されるため、現在日本で行われている首都機能の分散先を公開で議論するやり方は、その意味ではあまり有効でない。もちろん、複数個所への攻撃のすべてが成功するとは限らないので、首都機能を分散させる効果が全くないわけではないし、民間部門の事業継続での観点は別に評価すべきだが、分散先の秘匿の観点は無視できない。
5.まとめ
国の政治・経済が一極集中していない方が、災害その他の脅威に対する危機管理上は有利なのは当然である。しかし、現在の日本は、東京・首都圏に政治・経済機能が集中しているのが現実であり、その本格的な分散には多大なコストと時間がかかる。また、現状を前提にしたうえで、今年中の危機事象の発生にも備えて事業継続・業務継続の方法を考えなければならない。
BCPを推進する立場から言えば、東京都心の現拠点の代替拠点の確保は、どの組織・企業にも早急に検討を行っていただきたい。しかし、その代替拠点の場所を首都圏以外の地域とするか、あるいは首都圏の別の拠点とするかは、両方を候補として具体的に熟慮していくことが妥当と言えると考えられる。