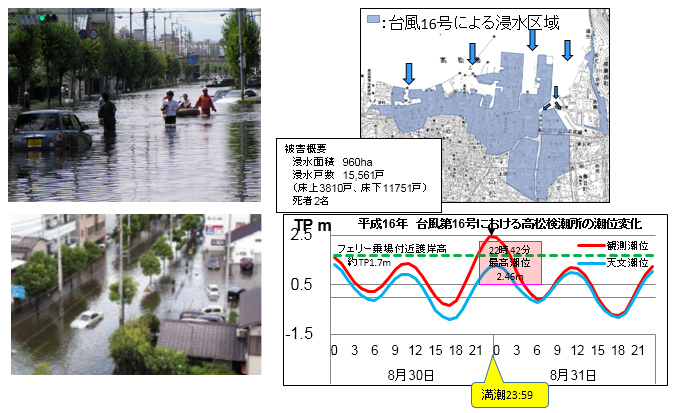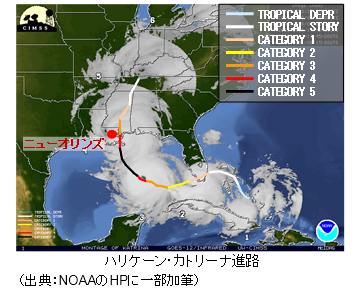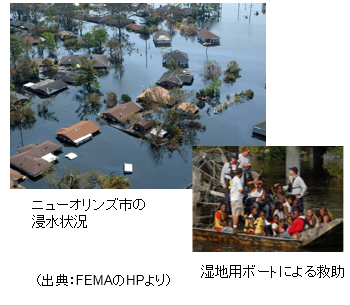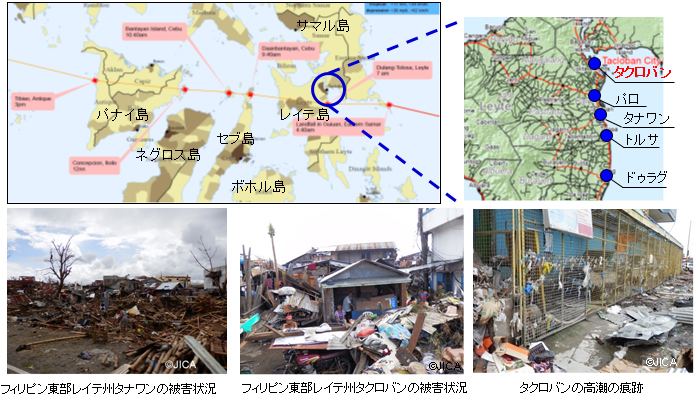伊勢湾台風体験記
本田 進(当時名古屋地方気象台勤務)
台風-しかも大型台風とくれば、社会全体が台風情報に注目し、気象台が最も華やかに活躍するチャンスである。伊勢湾台風は、その社会的影響もさることながら、私は個人的に、歴史に残るこの台風を迎えた同じ年に名古屋地方気象台に採用され、以来30年間この世界に身を置くようになったという。何か因縁めいたものを感じている。
しかしこの台風で家族や親戚あるいは友人・知人を失われた多くの方々から見れば、私の体験などは小さいものだ。しかも職場の片隅で、先輩の仕事をオロオロ眺めていた少年の小さな目-あるいは職場の中のほんの一部の又その一部しか見ていないかも知れない。だが、あのときの少年はすでに初老に近くなった。伊勢湾台風を直接経験した人は、私の職場でも数人になってしまった。少しは書き残しおく義務があるかも知れないな、と思って筆を持った次第である。
少年の目に映った思い出をもとにしているので厳密な意味での事実とは多少異なる部分があるかも知れない。その点はご容赦をお願いしたい。
あの日、朝方は、たまに木々の梢が揺れる程度で静かななものであった。厚い雲だけがやけに激しく上って(東から西へまたは南から北へ動くこと)いた。まさに嵐の前の静けさであった。
しかし天気図の上では嵐は始まっていた。
当時予報課に配属された新人は、まず天気図プロットを徹底的に仕込まれた。これは国内をはじめ、東アジア地域から入電する気象電報(気圧や風向・風速などの気象観測の結果を、型式を定めて通報する電報)を無線で傍受し、天気図へ記入する仕事である。等圧線や高・低気圧の位置などを決定する天気図描画、あるいは予報や注意報・警報などの作成は、予報官やベテランの仕事である。天気図は毎日何枚も記入するので、プロッター(プロットする人)でもベテランになると、どこの地点でどのくらい風が吹くか、というようなことは身体が覚え込んでいる。50ノット(平均風速25m/秒)を越す風はペナント(風速の…が戸の形になり、旗に似ていることからこう呼ぶ)といって、国内では富士山などの山岳官署と室戸岬の他は減多に現れないが、それが午後になると紀伊半島を中心に、あちこちで見られるようになった。
「オイッ、あちこちでペナントが出てきたぞ、スゲエナアー!」
ベテランプロッターが感嘆をこめて叫び声を上げた。
当日名古屋の気象台は、これよりだいぶ前の午前11時には警報(警報は重大な災害が発生すると予想されたときに発表する)を発表している。当時としてはまことに適確な早期発表で災害の結果からみて、もしこの警報を出し遅れていたら世間からどんな非難を浴びただろうか。後日談として、気象台としては胸を撫で下ろしていた次第なのだが…。
夕方になると、防災や報道関係の人たちが集まり、予報課の現業室(天気図を作成したり、予報や情報を発表する部屋)は慌しい雰囲気になってきた。
情報を発表するたびに、一斉電話でその内容を伝える気象台職員の緊迫した大声、独自の取材をして自社へ伝える報道記者、パトカーが来てその無線を利用して(防災無線は今ほど完備していなかった)情報を伝える県や市の消防関係者。それに、一般の人からの問い合わせに応ずる気象台職員の声などが混じり合う。
「おい、今、港の方へ行ってきたら物凄い雨と風で飛ばされそうになったぞ!」
別の新聞記者が、叫びながら飛び込んできた。そのころになると、通称日和山という、市内東部の小高い山の上にある気象台辺りでも、次第に風雨が強くなってきた。
雨合羽を羽織った観測員が、背中を丸めて露場(気象観測用の計機が設置されているところ。現在は観測機器の性能が上がり、遠隔観測ができるようになったが、当時は例えば気温や湿度なども露場の百葉箱の中で目盛りを読んだ)へ行き来する。若い職員が風に飛ばされて、行きたいと思った道とは別の道へ行ってしまった、という笑い声も混じる。
官舎が危ないとかで構内の官舎に住む予報官の家族が避難してきた。当の予報官は、奥さんに「その辺にいなさい」と一声かけただけで、そのあと家族の方を見向きもせず天気図の描画に真剣であった(レーダーや気象衛星のない当時、天気図の描画は、台風の中心などの決定の決め手になるもので、最も重要な仕事であった。)。
構内の松の木が電源室(一般家庭ではすでに停電していたのかも知れない。気象台は自家発電で電気をまかなっていた。その発電をしている建物)に倒れかかった。電気がなくては命とりだ。ロープで松の木をしばりつけ、みんなでワッショイワッショイと除ける声。
夜に入ると風雨はますます強まり、窓が唸り声を上げ破れそうになる。みんなで宿直室のタタミをめくって窓にあてがい、五寸釘で打ち付ける。このときは気象台職員だけでなく、県や市の防災関係の人も手伝ってくれた。
しかししばらくすると、今度は現業室(二階建ての建物の二階にあった)のトタンの屋根がめくれはじめて、雨がぢかに飛び込んでくる。天気図類の仕事は、急拠雨もりの少ない一階へ移したが……。
何時ごろだっただろうか。屋根の大半はめくれてしまい、建物自体が危険になってきた。
「建物が危険、これ以上の業務遂行は困難で、職員は避難する」旨の電報を台長が、上級官署である東京管区気象台長や気象庁官に発信した。
「オーイ、避難命令が出たぞー」
誰かが叫んだ。
皆が避難して、やや人影が少なくなり静かになった現業室の電話が、びっくりするような大きな音で響いた。まだ一部では電話は通じていたらしい。窓際の雨の土砂降りの中、Y先輩が受話器に飛びついた。
「もう少しです!頑張って下さい!もう少しの頑張りです!」絶叫であった。
しかし台風はまだ風向きも変えてはおらず(台風の風向きは、中心が通過すると急に反対の風向きとなる)、これからどの位の凄さを示すのか、本人にもわかっていなかったと思う。
この時刻になると電気はほとんど切れ、電話も不通。名古屋市内はマヒ状態になっていた。そしてこの瞬間、港付近では記録的な高潮が来襲、貯木場の大木が大暴れして阿修羅を呈していた。気象台でも、頭では大災害を予想できても、これほどの大惨事だったことを知るのはまだまだ先のことであった。
翌日は、北西の風が強く快晴であった。
その日が当番であった私は、プロットすべき天気図を広げた。しかし電気はなく、受信器(高性能ラジオ)はこわれ、電話は全く不通で、何の入電もなかった。
「今日は開店休業だなあ」
先輩のSさんが呟いた。昨晩の風雨にちぎれ飛んできた小枝や葉っぱが、壁といわず机といわず部屋中にこびりついていた。私たちはまず掃除から始めることにした。
私たちが、名古屋市の港区や南町あるいは東海地方全域の惨状を知りはじめたのはそれからであった。1日経ち2日経つと被害の大きさがおぼろ気にわかり、4日から5日経ってようやく未曾有の大惨事と知った。誰もが「エーツ」と声を呑んだ。
1週間ぐらい経ったところだったろうか。私は久しぶりに構内の寮を出て、ふるさとへの電車に乗った。名鉄(名古屋鉄道)で南区の呼続(ヨビツギ)辺りの高架を通過したとき、眼下の校庭にはまだ白い棺が累々と並び、車内はエも言われぬ異臭が充満した。悲しい鎮魂の臭いだったのだろうか。
気象台では比較的うまく警報を発表した。しかしそれが末端までうまく届かなかった、というような噂が、私のような新入りの技術員の耳にも届いてきた。今まで誰もが経験しなかったことで、無理もなかったとは思うが、そんな怨みもこめてか、後日のある会議の席上でS先輩が
「あれだけやってあの災害が出てしまった。力のなさというか、空しさをつくづく感じます。」
と発言された。
別の台風で、勤務中に子どもを亡くされたある先輩の姿、豪雨の中受話器に飛びつき絶叫した先輩、家族を勇気づける言葉さえ胸にしまって天気図を描画していた予報官。それらの姿が瞼に重なり私も大きく頷いた。
「そうですね。これを教訓に体勢を立て直して、二度とこういうことをくり返さないことが大事ですね」
座長をつとめていた別のSさんの声が今も耳に響いている。
-みなとの防災103号、平成元年 港湾海岸防災協議会-より転載