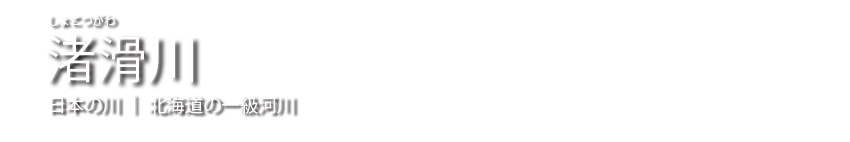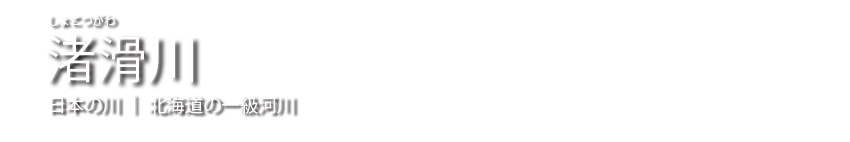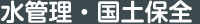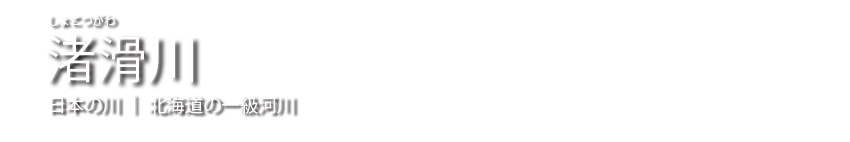渚滑(しょこつ)川という名は、滝上市街の下流部は滝となっており、その地形を示すアイヌ語の「ショ・コツ」(滝の・凹み)に由来してます。
渚滑川の開拓は明治26年に新潟県から渚滑原野に入植したのが始まりで、その後、徐々に奥地へと開拓が進められたことを受けて、農地面積拡大のための森林伐採が行われました。木材は渚滑川を使って河口まで流送し、木材積取船に搭載され運ばれたといわれています。
渚滑川の開拓の歴史は、明治26年に新潟県からの移民が渚滑原野に入植したのが始まりで、その後、徐々に奥地へと開拓が進められていきました。
その後、開拓が上流域に広がったことを受けて、農地面積拡大の為、森林の伐採が行われるようになりました。
伐採した木材は渚滑川を使って河口まで流送しました。紋別沖で待機する大型の木材積取船に搭載され、本州の各地へ運ばれたといわれています。木材流送は陸路の交通網が整備され、次第に衰退することとなりますが、大正時代まで続けられていました。これらの名残から、現在でも上流の滝上町では代々林業が受け継がれています。