
|
| 開会・挨拶 | 第5回(平成11年9月1日) |
|
|
||
| 3−1.ショートスピーチ (安部委員) | ||
| 大体、皆さんご存じのように、自分の恥をさらして世に出た小説家だから、学問もなければ、教養もない。何を話していいのか、とても困っているうちに9月1日になってしまった。
先日、この懇談会が終わってから、上に上がってご飯をいただいて、一杯飲ませていだたいた。これでは逃げるわけにいかない。僕たちの言葉でこれは「一宿一飯の義理」と言う。(笑)どうしても何か話さなければいけない。でも、そんな僕だから、余り まとまったことは喋れない。何を話したらいいか、いろいろ考えて、そして、「あっ、これだったら聞いて貰えるのではないか」と思ったのは、この4月に八ヶ岳に小さな山小屋をつくったことで、その経緯を20分間話すると決めた。 あれは2年前の97年8月のことである。松下幸之助さんのおつくりになったPHP研究所という出版社が、僕に「八ヶ岳にいる泉郷という別荘分譲業者が、ビジネスマンが避暑に来てそのまま仕事をすることが可能なオフィスオートメーションの設備を備えた貸別荘をつくったから、行ってレポートを書いてくれ」と依頼してきた。そんなわけで小さな車に乗って女房と一緒に出かけて行った。 早々と原稿を書き終わって、確か「なまいき」という変わったいい名前の地酒がとてもうまかったので、寝酒にガブガブ飲んだ。そうしたら、いい気持ちで寝ているところに隣に寝ていた女房が僕を起こしにかかった。何とはしたないことをいいおばさんがするのだと思ったら、そういうことではなくて、「あなた、誰か表に来た」と言うのである。確かにコンコン、コンコンとノックしている奴がいる。時間を見たら朝の5時だった。こんなに早く起きるのは、パン屋でなければ豆腐屋ぐらいだろうと思ったのだが、女房は寝巻だったので、仕方がなく僕が玄関のところまで行ったのである。開けてみたら誰もいない。「何だこの野郎」と思って、表に出て見回したら、まだノックが続いている。何と見上げた白樺の上にアカゲラが止まっていて、それがトントン、コンコン、トントン、トントントンと叩いていたのである。 そのときに何とも言えない感動が湧きあがった。武蔵野市の外れにある僕の家からわずか2時間で着けるところにこんな自然がある。アカゲラに朝起こされる自然があったというのは、東京で生まれて都会で暮らしてきた僕にとってはもう何とも言えない、これがうまく書けたら直木賞をいただけるのではないかと思うような、そんな感動であった。 そして、僕はその別荘業者に言ってしまったのである。「おい、切れっぽがあるだろう」と。「切れっぽ」というのは、土地を分譲するときに大抵は高台か南側から 100坪なり 150坪なり、単位で切っていくのだが、そうすると、必ず低いところの、ほとんど沢になったようなところに残る余りの土地のことである。分譲するといっても、自然の土地はそんなきちんと割り切れるものではない。「おい、切れっぽがあるだろう」と言ったら、そのテクニカル・タームを向こうは即座に理解して、「切れっぽがあります」と答える。「それ見せろ」と言ったら、何と誰が切ったのか、北の方から切っていって、南の高台が「切れっぽ」になっていた。僕は仰天した。「これ切った奴、首になったろう」と言ったら、「会社が始まったころなんで、誰だかわかりません」なんて言っていた。そうして、「この切れっぽ寄こせ。何坪あるんだ」と言ったら「74坪です」と。泉郷の規定で20%しか建てられない。そうすると、1階の床面積が14.8坪が限度である。そして、総2階はいけない、ロフトだったらいいという条件が付く。 実は、僕たちの「切れっぽ」の割と近所に弘兼・柴門夫妻が 350坪ぐらいのすごい土地をお持ちである。3年前に買ったのに、まだ何も建っていない。それは大きな坊ちゃんとピアノをなさっているお嬢さんと、おまけに女房の柴門ふみさんと、この3人がいろいろ言うので、島課長(弘兼氏)は困り果てているのである。(笑)それで、船頭が多くて山小屋は建たない。お金はあるのだが。 僕の場合はまるで逆で、お金はないけれども、絶対専制君主がいるのである。だから、僕は原稿に書いた。「これが自民党や社民党だったら、山小屋はいつまでも建たない。公明党だったらすぐ建つ」と。(笑) そして、僕はその74坪の「切れっぽ」を衝動買いしてしまったのである。その別荘業者の社長が一杯飲ませたので、「これはもしかしたら、あのアカゲラはおまえさんの放ったセールスバードか」と言い、アカゲラのせいにしてしまった。(笑) さて、74坪の「切れっぽ」はまんまと手に入れたのだが、女房は憮然とした。9年前に、突然バブルが弾けて、あわれや数億円の負債を背負うことになった。バブルの張本人たちは何と数億円の退職金をもらって悠々とどっかに隠居してゴルフをしていると聞いて、ほとんど血圧が上がって倒れそうになった。そのとき、女房は「奥の手を出してはいけない、これは何億円でも返さなきゃいけない」と僕を説得したのである。僕はいろいろ奥の手は知っている。(笑) それから9年間、5分の3返した。まだ5分の2弱負債がある。女房は、「あと4年、今のペースで働き続ければ無借金経営になる」と言って僕を励ます。そんなときに74坪の「切れっぽ」でも、アカゲラのおかげで……、この「何々のおかげ」というのは実にいいのである。何でも誰かのせいにしてしまえば、人生というのはとても楽しく朗らかに過ごせる。 まだ5分の2弱残っている。衝動買いをしたということで、女房は憮然としているのである。それが97年8月のことであった。 それから、僕は前にも増して一所懸命働きながら、絶対専制君主である女房に説き続けている。借金はまだある、まだ返さなければいけない。けれども、わずか2時間で行けるところに体を休められる、そして仕事もできる小屋をつくれば、もっと働けるに違いないと、2つの「アル」に気をつけて頑張ると言い含めた。それはアルツハイマー症とアルコール中毒である。残念ながらエイズはもう心配しなくてよくなったから、2つの「アル」に気をつけて頑張るから、どうぞあそこに小さな山小屋を建てておくれと。そして、弘兼夫婦の例を見ているから、これは女房にすべて、デザインから色から材質からみんな任せて、僕はもう何も言うまいと決めた。 たった1つ、寝室と同じフロアにトイレだけ1つつくってくれと。多分寝室はロフトになるのだろうけれども、どうぞつくっておくれと。なぜかと言えば、僕は寝酒を人並みに飲むので、必ず夜中に一度目が覚めて、階段を降りて下まで行って用を足して、そうしたら冬でなくても完全に目が覚めてしまうだろうと。そうするとまた寝酒を飲むことになる。(笑)それは「やばい」と言ったら、女房もそれは「やばい」と言ったのである。(笑)そして、女房に任せて、僕が希望したのは、「屋根にカザミドリを乗せることと寝室と同じレベルにトイレをつくってくれ」、それだけだった。 そうしたら、着々と作業は進行して、女房はインスタントカメラを振り回して、よそ様のすてきな山小屋を写しまくったのである。「ドアはこれにする」、「取っ手はこれにする」、いろいろ決めた。けれども、いくら女房が図面を引いてもこれだというのができない。そしたらそこにある建築家が現れて、僕たちの希望を聞いて、そして瞬く間に、1階の床面積が14.5坪、そしてロフトが四畳半の僕の仕事部屋と12畳の寝室、それに小さなトイレまで、見事につくったのである。いや、「専門家というのはすごい」と言って、工事にかかったのが去年の冬のことである。 お金の手配も、とある銀行が盛んにぶつぶつ言いながら貸してくれて、女房からは「あなた、これから毎月18万円ずつ余計に働きなさい」なんて言われた。(笑)そして、連載をとり過ぎてしまったのである。僕はある新聞の連載に、朦朧とした頭で苦し紛れに、某ご婦人方の悪口を書いてしまった。書いてから「しまった」と思った。(笑)活字になって、なおさら「しまった」と思った。18万円収入を増やすために連載をとって、そして朦朧とした頭でこんなに筆が飛んでしまって、連れ合いの方もいらっしゃるし、ファンもいるだろうし、お子さまたちもいらっしゃるだろうし、みんな怒っているだろうなと思って首をすくめた。女房も「あなたがそう書かれたら、今ごろここにいないね。木刀持って飛んでいっているわね」と言うから、確かにそうだと。書き過ぎた。こういうことのないようにする詫び状を書いてもしようがないから、「このまま謹慎する」といって、首をすくめて風化するのを待っていた。 そして、ついに4月4日に……、ちなみに4月4日というのはお節句なのだそうである。全部1月1日から始まって、12月12日まで、月と日にちが重なり合う日はすべてお節句なのだそうである。4月4日は何のお節句だと聞いたら、ひな祭りと5月5日に挟まれた4月4日はゲイボーイのお節句なのだそうである。本当なのだろうか。(笑) 4月4日にカザミドリの乗った山小屋の引き渡しを受けたところで、あきれたその新聞はたちまち連載を打ち切ったので、どこかに連載を増やさなければいけない。何か心当たりがあったら、どうぞ安部譲二に稼がせて下さい。(笑) 山小屋ができて、僕は男の、特に小説家の仕事部屋は、書庫だとか、そういうのを除いては「一畳半が理想だ」という持論がある。僕は建築家の牛尾さんに、「俺の仕事部屋は一畳半にしてくれ」と言ったら、「そんな馬鹿な、どうして一畳半なんだ」と聞かれたので、「手を伸ばせば何でも取れる、あとは本棚を置くスペースがあれば十分だ」と言い放った。ところが、「とにかく余り極端だ」と言って、四畳半のスペースの仕事部屋をロフトにつくってくれた。何と快適なことか。何と静かなことか。あそこで書けなかったら、もう小説家やめた方がいいと思う。飛躍的に仕事がはかどる。 女房のセンスを信頼してすべて任せて、仕様からカーテンから材質から、牛尾さんに希望を話して、すべて女房の好みで建てた。そして、昔の僕の子分が集まって、一番大切な台所だけ「自分たちにつくらせてください」と言って、洒落たイタリアンカラーのシステムキッチンをみんなでつくってくれた。 それにつけても思うことがある。住むところをつくる、家を建てる、その根本になければいけないものは、とてもキザなことなのだが「愛」だとつくづく思った。贅沢にお金を使っても、「愛」がもとになっていない建物は居心地がよくない。 いろいろ思い出す。僕がこの62年間の人生で住んだところを思い出す。居心地のよかったのは、共通して「愛」が基にあった。僕の武蔵野市の外れにある家もいろいろ引っかかるところはあるのだが、「愛」に基づいていると思う。そして、今度「切れっぽ」に建てた小さな山小屋も、間違いなく「愛」に基づいていると思う。そして「これが真理だな」と思ったのであった。 こんなことでいいのだろうか?一宿一飯の義理はこれで終わりです。(笑)(拍手) |
 |
|
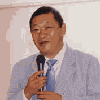 |
||
|
|
||