
|
| 開会・挨拶 | 第5回(平成11年9月1日) |
|
|
|||
| 4.ディスカッション | |||
| 【嶌委員】 | |||
| 本日のショートスピーチは住む家、場所の力、コミュニティといった話が中心だった。安部さんは住む人の側から話をされ、長谷川さんと林さんはつくる人の側から話をなさった。これまでの縦社会では、行政、国家の主導によってものをつくるという発想であった。しかし使用する人、生活する人の論理を重視してものづくりを行わないと、場所の力、歴史、伝統が生きる、本当に居心地のいい社会は生まれない。このことをお三方は共通しておっしゃっている。 |  |
||
| 【上山委員】 | |||
| 今日のお三方の話は個人、コミュニティ、建物といった等身大のお話で、感動した。
4つほどコメントがある。英語で恐縮だが外人は、「個人がどうしたいのか。」という意味である「アスピレーション」という言葉をよく口にする。やりたいことをやるのである。まさにアカゲラとの出会いはアスピレーションだと思う。アカゲラと出会って家まで建てしまう。日本においても潜在的なアスピレーションをひき出すことがまずはスタートになる。次に仲間を誘ってコミュニティをつくり、そこでまちづくりが始まる。そして最後にこの国のかたちができる。個人のあり方よりもまず我が国のあるべき姿を先に決めようなどという発想はこの際すてるべきだ。 2番目に、良いものをみなに広げるにはどうすればいいかについて。いいものを見れば、みなまねする。いいものを見せ、それを広く伝える。スピーチではそのようなに広げていくことをバザール形成とおっしゃっていた。規則、ビジョンではなくてバザールが必要である。 3番目に、市場の失敗、政府の失敗と経済学ではよく言う。政府が失敗したので市場に戻りましょうと言っている。だが、政府が存在する理由は市場の失敗をフォローするためである。今日のように両方失敗した場合どうすればいいか、やはり個人とコミュニティで解決するしかない。日本には個人という概念はありそうでない。コミュニティは昔あったが、なくなってしまった。だから政府の仕事は個人とコミュニティをつくることである。コミュニティを形成すれば、政府の仕事も減るし、市場の競争原理に直接さらされて悩む個人もいなくなる。個人とかコミュニティをどうやってつくっていくかという事をぜひ考えていただきたい。その結果、行政の中身も変わるのではないか。 それからもう1つ、コミュニティづくりは、ポリティックメイク、エンジニアリング、リーガルではなく、ネットワークづくりではないだろうか。安部さんの家に仲間がシステムキッチンを持ってきてくれた、それは気持ちと財を交換するという、やりとりである。こういう経済学が必要だ。それから人と人が集まって納得し、感動し、パワーを出す。そういう林さんの世界もある種政治学だと思う。今までとは違うパワーを引き出すテクニック、エンジニアリングが必要である。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 昔は技術の日産、技術の日立とか言っていれば、買ってくれる人がいた。今は使い勝手を考え、消費者の声を聞かなければ、買手が見つからない。Windows 95だって使い勝手がいいから、あれだけ爆発的に売れたのだろうと思う。 |  |
||
| 【成毛委員】 | |||
| お客さんに製品をそのまま押しつけることが難しくなっており、「シナリオマーケティング」が言われるようになってきている。製品のコンビネーション、自社製品だけでなく、他社製品も紹介したり、または使い方や使っている人たちを紹介したりし、ことような一連のシナリオをつくる。大企業、中企業や個人、個人もシングルから子供さん、お孫さんがいるような家庭まで、いろいろなシナリオをつくっていく。
建築もシナリオづくりをしていると思った。単純に箱だけではなくて、使い勝手、使い方、コミュニティのあり方も含めて考えられている。シナリオを提示するという意味では非常に最先端で、こんなところに原点があったのかと思った。 シナリオのあり方は多様化している。コミュニティというのはネットワークにおけるワールドワイドの上にも存在する。コミュニティより個人でいる方が快適な場合もある。多様化する製品、多様化する技術について語るのをやめ、多様化するシナリオ、多様化する個人の立場を考えていきたい。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 価値観が多様化してくれば、当然多様なシナリオが必要になってくる。世の中の潮流からして、例えば建築とか都市設計も多様化しているのか。それとも、バブル崩壊でコストが安いものをつくらなくてはいけない、なるべくマニュアル化して安くしなければならない。どちらの方向に進んでいるのですか。 |  |
||
| 【石井委員】 | |||
| それはやはり多様化だろう。せめぎ合いとしてあらわれてくるというか。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 坂井さんは選択肢の多い分野の中で仕事をされている。プレッシャーはあるのか。 |  |
||
| 【坂井委員】 | |||
| 我々がつくっているものは基本的にマスプロダクションである。その中でどのように多様化という問題を捉えるかは大変難しい。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 大量生産、大量消費の時代が終わって、昔に帰れといった回帰現象がおきている。例えば、安部さんのアカゲラの話の中にも、昔に戻りたいという気持ちが含まれていると思う。 |  |
||
| 【井上委員】 | |||
| 安部さんのお話を伺ってもアカゲラの姿形を思い浮かべられない。アカゲラを見分けることができるのはそういう環境になじんでいる方である。昔に帰りたいと言っても、私はアカゲラがどんな鳴き声をしているのか知らない。昔を知らない人間の昔に帰りたいという気持ちには、どこか嘘があるような気がする。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 確かに昔のことを知らな過ぎる。アカゲラをイメージできる人は手を挙げてください。(笑) |  |
||
| 【川勝委員】 | |||
|
私は3年前までアカゲラを知らなかった。それらが生息している環境に行けば、すぐにアカゲラやコゲラ、シジョウカラやゴジュウカラなどを見分けられるようになる。飛び方も違うし、木とのコミュニケーションも違う。生活環境が変わると、その知識はおのずと増える、ということで井上さんにも安心していただきたい。(笑) |
 |
||
| 【安部委員】 | |||
| イメージできなくても、テレビで見て知っている。だから、ペリカン見たときはペリカンと思うし。 | 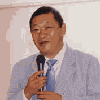 |
||
| 【井上委員】 | |||
| 私もペリカンとわかると思う。(笑) |  |
||
| 【安部委員】 | |||
| アカゲラを見たときに頭のこの辺が赤かった。だからアカゲラだと思った。 |  |
||
| 【井上委員】 | |||
| 不動産屋が放ったアカゲラではなかったのか。(笑) |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 同様に、そこに住んでいる人たちの声、林さんも、長谷川さんもおっしゃられたが、そういう声というものを聞かないと、その地域、環境をイメージすることは難しい。 |  |
||
| 【林委員】 | |||
| 日本人は、驚くほどみんな書く。普通会議で、何もしゃべらないおじいちゃん、おばあちゃんも、あるいは若い人も、ポストイットを渡して、とにかく書いてと言うと、調子が出てとっとっと書いてくる。またさらに、その書かれた意見をみんなの前に示すことが重要である。こんなふうに考えているのだと確認できる。日本人の一人一人が考えていないというのは嘘で、みんなものすごくいろいろと考えている。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| プレゼンテーション能力というか、自分を表現することに対して、日本人は余り慣れていない。しかしお上に対して市民パワー、そういうところからしかパワーは出てこない、と竹中さんと上山さんはおっしゃった。 |  |
||
| 【竹中委員】 | |||
| でけへんことが物理的にたくさんあればあるほど、エネルギーをたくさん持ってはる。それをどうやって出そうかと思っている。出す機会がなかったり、出せへん人やと周りが思ったり、それがまた余計にその人のたがになっている。
プロップの場合、仕事をしたい、お金儲けをしたいというより、自分を表現したいという気持ちが強い。住宅政策にしても、老人ホームにしても、住むなら住む、ホームだったら収容されるイメージがある。働ける老人ホームとか、そういう発想に変わっていかないだろうか。高齢社会においても働き続けることができ、自分を表現し続けることができれば、世の中大きく変わっていくと思う。ビジョンの中にもそういった住宅、施設のイメージを入れてもらいたい。 |
 |
||
| 【松田委員】 | |||
| 「多様化」という言葉を少し遊び過ぎたのではないか。日本人は何をしても構わないことを多様化と表現している。かえってそれが国の品位、質、レベルを落としてきた。まちづくりに対しても多様化を求め過ぎた。そのせいでまちの品位を落としてきたのではないのか。コミュニティの問題でも多様化ということを言い過ぎたために、個人主義になり過ぎたのではないのか。多様化という言葉に逃げ過ぎないことが重要であろう。行政は市民を規律で縛りながら、「多様化」という言葉で逃げているのではないかなという気がしている。
ヨーロッパの老人ホームでは老人は寝かされていることはなく、食事のときには起きて、普通の洋服に着替えて食事をしなければならない。テレビで映る限り、日本の施設では体操服を着せている。介護する側には楽かもしれないが、本人の自立という意味ではよくない。あなたはもう老人なのだからと、周り人がその人を老人にしてしまっている。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 澤登さんは、居心地のいい社会をどういうふうに考えているのか。 |  |
||
| 【澤登委員】 | |||
| 自立にこだわっている。都会の人たちは家庭や地域を消費の場と基本的に考えている。農村の人たちは自分たちがきちんと食べていける自信を持っている。都会の我々は土地から何かを生産することができないので、知恵を売ったり、工場で何かを生産してお金を稼いでいる。お金に対する執着心が身にしみついている。自分たちの中にあるそういう意識をどれだけ捨てきれるだろうか。家庭やコミュニティを生産の場として捉え直し、住まいやまちを協働の場であるとすることから始めてみる。家庭やコミュニティという場を働き、作業するところであると捉える必要がある。 |  |
||
| 【隈部委員】 | |||
| 学生が希望を持っていないと感じる。今の50代、60代の人たちがさらに10年も20年も頑張ってくれるだろうから、(笑)自分たちはしばらくフリーターでも大丈夫だろうと思っているようだ。ちょっと私も心配はしている。
3年ほど前に21世紀の高速道路はどういうものがいいのかという日米のプロジェクトに参加した。そのとき、アメリカと日本からの設計の専門家が出席し、私はユーザーとして入った。アメリカ人はまずコンセプトを決めて、その決定されたコンセプトをもとに、具体的な仕事を始めるべきであると主張した。日本人は何も調査もしていないのにコンセプトは決められない、すべて調査が終わった段階でコンセプトを決めると言い、意見が対立した。結局3日間討議し、アメリカ人いう手法でそのプロジェクトを実施した。 21世紀の暮らしをどうしていくのか、多様化に対応するためにはどうしたらいいのか、何らかのコンセプトを持つことがもっとも重要であると思う。 今日のお話聞いて、長谷川さんはコンセプトが大事だと強調した。林さんはまちづくりのコンセプトはTPOがあるとおっしゃった。それから、安部さんはコンセプトには愛があるとおしゃった。エーリッヒ・フロムの名言に「権力のあるところに愛あらず」という言葉があって、非常にそれが気になっていた。嶌さんにお願いがある。建設省のおえらい方たちがいつも同じテーブルに座っていらっしゃる。お時間があれば一言ずつでも。(笑) |
 |
||
| 【澤田委員】 | |||
| 観光の形態も忙しく見て回るより、滞在型になってきたと言われる。日本人の心の持ち方とか、求めるものが変わってきていると感じる。ただ見るだけのサイトシーイングから、勉強する、滞在する旅行に変化してきた。私もカリブの方に行かせて頂いていた。(笑)非常に忙しくて疲れていて。カリブには何もないので自然にゆったりとできた。しかし1週間、10日ぐらすると、仕事がしたくなる。
暮らしもそうだが、矛盾しているところがある。きれいさが必要だが、その反面ドロドロと汚さも必要。全世界のいろいろな町を回るが、すごくきれいな町は不思議と発展しない。きれいさがあって、例えば歌舞伎町みたいなドロドロとしたところがある町が発展する。気持ちはきれいな方がいいが。しかし、きれいさだけでは発展しない。パワーがない。 やはり両方あるのが一番いい。自然があって反面、何かをやっている、何かをやれる空間が必要ではないだろうか。 最終的には、人と自然との調和ではないかと思っている。これがうまく調和したまちづくりが必要ではないか。コンピュータはない方がいい。(笑)言い方が悪くて怒られるが。なくていいと言っているのではない。ないように見える、テクノロジーがないようなまちづくり、家づくりが必要であろう。必要なときに「ひらけごま」と言ったらコンピュータが出てくる。テクノロジーが下にあって、自然が前にある。人と自然が調和しながら、テクノロジーと調和したまちづくり、暮らし方がいいと感じる。 |
 |
||
| 【加藤委員】 | |||
| 例えば大きい政府から小さい政府、中央集権から地方分権、個の自立へと。地方分権、国があってコミュニティをつくる。みんな自立しましょうではなくて、逆。やはり個人があってコミュニティがあって、それで国が何を受け持つかという、順序であろう。江戸時代においては国は温泉饅頭の皮のようだった。警察から消防まで、コミュニティが担っていた。個人が多くの役目を果たしていた。それを欧米列強に追いつこうと、中央集権的なシステムに変えた。無理やりそういう仕組みをつくって、
100年間続けた。大化の改新のころからそのようなシステムの国ならば、日本はそういうものだと思って考えた方がいいかもしれない。しかしたかだか
100年ぐらいなら、変わる余地は大いにある。 コミュニティでやっていたことを国にアウトソースして、税金を払っている。国の方もパンクしそうだ。国ももたない。最近学生をはじめ、個人がNPOに非常な関心を持っている。個人は国家に多くの部分をアウトソースし、さあこれで時間もできたし、暇もできたしと思ったら、何していいかわからなくなった。ある種の空洞化というか。個人も気持ちの上でもたなくなってきている。 結局個人とかコミュニティに立ち戻って考えるのだろう。人間というのはそれほど複雑ではない。コミュニティづくりも難しい問題ではないだろう。何もなければ周りの人ともつき合わない。しかし何か必要があればつき合うわけで、そうやってコミュニティはつくられると思う。 昔はコミュニティ=エリアだったのが、エリアとコミュニティは必ずしも一致していない。これはまさに情報化の進展による。コミュニティを捨て去った東京にいると、物すごく気楽で、コミュニティに憧れている東京の人が田舎に住むと、恐らく住み始めた瞬間に辟易すると思う。そういう厄介さと気楽さのどの辺で落ち着きを見つけるかという話ではないか。情報化の結果、その折り合いをつけやすくなってきている。 |
 |
||
| 【川勝委員】 | |||
| 月並みな表現だが、大転換期にきている。日本の歴史は、縦社会から一人一人の個人におりてくる課程であったという気もする。
江戸時代、士農工商と言うが、士には士の役割があるし、商には商の役割があった。農民には農民の役割があって、役割において対等であるという思想もあった。しかし、士の役割は一応統治する役割、つまりお上の役割で、ヨーロッパの個人主義と出くわしたときに、日本の縦社会という側面が非常に強く見えた。しかし、お役人さんは公僕である。公僕である以上でも以下でもない。 「個人」という言葉はジュージェロの訳で、もとはヨーロッパの言葉である。日本人の生き方それ自体をなかなか表現できない。結局一人一人の人生のシナリオがあって、そのシナリオは極めて多様である。その多様性はいわば現象であって、それ自体を基調コンセプトにすることはできないと思う。安部さんは土地と一体化したコミュニティというよりも、人的なネットワークの中で一種独特のコミュニティをつくってこられた。一匹狼でやっていくと言いながら、そこに奥さんが、あるいはその兄弟分がいて、それに生かされていることに気づかされて、そこに居心地の良さというか、幸せを感じられている 新潟は水浸しの世界であって、1000年前は何もない、全部海であった。新潟は浮島である。だから水と見れば埋めてきた。日本一の川、信濃川の隣に長谷川さん設計の芸術劇場ができた。建物の上に上がったら、そこは丘で、そこから山々が、信濃川が見える。これは自分たちがつくってきた、まさに自然というのは自分たちのものだということを感得させるような装置になっている。恐らく県民は非常に誇りに思っておられることだろう。だからみんなが行く。コミュニティのキーコンセプトは何かと調査し、長谷川さんも地域に対する愛、人々の愛を感じて、ああいう形に表現されたと思わざるを得ない。 縦社会がついに終わって、主権在民で一人一人が生き、幸せを追及する権利がある。俺一人では生きていけない、生きているのではないというある種の公共性に気づかされて、そして新しいシナリオをつくることを求められていると思う。どういうコンセプトが大事であるかということを出さなければならない。我々自身の人生をかけて出してみたい。 人間はコンセプトをつくる動物ではないだろうか。カケスを初めて見て、あんなきれいな鳥だったのかと、そういう驚きというコンセプトを与えることによって、初めて自分の認識の中に入ってくる。1つ1つに対してコンセプトを与えることによって、お互いにともに共生しているという面があると思う。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| どこの地域も場所の力を持っている。来年沖縄でサミットをやることになったのも、沖縄の持っている場所の力が沖縄を選ばせたのだと思う。福岡と大阪と札幌とかいろいろなところが名乗りを上げていたにもかかわらず、一番可能性の少ない沖縄がなぜ選ばれたか。例えば自然だとか環境だとか、あるいは国際交流とか文化だとか、あるいは地域紛争がない世界だとか、そういう場所の力を沖縄の歴史は綿々として持っている。そういう場所の力が沖縄にサミットを引き寄せたのだろう。
そういう場所の力はどこから引き出せるか。やはり、そこに住んでいる人たちが、意見を出し、それをみんなの前に表現して、積み上げていく、個人、コミュニティ、国家という流れの中でしか積み上げられてこないと思う。 |
 |
||
| 【小野事務次官】 | |||
| 今日を合わせて5回、大変貴重なご意見をいただいている。冊子を通して読ませていただいた。今日初めて参加させていただいたが、いろいろな楽しいおもしろい話、このようなわきあいあいとした雰囲気の中、このようないろいろなご指摘がいただけるとは思っていなかった。私ども、行政も、将来の豊かな国民生活をどう築いていくかという一端を担っている。いろいろご示唆をいただければと思っている。
「権力のあるところに愛はない」というお話もあったが、私どもは愛の固まりである。(笑)よろしくお願いをいたします。 |
|||
| 【嶌委員】 | |||
| 多分、今のあいさつだと誰も愛を感じない。(笑)今の建前的なあいさつではなく、次官の個人的な顔を出すとみんな愛を感ずることができる。だから、もう1回やってください。(笑) |  |
||
| 【小野事務次官】 | |||
| やり直させていただく。(笑)大変感銘を感じた。本当にありがとうございました。大きな構造改革の流れの中で議論すると、流れに流されてしまっている、そう感じる。行政改革、地方分権についても、こういう場で議論をしていただきたいと私は率直に思う。 | |||
| 【嶌委員】 | |||
| まだ足りないが、しようがない。(笑) |  |
||
| 【川勝委員】 | |||
| 愛をみんなで注がないと。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 裸になるということが肝心だという意味だろうと思う。一応これで終わりたい。 |  |
||
| 5.閉会 | |||
|
|
|||