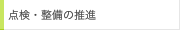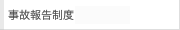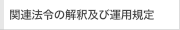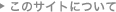‚Pپ@‚ح‚¶‚ك‚ة
‰ن‚ھچ‘‚ة‚¨‚¯‚éژ©“®ژش•غ—L‘نگ”‚ح–ٌ8,200–œ‘ن‚ة’B‚µپA‚ـ‚³‚ة“ْپX‚جگ¶ٹˆ‚ئژذ‰ïپEŒoچدٹˆ“®‚ةŒ‡‚‚±‚ئ‚ج‚إ‚«‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA‹ك”NپAژ©“®ژش‚ح“dژqگ§Œن‚ً—p‚¢‚½گV‹Zڈp‚جچج—p‚ة‚و‚è‰vپXچ‚“x‰»‚µ‚ؤ‚¨‚èپA‚و‚è•ض—ک‚ب‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پBˆê•ûپAŒً’تژ–Œج‚âٹآ‹«–â‘è‚حˆث‘R‚ئ‚µ‚ؤ‘ه‚«‚بژذ‰ï–â‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپAˆہ‘S‚إٹآ‹«•‰‰×‚جڈ¬‚³‚¢ژشژذ‰ï‚جٹm—§‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB
ژ©“®ژش‚حگ”‘½‚‚ج—lپX‚ب•”•i‚إچ\گ¬‚³‚ꂽ‹@ٹB‚إ‚ ‚邽‚كپAژg—p‚ة”؛‚¢پA‚ـ‚½ژٹش‚جŒo‰ك‚ة‚و‚ء‚ؤ—ٍ‰»پE–€–ص‚ھگi‚فپA‚»‚جچ\‘¢‚â‘•’u‚جگ«”\‚ھ’ل‰؛‚µ‚ـ‚·‚ج‚إپA“_Œںگ®”ُ‚ً‘س‚ê‚خپAŒجڈل‚â”rڈoƒKƒX‚ج‘‰ءپA”R—؟‚جکQ”ï“™‚ًڈµ‚«‚©‚ث‚ـ‚¹‚ٌپB—ل‚¦‚خپAƒ^ƒCƒ„‚ج‹َ‹Cˆ³‚ھ•s‘«‚·‚ê‚خˆہ‘Sڈم‚جƒgƒ‰ƒuƒ‹‚ًˆّ‚«‹N‚±‚·‚¨‚»‚ê‚ھ‚ ‚邾‚¯‚إ‚ب‚پA”R”ï‚جˆ«‰»‚ة‚à‚آ‚ب‚ھ‚è‚ـ‚·پBژ©“®ژش‚ًڈي‚ة—اچD‚بڈَ‘ش‚إژg—p‚·‚邽‚ك‚ة‚حپAƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌ‚ھگس”C‚ً‚à‚ء‚ؤڈي“ْچ ‚©‚çژ©“®ژش‚جڈَ‘ش‚ً”cˆ¬‚µپA“Kگط‚ةˆغژ‚·‚邱‚ئ‚ھڈd—v‚إ‚·پB
“_Œںگ®”ُ‚جژہژ{‚ة“–‚½‚èپAƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌ‚حژ©“®ژش‚جژg—pڈَ‹µ(‘–چs‹——£‚∫کHپAگل“¹‚ب‚ا‚جژg—pٹآ‹«)‚âچ\‘¢پE‘•’u‚جژي—ق‚ة‰‚¶‚ؤپAژ©“®ژشƒپپ[ƒJپ[‚ب‚ا‚ھŒِ•\‚µ‚ؤ‚¢‚é“_Œںگ®”ُ‚جڈî•ٌ(ژ©“®ژش‚ة”ُ‚¦•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚¢‚ي‚ن‚éƒپƒ“ƒeƒiƒ“ƒXƒmپ[ƒg‚ب‚ا)‚ًژQچl‚ئ‚µپA•K—v‚ھ‚ ‚ê‚خگê–ه“I‚ب’mژ¯‚ً—L‚·‚é‹Zڈpژز‚ة‘ٹ’k‚·‚é‚ب‚ا‚ة‚و‚èپAٹeپX‚جژ©“®ژش‚ة‚س‚³‚ي‚µ‚¢“Kگط‚ب“_Œںگ®”ُ‚ًژہژ{‚·‚邱‚ئ‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA“_Œںگ®”ُ‚ة”؛‚ء‚ؤ•s—v‚ئ‚ب‚éژg—pچد‚فƒoƒbƒeƒٹپ[پA”pƒ^ƒCƒ„‚ب‚ا‚ج”pٹü•¨‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‚»‚ê‚ç‚جڈˆ—‚ھ‰آ”\‚بژ–‹ئژز‚ةˆث—ٹ‚·‚é‚ب‚ا“Kگ³‚ةڈˆ—‚·‚邱‚ئ‚à•K—v‚إ‚·پB
‚±‚جژèˆّ‚حپAƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌˆêگlˆêگl‚ھژ©“®ژش‚ج“_Œںگ®”ُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج—‰ً‚ًگ[‚كپAژg—p‚·‚éژ©“®ژش‚ة‘خ‚µ‚ؤگس”C‚ً‚à‚ء‚ؤپu“ْڈي“_Œںگ®”ُپv‹y‚رپu’èٹْ“_Œںگ®”ُپv‚ًٹmژہ‚©‚آ“Kگط‚ةژہژ{‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚é‚و‚¤پAˆê”ت“I‚بژ©“®ژش‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚»‚ج•Wڈ€“I‚بژg—p‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚½پu“ْڈي“_Œںپv‹y‚رپu’èٹْ“_Œںپv‚جژہژ{•û–@•ہ‚ر‚ة‚±‚ê‚ç‚ج“_Œں‚ة”؛‚¢•K—v‚ئ‚ب‚éگ®”ُ‚جژہژ{•û–@‚جژwگj‚ًژ¦‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB
چ،گ¢‹I‚ة‚س‚³‚ي‚µ‚¢پAˆہ‘S‚إٹآ‹«•‰‰×‚جڈ¬‚³‚¢ژشژذ‰ï‚ھŒ`گ¬‚³‚ê‚é‚و‚¤پAƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌ‚ھ‚±‚جژèˆّ‚ًگد‹ة“I‚ةٹˆ—p‚³‚êپAژ©“®ژش‚ًˆہ‘S‚©‚آ‰ُ“K‚ةژg—p‚·‚邱‚ئ‚ھٹْ‘ز‚³‚ê‚ـ‚·پB
پi’چپj
- ‚±‚جپuژèˆّپv‚ج’†‚إ—p‚¢‚éپu“ْڈي“_Œںپv‚ئپu’èٹْ“_Œںپv‚ج“à—e‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA•½گ¬19”N4Œژ1“ْ‚©‚çژ{چs‚³‚ê‚é‰üگ³Œم‚جژ©“®ژش“_Œںٹîڈ€(ڈ؛کa26”N‰^—Aڈب—ك‘و70چ†)‚ج’è‚ك‚é‚ئ‚±‚ë‚ة‚و‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
- ‚±‚جپuژèˆّپv‚ج’†‚إ—p‚¢‚éپu‘هŒ^ژشپv‚ئ‚حپAژش—¼‘چڈd—ت8ƒgƒ“ˆبڈم–”‚حڈوژش’èˆُ30گlˆبڈم‚جژ©“®ژش‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB
- ‚±‚جپuژèˆّپv‚ج’†‚إ—p‚¢‚éپuƒŒƒ“ƒ^ƒJپ[پv‚ئ‚حپA“¹کH‰^‘—–@‘و80ڈً‘و‚Pچ€‚ج‹K’è‚ة‚و‚é—Lڈ‘ف“n‚µ‚ج‹–‰آ‚ًژَ‚¯‚½ژ©‰ئ—pژ©“®ژشپi“ٌ—ضژ©“®ژش‚ًڈœ‚پBپj‚ً‚¢‚¢پAپuƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒoƒCƒNپv‚ئ‚حپA“¯چ€‚ة‹K’è‚·‚é—Lڈ‘ف“n‚µ‚ج‹–‰آ‚ًژَ‚¯‚½ژ©‰ئ—pژ©“®ژشپi“ٌ—ضژ©“®ژش‚ةŒہ‚éپBپj‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB
- ‚±‚جپuژèˆّپv‚ج’†‚إ—p‚¢‚éژ©“®ژش‚ج‹و•ھپiپuژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚اپvپAپuژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚اپvپAپuژ–‹ئ—p‚ب‚اپvپj‚جˆس–،‚حژں‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
| ‘خڈغ‚ئ‚ب‚éژه‚بژ©“®ژش | ژ©“®ژش“oک^”شچ†•W–”‚حژش—¼”شچ†•Wپi—لپj | ||
|---|---|---|---|
| •ھ—ق”شچ† | “hگF‚ب‚ا | ||
| ژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚ا | ژ©‰ئ—pڈو—pژ©“®ژش | ‚RپA30پ`39پA300پ`399پA30Aپ`39ZپA3A0پ`3Z9پA3AAپ`3ZZپA‚TپA50پ`59پA500پ`599پA50Aپ`59ZپA5A0پ`5Z9پA5AAپ`5ZZپA‚VپA70پ`79پA700پ`799پA70Aپ`79ZپA7A0پ`7Z9پA7AAپ`7ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑژل‚µ‚‚ح‰©’n‚ةچ••¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF |
| ‰ف•¨‚ج‰^‘—‚ج—p‚ة‹ں‚·‚éژ©‰ئ—p‚جŒںچ¸‘خڈغŒyژ©“®ژش | 40پ`49پA400پ`499پA40Aپ`49ZپA4A0پ`4Z9پA4AAپ`4ZZ | ‰©’n‚ةچ••¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| “ءژي‚ج—p“r‚ة‹ں‚·‚éژ©‰ئ—p‚جŒںچ¸‘خڈغŒyژ©“®ژش | 80پ`89پA800پ`899پA80Aپ`89ZپA8A0پ`8Z9پA8AAپ`8ZZ | ‰©’n‚ةچ••¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| ‰ف•¨Œyژ©“®ژش‰^‘—ژ–‹ئ‚ج—p‚ة‹ں‚·‚éŒںچ¸‘خڈغŒyژ©“®ژش | 40پ`49پA400پ`499پA40Aپ`49ZپA4A0پ`4Z9پA4AAپ`4ZZ | چ•’n‚ة‰©•¶ژڑ | |
| “ٌ—ض‚جڈ¬Œ^ژ©“®ژش | —خ’n‚ة”’•¶ژڑپAکg‚ح”’گF–”‚ح”’’n‚ة—خ•¶ژڑپAکg‚ح—خ’n | ||
| “ٌ—ض‚جŒyژ©“®ژش | —خ’n‚ة”’•¶ژڑ–”‚ح”’’n‚ة—خ•¶ژڑ | ||
| ژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚ا | ژش—¼‘چڈd—ت‚ھ8ƒgƒ“–¢–‚ج‰ف•¨‚ج‰^‘—‚ج—p‚ة‹ں‚·‚éژ©‰ئ—p‚ج•پ’تژ©“®ژش‹yڈ¬Œ^ژ©“®ژش | ‚PپA10پ`19پA100پ`199پA10Aپ`19ZپA1A0پ`1Z9پA1AAپ`1ZZپA‚SپA40پ`49پA400پ`499پA40Aپ`49ZپA4A0پ`4Z9پA4AAپ`4ZZپA‚UپA60پ`69پA600پ`699پA60Aپ`69ZپA6A0پ`6Z9پA6AAپ`6ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF |
| ڈوژش’èˆُ‚ھ10گlˆب‰؛‚جگê‚ç—cژ™‚ج‰^‘—‚ً–ع“I‚ئ‚·‚éژ©‰ئ—p‚ج•پ’تژ©“®ژشپAڈ¬Œ^ژ©“®ژش | ‚RپA30پ`39پA300پ`399پA30Aپ`39ZپA3A0پ`3Z9پA3AAپ`3ZZپA‚TپA50پ`59پA500پ`599پA50Aپ`59ZپA5A0پ`5Z9پA5AAپ`5ZZپA‚VپA70پ`79پA700پ`799پA70Aپ`79ZپA7A0پ`7Z9پA7AAپ`7ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| ڈوژش’èˆُ‚ھ10گlˆب‰؛‚إژش—¼‘چڈd—ت‚ھ8ƒgƒ“–¢–‚ج“ءژي‚ج—p“r‚ة‹ں‚·‚éژ©‰ئ—p‚ج•پ’تژ©“®ژشپAڈ¬Œ^ژ©“®ژش | ‚WپA80پ`89پA800پ`899پA80Aپ`89ZپA8A0پ`8Z9پA8AAپ`8ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| ڈوژش’èˆُ‚ھ10گlˆب‰؛‚إژش—¼‘چڈd—ت‚ھ8ƒgƒ“–¢–‚جژ©‰ئ—p‚ج‘هŒ^“ءژêژ©“®ژش | ‚XپA90پ`99پA900پ`999پA90Aپ`99ZپA9A0پ`9Z9پA9AAپ`9ZZپA‚OپA00پ`09پA000پ`099پA00Aپ`09ZپA0A0پ`0Z9پA0AAپ`0ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| ڈوژش’èˆُ‚ھ10گlˆب‰؛‚جڈو—p‚ج•پ’تژ©“®ژشپAڈ¬Œ^ژ©“®ژش‹y‚رŒںچ¸‘خڈغŒyژ©“®ژش‚إ‚ ‚郌ƒ“ƒ^ƒJپ[ | ‚RپA30پ`39پA300پ`399پA30Aپ`39ZپA3A0پ`3Z9پA3AAپ`3ZZپA‚TپA50پ`59پA500پ`599پA50Aپ`59ZپA5A0پ`5Z9پA5AAپ`5ZZپA‚VپA70پ`79پA700پ`799پA70Aپ`79ZپA7A0پ`7Z9پA7AAپ`7ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑژل‚µ‚‚ح‰©’n‚ةچ••¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF‚إ‚ ‚ء‚ؤپA•½‰¼–¼•¶ژڑ‚ھپu‚êپvپAپu‚يپv‚ج‚à‚ج | |
| ‰ف•¨‚ج‰^‘—‚ج—p‚ة‹ں‚·‚éŒںچ¸‘خڈغŒyژ©“®ژش‚إ‚ ‚郌ƒ“ƒ^ƒJپ[ | 0پ`49پA400پ`499پA40Aپ`49ZپA4A0پ`4Z9پA4AAپ`4ZZ | ‰©’n‚ةچ••¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF‚إ‚ ‚ء‚ؤپA•½‰¼–¼•¶ژڑ‚ھپu‚يپv‚ج‚à‚ج | |
| ڈ¬Œ^ژ©“®ژش‚إ‚ ‚郌ƒ“ƒ^ƒ‹ƒoƒCƒN | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑپAکg‚ح—خ’n‚إ‚ ‚ء‚ؤپA•½‰¼–¼•¶ژڑ‚ھپu‚ëپvپAپu‚يپv‚ج‚à‚ج | ||
| Œyژ©“®ژش‚إ‚ ‚郌ƒ“ƒ^ƒ‹ƒoƒCƒN | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ‚إ‚ ‚ء‚ؤپA•½‰¼–¼•¶ژڑ‚ھپu‚يپv‚ج‚à‚ج | ||
| ژ–‹ئ—p‚ب‚ا | ژ©“®ژش‰^‘—ژ–‹ئ(‰ف•¨Œyژ©“®ژش‰^‘—ژ–‹ئ‚ًڈœ‚پB)‚ج—p‚ة‹ں‚·‚éژ©“®ژش | —خ’n‚ة”’•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| ‰ف•¨‚ج‰^‘—‚ج—p‚ة‹ں‚·‚é•پ’تژ©“®ژش‹y‚رڈ¬Œ^ژ©“®ژش‚إ‚ ‚郌ƒ“ƒ^ƒJپ[ | ‚PپA10پ`19پA100پ`199پA10Aپ`19ZپA1A0پ`1Z9پA1AAپ`1ZZپA‚SپA40پ`49پA400پ`499پA40Aپ`49ZپA4A0پ`4Z9پA4AAپ`4ZZپA‚UپA60پ`69پA600پ`699پA60Aپ`69ZپA6A0پ`6Z9پA6AAپ`6ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF‚إ‚ ‚ء‚ؤپA•½‰¼–¼•¶ژڑ‚ھپu‚êپvپAپu‚يپv‚ج‚à‚ج | |
| ڈوژش’èˆُ‚ھ11گlˆبڈم‚جژ©‰ئ—pژ©“®ژش(‚¢‚ي‚ن‚éژ©‰ئ—p‚جƒoƒX‚ب‚ا) | ‚QپA20پ`29پA200پ`299پA20Aپ`29ZپA2A0پ`2Z9پA2AAپ`2ZZپA‚WپA80پ`89پA800پ`899پA80Aپ`89ZپA8A0پ`8Z9پA8AAپ`8ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
| ڈوژش’èˆُ‚ھ10گlˆب‰؛‚إژش—¼‘چڈd—ت‚ھ8ƒgƒ“ˆبڈم‚جژ©‰ئ—pژ©“®ژش(‚¢‚ي‚ن‚éژ©‰ئ—p‚ج‘هŒ^‰ف•¨ژ©“®ژش‚ب‚ا) | ‚PپA10پ`19پA100پ`199پA10Aپ`19ZپA1A0پ`1Z9پA1AAپ`1ZZپA‚WپA80پ`89پA800پ`899پA80Aپ`89ZپA8A0پ`8Z9پA8AAپ`8ZZپA‚XپA90پ`99پA900پ`999پA90Aپ`99ZپA9A0پ`9Z9پA9AAپ`9ZZپA‚OپA00پ`09پA000پ`099پA00Aپ`09ZپA0A0پ`0Z9پA0AAپ`0ZZ | ”’’n‚ة—خ•¶ژڑ–”‚حچ‘“yŒً’ت‘هگb‚ھ’è‚ك‚é“hگF | |
‚Qپ@“ْڈي“_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@
“ْڈي“_Œں‚حپAƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌ‚ھپA“ْچ ژ©“®ژش‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚’†‚إپAژ©•ھژ©گg‚جگس”C‚ة‚¨‚¢‚ؤچs‚¤“_Œں‚إ‚·پB‚±‚ج“_Œں‚حپAƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌژ©گg‚ھ‰^“]گب‚ة‚·‚ي‚ء‚½‚èپAƒGƒ“ƒWƒ“پEƒ‹پ[ƒ€‚ً‚ج‚¼‚¢‚½‚èپA‚ـ‚½پAژ©“®ژش‚جژü‚è‚ً‰ٌ‚è‚ب‚ھ‚çژ©“®ژش‚جڈَ‘ش‚ً‚ف‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ—eˆص‚ةژہژ{‰آ”\‚ب‚à‚ج‚ً’†گS‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پuژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚جƒ†پ[ƒUپ[‚جٹF‚³‚ٌ‚حپA‘–چs‹——£‚â‰^چsژ‚جڈَ‘ش‚ب‚ا‚©‚ç”»’f‚µ‚½“Kگط‚بژٹْ‚ةپA—ل‚¦‚خپAچsٹy‚â‹Aڈب‚ب‚ا‚جچ‚‘¬“¹کH‚ً—ک—p‚µ‚½’·‹——£‘–چs‚ج‘O‚âپAگôژشپE‹‹–û‚ًچs‚¤‚ئ‚«‚ب‚ا‚ًˆê‚آ‚ج–عˆہ‚ةژہژ{‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚·پB‚ب‚¨پA‘S‚ؤ‚ج“_Œںچ€–ع‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚ؤژہژ{‚·‚é•K—v‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBƒ^ƒCƒ„‚ج“_Œں‚ب‚ا‚ح‹@‰ï‚ ‚邲‚ئ‚ةچs‚¤‚ج‚ھ‚و‚پAژg—pٹْٹش‚ج’·‚¢ƒoƒbƒeƒٹپ[‚ب‚ا‚à’چˆس‚ً•¥‚¤‚ج‚ھ‚و‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB
‚ـ‚½پAپuژ©‰ئ—p‰ف•¨ژش‚ب‚اپv‚ئپuژ–‹ئ—p‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAˆê“ْˆê‰ٌپA‚»‚ج‰^چs‚ج‘O‚ةژہژ{‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚·پBپw‚±‚ê‚ح‘هŒ^ƒgƒ‰ƒbƒN‚âƒoƒXپAƒ^ƒNƒVپ[‚ب‚ا‚جژ©“®ژش‚حپA‘½‚‚جگl‚╨‚ً‰^”ہ‚µپAŒِ‹¤گ«‚ھچ‚‚¢‚±‚ئ‚ب‚ا‚©‚çپA‚و‚èٹmژہ‚ب“_Œں‚ًژہژ{‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‚½‚ك‚ج‚à‚ج‚إ‚·پBپx“ء‚ةˆہ‘Sڈمڈd—v‚ب‘•’u‚إ‚ ‚éƒ^ƒCƒ„پAƒuƒŒپ[ƒL“™‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA‘هŒ^ژش‚ً‘خڈغ‚ئ‚µ‚ؤپA‹@چ\‚ة‰‚¶‚½‚و‚è’ڑ”J‚ب“_Œں‚ً“Kگط‚بژٹْ‚ةژہژ{‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚·پB
‚±‚±‚إ‚حپAˆبڈم‚ج“_‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤ•Wڈ€“I‚ب“_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@‚ة‚آ‚¢‚ؤگà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
| “_Œں‰سڈٹ | “_Œںچ€–ع | “_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@ | ||
|---|---|---|---|---|
| ‰^چs’†‚جˆظڈَ‰سڈٹ | “–ٹY‰سڈٹ‚جˆظڈَ |
|
||
| ‰^“]گب‚إ‚ج“_Œں | ƒuƒŒپ[ƒLپEƒyƒ_ƒ‹ | “¥‚ف‚µ‚ëپAƒuƒŒپ[ƒL‚ج‚«‚« |
|
|
| ’“ژشƒuƒŒپ[ƒLپEƒŒƒoپ[(ƒpپ[ƒLƒ“ƒOپEƒuƒŒپ[ƒLپEƒŒƒoپ[) | ˆّ‚«‚µ‚ë(“¥‚ف‚µ‚ë) |
|
||
| ƒ^ƒCƒ„ | ‹َ‹Cˆ³ |
|
||
| Œ´“®‹@(ƒGƒ“ƒWƒ“) | پ¦‚©‚©‚è‹ïچ‡پAˆظ‰¹ |
|
||
| پ¦’ل‘¬پA‰ء‘¬‚جڈَ‘ش |
|
|||
| ƒEƒBƒ“ƒhپEƒEƒHƒbƒVƒƒ | پ¦•¬ژثڈَ‘ش |
|
||
| ƒڈƒCƒpپ[ | پ¦گ@(‚س)‚«ژو‚è‚جڈَ‘ش |
|
||
| پ‹َ‹Cˆ³—حŒv | ‹َ‹Cˆ³—ح‚جڈم‚ھ‚è‹ïچ‡ |
|
||
| پƒuƒŒپ[ƒLپEƒoƒ‹ƒu | ”r‹C‰¹ |
|
||
| ƒGƒ“ƒWƒ“پEƒ‹پ[ƒ€‚ج“_Œں | ƒEƒBƒ“ƒhپEƒEƒHƒbƒVƒƒپEƒ^ƒ“ƒN | پ¦‰t—ت |
|
|
| ƒuƒŒپ[ƒL‚جƒٹƒUپ[ƒoپEƒ^ƒ“ƒN | ‰t—ت |
|
||
| ƒoƒbƒeƒٹ | پ¦‰t—ت |
|
||
| ƒ‰ƒWƒGپ[ƒ^‚ب‚ا‚ج—â‹p‘•’u | پ¦گ…—ت |
|
||
| ڈپٹٹ‘•’u | پ¦ƒGƒ“ƒWƒ“پEƒIƒCƒ‹‚ج—ت |
|
||
| پ¢ƒtƒ@ƒ“پEƒxƒ‹ƒg | پ¦’£‚è‹ïچ‡پA‘¹ڈ |
|
||
| ژش‚جژü‚è‚©‚ç‚ج“_Œں | “”‰خ‘•’uپA•ûŒüژwژ¦ٹي | “_“”پE“_–إ‹ïچ‡پA‰ک‚êپA‘¹ڈ |
|
|
| ƒ^ƒCƒ„ | ‹َ‹Cˆ³ |
|
||
| پ ژو•t‚¯‚جڈَ‘ش |
|
|||
| ‹T(‚«)—ôپA‘¹ڈ |
|
|||
| ˆظڈَ‚ب–€–ص |
|
|||
| پ¦چa‚جگ[‚³ |
|
|||
| پƒGƒAپEƒ^ƒ“ƒN | ƒ^ƒ“ƒN“à‚ج‹أگ… |
|
||
| پپiƒuƒŒپ[ƒLپEƒyƒ_ƒ‹پj | پ¦پi“¥‚ف‚µ‚ëپAƒuƒŒپ[ƒL‚ج‚«‚«پj |
|
||
پi’چپj
- پ¦ˆَ‚ج“_Œںچ€–ع‚حپAپuژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚اپvپAپuژ–‹ئ—p‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚àپAژ©“®ژش‚ج‘–چs‹——£‚â‰^چsژ‚جڈَ‘ش‚ب‚ا‚©‚ç”»’f‚µ‚½“Kگط‚بژٹْ‚ةچs‚¦‚خ‚و‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB
- پˆَ‚ج“_Œں‰سڈٹ‚حپAƒGƒAپEƒuƒŒپ[ƒL‚ھ‘•’…‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚ة“_Œں‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
- پ¢ˆَ‚ج“_Œں‰سڈٹ‚حپAپuژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حپA’èٹْ“_Œں‚جچغ‚ةژہژ{‚·‚é‚ب‚ا‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
- پ ˆَ‚ج“_Œںچ€–ع‚حپAپu‘هŒ^ژشپv‚جڈêچ‡‚ة“_Œں‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
‚Rپ@’èٹْ“_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@
’èٹْ“_Œں‚حپAˆê”ت“I‚بچ\‘¢پE‘•’u‚جژ©“®ژش‚ةٹض‚µ•Wڈ€“I‚بژg—p‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤپA’èٹْ“I‚ةچs‚¤•K—v‚ج‚ ‚é“_Œں‚ً’è‚ك‚½‚à‚ج‚إ‚·پBپuژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚ة‚حپA‚P”N“_Œں‚ئ‚Q”N“_Œں‚ج‚Qژي—ق‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBپuژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚ة‚حپA‚UŒژ“_Œں‚ئ‚P‚QŒژ“_Œں‚ج‚Qژي—ق‚ھپA‚ـ‚½پAپuژ–‹ئ—p‚ب‚اپv‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éژ©“®ژش‚ة‚حپA‚RŒژ“_Œں‚ئ‚P‚QŒژ“_Œں‚ج‚Qژي—ق‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚±‚إ‚حپA•Wڈ€“I‚ب“_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@‚ًگà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚ب‚¨پA“ءژي‚بچ\‘¢پE‘•’u‚جژ©“®ژش‚âپA‘–چs‹——£‚ھ‘½‚¢‚ب‚اژg—p‚جڈَ‹µ‚ھŒµ‚µ‚¢ڈêچ‡پi‚¢‚ي‚ن‚éƒVƒrƒAƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“پj‚ة‚حپA•\‚ةژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢“_Œںپiƒپپ[ƒJپ[‚ب‚ا‚ھ”چs‚·‚é“_Œںگ®”ُ‚جڈî•ٌ‚ًژQچl‚ئ‚µ‚ؤچs‚¤“_Œںپj‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB
“_Œں‚جچغ‚ةپA“ء‚ة’چˆس‚ً—v‚·‚éژ–چ€‚حپAژں‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
- ˆہ‘S‚بڈêڈٹ‚ً‘I‚شپB
- ƒ†پ[ƒUپ[ژ©گg‚ھ’èٹْ“_Œں‚ج‚¤‚؟‚جˆê’è•”•ھ‚ًچs‚¨‚¤‚ئ‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپA’mژ¯پA‹Z—ت‚ةŒ©چ‡‚ء‚½‚à‚ج‚ًچs‚¤پB
- “Kگط‚ب‹@ٹBپEچH‹ï‚â‘ھ’èٹي‹ï‚ًژg—p‚·‚éپB
- ژ©“®ژش‚ًƒٹƒtƒgپEƒAƒbƒv‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپA“Kگط‚بƒWƒƒƒbƒLپAƒXƒ^ƒ“ƒhپAƒٹƒtƒg‚ب‚ا‚ًژg—p‚µ‚ؤˆہ‘S‚ة“_Œں‚ًچs‚¤پBپiژ©“®ژش‚ة”ُ•t‚¯‚جٹبˆص‚بƒWƒƒƒbƒL‚حپAƒ^ƒCƒ„Œًٹ·ژ‚ةژg—p‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پBپj
’چˆس
- •\’†پuژہژ{•û–@پv—“‚إ—p‚¢‚ؤ‚¢‚é—pŒê‚ب‚ا‚جˆس–،‚حپAژں‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
- پuژl—ضژ©“®ژش‚ب‚اپv‚ج•\’†پu“_Œںژٹْپv—“‚إپAپu‹——£پv‚ئ•t‚µ‚½“_Œںچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘O‰ٌ‚»‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤ’èٹْ“_Œں‚ً‚µ‚½‚ئ‚«‚©‚ç‚ج‘–چs‹——£‚ھپAپuژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚اپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح”Nٹش“–‚½‚è5,000kmپi2”N“_Œں‚ج‘خڈغ‚جڈêچ‡‚ح2”Nٹش‚إ10,000kmپj‚ة–‚½‚ب‚¢ڈêچ‡پAپuژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚اپv‚ئپuژ–‹ئ—p‚ب‚اپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح3Œژ“–‚½‚è2,000kmپAپi“_Œںچ€–ع‚ھ6Œژ“_Œں‚ج‘خڈغ‚جڈêچ‡‚ح6Œژ‚إ4,000kmپA12Œژ“_Œں‚ج‘خڈغ‚جڈêچ‡‚ح”Nٹش‚إ8,000kmپj‚ة–‚½‚ب‚¢ڈêچ‡‚ة‚حڈب—ھ‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپA2‰ٌکA‘±‚µ‚ؤڈب—ھ‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB
- پu“ٌ—ضژ©“®ژشپv‚ج•\’†پu“_Œںژٹْپv—“‚إپAپu‹——£پv‚ئ•t‚µ‚½“_Œںچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘O‰ٌ‚»‚جچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤ’èٹْ“_Œں‚ً‚µ‚½ژ‚©‚ç‚ج‘–چs‹——£‚ھپA”Nٹش“–‚½‚è1,500km‚ة–‚½‚ب‚¢ڈêچ‡‚ة‚حڈب—ھ‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپA2‰ٌکA‘±‚µ‚ؤڈب—ھ‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB
- پuژl—ضژ©“®ژش‚ب‚اپv‚ج•\’†پu“_Œںچ€–عپv—“‚إپAپ¦ˆَ‚ً•t‚µ‚½“_Œںچ€–ع‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒoƒXپAƒ^ƒNƒVپ[پAڈو—p‚جƒŒƒ“ƒ^ƒJپ[‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤچs‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
| پuƒٹƒtƒgپEƒAƒbƒv‚ب‚ا‚جڈَ‘ش‚إپv | ƒWƒƒƒbƒLپEƒAƒbƒv‚µƒXƒ^ƒ“ƒh‚إ•غژ‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپA–”‚حƒٹƒtƒg‚âƒsƒbƒg‚ا‚ًژg—p‚µ‚ؤپAژ©“®ژش‚ج‰؛•”‚ً“_Œں‚µ‚â‚·‚¢ڈَ‘ش‚ة‚·‚邱‚ئ‚ً‚¢‚ـ‚·پB |
| پuƒXƒpƒi‚ب‚ا‚ة‚و‚è“_Œں‚·‚éپv | ƒXƒpƒiپAƒŒƒ“ƒ`پAŒںƒnƒ“ƒ}‚ب‚ا‚جچH‹ï‚ًژg—p‚µ‚ؤ“_Œں‚·‚邱‚ئ‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB |
| پuƒXƒPپ[ƒ‹‚ب‚ا‚ة‚و‚è“_Œں‚·‚éپv | ƒXƒPپ[ƒ‹پAƒmƒMƒXپAƒ_ƒCƒ„ƒ‹پEƒQپ[ƒW‚ب‚ا‚ج‘ھ’èٹي‚ة‚و‚èپA‘ھ’èپE“_‚·‚邱‚ئ‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB |
| پu‹K’èپEپEپEپv | ژ©“®ژشگ»چىژز‚ج’è‚ك‚é•û–@پA”حˆح–”‚ح’l‚ب‚ا‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB |
| پuپƒپ@پ@پ@پ„پv | “_Œں‚ج‘خڈغ‚ئ‚ب‚éچ\‘¢پE‘•’u‚ب‚ا‚ًژ¦‚µ‚ـ‚·پB |
’èٹْ“_Œں‚جژہژ{•û–@
پi1پjژl—ضژ©“®ژش‚ب‚ا
| “_Œں‰سڈٹ | “_Œںچ€–ع | “_Œںژٹْ پi”N–”‚حŒژ‚²‚ئپj |
“_Œں‚جژہژ{•û–@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚ا | ژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚ا | ‘هŒ^“ءژê | ژ–‹ئ—p‚ب‚ا | ”يŒ،ˆّژ©“®ژش | ||||
| ‚©‚¶ژو‚è‘•’uپiƒXƒeƒAƒٹƒ“ƒOپj | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ‘€چى‹ïچ‡ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|
| ƒMƒ„پEƒ{ƒbƒNƒX | ƒIƒCƒ‹کR‚ê | 12Œژ |
|
|||||
| ژو•t‚¯‚جٹة‚ف | 2”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒچƒbƒhپAƒAپ[ƒ€—ق(ƒXƒeƒAƒٹƒ“ƒOپEƒٹƒ“ƒPپ[ƒW) | ٹة‚فپA‚ھ‚½پA‘¹ڈ | 2”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ |
|
||
| ƒ{پ[ƒ‹پEƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg‚جƒ_ƒXƒgپEƒuپ[ƒc‚ج‹T(‚«)—ô‚ئ‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒiƒbƒNƒ‹ | کAŒ‹•”‚ج‚ھ‚½ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ |
|
|||
| ‚©‚¶ژو‚èژش—ض | ƒzƒCپ[ƒ‹پEƒAƒ‰ƒCƒپƒ“ƒg | 2”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒpƒڈپ[ƒXƒeƒAƒٹƒ“ƒO‘•’u | ƒxƒ‹ƒg‚جٹة‚ف‚ئ‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
||
| ƒIƒCƒ‹کR‚êپAƒIƒCƒ‹—ت | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ |
|
|||
| ژو•t‚¯‚جٹة‚ف | 2”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| گ§“®‘•’uپiƒuƒŒپ[ƒLپj | ƒuƒŒپ[ƒLپE‚طƒ_ƒ‹ | —V‚رپA“¥‚فچ‚ٌ‚¾‚ئ‚«‚جڈ°”آ‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 1”N | 6Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
|
| ƒuƒŒپ[ƒL‚جŒّ‚«‹ïچ‡ | 1”N | 6Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
||
| ’“ژشƒuƒŒپ[ƒL‹@چ\ | ˆّ‚«‚µ‚ë(“¥‚ف‚µ‚ë) | 1”N | 6Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|
| ƒuƒŒپ[ƒL‚جŒّ‚«‹ïچ‡ | 1”N | 6Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
||
| ƒzپ[ƒX‹y‚رƒpƒCƒv | کR‚êپA‘¹ڈ‹y‚رژو•tڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|
| ƒٹƒUپ[ƒoپEƒ^ƒ“ƒN | ƒuƒŒپ[ƒL‰t‚ج—ت | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
|||
| ƒ}ƒXƒ^پEƒVƒٹƒ“ƒ_پAƒzƒCپ[ƒ‹پEƒVƒٹƒ“ƒ_پAƒfƒBƒXƒNپEƒLƒƒƒٹƒp | ‰tکR‚ê | 1”N |
|
|||||
| ‹@”\پA–€–صپA‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | (–€–صپA‘¹ڈ‚ج“_Œں)
|
|||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒ`ƒƒƒ“ƒo | ƒچƒbƒh‚جƒXƒgƒچپ[ƒN | 3Œژ | 3Œژ |
|
||||
| ‹@”\ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒoƒ‹ƒuپAƒNƒCƒbƒNپEƒŒƒٹپ[ƒYپEƒoƒ‹ƒuپAƒٹƒŒپ[پEƒoƒ‹ƒu | ‹@”\ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒٹƒŒپ[پEƒGƒ}پ[ƒWƒFƒ“ƒVپEƒoƒ‹ƒu | ‹@”\ | 12Œژ |
|
|||||
| ”{—ح‘•’u(ƒuƒŒپ[ƒLپEƒuپ[ƒXƒ^) | ƒGƒAپEƒNƒٹپ[ƒi‚ج‹l‚ـ‚è | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ‹@”\ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | پƒگ^‹َ–”‚ح‹َ‹C”{—حژ®پ„
|
||||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒJƒ€ | –€–ص | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒhƒ‰ƒ€پAƒuƒŒپ[ƒLپEƒVƒ…پ[ | ƒhƒ‰ƒ€‚ئƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 1”N‹——£ | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ | 3Œژ | پƒژ©“®’²گ®•ûژ®پ„
|
|
| ƒVƒ…پ[‚جگ (‚µ‚م‚¤)“®•”•ھ‹y‚رƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‚ج–€–ص | 1”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
||
| ƒhƒ‰ƒ€‚ج–€–ص‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||
| ƒoƒbƒNپEƒvƒŒپ[ƒg | ƒoƒbƒNپEƒvƒŒپ[ƒg‚جڈَ‘ش | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒfƒBƒXƒN‹y‚رƒpƒbƒh | ƒfƒBƒXƒN‚ئƒpƒbƒh‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 1”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
|
| ƒpƒbƒh‚ج–€–ص | 1”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
||
| ƒfƒBƒXƒN‚ج–€–ص‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||
| ƒZƒ“ƒ^پEƒuƒŒپ[ƒLپEƒhƒ‰ƒ€پAƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | ƒhƒ‰ƒ€‚جژو•t‚¯‚جٹة‚ف | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
|||
| ƒhƒ‰ƒ€‚ئƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
||||
| ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‚ج–€–ص | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒhƒ‰ƒ€‚ج–€–ص‚ئ‘¹ڈ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| “ٌڈdˆہ‘SƒuƒŒپ[ƒL‹@چ\ | ‹@”\ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | پƒ–ûˆ³ژ®“ٌڈdˆہ‘SƒuƒŒپ[ƒL‹@چ\(ƒZƒtƒeƒBپEƒVƒٹƒ“ƒ_ژ®)پ„
|
|||
| ‘–چs‘•’u | ƒzƒCپ[ƒ‹ | ƒ^ƒCƒ„‚جڈَ‘ش | 1”N‹——£ | 12Œژ‹——£ | 12Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
| ƒzƒCپ[ƒ‹پEƒiƒbƒg‹y‚رƒzƒCپ[ƒ‹پEƒ{ƒ‹ƒg‚جٹة‚ف | 1”N‹——£ | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
||
| ƒzƒCپ[ƒ‹پEƒiƒbƒg‹y‚رƒzƒCپ[ƒ‹پEƒ{ƒ‹ƒg‚ج‘¹ڈپi‘هŒ^ژش‚ة‚¨‚¢‚ؤچs‚¤“_Œںپj | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||||
| ƒٹƒ€پAƒTƒCƒhپEƒٹƒ“ƒO‹y‚رƒfƒBƒXƒNپEƒzƒCپ[ƒ‹‚ج‘¹ڈ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||||
| ƒtƒچƒ“ƒgپEƒzƒCپ[ƒ‹پEƒxƒAƒٹƒ“ƒO‚ج‚ھ‚½ | 2”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ‹——£ |
|
|||
| ƒٹƒ„پEƒzƒCپ[ƒ‹پEƒxƒAƒٹƒ“ƒO‚ج‚ھ‚½ | 2”N‹——£ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒzƒCپ[ƒ‹پEƒxƒAƒٹƒ“ƒO‚ج‚ھ‚½ | 12Œژ |
|
||||||
| ٹةڈص‘•’u | ƒٹپ[ƒtپEƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒXƒvƒٹƒ“ƒO‚ج‘¹ڈ | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|
| ژو•t•”‹y‚رکAŒ‹•”‚جٹة‚فپA‚ھ‚½‹y‚ر‘¹ڈ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒRƒCƒ‹پEƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“(ƒgپ[ƒVƒ‡ƒ“پEƒoپ[‚ًٹـ‚قپB) | ƒXƒvƒٹƒ“ƒO‚ج‘¹ڈ | 12Œژ |
|
|||||
| ژو•t•”پAکAŒ‹•”‚جٹة‚فپA‚ھ‚½پA‘¹ڈ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚جژو•t•”‚ئکAŒ‹•” | ٹة‚فپA‚ھ‚½پA‘¹ڈ | 2”N |
|
|||||
| ƒGƒAپEƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ƒGƒAکR‚ê | 3Œژ | 3Œژ |
|
||||
| ƒxƒچپ[ƒY‚ج‘¹ڈ | 3Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
|||||
| ژو•t•”‹y‚رکAŒ‹•”‚جٹة‚ف•ہ‚ر‚ة‘¹ڈ | 3Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
|||||
| ƒŒƒxƒٹƒ“ƒOپEƒoƒ‹ƒu‚ج‹@”\ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||||
| ƒVƒ‡ƒbƒNپEƒAƒuƒ\پ[ƒo | –ûکR‚ê‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|
| “®—ح“`’B | ƒNƒ‰ƒbƒ` | ƒyƒ_ƒ‹‚ج—V‚رپAگط‚ꂽ‚ئ‚«‚جڈ°”آ‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
|
| چى—p | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
||||
| ‰t—ت | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
||||
| ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒgƒ‰ƒ“ƒXƒtƒ@پ[ | ƒIƒCƒ‹کR‚êپAƒIƒCƒ‹—ت | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ | 6Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ | (ƒIƒCƒ‹کR‚ê‚ج“_Œں) پƒMپ^Tژشپ„
پƒMپ^Tژشپ„
|
||
| ƒvƒچƒyƒ‰پEƒVƒƒƒtƒgپAƒhƒ‰ƒCƒuپEƒVƒƒƒtƒg | کAŒ‹•”‚جٹة‚ف | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ | 6Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
||
| ژ©چفŒpژè•”(ƒ†ƒjƒoپ[ƒTƒ‹پEƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg)‚جƒ_ƒXƒgپEƒuپ[ƒc‚ج‹T(‚«)—ô‚ئ‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| Œpژè•”‚ج‚ھ‚½ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒZƒ“ƒ^پEƒxƒAƒٹƒ“ƒO‚ج‚ھ‚½ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒfƒtƒ@ƒŒƒ“ƒVƒƒƒ‹ | ƒIƒCƒ‹کR‚êپAƒIƒCƒ‹—ت | 2”N‹——£ | 6Œژ‹——£ | 6Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
||
| “d‹C‘•’u | “_‰خ‘•’u | “_‰خƒvƒ‰ƒOپiƒXƒpپ[ƒNپEƒvƒ‰ƒOپj‚جڈَ‘ش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ | 6Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
|
| “_‰خژٹْ | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
|||
| ƒfƒBƒXƒgƒٹƒrƒ…پ[ƒ^‚جƒLƒƒƒbƒv‚جڈَ‘ش | 1”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒoƒbƒeƒٹ | ƒ^پ[ƒ~ƒiƒ‹•”‚جگع‘±ڈَ‘ش | 1”N | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
||
| “d‹C”zگü | گع‘±•”‚جٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|
| Œ´“®‹@پiƒGƒ“ƒWƒ“پj | –{‘ج | ’ل‘¬‚ئ‰ء‘¬‚جڈَ‘ش | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
||
| ”r‹C‚جڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ | پƒƒKƒ\ƒٹƒ“ژشپALPGژشپ„
|
|||
| ƒGƒAپEƒNƒٹپ[ƒiپEƒGƒŒƒپƒ“ƒg‚جڈَ‘ش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ | 6Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
|||
| ƒGƒAپEƒNƒٹپ[ƒi‚ج–û‚ج‰ک‚ê‚ئ—ت | 6Œژ |
|
||||||
| ƒVƒٹƒ“ƒ_پEƒwƒbƒh‚ئƒ}ƒjƒzپ[ƒ‹ƒhٹe•”‚ج’÷•tڈَ‘ش | 12Œژ |
|
||||||
| ڈپٹٹ‘•’u | ƒIƒCƒ‹کR‚ê | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
||
| ”R—؟‘•’u | ”R—؟کR‚ê | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ |
|
||
| —â‹p‘•’u | ƒtƒ@ƒ“پEƒxƒ‹ƒg‚جٹة‚ف‚ئ‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
||
| گ…کR‚ê | 1”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ‚خ‚¢‰ŒپAˆ«ڈL‚ج‚ ‚éƒKƒXپA—LٹQ‚بƒKƒX“™‚ج”ژU–hژ~‘•’u | ƒuƒچپ[ƒoƒCپEƒKƒXٹزŒ³‘•’u | ƒپƒ^پ[ƒٹƒ“ƒOپEƒoƒ‹ƒu‚جڈَ‘ش | 2”N | 12Œژ | 12Œژ |
|
||
| ”zٹا‚ج‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ”R—؟ڈِ”ƒKƒX”rڈo—}ژ~‘•’u | ”zٹا“™‚ج‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒ`ƒƒƒRپ[ƒ‹پEƒLƒƒƒjƒXƒ^‚ج‹l‚ـ‚è‚ئ‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒ`ƒFƒbƒNپEƒoƒ‹ƒu‚ج‹@”\ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ˆêژ_‰»’Y‘f“™”ژU–hژ~‘•’u | گG”}”½‰•ûژ®“™”rڈoƒKƒXŒ¸ڈ‘•’u‚جژو•t‚¯‚جٹة‚ف‚ئ‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||
| “ٌژں‹َ‹C‹ں‹‹‘•’u‚ج‹@”\ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ”r‹CƒKƒXچؤڈzٹآ‘•’u‚ج‹@”\ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| Œ¸‘¬ژ”r‹CƒKƒXŒ¸ڈ‘•’u‚ج‹@”\ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ”zٹا‚ج‘¹ڈ‚ئژو•tڈَ‘ش | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| Œx‰¹ٹي(ƒzپ[ƒ“)پA‘‹گ@(‚س‚«)ٹي(ƒڈƒCƒpپ[)پAگôڈٍ‰t•¬ژث‘•’u(ƒEƒBƒ“ƒhپEƒEƒHƒbƒVƒƒ)پAƒfƒtƒچƒXƒ^پAژ{ڈù‘•’u(ƒXƒeƒAƒٹƒ“ƒOپEƒچƒbƒN) | چى—p | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | (ƒzپ[ƒ“‚ج“_Œں)
|
|||
| ƒGƒOƒ]پ[ƒXƒgپEƒpƒCƒv‚ئƒ}ƒtƒ‰ | ژو•t‚¯‚جٹة‚ف‚ئ‘¹ڈ | 1”N‹——£ | 12Œژ‹——£ | 12Œژ‹——£ | 3Œژ‹——£ |
|
||
| ƒ}ƒtƒ‰‚ج‹@”\ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
|||
| ƒGƒAپEƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ƒGƒAپEƒ^ƒ“ƒN‚ج‹أگ… | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
||
| ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒTپAƒvƒŒƒbƒVƒƒپEƒŒƒMƒ…ƒŒپ[ƒ^‚ئƒAƒ“ƒچپ[ƒ_پEƒoƒ‹ƒu‚ج‹@”\ | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | (ƒGƒAپEƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚ج“_Œں)
|
||||
| چ‚ˆ³ƒKƒX‚ً”R—؟‚ئ‚·‚é”R—؟‘•’u“™ | “±ٹاپAŒpژè•”‚جƒKƒXکR‚ê‹y‚ر‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ |
|
||
| ƒKƒX—eٹيژو•t•”‚جٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ |
|
ƒKƒX—eٹي‹y‚رƒKƒX—eٹي•چ‘®•i‚ج‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ | 3Œژ |
|
| ژشکg(ƒtƒŒپ[ƒ€)پAژش‘ج(ƒ{ƒfƒBپ[) | ”ٌڈيŒû‚ج”à‚ج‹@”\ | 3Œژ |
|
|||||
| ٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 12Œژ | 12Œژ | 3Œژ | 3Œژ | پƒڈو—pژش‚ب‚اپ„
|
||
| ƒXƒyƒAƒ^ƒCƒ„ژو•t‘•’u‚جٹة‚فپA‚ھ‚½‹y‚ر‘¹ڈ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|||||
| ƒXƒyƒAƒ^ƒCƒ„‚جژو•tڈَ‘ش | 3Œژ | 3Œژ |
|
|||||
| ƒcپ[ƒ‹ƒ{ƒbƒNƒX‚جژو•t•”‚جٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 3Œژ | 3Œژ |
|
|||||
| کAŒ‹‘•’u | ƒJƒvƒ‰‚ج‹@”\‹y‚ر‘¹ڈ | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ƒLƒ“ƒOپEƒsƒ“‹y‚رƒ‹ƒlƒbƒgپEƒAƒC‚ج–€–صپA‹T(‚«)—ô‹y‚ر‘¹ڈ | 12Œژ |
|
||||||
| ƒsƒ“ƒgƒ‹پEƒtƒbƒN‚ج–€–صپA‹T(‚«)—ô‹y‚ر‘¹ڈ | 12Œژ |
|
||||||
| چہگب | پ¦چہگبƒxƒ‹ƒg(ƒVپ[ƒgپEƒxƒ‹ƒg)‚جڈَ‘ش | 12Œژ | 12Œژ |
|
||||
| ٹJ”à”ژش–hژ~‘•’u | ‹@”\ | 12Œژ |
|
|||||
| ‚»‚ج‘¼ | ƒVƒƒƒVٹe•”‚ج‹‹–ûژ‰ڈَ‘ش | 6Œژ | 6Œژ | 3Œژ | 3Œژ |
|
||
| ژشچعژ®Œجڈلگf’f‘•’u‚جگf’f‚جŒ‹‰ت | 12Œژ | 12Œژ | 12Œژ | پƒƒXƒLƒƒƒ“ƒcپ[ƒ‹‚ً—p‚¢‚éڈêچ‡پ„
|
||||
پi2پj“ٌ—ضژ©“®ژش
| “_Œں‰سڈٹ | “_Œںچ€–ع | “_Œںژٹْ پi”N–”‚حŒژ‚²‚ئپj |
“_Œں‚جژہژ{•û–@ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ژ©‰ئ—pڈو—p‚ب‚ا | ژ©‰ئ—p‰ف•¨‚ب‚ا | ||||
| ‚©‚¶ژو‚è‘•’uپiƒnƒ“ƒhƒ‹پAƒtƒچƒ“ƒgپEƒtƒHپ[ƒNپj | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ‘€چى‹ïچ‡ | 2”N | 1”N |
|
| ƒtƒچƒ“ƒgپEƒtƒHپ[ƒN | ‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
|
| ƒXƒeƒAƒٹƒ“ƒOپEƒXƒeƒ€‚جژو•tڈَ‘ش | 2”N | 1”N |
|
||
| ƒXƒeƒAƒٹƒ“ƒOپEƒXƒeƒ€‚جژ²ژَ•”‚ج‚ھ‚½ | 1”N | 6Œژ |
|
||
| گ§“®‘•’uپiƒuƒŒپ[ƒLپj | ƒuƒŒپ[ƒLپEƒyƒ_ƒ‹‹y‚رƒuƒŒپ[ƒLپEƒŒƒoپ[ | —V‚ر | 1”N | 6Œژ |
|
| ƒuƒŒپ[ƒL‚جŒّ‚«‹ïچ‡ | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒچƒbƒh‹y‚رƒPپ[ƒuƒ‹—ق | ٹة‚فپA‚ھ‚½‹y‚ر‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ƒzپ[ƒX‹y‚رƒpƒCƒv | کR‚êپA‘¹ڈ‹y‚رژو•tڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ƒ}ƒXƒ^پEƒVƒٹƒ“ƒ_پAƒzƒCپ[ƒ‹پEƒVƒٹƒ“ƒ_‹y‚رƒfƒBƒXƒNپEƒLƒƒƒٹƒp | ‹@”\پA–€–ص‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
|
| ‰tکR‚ê | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒhƒ‰ƒ€‹y‚رƒuƒŒپ[ƒLپEƒVƒ…پ[ | ƒhƒ‰ƒ€‚ئƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
|
| ƒVƒ…پ[‚جگ (‚µ‚م‚¤)“®•”•ھ‹y‚رƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO‚ج–€–ص | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
||
| ƒhƒ‰ƒ€‚ج–€–ص‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
||
| ƒuƒŒپ[ƒLپEƒfƒBƒXƒN‹y‚رƒpƒbƒh | ƒfƒBƒXƒN‚ئƒpƒbƒh‚ئ‚ج‚·‚«ٹش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
|
| ƒpƒbƒh‚ج–€–ص | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
||
| ƒfƒBƒXƒN‚ج–€–ص‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
||
| ‘–چs‘•’u | ƒzƒCپ[ƒ‹ | ƒ^ƒCƒ„‚جڈَ‘ش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
| ƒzƒCپ[ƒ‹پEƒiƒbƒg‹y‚رƒzƒCپ[ƒ‹پEƒ{ƒ‹ƒg‚جٹة‚ف | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒtƒچƒ“ƒgپEƒzƒCپ[ƒ‹پEƒxƒAƒٹƒ“ƒO‚ج‚ھ‚½ | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
||
| ƒٹƒ„پEƒzƒCپ[ƒ‹پEƒxƒAƒٹƒ“ƒO‚ج‚ھ‚½ | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
||
| ٹةڈص‘•’u | ƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“پEƒAپ[ƒ€پiƒXƒCƒ“ƒOپEƒAپ[ƒ€پj | کAŒ‹•”‚ج‚ھ‚½‹y‚رƒAپ[ƒ€‚ج‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
| ƒVƒ‡ƒbƒNپEƒAƒuƒ\پ[ƒo | –ûکR‚ê‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
|
| “®—ح“`’B‘•’u | ƒNƒ‰ƒbƒ` | ƒNƒ‰ƒbƒ`پEƒŒƒoپ[‚ج—V‚ر | 1”N | 6Œژ |
|
| چى—p | 2”N | 1”N |
|
||
| ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ | –ûکR‚ê‹y‚ر–û—ت | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
|
| ƒvƒچƒyƒ‰پEƒVƒƒƒtƒg‹y‚رƒhƒ‰ƒCƒuپEƒVƒƒƒtƒg | Œpژè•”‚ج‚ھ‚½ | 2”N | 1”N |
|
|
| ƒ`ƒFپ[ƒ“‹y‚رƒXƒvƒچƒPƒbƒg | ƒ`ƒFپ[ƒ“‚جٹة‚ف | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ƒXƒvƒچƒPƒbƒg‚جژو•tڈَ‘ش‹y‚ر–€–ص | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒhƒ‰ƒCƒuپEƒxƒ‹ƒg | –€–ص‹y‚ر‘¹ڈ | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
|
| “d‹C‘•’u | “_‰خ‘•’u | “_‰خƒvƒ‰ƒOپiƒXƒpپ[ƒNپEƒvƒ‰ƒOپj‚جڈَ‘ش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
| “_‰خژٹْ | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒoƒbƒeƒٹ | ƒ^پ[ƒ~ƒiƒ‹•”‚جگع‘±ڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
|
| “d‹C”zگü | گع‘±•”‚جٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
|
| Œ´“®‹@پiƒGƒ“ƒWƒ“پj | –{‘ج | ’ل‘¬‹y‚ر‰ء‘¬‚جڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
| ”r‹C‚جڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒGƒAپEƒNƒٹپ[ƒiپEƒGƒŒƒپƒ“ƒg‚جڈَ‘ش | 1”N‹——£ | 6Œژ‹——£ |
|
||
| ڈپٹٹ‘•’u | –ûکR‚ê | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ”R—؟‘•’u | ”R—؟کR‚ê | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ƒٹƒ“ƒN‹@چ\‚جڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒXƒچƒbƒgƒ‹پEƒoƒ‹ƒu‹y‚رƒ`ƒ‡پ[ƒNپEƒoƒ‹ƒu‚جچى“®ڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
||
| —â‹p‘•’u | گ…کR‚ê | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ‚خ‚¢‰ŒپAˆ«ڈL‚ج‚ ‚éƒKƒXپA—LٹQ‚بƒKƒX“™‚ج”ژU–hژ~‘•’u | ƒuƒچپ[ƒoƒCپEƒKƒXٹزŒ³‘•’u | ”zٹا‚ج‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
| ˆêژ_‰»’Y‘f“™”ژU–hژ~‘•’u | “ٌژں‹َ‹C‹ں‹‹‘•’u‚ج‹@”\ | 2”N | 1”N |
|
|
| ”zٹا‚ج‘¹ڈ‹y‚رژو•tڈَ‘ش | 2”N | 1”N |
|
||
| ƒGƒOƒ]پ[ƒXƒgپEƒpƒCƒv‹y‚رƒ}ƒtƒ‰ | ژو•t‚¯‚جٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ƒ}ƒtƒ‰‚ج‹@”\ | 2”N | 1”N |
|
||
| چ‚ˆ³ƒKƒX‚ً”R—؟‚ئ‚·‚é”R—؟‘•’u“™ | “±ٹاپAŒpژè•”‚جƒKƒXکR‚ê‹y‚ر‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ƒKƒX—eٹيژو•t•”‚جٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 2”N | 1”N |
|
||
| ƒKƒX—eٹي‹y‚رƒKƒX—eٹي•چ‘®•i‚ج‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ |
|
||
| ƒtƒŒپ[ƒ€ | ٹة‚ف‹y‚ر‘¹ڈ | 1”N | 6Œژ |
|
|
| ‚»‚ج‘¼ | ƒVƒƒƒVٹe•”‚ج‹‹–ûژ‰ڈَ‘ش | 1”N | 6Œژ |
|
|
‚Sپ@گ®”ُ‚جژہژ{‚ج•û–@
‚±‚±‚إ‚حپAپu‚Qپ@“ْڈي“_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@پv‚âپu‚Rپ@’èٹْ“_Œں‚جژہژ{‚ج•û–@پv‚ةٹî‚أ‚«“_Œں‚ًچs‚ء‚½Œ‹‰ت–”‚ح“_Œں‚ًچs‚ي‚ب‚‚ئ‚àژg—pڈَ‹µ“™‚ة‚و‚ء‚ؤپAگ´‘|پA’²گ®پAŒًٹ·‚ب‚ا‚جگ®”ُ‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚ء‚½ڈêچ‡پA’تڈيچs‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚à‚ج‚ج‘م•\—ل‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚»‚جژہژ{‚ج•û–@‚ًگà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@گ®”ُ‚جچغ‚ةپA“ء‚ة’چˆس‚ً—v‚·‚éژ–چ€‚حپAژں‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
- ˆہ‘S‚بڈêڈٹ‚ً‘I‚شپB
- ƒ†پ[ƒUپ[ژ©گg‚ھگ®”ُ‚ًچs‚¨‚¤‚ئ‚·‚éڈêچ‡‚حپA’mژ¯پA‹Z—ت‚ج”حˆح“à‚إچs‚¤پB
- “Kگط‚بچH‹ï‚ًژg—p‚·‚éپB
- ƒGƒ“ƒWƒ“‚ح’âژ~ڈَ‘ش‚إچs‚¤پB
- ’“ژشƒuƒŒپ[ƒLپEƒŒƒoپ[‚ًڈ\•ھ‚ةˆّ‚«پAژش—ض‚ة—ضژ~‚ك‚ً‚©‚¯‚é‚ب‚ا‚µ‚ؤپAژش—¼‚ً“®‚©‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤچs‚¤پB
- ژ©“®ژش‚ًƒٹƒtƒgپEƒAƒbƒv‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپA“Kگط‚بƒWƒƒƒbƒLپAƒXƒ^ƒ“ƒhپAƒٹƒtƒg‚ب‚ا‚ًژg—p‚µ‚ؤˆہ‘S‚ةچs‚¤پB(ژ©“®ژش‚ة”ُ•t‚¯‚جٹبˆص‚بƒWƒƒƒbƒL‚حپAƒ^ƒCƒ„Œًٹ·ژ‚ةژg—p‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پB)
- ”pٹü•”•i‚â–ûژ‰‰t—ق‚حپAٹآ‹«‚ةˆ«‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ب‚¢‚و‚¤“Kگط‚ةڈˆ—‚ًچs‚¤پB
پi1پjژl—ضژ©“®ژش‚ب‚ا
| ‘•’u | گ®”ُچ€–ع | گ®”ُ‚جژہژ{•û–@ | ’چˆسژ–چ€ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گ§“®‘•’uپiƒuƒŒپ[ƒLپj | ƒuƒŒپ[ƒL‰t‚ج•â‹‹ |
|
|
||||||||||||
| ‘–چs‘•’u | ƒ^ƒCƒ„‚جŒًٹ· |
|
|
||||||||||||
| “d‹C‘•’u | ƒoƒbƒeƒٹپEƒ^پ[ƒ~ƒiƒ‹•”‚جگ´‘| |
|
|
||||||||||||
| ƒoƒbƒeƒٹ‰t‚ج•â‹‹ |
|
ƒoƒbƒeƒٹ‰t‚حپA•…گHگ«‚ھ‘ه‚«‚”畆‰ٹ‚ً‹N‚±‚µ‚½‚èپA‹à‘®‚ً•…گH‚³‚¹‚é‚ب‚ا”ٌڈي‚ةٹ댯‚ب‚ج‚إپAگl‘جپAˆك•پAژش‘ج‚ب‚ا‚ة•t’…‚µ‚ب‚¢‚و‚¤ژوˆµ‚¢‚ة‚حڈ\•ھ’چˆس‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB (ƒپƒ“ƒeƒiƒ“ƒXپEƒtƒٹپ[پEƒoƒbƒeƒٹ(–§••Œ^)‚جڈêچ‡‚حپAƒoƒbƒeƒٹ‚ة‚ح‚ء‚ؤ‚ ‚é’چˆسڈ‘‚«‚ةڈ]‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB) |
|||||||||||||
ƒqƒ…پ[ƒY‚جŒًٹ·
|
|
|
|||||||||||||
| Œ´“®‹@(ƒGƒ“ƒWƒ“) | ƒGƒAپEƒNƒŒپ[ƒiپEƒGƒŒƒپƒ“ƒg‚جگ´‘|پAŒًٹ· |
|
|
||||||||||||
| ƒGƒ“ƒWƒ“پEƒIƒCƒ‹‚ج•â‹‹ |
|
|
|||||||||||||
| ƒWپ[ƒ[ƒ‹ژش‚ج”R—؟ƒtƒBƒ‹ƒ^‚جگ…”²‚« | ”R—؟ƒtƒBƒ‹ƒ^–”‚حگ…•ھ—£ٹي‚ج’ê‚ةگ…‚ھ‚½‚ـ‚ء‚½ڈêچ‡‚ة‚حپA‰؛‚ةژَ‚¯ژM‚ً’u‚«پAگ…”²‚«—pƒvƒ‰ƒO‚ًٹة‚ك‚ؤ”rگ…‚µ‚ـ‚·پB ‚ب‚¨پAƒvƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO(ژè“®)ƒ|ƒ“ƒv‚ً‘€چى‚µ‚ؤ”R—؟‚ً‘—‚é‚ئ‘پ‚”rگ…‚إ‚«‚ـ‚·پB |
ژüˆح‚ة•t’…‚µ‚½”R—؟‚ً‚و‚گ@(‚س)‚«ژو‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB | |||||||||||||
| ƒWپ[ƒ[ƒ‹ژش‚ج”R—؟Œn“‚جƒGƒA”²‚« |
|
|
|||||||||||||
| —â‹pگ…‚ج•â‹‹ | (ƒٹƒUپ[ƒoپEƒ^ƒ“ƒN•t‚«‚جژش—¼)
|
|
|||||||||||||
| —â‹pگ…‚جŒًٹ· | (—â‹pگ…‚ج”²‚«•û)
|
|
|||||||||||||
| ‚»‚ج‘¼ | گôڈٍ‰t•¬ژث‘•’u‚جگôڈٍ‰t(ƒEƒBƒ“ƒhپEƒEƒHƒbƒVƒƒ‰t)‚ج•â‹‹ | ƒEƒBƒ“ƒhپEƒEƒHƒbƒVƒƒ‰t‚جŒ´‰t‚جٹَژكٹ„چ‡‚ح‹C‰·‚ة‚و‚ء‚ؤˆظ‚ب‚é‚ج‚إپAژں‚جٹ„چ‡‚ًژQچl‚ة‚µ‚ؤٹَژك‚µ‚½گôڈٍ‰t‚ًƒ^ƒ“ƒN‚ة•â‹‹‚µ‚ـ‚·پB
|
ƒ^ƒ“ƒN‚ھ‹َ‚ج‚ـ‚ـƒEƒBƒ“ƒhپEƒEƒHƒbƒVƒƒ‚ًژg—p‚·‚é‚ئپAƒ‚پ[ƒ^پ[‚ھ”j‘¹‚·‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB | ||||||||||||
| ‘‹گ@(‚س‚«)ٹي(ƒڈƒCƒpپ[)‚جƒuƒŒپ[ƒh‚جŒًٹ· | ƒڈƒCƒpپ[‚جƒAپ[ƒ€‚ً‹N‚±‚µپAƒuƒŒپ[ƒhژو•t•”‚ًٹO‚µ‚ؤƒuƒŒپ[ƒh‚ًŒًٹ·‚µ‚ـ‚·پB |
|
پi2پj“ٌ—ضژ©“®ژش
| ‘•’u | گ®”ُچ€–ع | گ®”ُ‚جژہژ{•û–@ | ’چˆسژ–چ€ |
|---|---|---|---|
| گ§“®‘•’uپiƒuƒŒپ[ƒLپj | ƒuƒŒپ[ƒL‰t‚ج•â‹‹ |
|
|
| ƒtƒچƒ“ƒgپEƒuƒŒپ[ƒLپEƒŒƒoپ[پAƒٹƒ„پEƒuƒŒپ[ƒLپEƒŒƒoپ[‚ج—V‚ر‚ج’²گ®(ƒfƒBƒXƒNپEƒuƒŒپ[ƒL‚ًڈœ‚پB) |
| ||
| ƒٹƒ„پEƒuƒŒپ[ƒLپEƒyƒ_ƒ‹‚ج—V‚ر‚ج’²گ®(ƒfƒBƒXƒNپEƒuƒŒپ[ƒL‚ًڈœ‚پB) |
|
||
| ٹةڈص‘•’u | ƒٹƒ„پEƒVƒ‡ƒbƒNپEƒAƒuƒ\پ[ƒo‚ج’²گ® | ƒXƒvƒٹƒ“ƒO‚ج‹ژم‚ًƒAƒWƒƒƒXƒ^‚ة‚و‚è’²گ®‚µ‚ـ‚·پB | ƒAƒWƒƒƒXƒ^‚ة‚و‚é’²گ®‚حپAچ¶‰E‚ج•s‘µ(‚»‚ë)‚¢‚ھ‚ب‚¢‚و‚¤ˆت’u–”‚حگ”ژڑ‚ب‚ا‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤچs‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB |
| “®—ح“`’B‘•’u | ƒNƒ‰ƒbƒ`پEƒŒƒoپ[‚ج—V‚ر‚ج’²گ®(–ûˆ³ژ®‚ًڈœ‚پB) |
|
|
| “d‹C‘•’u | ƒoƒbƒeƒٹپEƒ^پ[ƒ~ƒiƒ‹•”‚جگ´‘| |
|
|
| ƒoƒbƒeƒٹ‰t‚ج•â‹‹ |
|
ƒoƒbƒeƒٹ‰t‚حپA•…گHگ«‚ھ‘ه‚«‚”畆‰ٹ‚ً‹N‚±‚µ‚½‚èپA‹à‘®‚ً•…گH‚³‚¹‚é‚ب‚ا”ٌڈي‚ةٹ댯‚ب‚ج‚إپAگl‘جپAˆك•پAژش‘ج‚ب‚ا‚ة•t’…‚µ‚ب‚¢‚و‚¤ژوˆµ‚¢‚ة‚حڈ\•ھ’چˆس‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB (ƒپƒ“ƒeƒiƒ“ƒXپEƒtƒٹپ[پEƒoƒbƒeƒٹ(–§••Œ^)‚جڈêچ‡‚حپAƒoƒbƒeƒٹ‚ة‚ح‚ء‚ؤ‚ ‚é’چˆسڈ‘‚«‚ةڈ]‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB) |
|
ƒqƒ…پ[ƒY‚جŒًٹ·
|
|
|
|
| Œ´“®‹@(ƒGƒ“ƒWƒ“) | ƒGƒAپEƒNƒٹپ[ƒiپEƒGƒŒƒپƒ“ƒg‚جگ´‘|پAŒًٹ· |
|
ژ¼ژ®ƒEƒŒƒ^ƒ“پEƒ^ƒCƒv‚جڈêچ‡‚حپAژش—¼‚ة‚ ‚ء‚½•iژ؟‚جƒIƒCƒ‹‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB |
| ƒGƒ“ƒWƒ“پEƒIƒCƒ‹‚ج•â‹‹ |
|
|
|
| —â‹pگ…‚ج•â‹‹ | (ƒٹƒUپ[ƒoپEƒ^ƒ“ƒN•t‚«‚جژش—¼)
|
|
|
| —â‹pگ…‚جŒًٹ· | (—â‹pگ…‚ج”²‚«•û)
|
|
|
| ‚»‚ج‘¼ | ƒhƒ‰ƒCƒuپEƒ`ƒFپ[ƒ“‚ج‹‹–û |
|
|
‚Tپ@‚»‚ج‘¼
“_Œںگ®”ُ‹Lک^•ë
“_Œںگ®”ُ‹Lک^•ë‚حپA“_Œں‚جŒ‹‰ت‚ئگ®”ُ‚جٹT—v‚ً‹Lک^پA•غ‘¶‚µ‚ؤپAژ©“®ژش‚جˆغژٹا—‚ة–ً—§‚ؤ‚邽‚ك‚ج‚à‚ج‚إ‚·پB
“_Œںگ®”ُ‹Lک^•ë‚حپAژ©“®ژش‚ة”ُ‚¦•t‚¯‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ج•غ‘¶ٹْٹش‚حپAژ©‰ئ—pڈو—pژ©“®ژش‚ب‚ا‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚ح‚Q”NٹشپA‚»‚ج‘¼‚جژ©“®ژش‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚ح‚P”Nٹش‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ب‚¨پAژ©“®ژش‚جˆغژٹا—‚ً“Kگط‚ةŒp‘±‚µ‚ؤ‚¢‚‚½‚ك‚ة‚àپA‚±‚ج‹Lک^•ë‚ً‰آ”\‚بŒہ‚è’·ٹْٹش•غ‘¶‚µپAژ©“®ژش‚جپuگ¶ٹU‹Lک^•ëپv‚ئ‚µ‚ؤٹˆ—p‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ–]‚ـ‚ê‚ـ‚·پB
“_Œںگ®”ُ‹Lک^•ë‚ج‹Lچعژ–چ€‚ئ‹Lچع—v—ج‚حژں‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB
| (1)پu“_Œں‚ج”NŒژ“ْپv | “_Œں‚ًژہژ{‚µ‚½”NŒژ“ْ‚ً‹Lچع‚µ‚ـ‚·پB |
| (2)پu“_Œں‚جŒ‹‰تپvپAپuگ®”ُٹT—vپv |
|
| (3)پuگ®”ُ‚ًٹ®—¹‚µ‚½”NŒژ“ْپv | گ®”ُ‚ًٹ®—¹‚µ‚½”NŒژ“ْ‚ً‹Lچع‚µ‚ـ‚·پB |
| (4)پuژش‘ن”شچ†پvپAپuژ©“®ژش“oک^”شچ†–”‚حژش—¼”شچ†پv | ژ©“®ژش‚ة”ُ‚¦•t‚¯‚جژ©“®ژشŒںچ¸ڈط–”‚حŒyژ©“®ژش“حڈoچدڈط‚ًŒ©‚ؤ‹Lچع‚µ‚ـ‚·پB |
| (5)پu“_Œںژ‚ج‘چ‘–چs‹——£پv | گدژZ‹——£Œv(ƒIƒhƒپپ[ƒ^)‚ًŒ©‚ؤ“_Œںژ‚ة‚¨‚¯‚éژ©“®ژش‚ج‘چ‘–چs‹——£‚جگ”’l‚ً‹Lچع‚µ‚ـ‚·پB |
| (6) “_Œں–”‚حگ®”ُ‚ًژہژ{‚µ‚½ژز‚جژپ–¼–”‚ح–¼ڈج‹y‚رڈZڈٹپv | “_Œں–”‚حگ®”ُ‚ًژہژ{‚µ‚½ژز‚جژپ–¼(–@گl‚ح‰ïژذ–¼)‚ئڈZڈٹ‚ً‹Lچع‚µ‚ـ‚·پB ‚ب‚¨پAƒ†پ[ƒUپ[ژ©گg‚ھ“_Œں–”‚حگ®”ُ‚ًژہژ{‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚حپAڈZڈٹ‚ج‹Lچع‚حڈب—ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB ‚ـ‚½پA“_Œں‚ئگ®”ُ‚ًژہژ{‚µ‚½ژز‚ھˆظ‚ب‚é‚ئ‚«‚حپA—¼ژز‚ً‹Lچع‚µ‚ـ‚·پB |
(چى‹ئ‹و•ھ)
| چى‹ئ‹و•ھ | ˆس–، | چى‹ئ—ل | ƒ`ƒFƒbƒN‹Lچ†‚ج—ل | |
|---|---|---|---|---|
| “_Œں | “_Œں‚جŒ‹‰تپAˆظڈَ‚ھ‚ب‚©‚ء‚½پB | پ| | ƒŒ | |
| گ®”ُچى‹ئ | Œًٹ· | “_Œں‚جŒ‹‰تپAŒًٹ·‚µ‚½پB(•”•iپA–ûژ‰پA‰t—ق‚جŒًٹ·چى‹ئ‚ًژ¦‚·پB) |
|
پ~ |
| ڈC— | “_Œں‚جŒ‹‰تپAڈC—‚µ‚½پB(–€–صپA‘¹ڈ‚ب‚ا‚ج‚½‚ك•”•i‚ًڈC•œ‚·‚éچى‹ئ‚ًژ¦‚·پB) |
|
پ¢ | |
| ’²گ® | “_Œں‚جŒ‹‰تپA’²گ®‚µ‚½پB(‹@”\ˆغژ‚ج‚½‚كپA—V‚رپA‚·‚«ٹشپAٹp“x‚ب‚ا‚ًٹîڈ€’l‚ة–ك‚·چى‹ئ‚ًژ¦‚·پB) |
|
A | “_Œں‚جŒ‹‰تپA’²گ®‚µ‚½پBپiƒXƒLƒƒƒ“ƒcپ[ƒ‹“™‚إ‹@”\’²گ®‚·‚éچى‹ئ‚ًژ¦‚·پBپj |
|
’÷•t | “_Œں‚جŒ‹‰تپA’÷‚ك•t‚¯‚½پB(ٹة‚ٌ‚¾‰سڈٹ‚ً‘‚µ’÷‚ك‚·‚éچى‹ئ‚ًژ¦‚·پB) |
|
‚s |
| گ´‘| | “_Œں‚جŒ‹‰تپAگ´‘|‚µ‚½پB(•²گoپA–û‚ب‚ا‚ة‚و‚é‰ک‚ê‚ًژو‚èڈœ‚چى‹ئ‚ًژ¦‚·پB) |
|
‚b | |
| ‹‹–û | “_Œں‚جŒ‹‰تپA‹‹–û‚µ‚½پB(–ûژ‰پA‰t—ق‚ً•â‹‹‚·‚éچى‹ئ‚ًژ¦‚·پB) |
|
‚k | |
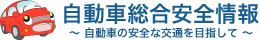

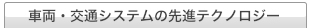
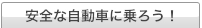
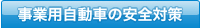
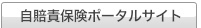

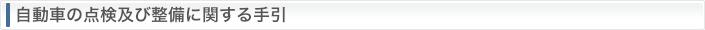
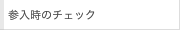
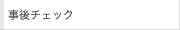
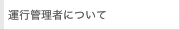
![‰^“]ژز‚ة‘خ‚·‚鋳ˆç](resourse/img/navi/safety_003.gif)
![‰^“]ژز‚جکJ–±ٹا—“™](resourse/img/navi/safety_002.gif)
![‰^“]ژز‚جŒ’چNٹا—](resourse/img/navi/safety_008.gif)