| 2.市民団体等との連携を必要とする背景 |
| (1)川そのものに対する各種ニーズの高まり | |
| 1.安全な地域づくり | |
| 我が国は、台風、梅雨等が発生しやすいアジアモンスーン地域に位置し、山地が急峻であることに加えて火山噴火や地震が多い上、高潮や津波の来襲頻度も高いなど、水害、土砂災害が発生する可能性が常に内在しており、災害と共存せざるを得ない現状にある。さらに、低平地への人口・資産の集中に加え、地下街における浸水被害等新たなタイプの災害が発生するなど、災害ポテンシャルが増大している。このような中、安全な地域づくりを行うべく、河川改修等の治水事業を進めるだけでなく、仮に河川が氾濫した場合でも、被害を最小限に食い止めるような危機管理体制を地域全体で整えることが必要となっている。 | |
| 我が国においては、国土の約10%にあたる沖積平野に、総人口の 約50%の人々が居住。その資産は全国の約75%が集中。 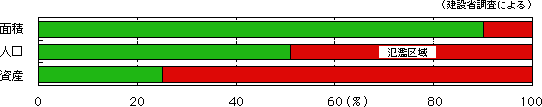 | |
| 淀川の想定氾濫区域における 地下街の延床面積 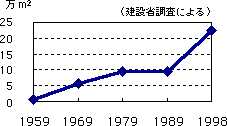 |  地下鉄博多駅への洪水流入 (平成11年6月末梅雨前線豪雨) |
| 2.清らかで自然豊かな川 | |
| 人口の増加、産業の発達等の急速な社会変化は、流域における水や緑の減少を招いた。また、治水・利水事業を緊急かつ効率的に推進した結果、環境への配慮が足りなかった面も否定できない。このようなことから、自然との関わりを重視し、流域及び河川の自然環境と人間の諸活動とのバランスのとれた自然共存型社会の実現を図るべく、水と緑の清らかで自然豊かな川を保全、復元することが必要となっている。 | |
 貫川(福岡県) |  天竜川における市民によるアヤメの移植 |  稚魚の放流(最上川水系立谷沢川) |
| 3.人間が憩い、楽しむことのできる川 | |
| 都市の発展と裏腹に、都市内の一部の河川は生物の住まない単なるコンクリートの排水路と化し、フェンス張りや暗渠化により住民からは遠い存在と化してしまった。川は、住民が身近な自然とふれあいながら、憩い、楽しむことのできる貴重な空間としての役割が期待されており、川におけるオープンスペースや自然地の整備が重要となっている。 | |
地域における河川の役割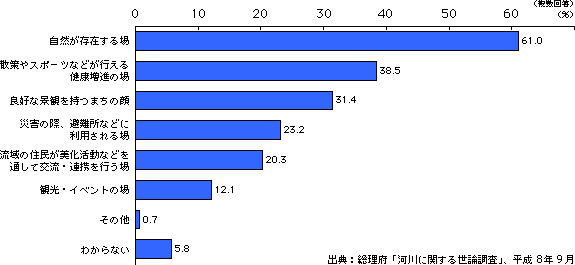 | ||
| 市民団体との協力によるいたち川の整備(横浜市) |  整備前(ゴミ捨て場と化した川) |  整備後(自然豊かなふれあいの空間) |
| 戻る | 目次 | 次へ |
| -2- | ||