| 通船川の再生プランづくり (つうくり市民会議による川づくり案の作成) |
| 【背景】 | |
| ● | かつて舟運の大動脈として栄え親しまれてきた通船川の再活用を望む声や、都市化による水質汚濁の改善要望が流域市民から高まり、現況調査や清掃などの活動を続けてきた住民団体間の連携である「通船川ネットワーク」が発足するなど、市民活動が活発に展開されてきた。 |
| ● | 昭和39年の新潟地震によって水害の危険性が高まった地域からの改善要望があり、通船川の老朽化した護岸の抜本的改修の必要から、新潟県と新潟市は平成9年に「通船川・栗ノ木川下流再生検討委員会」をつくり、河川改修事業計画の検討を始めた。 |
| 【内容】 | |
| ● | 「通船川・栗ノ木川下流再生検討委員会」では、今後の川づくりにおいては住民の要望も取り入れる必要性が議論され、流域住民や市民団体に呼びかけ市民会議準備会が発足した。その後、98年には「通船川・栗ノ木川下流再生市民会議(つうくり市民会議)」が設置された。 |
| 1. | 通船川流域での住民アンケート調査から課題を洗い出し、これを多様な価値観を持つ市民団体間で共有する作業を行っている。 |
| 2. | 活動を伝えるメディアとして「つうくり通信」の発行を行っており、町内会・自治会による回覧版や、市民センター等の窓口で配布している。 |
| 3. | 「再生検討委員会」が川づくりの基本的考えを提示し、「市民会議」が川づくり案を作成する。 |
| 4. | 行政(委員会)による徹底した河川に関する情報提供を行っている。県では資料集を作成し、主要公共施設に設置し公開している。 |
| ● | 市民参加によるプランづくりを行うために、「通船川河口ワークショップ」が全10回の行程で行われている。また、この広報として「通船川河口ワークショップニュース」が毎回発行されている。 |
| 【特徴】 | |
| ● | 「市民会議」は行政、住民、市民団体等、参加の自由なオープンな話し合いを通して市民プランを作成することをめざしており、プロセスを重視した運営が行われている。その結果、行政及び参加市民相互の意志疎通が、良くなり川の課題のイメージの共有化が図られつつある。 |
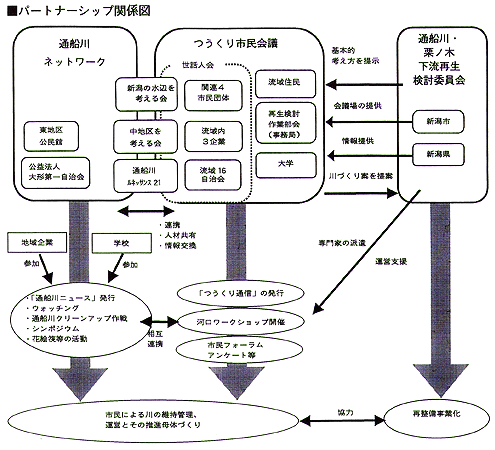 |
|
 「通船川クリーンアップ作戦」の様子 |
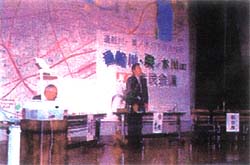 第2会 通船川・栗ノ木川下流再生市民会議で 開会の挨拶をする大熊会長 |
| 戻る | 目次 | 次へ |
| -10- | ||