
|
開会・建設大臣挨拶・委員紹介・会の公表 第2回(平成11年4月21日) |
|
|
|||
| 5−3.ショートスピーチ (隈部まち子委員) | |||
| 私は、大学ではコミュニケーション論を主に教えている。今日はマイクロ環境について話したい。
私は、社会資本整備をめぐる環境には、その規模によって小、中、大の3種類があると考えている (参考資料) 。まず、真ん中の中という環境であるが、これは現在私たちが生活しているそれぞれの地域の環境問題を指す。この中には、例えば街路の整備などといった、現代の生活者が共通に抱えている課題と、個性的な都市づくりをしましょうというように、ある地域だけが関わっている固有の環境問題、その両方が含まれる。これを私はリージョナル環境と名づけた。それに比べて小という環境は、小規模な環境である。いわゆる私たちが日常生活を送っていて直接影響のある環境問題を指す。なかなかこういう激動の世の中になると、国のいろいろな政策の中ではつい見過ごされてしまうような問題を指す。例えば、工事用のダンプの騒音がうるさいとか、排ガス、振動、日当たりなどといった、個人個人が抱えているような社会資本整備をめぐる環境問題である。これを小さいのでマイクロ環境と名づけた。もう一つ、大の環境というのは、地球規模または国家的な環境問題を指す。例えば、アジアハイウエーなどの国際的な課題とか、それからダムや治水、橋梁、全国の立体交差などのいわゆる国家的プロジェクトを指す。これがさらに右の方にいくと、これは無限大ということになっていて、これは将来、宇宙規模の環境問題ということになる。 実は、戦後の日本というのは、初めは自分の身の回りの環境を整えるということで、マイクロ環境を整えることに忙しかったわけだが、それから地域のリージョナル環境に、そしてさらにダイナミックないろいろな環境整備というふうに、環境のパラダイムがシフトしていったのではないかと思う。しかし、21世紀を考えたときには、このまま永遠に大規模なものを目指していっていいのかということを私は大変疑問に思っている。つまり、ダイナミック環境だけに専心するのではなくて、ほかのリージョナル環境あるいはマイクロ環境にももっと目を向けたらいいのではないかと思う。この点が、先ほど建設大臣も、パラダイムシフトだけを追求する、そしてまた大規模な開発、進歩を望むことが果たしていいのかということをもう一度考えた方がいいと言われた。そのことを私も考えている。 このうち、中のリージョナル環境に関しては、中部地方建設局が主催する文化アセスメント委員会の末席に私も実は入れていただいており、3年間にわたってこれを研究してきて、近々最終報告書が出されることになっているので、委員の先生方には後ほどこれを参考にしていただけたら大変ありがたいと思う。そこで、中の環境については今日は省略させていただきたい。 そして、ダイナミック環境の方だが、これは政府や建設省、そして先ほど発表された石井先生のような専門家の先生が推進されている分野で、特に20世紀の後半というのはこうした専門家の方々の的確な判断によって急速な発展を遂げたと思う。日本のインフラ環境が著しく改善されたということは、皆さんが認めることだと思う。しかし、合理性というものが余りにも強調され、効率化ばかりが偏重されて、本来の目的であるはずの暮らしの快適さとか、それから豊かさというのが見過ごされてきたのではないかと思う。したがって、これからはもっとマイクロ環境に目を向けていったらいいのではないかと思っている。 ところで、マイクロ環境というものを考えるということだが、私はマイクロ環境というのは大変相対的なものだと思っている。かの有名なアインシュタインはこういうふうに言っている。「きれいな女性と一緒にいると、1時間が1分のように感じる。でも、熱いストーブの上に1分座ったら、何時間にも感じる。これが相対性理論だ」と。相対性理論を発表した後に、一般の人たちの「それはどういった理論ですか」という質問に対してこう答えたら、すぐに一般の方が理解したということである。アインシュタインが言ったのは50年ほど前なのだけれども、今は女性と言うと何か弊害があるみたいなので、魅力的な男性と一緒に座っていると、1時間が1分のように感じるということを補足しておきたいと思う。なお、今日は幾つか名言を紹介するけれども、それは前回お配りした「世界を動かした名言」の中に全部掲載されているので、原文の英文をお使いになりたい方はそちらを参考にしていただきたい。 したがって、マイクロ環境というのは非常に相対的なわけなのだけれども、この相対的なマイクロ環境がいかにプラスにシフトされるかということについては、非常にPAというか、一般の人たちにいかに周知するかというコミュニケーションが非常に大切になってくると思う。 そこで、マイクロ環境をプラスに作用させるための3つのポイントを考えてみたい。 1つ目のプラス要因というのは、マイクロ環境の大切さを社会資本整備の供給者がより強く理解するということである。つまり、アメリカの名言に「世論とは大衆の意見ではなく大衆の感情である」という言葉がある。従来の社会資本整備のPAのあり方を見てみると、建設の方針は明らかにするけれども、個人に対しては情報を直接余り配布することがない。したがって、一般の人は自分が住んでいるマイクロ環境が近い将来どういうふうになっていくのかということをほとんど知らないというケースがあった。世論とは大衆の意見ではなく大衆の感情であるので、例えば道路建設によって生活者に騒音などの影響が出る場合に、事前に詳細を知らされていなかった場合には、その人が騒音を何倍にも大きく感じるということがあると思う。その逆に、情報を周知させて理解を求めると、住民の気が済んで、大きな騒音も半分ぐらいにしか聞こえないという心理的な効果というのはあると思う。 1971年のことだが、ニューヨーク市の環境をよくしようと思った当時の市長のリンゼイさんが、まず一般市民にその気持ちを直接伝えた。ニューヨーク市の全世帯にパンフレットを配布して、その中でニューヨーク市の環境をよくすることは私たち生活者みんなの問題だということを呼びかけたのである。さらに、「アメリカ流の暮らし、これが私たちを殺しているのか」というメッセージを中に入れた。 “The American way of living, is it killing us? ” こんな疑問を市民に投げかけたのである。そのパンフレットの中身を見てみると、7つの大きな項目に分かれている。その7つというのは、空気、エネルギー、水、騒音、交通、食べ物、ごみ、そしてリサイクルとなっている。交通のところをあけてみると、道路環境の重要性を大変強調していて、中にこんな文章があった。「道路を大切にするために、そして歩きやすく保つために、美しくするために、ニューヨーク市内では犬を飼うことを禁止しましょう。断固としてこれをやり抜きましょう」と書いてある。井上先生同様、リンゼイさんは犬の糞を前にしてコーヒーは飲めなかったということなのだと思うけれども、もちろんこのパンフレットを読んだ市民の人たちは、「市長さん、何もそこまでおっしゃらなくても」というような反応だったようである。しかし、市民の気持ちになってこういう具体的な生活の環境美化を訴えたということで、このパンフレットはアメリカでとても有名になった。まさにインフラ整備の供給者のリーダーが生活者に直接いろいろなことを呼びかけて成功した一つの例である。 マイクロ環境をプラスにする2つ目のポイントは、今度は私たち自身のことだが、インフラのユーザー自身の意識を高めるということではないだろうか。つまり、例えば近隣の環境に問題が生じて、情報が錯綜することがある。そういうときでも自分で的確な判断ができるように、日ごろから自分がマイクロ環境について正しい情報を知っておかなければいけない。そうしないと、誤った情報に振り回されるということになる。 例えば、私は原宿に住んでいるのだが、去年のクリスマスにイルミネーションをめぐって反対運動が一部の住民から起こった。マスコミはこれに非常に注目して連日のように報道したわけである。反対する住民の方たちの主張は、1つは人込みがひどくて日常生活に支障を来すということ、2つ目は交通渋滞が起こるということ、そして3つ目はごみが散乱して原宿の環境が著しく悪化するということだった。大体この3点に絞られたのだが、こういう方たちはゴールデンタイムにテレビに何回も出演してこればっかり繰り返したわけである。私たち住民に対しても、署名を集めたりとか、お金を集めたりとか、ということをやろうとした。ところが、私自身は、イルミネーションというのはすごく町を美しく照らして、みんなが楽しんで幸せそうにしているので、とてもいいことだと思っていた。そこで、反対運動をやっている人たちの3点に注目していろいろ観察してみたところ、クリスマスイブとクリスマス当日は確かに人込みがすごかったのだけれども、最近不況のせいか、あとの日は全く大したことがなくて、交通渋滞も数年前にイルミネーションが始まったころは大変だったけれども、今はみんな慣れてしまって大したことはなかった。それから、ごみ問題だが、商店やレストランのボランティアの人たちがごみをきれいに清掃していたので、むしろいつもよりもきれいだったというのがその印象である。結局、原宿の環境というのは、イルミネーションによって美しさは増したけれども、悪化したとは私にはとても思えなかった。ところが、今の社会というのは、何か非常に対立的な問題が起きたときだけ賛成という意見が言えるのだけれども、そうでない限りは、反対の意見をすくうところはあっても、賛成ですという意見をすくう機関、ルートというものはほとんどないと思う。 これはちょっと些細な例だったと思うけれども、今後、社会資本整備を行っていく上で、こういった問題はいろいろなところに頻繁に起こってくるのではないかと思う。そのときには、マスコミに限らず、エキセントリックな情報が流れるわけだから、それに左右されない客観的な情報ルートを生活者が各自持っているということは非常に大事だと思う。 その情報ルートの一つの参考になるかと思って今日紹介しようと思うのが、アメリカでかって行われた消費者運動の動きである。ご承知の通り、アメリカでは、消費者の権利ということを5つに分けている。1つは安全の権利、2つ目は事実を知らされる権利、3番目は選択の権利、4番目は意見が取り入れられる権利、そして5番目が保障の権利となっている。このうち1番目から4番目まではケネディ大統領、そして5番目はニクソン大統領によって提示された。 すなわち、消費者運動の権利をそっくりそのままマイクロ環境の権利に置きかえると、これが何か有効になるのではないかなと思う。すなわち、マイクロ環境の安全の権利であったり、事実を知らされる権利、それから選択の権利、またマイクロ環境に関する意見が取り入れられる、受け入れられる権利、そしてマイクロ環境の保障の権利という流れが一つ考えられるのではないかと思う。 今紹介したのはどういうことかというと、消費者運動というのは、アメリカではラルフ・ネーダーやデニス・ヘイズといったいわゆる専門家の方たちがリーダーシップを取って起こったということも事実なのだが、同時にアメリカでは政府のリーダーシップによって消費者運動が大変促進された。その一つの例としては、1962年にケネディ大統領が消費者教書というものを発表したのだけれども、これが糸口になって1969年までに全米29州に消費者団体結成の素地になるような団体がつくられた。そのケネディ大統領はこういうふうに言っている。「人間の基本的資源は頭脳である」 それから、マイクロ環境をよくする3つ目の提案である。それは、20世紀の退屈なインフラ環境から脱却するということではないだろうか。アメリカの作家のピーター・シェーファーという人は、「ロンドンを水彩画とすれば、ニューヨークは油絵だ」と言っている。また、アメリカの作家のトルーマン・カポーティーという人は次のように言っている。「ベニスは、リキュール入りのチョコレートを一箱、一遍に食べたような気になる町だ」それでは東京とか大阪というのは、世界の人が見たときにどういうふうになるのだろうか。関西空港を建設したイタリアの建築家のレンゾピアノはこういうふうに言っている。「日本の空港ビルは悲劇。世界的悲劇。揃いも揃ってげた箱のよう」続けて彼はこういうふうに言っている。「急ピッチで整備が始められたことは承知している。しかし、あれは予算の問題ではなく、心意気の問題です」 そう言われてみると、新幹線の駅はかまぼこのようだし、日本を旅していると、空港とか新幹線の駅もまるで退屈だという感じがする。これによって旅のマイクロ環境が著しく退屈になっているに違いないと思う。スポット的には、先ほど石井先生の方から紹介があったよいインフラがたくさんあると思うけれども、大勢の人が日常的に利用するインフラは、日本では大変画一的な退屈なものになっているのではないだろうか。アメリカのデンバー空港に降り立ったときの空港の美しさというのは、私はいつも忘れることができない。ロッキー山脈をイメージした、山々が波打つような感じのいわゆる幕屋根でできていて、これを見ると、旅の非日常性というものを何となく感じることができる。特に、夕やみ迫るころに飛行機で降り立っていくと、夕日がテントに反射していて、それはすばらしい光線の輝きというものを目にすることができる。だから、21世紀には、何かこういった自然も取り入れた、自然と協調するような、デンバー空港のコンセプトというのがいろいろなところに入れられないだろうか。もし入れられたら大変すばらしいと思う。そうすると、ふだん私たち都会人は自然とはほとんど無縁のマイクロ環境の中で暮らしているわけだけれども、旅に出て大いにリフレッシュすることができると思う。そういうことの結果として、マイクロ環境が非常にプラスにシフトすると思う。 私は、21世紀には、お金とか機械に余り振り回されないで、ぜいたくな環境の中で暮らしたいと思っている。最後に、シャネル創業者のココ・シャネルの名言を紹介したいと思う。「贅沢とは、居心地がよくなることです。そうでなければ、贅沢ではありません」 “Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury. ” どうもありがとうございました。 |
 |
||
 |
|||
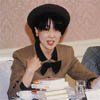 |
|||
|
|
|||