
|
開会・建設大臣挨拶・委員紹介・会の公表 第2回(平成11年4月21日) |
|
|
|||
| 6.ディスカッション | |||
| 【嶌委員】 | |||
| これからの進め方としては、月1回程度で毎回3人ずつぐらいにスピーチをしてもらい、その度に活発な討論を中心に進めたい。また、議論の成果は今までとは違った形で情報発信をしていきたい。夢のあるものにまとめて行ければよいと考える。
経済効率を追求して、進歩、開発、安全、科学技術等の思想は善であると考えてきたが、今、その反作用もでてきており、もう一度新しい考え方も入れてこれまでの社会を見直す時期にきているのではないか。本当に居心地の良い社会というものをもう一度根本から考え直すべきではないかという議論が高まっている。 今までの延長で21世紀を考えるのではなく、まず居心地の良い社会、くらしの理想像を描き、逆にその理想像に近づくためにどうしたら良いのか考えるのが、この懇談会の大きな意義であると思う。 まず、前回欠席された成毛委員と安部委員に自己紹介も兼ねてご意見を伺いたい。 |
 |
||
| 【上山委員】 | |||
| 日本にいる外資系の特に経営者層には特徴がある。日本の会社に勤めていると海外への転勤がある。海外転勤を嫌がって外資系に務めているという人が外資系のトップだと3割程度いる。アメリカを好かず、あまり住みたくない国の一つにアメリカを挙げている者は多い。外資系の経営者がアメリカを好まず、日本の方が良いと言う理由には、建物もしくは社会的なインフラ整備の状況によるのではなく、社会の構成要素である人間によるようである。
マイクロソフトの本社のあるシアトルはきれいで住みたいと思うことがある。しかしごちゃごちゃで、カオス的な日本特有の都市空間の方が安心感をもたらしてくれるような気がする。日本は21世紀も今のまま、ごちゃごちゃのままでいいのではないか。 |
 |
||
| 【安部委員】 | |||
| 一市民の立場から専門家が気付かないことを発言したいと思っている。野蛮な意見を申し上げたい。
近頃は音に苦しんでいる。以前、国分寺に7年間住んでいた。向かいのお宅の犬が朝7時から鳴き出し、うるさいので町内会長や警察に訴えた。しかし犬が早朝に鳴くことを止めることは誰も出来ず、無力である。仕方なく武蔵野市へ引越した。周囲半径50m内に犬を飼っている家がないところを探した。しかしそこでは一日中、信号機から「通りゃんせ」が鳴り響く。ちっとも美しくない、あの奇怪な音が一日中鳴り響く。この信号機を壊したら、また近くの府中刑務所に、、、。もう何度ニッパーを握って電線を切断しようと思ったか。しかし、どこへも言っていくところがない。あげくの果て、先日文化放送から、チャリティーがあるからギャラなしで来いと。とりあえず、評判が悪くなるといけないから行くと、何とその「とおりゃんせ」の機械を信号機ごとにつけようというチャリティーだった。おなかが痛いと嘘をついて、帰ったわけです。 新幹線の車内でも目的地に到着するためには不要不急の放送が頻繁に流れている。車掌に訴えても取り上げてもらえるとは決して思えない。あるとき、近鉄電車に乗った。車掌が社内アナウンスを流すのだが、車掌特有の発声法でほとんど聞き取ることは不可能であった。だから僕の持っている媒体に書くことにした。「近鉄は電車内で、ああいいうアナウンスをするから野球が弱いのではないか」と。 このように今、私は音に悩んでいる。「信号では目不自由な人の手をとって渡りましょう。」と学校で教えれば済むことではないか。「通りゃんせ」のメロディーから逃れるためここからもっと静かなところへ引越しすることを考えている。 |
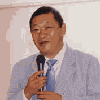 |
||
| 【竹中委員】 | |||
| 私たちは「障害を持っている人(チャレンジドという新しい言葉で呼んでいます)を納税者にできる日本」というキャッチフレーズで運動している。障害者に親切にしようとか、障害者に対する補助金を上げようという運動が主流だったが、チャレンジドが誇りを持って働き、納税できるようにしなければ、という意見が近年増えてきた。同時に、チャレンジド自身の中にも、保護の対象とみなされるのでなく、自己投資をして勉強しよう、とか、リスクを負ってでも冒険したい、という人が増えてきた。阿部委員から音響信号に関するご意見があったが、実は音響信号でなければ視覚障害者が横断できない訳ではない。海外では様々な方法で視覚障害者のバリアフリーが考えられているが、例えば(携帯電話に使われている)バイブレータ機能を信号機に付けたり、赤外線を利用した音声ガイドを導入している都市もある。日本では「この方法でなければダメ」と発想が硬直化しているような気がする。例えばウィンドウズがアイコン式になり、視覚障害者には使いにくくなった。マイクロソフト社に対して一時、「視覚障害者に不便な製品を作ったマイクロソフトは潰れろ」などという抗議の声が上がった。しかしプロップの会員だった一人の全盲の青年は「目の見えない自分達が、アイコンという見える人にとって便利なものを否定することは、自分たちが社会からされてきたことの繰り返しであり、自分達のエゴだ。僕は、ウィンドウズを目の不自由な人にも使えるようにする仕事をしたい」といい、彼は現在、アクセシブルなウィンドウズを開発するため、マイクロソフト社の社員として開発を行っている。街づくりにも、チャレンジド自らが平衡感覚と専門知識を持って参画することが求められていると思う。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 今日の大きなテーマの一つは安全と自己リスクでしょうか。安全に関する全ての基準を満たさないと許可しないという発想が役所にあるのではなかろうか。また、人々も問題がおこるとリスクの責任を公や他人に求めすぎてきた傾向もあった。その発想が世の中を画一的にしているのではないか。また責任の免罪のためにそのような許可制度にしていた面もあった。 |  |
||
| 【林委員】 | |||
| 結局だれが決めているのか、そこが問題である。信号機に「通りゃんせ」を備え付けるか否か、その地域の人がみんなで相談し、それが必要かどうか、また手を引いて渡るお世話ができる人はいるのかとか、そういった話し合い、意見を述べるチャンスがあれば随分と違うと思う。 |  |
||
| 【松田委員】 | |||
| 地方に行くとよく「道の駅」へ案内される。地域によってはすてきなレストランがあったり、特産物を販売していたり、かなり思い入れのあるいい建物が建っている。その「道の駅」の駐車場は間違いなくアスファルトで舗装されている。一面アスファルトにすると見ばえが悪いし、熱い。ヨーロッパでみる駐車場はレンガと芝によって整備されている。アスファルト舗装から透水性のある工法に変えてほしいが、誰がどうやって決めているのだろうか。 |  |
||
| 【澤田委員】 | |||
| 海外にスチールハウスを取り扱っている友人がいる。海外から日本に持ち込もうとしているエムチャンという製品がある。丈夫で薄く、コストが低いにも拘わらず日本では許可が下りない。何の規制によって許可がおりないのだろうか。一体、どこが許可を出さないのか。 |  |
||
| 【澤登委員】 | |||
| 生活者はもっと木材を使いたいと思っているにも拘わらず、木材使用には多くの制約がある。木は火事の際にも内部まで燃えないという耐火性を有し、毒ガスもでない。河川の土木工事では、木は腐るという理由で丸太もどきのコンクリートが使われている。何を基準に規制をしているのか不明である。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 市民には分らないところで様々な事柄が決められているのが不満、また意見を言うルート、訴えるチャンスさえない。
また高度経済成長時に決められた安全、経済効率重視の社会がわずらわしくなってきているのではないか。 |
 |
||
| 【川勝委員】 | |||
| 隈部氏のおしゃった「一番の贅沢は居心地の良いこと」にみなさん賛成であろう。その居心地の良さをどのようにつくっていくかが問題である。
また石井氏の「宇宙には四角四面のものはなく、逆に画一的なものは不自然である。」というのも一つのメッセージになるであろう。 木に対する愛着は直感的なもので、感性的なものである。その愛着はどこから湧いてくるのだろうか。日本には森がありながら、木を十分活かしていない。木材がコスト高であることも問題であり、これから木の使い方を考えていかなければならないであろう。 また井上氏のおしゃった日本人の持つ清潔感をこれからも守っていきたい。これは安全を重視することにつながる。 様々な事柄が人知れず決まっており、責任の所在がはっきりしないというのが日本の特徴である。皆が「いいな」と思える決まり方になれば良いと思う。 日本は「かまう」文化で、この文化は良いと思う。お上からだけ「かまわれる」のではなく、お互いに「かまい合う」ことができれば良いのではないか。安部氏がおっしゃったように子供が目の不自由な方の手を引っ張って渡ってさしあげれば、音響信号はなくても済むのではないか、そういったかまい方を大切にしていくべきであろう。 成毛氏が発言されたように日本には多様なものがあることを前提に、多様なものそれぞれが居心地良く収まると思える状態にしていくにはどのようなイメージを提示すべきであろうか。画一性を排しながら、「宇宙の記憶」をベースにしてマイクロな環境をどのようにつくるかが課題であろう。 |
 |
||
| 【関谷大臣】 | |||
| 敷居をなくすなど、高齢者が生活しやすいバリアフリー住宅をつくると公庫の割増融資が受けられる。しかしながらそのよう配慮をしたところで、やはり人間には寿命がある。家に敷居があれば、お孫さんがおじいちゃんの手を引いてあげましょうという、孫とのまたコミュニケーションも生じる。
常に前進していくことが良いのではなく、現在の状態でもいいところが十分にあるとこの委員会では認識されている方がいらしてうれしく思っている。 移動で飛行機を利用することがしばしばある。飛行中、心を休める音楽つまり、リラクゼーション・ミュージックを多くの人々が聞いているようである。みんな疲れているのであろう。余りにも前向きの方向に行き過ぎているのではないか、もう少しスローダウンしてもよいのではなかろうかと思う。 |
 |
||
|
|
|||