
|
| 開会・建設大臣挨拶・委員紹介 | 第4回(平成11年7月5日) |
|
|
|||
| 5.ディスカッション | |||
| 【嶌委員】 | |||
| 今日の話は、何かみんなばらばらのように見えながら、やはり一つの次世代を考える、
10年、30年後を考える上でのいろいろな示唆に富んだ話だったと思う。 これからを討論を始めたい。最初、川勝さんから問題提起をしていただきたい。 |
 |
||
| 【川勝委員】 | |||
| 前回の話の流れでは、まず澤登さんが家族ないし家庭が進化していると言われた。内実を見れば、ばらばらになっているというようにも見える。しかし、一人一人が自立していくような社会になって、旧来の役割はもう変わっていく。そういうチャンスとしてとらえようという話だったと思う。
加藤さんは似たようなレベルで、やはりコミュニティが崩壊していると言われた。しかし、一方でボランティアという新しいコミュニティづくりの機運が盛り上がっている。危機感がありつつも、そこにいわば新しいルールづくりの可能性を示唆されたと思う。 一方、成毛さんは、すさまじいとしか形容のできないほどの勢いで進んでいる情報産業の現場とその見通しを報告された。それが我々のライフスタイルを確実に変えることを説得力を持って言われた。それについて結局「基礎は裸のつき合いである」という建設大臣の名言があった。要するにゼロから出発しようということであった。 今日はそういう問題提起を受けた話だったと思う。最初に坂井さんが今までも高いものが大きくていいと思っていたものを、ひっくり返して小さくても高いものがあり得ると言われた。それから、デザインというのはどんどん革新していくべきはずだけれども、長続きするデザインというのは初めから古いものを形づくっていれば長く続くというような話があった。そうした話のいわば基礎にあるのは、日本人の空間認識というか、狭いスペースを広く使う知恵、お箸でもちゃんとしまうとか、もちろん布団を畳み、そしてそこが居間になり、そこが団らんの場になりということで、そういう日本の空間というものに応じたデザインというものをこれから考えていくことが必要であろうという提言だった。 竹中さんの話は非常に感動的で、身体障害者が生まれつきという身体障害の人と、それとラグビーをやっていて、そして首の骨を折って身体障害者になってしまうという、結局だれにでもあり得る問題であることを教えて貰った。人間にとって道具は身体の延長であり、道具を使わないで人間は生きていけないという宿命を負っている。そういう道具の使い方を一番身体的に困難な人の立場から考えていこうということで、道具というのは人間にとって何ぞやと深い問いかけでもあった。それは、よく考えれば日本の中における道具のシステム、あるいはもののシステムがどうあるべきかということへの問題提起である。今までは、大量生産、大量消費だったが、それぞれの道具がすべて、いわば固有の名前と役割を持つ一人一人にとっての道具やシステムでなければならないというメッセージでなかったかと思う。 澤田さんがそれを受ける形で、50年後というのを出されたのが面白い。富国強兵といったときに、国家目標を50年ぐらいは念頭に置いていたのではないかと思う。しかし、そこには自然を大切にするとか、人間と自然がマッチした街づくりをするというようなコンセプトは皆無である。戦後復興はそういうシステムの復興であったわけだが、これが制度疲労を来している状況にある。そしていみじくも日本人が誇れるような街づくりや国づくりをしていく時期にきていると言われて、私も大いに同感した。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 澤田さんは恐らく今、国家というか、日本は次の世紀、30年、50年後、どういう目標で社会をつくったらいいのかというのがどうも見えなくなってきていると指摘された。僕も経済審議会とか幾つかメンバーになっているのだが、どこでも何を目標にするかということよりも、やはり今ある計画をどう延長するのかという話が中心になっていて、目標がはっきりしない。こういうところが今日本が一番混迷しているところなのではないかと思う。国家が目標がはっきりしないから、企業だってなかなか先が見えないということも多分あるだろうと思う。
一方で、国家とか社会の思想とは別に、そこがきちんとしてくれないんだったら、自分たちでやろうというのが竹中さんの話だったという感じがした。 それから坂井さんの話。国家や企業には、居心地をよくするにはどうしたらいいかということをソフトの面からいろいろ考えてきている部門というのがあって、国家や企業が今までつくってきたものの中にもいろいろある。しかし将来、国家というものが30年、40年後にどうなるかということがはっきりしなければ、そういうソフトの方々も思い切った知恵が発揮できないのではないかという印象を持った。 |
 |
||
| 【上山委員】 | |||
| 今日、前半お2人のプレゼンテーションを拝見して、私は非常にわかりやすかった。ビジュアルであって、しかも日本のいい部分が素直に出ているという感じをすごく受けた。
その後、澤田さんの話を聞いて、日ごろ若干似た仕事をしていて日本の経営に関して非常にフラストレーションを感じていた部分を、また非常にビジュアルに感じて、今日は非常に共感を覚えるプレゼンテーションの3つだった。恐らく澤田さんが言われたような、ある種抽象的に、トータルに組み立てて考えていくという抽象思考が日本人はすごく弱いと思う。しかし、一方では、現場でいろいろないいデザインもあるし、チャレンジドの活動もあるし、NPOもあるし、すごくいいものができてきている。いいものの中のいい要素を組み立てて、それで目標であるとか、あるいは戦略に再編成していくというか、その作業をだれがどういう方法論でいつまでにやるのかという、そのあたりが恐らく国家戦略を考えるときにすごく重要な部分だろうと思う。 少しコメントを述べる。恐らく日本人は、何か目の前に危機を見せないと、将来どうなりたいということを考えないのではないかと思う。目の前にある非常にわかりやすい危機は、恐らく環境問題と失業問題だろうと思う。この2つがどれぐらい危機なのかということを数字で定量化して出すという作業が今目の前では非常に重要で、あちこちでできてきている非常にいいモデル、これをビジュアル化してどんどん宣伝していく。それをまたリストアップして、編集して、ある種何か国民運動のようにする。そういうことをやっていく中からまともな戦略論というのはできていくような感じがした。 |
 |
||
| 【井上委員】 | |||
| 坂井さんの発表で、あらかじめ落ちることを前提にしてプレゼンテーションをつくられることがあるというのが私はすごく面白いと思った。あらかじめ落ちるであろうことを見越してつくった図案が万が一通るというようなことはなかったのか。 |  |
||
| 【坂井委員】 | |||
| 意外とない。残念なことだが、企業の思考パターンというのは、そう大きく格差はない。 |  |
||
| 【井上委員】 | |||
| いずれはプレゼンテーション用に生かせるという気持ちもあるから、そういう制作にも力が込められるのだろう。 |  |
||
| 【坂井委員】 | |||
| それもあるし、向こう側から意思決定をするということは、責任を一緒に取ろうという行為だから、1個しか出さないと、それは僕が押しつけたことになる。だから、共犯者の関係にならない。そこがあるとプロダクトはスムーズに流れる。 |  |
||
| 【井上委員】 | |||
| これは竹中さんの話と絡むかどうか自信がないが、ゲイの方のセンスが大事だということについて。というのは、チャレンジドの方がもしかしたら、コンピュータに没頭できる点で優れているかもしれないという話と、ゲイの方への世間の差別の目とチャレンジドの方への世間の差別の目を一緒にしたらいけないとは思うが、むしろそういう人材こそ生かせないかという話は何か共通点があるような気がした。 |  |
||
| 【坂井委員】 | |||
| ゲイは、例えばシドニーとかサンフランシスコに多い。そういう都会的というか、文明がしっかり根付いているというようなバックグラウンドがないと、なかなかゲイはたくさん出てこない。だから、割合クリエイティブなところに近いと僕は感じている部分がある。 |  |
||
| 【竹中委員】 | |||
| ゲイの人とチャレンジドを一緒にしたらいけないかもしれないと言われたが、一緒に語り合われて良い問題だと思う。日本というのは、チャレンジドの問題も女性の問題なども、全部根っこは一緒だと思っている。うちにボランティアで来てくれる人にアル中の人とかゲイの人とかもいる。 |  |
||
| 【井上委員】 | |||
| これはやはり次世代に考え直さないといけないテーマである。 |  |
||
| 【竹中委員】 | |||
| 一度、東京でトップクラスといわれる「おかまバー」に連れて行ってもらったことがあるが、そのときに、サービス精神いうか、人をくつろがす技はこれか!という体験をした。大変、勉強になった。 |  |
||
| 【長谷川委員】 | |||
| 本当にゲイバーに行くといつも女性が多い。言われたように、本当にあのサービス精神だと思う。アメリカに行くと、建築家はほとんどがホモのようである。(笑)フランスとか、ヨーロッパに行ってもよくそう言われる。建築というものが、男性社会が支えているビジネスと社会の中にあるという一つの記号みたいなもの。だから近代建築の間で、建築家はホモだと、ずっと言われている。(笑) |  |
||
| 【石井委員】 | |||
| 建築家は非常に完成した姿を予想しているというか、求めている。例えば建物の中などでも。そういう人は大体ホモ。やはりミケランジェロとかレオナルドとか、ああいう人たちの異常な精度に対する追求心というのは、人口の半分は女だみたいなことを思っていたらできないのだろう。俺が全部やると。 |  |
||
| 【長谷川委員】 | |||
| 女性は不完全な野郎なのである。女性が建築家をやっているとそう感じる。私はコンペを通して公共建築をたくさんやってきたわけだが、その不完全さみたいなものがなぜかコンペの中で出てくる。私は、コンペの概要を読んでそのとおりにやったことはない。コンペの中では提案という形で、何かを提案しなかったら面白くないという形でやっている。読み込んだままを整理するのでは、それはもっとうまい、ベストの人がいるはずだから。私はもう少し違う角度で、大体違反していると思うが、読んでいくということをして提案型で出す。しかし、それが受け入れられるという公共の部分があって、もちろん受け入れられないこともあるのだが、それでコンペティションをずっと勝ち取って、落ちることも多いのだが、もう15年くらい公共建築をやっている。
私のことでも外国の人はそんなによくコンペが通れるとびっくりするわけだが、そうしたまさに男性が中心にいて、それを認めたくない私が仕事をしているという状況がある。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 長谷川さんの落ちるというのは、かつての時代から比べるとやっぱり変わってきているということか。行政の方が多様性を認めるようになってきたから落ちるようになったのか。 |  |
||
| 【長谷川委員】 | |||
| ある意味でパーフェクトで、そして何か力強く男性的で、そのコンペ要件に1つも違反していないような仕事が必要だというようにしか考えない審査員の前では落ちるだろう。しかし、そうではないものを求めている人もいるから採用されるわけである。それで私は落ちたり、入ったりしながら続けて、公共建築を15年ぐらいやっていて、それはすべてコンペティションを通ってやっている。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 先の建築家は男性的だという話。その中で公共というのはもっとそういう意味では完璧で、誰にも文句が言われないようなものになってしまう、何となくつまらなくなってしまう可能性があるということである。長谷川さんの案が採用されるようになるケースというのは、時代によって変わってきているということか。 |  |
||
| 【長谷川委員】 | |||
| 私がコンペに入るということは、開けているということだろう。 |  |
||
| 【石井委員】 | |||
| そういう意味で開けていないのは、例えば黒人の世界だろうと思う。黒人の人たちには、建築の世界においては、非常にバリアが高い。黒人が超高層とか、それから黒人が例えば彼らのつくっている建築のテーマにしても、映画とかに余りあらわれたことがない。 |  |
||
| 【安部委員】 | |||
| 澤田さんの話で、理念があって目標がある、それから戦略があると言われた。最初に企業としての理念があって、目標が定まって、そして戦略の段階になる。20年後をにらんだのと、50年後をにらんだのと、それと現在とのバランスの難しさということを話された。
これは少々極端な考え方かもしれないけれども、僕は日本の現状というのは大多数の愚民と、ほんの一握りのすばらしい人たちで成り立っている国だと思っている。そうすると、それがだんだん具体的な戦術レベルになると、そのときに今の大多数の日本人で、いい労働力になるのだろうか。どうして日本人が評価されたか、これは独自性の問題にもつながるのだが、それは日本人がやはり勤勉で誠実だったからだと思う。今の若い人たちを中心に得られる労働力というのは、果たして澤田さんが満足されるほど勤勉で誠実だろうか。 |
 |
||
| 【澤田委員】 | |||
| 今日は暮らしだけで話したが、その問題は本来はやはり教育の問題だと思う。教育の問題も一緒に考えて、20年後、30年後を考えなかったら、僕は大きな問題になると思う。
今の子供がいいか悪いはともかくとして、覚えること、受験のために勉強している。そうでなかったら除け者になる。僕はまず教育をもっと変えなくてはいけないと考えている。やはり子供はもっと遊ばすべきだと。遊ぶことによって新しい発想ができるし、新しい創造力ができるし、切磋琢磨することによって痛さもわかるし、辛さもわかるわけだから。それを小学校から中学受験、高校受験、大学受験と。覚えることだったら、コンピュータの方が優れていると思う。それを一生懸命、中国の歴史の何か知らないような遠いところまで全部覚えている。そういうことはコンピュータ叩けばすぐ出てくるわけだから、これからはもっと創造性豊かな、発想力ある教育をやらなくてはいけないと思う。 それがここ何十年間、非常に均一的な教育をされてきている。20年後、30年後を考える場合は、やはり教育をもう一度きちんと見直してやっていかなくてはいけないという気がしている。 |
 |
||
| 【安部委員】 | |||
| そうすると、将来の戦術的な労働力の確保ということで、日本人には限らないというケースもあり得る。 | 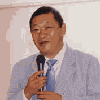 |
||
| 【澤田委員】 | |||
| 一番はやはり人間性だと思うから、人間性豊かな、きちんとした人間性であれば、別に日本人でなくても僕はいいと思う。ただ会社が大切ではなしに、人を育てる教育が一番大事だと思う。企業をやるのも国家をつくるのも人だから、一番大切なのは人である。ただ、それに関しては、今どうだと言われると一杯問題があるのではないかというしかない。 |  |
||
| 【林委員】 | |||
| 竹中さんの話で、コンピュータを使うときに、障害のある人によっていろいろな条件があるから、普通のキーボードではなかなかうまくいかないのではないか。その話と坂井さんのデザインの話を視聴していると、あのような量産もののデザインの仕方というのがいろいろ面白い課題を持っているのではないかと思った。坂井さんは機械的な部分をできるだけ残しておくと言われた。機械的な部分というのは、場合によると工場じゃなくても、何か比較的容易に手元で工夫してつくれる要素があるのではないか。
消費者が一緒に参加して、それで自分たちなりにつくり変えていくという、何かそういう部分がすごく重要だと思う。カスタマイズということかもしれない。 要するに、今のシステムの中でどのようにあり得るのかということ。案外そういうことを楽しみにして、みんなが使いこなすようになると、また少し違う文化ができてくるのではないかという気がする。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 先の戦略とか理念とか、戦略、戦術という話で、消費者の意見とか、消費者に理解してもらうという話があった。情報戦略という言葉もあって、消費者が考えていることを理念の中に取り込むとか、そういうことも多分これからは重要なのではないかという感じがする。多分竹中さんがやられているようなことも、初めは本当に小さな社会の中でやっていたのが、行政もだんだんそういうことの重要性に気づいて、それを取り込んでいかないと世の中が動かなくなってきたという気もする。 |  |
||
| 【林委員】 | |||
| 公園などでも、全部初めにつくってしまわない方がいいと思っている。3分の1ぐらいお金残して、それは公園のための基金か何かにしておいて使う。使っていくうちに、こんなふうにした方がいい、あんなふうにした方がいいとみんなわかってくる。そうしたらその基金から少しずつをお金を出してつくっていけばいいのである。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| やはり50年先と目先のこととを考えると、そのバランスとるためには、そういう糊代を少しとっておくということも大事だということになるかもしれない。 |  |
||
| 【松田委員】 | |||
| とても感動して聞いた。特に一番心に残ったのは、「毎月50万かかるんだったら、そのお金を自立するために使った方がいい」という言葉。
こういうところで話を聞くことが自分のエネルギーになってくるというのが今日の感想である。 |
 |
||
| 【隈部委員】 | |||
| 坂井さんの話を聞いて思い出した。今から12〜13年ぐらい前に、日本のデザイン、ジャパニーズ・デザインとかそのようなタイトルだったと思うのだが、「TIME」で特集された。日本のデザインは、ポスターとかそういうのに限らず、あらゆる日常の製品でも世界のトップクラスであって、そのデザインのよさが日本の将来をリードするという内容の特集だった。それを読んで初めて、そんなに日本のデザインはすごいのかと思った。現在、民間企業のいろいろなプロジェクトに参加していているが、今はデザインの話はほとんど出ない。先ほどトレンクルというのを見て、慶応の後輩があれをアルバイトで試乗してその報告を出すという実験をやっている。その話を学生などにすると、すごくいいアイデアだ、乗ってみたいなどという強い関心が示される。
多分これからは何が採用されるかという点で、デザインのいいものに対する消費者のニーズが無視できない気がしている。ただ、何が採用されるのかわからないところがある。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 大蔵省は、ある意味では予算を査定するときに、学校つくるにしても何にしても、一つ一つにあるべき姿のようなものを一応持っていて、それで予算つくっていくというのがある。一人何平米だとかいうようなこと。そういうことで、デザインなどが決められるということが十分あり得ると思う。そういう思想というのもやはり今では役所の中で変わってきているのか。もっと多様性を認めようとか、そういうふうに変わってきているのか。 |  |
||
| 【加藤委員】 | |||
| 余りまだ変わっていないのではないか。ただ、いろいろな役所の人と話をしていて、意外と建設省の人は変わり方が進んでいる感じがする。やはり、現場に近いところほど変わらざるを得ないということだと思う。
大蔵省、特に予算というのは、現場があって、担当官庁があって、その先に大蔵省があるわけだから遠い。だから、一番変わりにくいかもしれない。 前回と同じ話なのだが、私は最近、面白がって使っている言葉に「公益国家独占主義」というのがある。民法学者の星野さんが使っている言葉なのだが、公益、公共の利益というのは国が独占的に、判断し提供するというしくみをあらわした言葉だ。今の話も、学校はおろか、部屋の大きさからデザインから何でも全部これがいいんだというものを国が決めて与える。行政関係の法律というのは大抵最初の第1条に「目的」があって、その末尾に大抵「もって公共の福祉に資することを目的とする」と書いている。 公共の利益というのは世の中の役に立つことと解釈すれば、世の中の役に立つかどうかは世の中が本当は判断するのである。恐らく竹中さんが社会福祉法人の法人格を取るときに、やはり所管の厚生省の担当者がこうだとかああだと言うわけでしょう。それは要するに公益を、国を代理に担当者が判断しているわけである。恐らくそれでうまくいっていた時代が戦後30年ぐらいあったのかもしれないけれども、明らかに仕切れなくなっているということだと思う。そういう意味で、先ほど澤田さんが言われた、まさに仕切れた時代でなくなったときの理念とか、目標というのが見えないのではないか。 最近よく思うのは、今はとにかく景気を何とかしないと何にもできないという感じが溢れている。テレビで毎日、株価とか為替レートを報道しているけれども、大抵の人は関係ないし、本当に必要としている人はああいうものは見はしない。本来、必要な情報が世の中の雰囲気を動かしている。だから、一度、成長率とか失業率というのは一切公表しないことにしたらどうかと思っている。商売やっている人は、別に成長率が何%だって関係ないわけで、あれを見て商売している人たちというのは、余り世の中の役に立っていないのではないか。そういう世界からジャンプして、何をすべきか考えないといけないと思う。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 恐らく、もう2〜3日すると経済審議会がそれこそ同じような21世紀のあるべき姿というものを発表する。付録に10年後の経済成長率が何%と書いてあるわけである。下手すると新聞は10年後の失業率はこうだ、成長率はこうだということに見出しを付けてしまうのではないかという感じがする。マスコミ側も受け手の感性が非常に鈍くなっている感じがする。 |  |
||
| 【林委員】 | |||
| 公園などでも、全部初めにつくってしまわない方がいいと思っている。3分の1ぐらいお金残して、それは公園のための基金か何かにしておいて使う。使っていくうちに、こんなふうにした方がいい、あんなふうにした方がいいとみんなわかってくる。そうしたらその基金から少しずつをお金を出してつくっていけばいいのである。 |  |
||
| 【加藤委員】 | |||
| よく日本はお上が仕切る国だという。こういう話になると、それは日本の文化であるように言われるけれども、例えば田中委員の本などを見ると、決してそうではない。竹中さんが身障者を納税者にしようと言われた。江戸時代はまさにそうだった。目の見えない人は音楽弾いたり、按摩したりして、それでちゃんと家族を養っていたわけである。だから恐らく竹中さんの目標達成の日というのは、チャレンジドという言葉がなくなる日であると思う。江戸時代には、全然お上は世の中を仕切っていなかった。1000年前から日本はお上が仕切っている国ならもうあきらめた方がいいが、そうではないのだから、そうではない仕方をいろいろ工夫すべきである。 |  |
||
| 【澤登委員】 | |||
| やはりお金の使い方を考えた方がいいとつくづく感じる。それと場の提供、行政は行政、あるいは企業、みんなが場の提供をしていく。そこでも、やはり主体はそれぞれの個々人である。発酵する時間、あるいは面白がるために場を提供していったらいろいろなものが出てくるであろう。そこで主役になるのは、今の経済界の中の少し端っこにいる自由人ではないか。そこに新しい核ができて、フュージョンして、次なる場の創出を期待したい。いずれにしても、すべては一人一人を信頼し合うことから始まると思っている。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 建設省も10年、20年後を一体どういう国土計画、人と関係する国土計画をどうつくったらいいかということに迷いがあるのではないかと思う。いろいろな、多様な考え方の人たちの意見を吸い上げながらつくっていかないと、どんどん乖離してしまうという気がする。また、こんなことをやっているのは建設省だけではなく、経済企画庁も、郵政省もやっている。つまり、日本の国家、一種のエリートたちも何か迷ってきている。迷ってきているとすると、やっぱり現場に戻るしかない。現場の感性をどうやって情報整理というか、国家戦略とかそういうところに組み込んでいくかという話がこういう懇談会をつくらせている原因なのではないかとも思った。
一つ面白いと思ったのは、「豊かさ指標」である。「育てる」とか、「費やす」とか、「暮らす」とか、「遊ぶ」とか、「働く」とか、経企庁が8つぐらいの指標で示すもの。僕はあの指標の中で、それぞれ10年後、20年後、どうしたらいいのかという、そういう話がこの中から出てくると面白いのではないかと思った。今年の新聞を見ていると、「費やす」と「働く」がマイナスである。要するに前年比マイナス。つまり消費と失業率が増えたということである。ところが、「暮らす」とか「遊ぶ」とかそういうものは、むしろプラスになっている。新聞はどちらかというと、「費やす」と「働く」というのがマイナスになって世の中が暗くなったという論調が多いように見えた。僕は逆に、無駄なものを使わないで、働く時間も減って、しかも遊ぶとか、暮らすとか、そういうものがだんだん豊かになるということは、逆によくなっているというようにとらえることもできるのではないかとも考えたわけである。 そういう意味で言うと、「豊かさ指標」のようなものを軸にしながら、少し感性を出してデザインを描くと何か面白いものができるかもしれないという感じがした。 |
 |
||
| 【坂井委員】 | |||
| バブルがあって、不景気になった。僕の、特に外人系の友達はあと2、3年で復帰すると言う。そのときに、日本人の消費はどういうふうに変わるのか。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| 独自性だとか、個人個人のライフスタイルをもっと持とうとか、そういうふうに変わっていくのではないか。 |  |
||
| 【坂井委員】 | |||
| 質とか、豊かさとか、暮らしとか。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| ただ、それは個人できる部分と、あるいは日本人は企業社会の側に属しているから、企業社会としてやれる部分と、それから地域社会としてやれる部分と、国家としてやれる部分と、いろいろの段階があるだろうと思う。今、個人と企業社会というところが傷んでいるわけである。国家もある程度財政が赤字になって傷んでいる。そこのところで、個人でやれる部分は個人でやるけれども、個人でやっても、どうしても豊かに暮らせない部分というのは地域の問題だとか国家のインフラの問題であると思う。その辺をどうしていくかという感性を引き出すことが大事なのではないかという感じがする。 |  |
||
| 【坂井委員】 | |||
| バブルで反省とか勉強をした。不景気でまた勉強した。その結果として、両方体験した人々がどっちに向かうのかということに大変興味がある。 |  |
||
| 【嶌委員】 | |||
| そういう意味でいうと、何か自分の人生は自分らしく生きよう、消費についても生き方についてもそういう感じになってきているのが今の流れなのではないか。自分のブランドは自分でつくるということ。子供たちが一番やりたい職業は何かと言ったら、男は大工さんで、女の子はケーキ屋さんというのになってきた。かつてはスチュワーデスとか女優とかタレントが、あるいは男だと医者だとか弁護士とか会社の社長とか、そういうのが多かった。そういう意味で言うと、親の姿を見ながら子供たちも、俺は自分の好きなことやるのがいいんだというようになってきた。それが消費から生き方から、すべてにわたってだんだん多様化してきていることだと思う。 |  |
||
| 【上山委員】 | |||
| 大阪へ行くと、「このネクタイ何ぼやと思う?」と友達に言って、「 5,000円かな」「違う、 3,000円や」と。要するに7割引きで高価そうに見えるものを手に入れ、その差額分、自分の選択、センスに満足や誇りを感じるわけである。 |  |
||
| 【竹中委員】 | |||
| 実は私の知り合いで、ご主人が大企業の高給取りで奥さんもすごく素敵な方がいる。かわいい子供さんもいて、その人が私に「あんた、障害児のお母さんでよかったわね。何かやることがあって。私、今何にもすることがないの」と言われた。(笑) ハンディがあることは決してマイナスではない。世の中は確実に変わってきていると思う。 |  |
||
| 【川勝委員】 | |||
| 安部さんの発言の、すばらしいエリート、少数のエリートと多数の愚民という構図について。実はエリートというのが崩れている。澤登さんが言われたように、やっぱり自由人の発想でやっていけるところに、つまりエリートでなくて、そういう階段に乗っていない人のところにむしろ可能性があるということではないだろうか。
例えばここに石井さんの「自立する直島」がある。これは中央から離れた 3,000人の、離れ島みたいなところである。そこにすばらしい小学校をつくった。それが一体何を生んだかというと、感動と誇りだったわけである。それはしかし、彼らだけではつくれない。 チャレンジド、あるいは多くの自由人は、それだけでは自立できないと思う。やはり両者の間に信頼とか、あるいは何か感動するところがあって、そこに初めて新しいものが生まれるのではないかと思う。 今はもうある種のエリート、つまり教育組織がエリートを生まないと認識できる。だとすれば、その教育組織のトップにある東大は、例えばもう民営化したらいいとはっきり言ってしまったらいい。そうするとシステムが崩れる。あるいは違うふうになると思う。だから、下の方からどうしていくかという話と同時に、そのトップにあるものを変えていく。 僕は、上も下も両方とも実は同じ土俵で、互いに補完的で馴れ合いだと思う。むしろ可能性は「辺境」にある、あるいは「自由人」にあると思う。しかし、それだけでは自立できないので、やはりネットワークを通じて信頼とか、あるいは感動を生むような、そういう場を提供していく前夜にいるのではないかという気がする。 |
 |
||
| 【嶌委員】 | |||
| エリートがエリートたるために、今の現場、自由化している現場の感性をどうくみ取って論理化し、戦略化するかがエリートが生き残れる唯一の道ではないかと思う。 |  |
||
|
|
|||