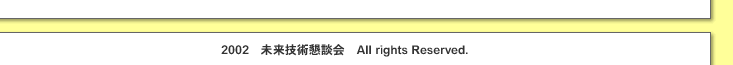|
|
| 6.ショートスピーチ 【月尾委員】  佐藤副大臣が冒頭の挨拶でおっしゃった100年以上先を見た夢のある話ということについてだが、東北大学の学長もされ、現在、県立岩手大学の学長をしておられる西澤潤一先生が4年程前に、「人類はあと80年で絶滅する」という本を書いておられる。 本当にそういうことになるかも知れない。 だから100年先を考えてもあまり意味はないということで悲観的な話もあるが、それでは困るので、何とかそれを克服していかなければいけない。 人間がこの地球に出てからの話を紹介させていただくが、農業を発明する以前は狩猟採集生活ということで、自然のものを採って生活していた。 ところが現在、この生活形態は人類にとっては限界に来ている。 狩猟採集の典型的な例である世界の漁獲高というのは1990年頃にピークに達しており、それ以降横ばいで、もはや世界中で魚がとれる量は増えていない。佐藤副大臣の地元でも昔はニシンが捨てるほど獲れたが、現在はほとんど獲れないという状況になっている。 そのような限界が来て、狩猟採集文明という人類が最初に生活していたスタイルは難しくなってきた。それから鉱物も、先が見えてきたものが沢山出てきている。 その次に、農耕牧畜文明を我々は手にしたが、これも1990年頃から穀物などの生産量は横ばいになっており、これ以上増えないような状況である。 特に水の制約などがあり、増えることは困難である。 それから牧畜も、今回の狂牛病問題は別にしても、世界に10億頭ほど牛がいるそうだが、それ以上は環境問題などでなかなか増やせない。農耕牧畜文明も、1万年近く行ってきたが、そろそろ限界に近づいてきたということである。 産業革命は、別の見方をすると化石燃料文明であり、石炭、石油という化石燃料をもとに発展してきたが、これもそろそろ先が見えてくるという状況になってきている。石油があと何年分しかないとか、いろいろな鉱物資源が何年分しかないということも見えてきた。 そこで希望は何かあるかということだが、情報というものが新しい文明をつくる可能性があるかということである。人間はいろいろなスタイルの文明を積み重ねてきたが、出現の古い順番から限界が近づいてきた。これを何とか変えるということを考える必要があるだろうということである。 次に100年単位で考えて、人類にとってどういうことが必要とされているかということを考えてみると、まず1番目は、さまざまな鉱物資源やエネルギー資源が限界に来ているので、それを転換するということを考える必要がある。 次に、地球環境というものが限界に近づいたと言われているので、これをどのように回復するかということも考えなければいけない。 それから、人間というものが圧倒的に地球の上では優位だとか偉いというように考えてきた訳だが、これも別の視点が必要ではないか。 それから最近、グローバリゼーション、デファクトスタンダードと言われるような現象が進み、世界全体が1つの文明に収斂されていくということが起こっているが、これについても本当に良いのか、独自の文化、文明というものが必要ではないかということを考えなければならない。 5番目は、ごく最近まで人類は必ず増大するということを前提として技術開発を行ってきており、生活様式も営んできたが、違う方向の文明も考える時期に来ているのではないかということが、100年単位で考えるべきことである。 順番に見ていくと、我々の生活を支えている基幹資源は、石油が50年、石炭が200年、天然ガスが70年と予測されている。 それから、原子力エネルギーの原料であるウランも、現在のように1回だけで使い捨てということであると3、40年と言われている。 それから、銀が20年、銅が50年ということである。この数字は多少変わることがあっても、これが何万年になるとか、何千年になるということは考えにくく、せいぜい数十年から、長いものでも数百年程度しかないという状況になってきた。 これをどう転換していくかということが、これからの未来技術の重要な視点だと考えている。 それから、地球環境については大変なことが発生しており、まず森林の伐採が年間1,500万ヘクタールである。 これは、ゴルフ場が1日に500カ所分ずつ消滅しているという状況である。 それから、生物が15分に1種類ずつ絶滅しており、これは計算し直すと、年間35,000種類の生物が絶滅していることとなる。 これは大型の哺乳類だけではなく、土の中の細菌とか、昆虫とかあらゆる生物を含めた数字である。地球上には5,000万種類ぐらいの生物がいると推定されているので、1000年以上もつという計算にもなるが、これは生物のピラミッドを崩すという点では大変な問題である。 それから、これも一時的なことかも知れないが、暴風雨などによる災害がこの十数年間急速に増大しており、最近では年間200億ドルの被害が出ており、10年前に比べると何十倍も増えている。 大気気温の上昇についても、何十億年という地球の歴史で見れば一時的なことかも知れないが、少なくとも過去100年で0.5度上昇し、これから100年で最悪の場合5.8度は上昇すると予測されている。海面はその場合88センチメートル上昇するという予測もあり、現在の人類が出現してから経験したことのない問題が起こっており、この問題をどう解決していくかということも、これからの技術の問題である。 それから、人間優位の思考や宗教というものが、社会もしくは地球への大きな圧迫になっている。例えばキリスト教をはじめとする一神教というのは、人間が増大することを良しとする宗教であり、そのために人間が地球を支配していくという発想に立った宗教が世界全体でかなり優位になった。 今回のアフガンでの戦争はその一神教の2つがぶつかったと見れる訳だが、キリスト教とイスラム教という人間こそ世界の頂点に立っているという宗教がこれまでの社会を支配してきた。 それから、15世紀頃からルネッサンスが起こったが、これは人間復興とも言われ、人間が最もすばらしい存在だということを社会の大きな理念にするということになった。 それから、17世紀になってデカルトが西洋近代科学と言われるものの基礎をつくり出したが、これは人間にとって役に立つ科学をつくっていくという発想に立ったものであり、その結果として、自然を征服していくという技術が発展するということにもなった。一般にヨーロッパを中心とした社会で、人間というものは優れた存在だという思想が広がったが、これも見直すような時期に来ている。 独自の文明を再考しなければいけないというのは、現在、グローバリゼーションが進展しているが、それを見直すということである。 例えば言語というのは6,500程度世界に存在しているが、より普遍性のあるものほど良いと考えられている。例えば学界で言うと、論文は英語で書くのが良く、少数民族にしか通用しない言語の論文は劣るという考え方がある。 6,500程度ある言語が、年間平均すると60程度地上から消滅している。 その結果、最悪の場合2100年、100年後にはせいぜい10%程度、つまり650から700程度の言語しか地球上に存在しなくなるということさえ予測されている。 一方では、誰もが英語や中国語を話して便利だという世界かも知れないが、それが本当に人間にとって良いことなのかという反省も行わなければいけない。 IT時代になり、英語というデファクトスタンダード言語が優性になった。 書籍の世界では現在でも大体3割弱が英語である。2番目が中国語で13%程度である。 ところが、インターネットの世界でウェブがどのような言語で構成されているかという統計を見ると、84%が英語である。 つまりITが、一気に英語を支配的な言語にするということが起こっている。その結果、まさに世紀の幕開けのときに、キリスト教とイスラム教の激突が起こった訳だが、これからサミュエル・ハンチントン教授が予測したようなことが起こり得るという状況が出てきた。 もう一度多様な文明を世界全体で維持していくということも、我々は考えなければいけない状況にあるということである。 もう1つ、縮小するということも考える必要があると考えている。 これまではどういう方向かと言うと、生活を向上させるということは経済の拡大になる。例えば誰もが自動車を使えるようにする、誰もがエアコンを使えるようにする、といったことが経済の拡大になってきた。 しかし、それはエネルギー資源、鉱物資源などの消費につながり、結果として、環境を破壊するという方向に来たということである。 これが世界規模の環境問題になっている。解決する1つの方法は、生活の水準を低下させることである。 自動車をやめて自転車にする、エアコンをやめて暑くても我慢する、といったことを実践していけば、自動車が売れなくなり、エアコンが売れなくなり、電気の消費が下がり、経済が縮小していく。 しかし、そのエネルギー資源、鉱物資源の消費の縮小によって、環境への負荷が低減するという方向は実現出来る。 それに対して、1970年代頃から言われているのがサスティナブルデベロップメントということで、生活は向上させる、経済も拡大させる、それでもエネルギーや資源の消費は減少するというような仕組みを考え、環境への負荷を低減していくという新しい社会をつくるということも必要だろうということであり、これからの技術は何を目指すかということで考えれば、持続への道筋をたどれるような技術を考えていくということが重要になると思う。 ここまで、1万年程度のことについて話したが、別の視点から技術というものを考えたらどうかということについて話をさせていただく。 産業というのは、一次、二次、三次と分けている。これは1941年にコーリン・クラークというオーストラリアの経済学者が考案した分類である。ご存じの方も多いと思うが、多摩大学前学長であるグレゴリー・クラーク先生はコーリン・クラーク先生のご子息である。 そのコーリン・クラーク先生が考えられたのがこの分類であり、自然界の中から人間にとって必要な物質を奪取してくる産業が一次産業である。 漁業は分かりやすいが、海洋から必要な魚を獲ってくるということである。 それを加工して、人間に有用な物質にするというのが二次産業の役割である。米を餅にする、鉄鉱石を鉄にするというのは二次産業であり、その鉄を自動車に変えるのも二次産業である。 三次産業は、それを人間が利用出来るように配分することである。分かりやすいのは輸送業だが、北九州で作った鉄を世界で必要とするところへ分ける、アメリカで大量に出来た食料を世界中に配分するのが三次産業である。それに付随して、情報がなければ食料も物もどこへ輸送するか分からないということになれば、情報通信も三次産業である。 輸送途中での保険が必要だということであれば、それも三次産業である。 また、物をつくるためには初期投資が必要であり、金融も三次産業になる。 ところが、日本の1930年時点では、一次産業の就業者が52%、二次が19%、三次が29%であった。 ところが現在、一次産業はわずか6%に減少し、三次産業は62%に増加している。 クラーク先生の分析の中心は、社会が発展していくに従い、産業構造は三次産業主導の方向にいくということであり、日本もコーリン・クラーク理論のとおりに進んできたということである。 ところが、このように変化したにもかかわらず、従来のように一次、二次、三次という産業構造で社会を考えるということは矛盾があるということである。何故かというと、従来とは全く違う社会のパラダイムが現れたからである。例えば、人口も経済も増大する社会から減少する社会に変わった、大都会へ集中するという社会構造が分散し始めた、国民の価値観が生産や企業であった時代から家庭や生活へ移った、開発が重要とされていた時代から開発に対する反対が起こるようになり、むしろ保全、更には、釧路川で検討しているが、かつて直線の運河にした川をもう一度蛇行した自然河川に戻すということさえ始まるということになった。 また、地域で自給していたものが国際的な社会へ依存するようになってきた。日本の食料は、60%以上を海外に依存し、エネルギー資源は80%以上、石油だけをとれば99.9%は海外に依存するという構造になってきた。 このような大きな構造変化が起こりつつある中で、従来の産業構造を以下のように考えてはどうだろうかということである。 一次産業は、食料を生産するということに主眼を置くより、環境を保全していることがより重要だと考えてはどうかと思う。 その過程の中で食料も同時に生産している程度に考えた方が良いのではないかということである。 二次産業については、資源循環活動と考えてはどうか。 アメリカでは、理論上は新規の鉄鋼は社会に投入しなくても社会を維持出来るというシミュレーション結果がある。 それはスクラップ・アンド・ビルドで、アメリカの社会に存在している建物、自動車、橋梁などの鉄を順次循環させていくだけで、十分アメリカの鉄鋼需要は賄えるということである。日本においても、ここ数年、国会でリサイクル関係の法案が次々と通過しており、リサイクル社会へ転換している。リサイクルをするということが、二次産業の中心的な課題になり、新規のものをつくるというよりは、循環の方に重点を置くべきではないかという発想で産業を見直したらどうかということである。 サービス産業というのは、様々な分野が入っているので整理し、1つは私達の生活を支援する、つまり生活が成り立つようにする活動とする。 通信や輸送というのはその典型であり、金融や保険もそのようなものであると考える。 もう1つは、これまであまり重視されていなかったもので、情報公開が急速に浸透しているが、そのような情報を社会が共有するということがこれからの時代に重要になるが、それを促進するための社会活動を新しい産業構造の中に位置づける。 もう1つは、医療や教育というのはそのためにあるが、文化を次の世代へ伝承していくということも産業として考えてはどうか。 一次産業についての例を紹介すると、林野庁が10年毎に計算している森林の公益機能評価というものがある。森林というのは、これまでは木材を産出したり、椎茸などの副産物を産出するということに大きな価値が置かれていた。ところが、林野会計は3兆円の累積赤字であり、そのうち2兆円を棚上げし、1兆円を林野庁が抱えて苦労している。毎年約5,000億円の資金が投入されるが、国有林から産出される製品というのは、2,000億円から2,500億円程度しかない。それは、普通の視点でいえば、産業ではない。 ところが、林野庁の計算によると、例えば森林があるために水源が涵養されている。つまり雨が一気に川に流出してしまうのでなく、長時間に渡って水が留め置かれて徐々に供給されるので、水不足にならないということである。 森林がないとすれば、ダムなどを膨大に建設するということになるのだが、その年間償却費用は27兆円である。 それから、土砂の流出などを防止しているという役割も同じような方法で換算すれば年間28兆円であるとか、炭酸ガスを酸素に変えるという機能を森林が果たさないとすれば、化学プラントに年間5兆円程度はかかる。結局75兆円の価値があるということを林野庁は言っている。 実際、国民もそういう意識が高く、総理府が行ったアンケートで、森林に何を期待しているかと言うと、木材や林産製品を期待しているのは非常に僅かであり、公益的価値と言われるようなものを国民も期待している。 確かに林野庁が言うような価値を国民も高く評価しているということである。 それから、世界の自然が地球を維持するために果たしている価値を、先程と同じように計算すると、大体32兆ドル程度であると言われている。 円に換算すれば3,500兆円程度ということになる。 この3,500兆円がどのような数字に匹敵するかというと、現在の世界全体のGDPが32〜33兆ドルであるので、人間が1年間働いて生産するのと同じ程度の価値を、自然というものが地球の上にもたらしていると考えられる。 そうすると、これまでは、役に立つ部分だけを私達は経済活動や産業活動の中に取り込み、それを高めるという形で技術開発を行ってきた訳だが、これまでは内部経済に入れずに、外部経済として放置してきた部分に大変な価値があるということになる。 それを維持している1つが森林であると考えてはいかがかということである。 そのように、従来とは違う形で産業構造を考えると、これまでは考えなかったような様々な活動が出てくる。 例えば、森林というのは針葉樹を植林していた。これは木材を生産するということが目的だったのだが、最近は役に立たない広葉樹を植えている。 かつて開発した自然を元に戻すということが新しい産業になる。 循環という視点からいえばリサイクルがビジネスになる、生活支援でいえば安心というものを提供することが大きなビジネスになるなど様々なことが考えられる。従来は、産業という視点からは捉えられていなかったような活動が出てくるということがこれからの社会の中で重要になる。 そのような視点からも、新しい技術開発の目的や内容を考えてはどうか。 次に、佐藤副大臣がおっしゃった夢のある話になるのではないかと思うが、フロンティアを開発するということに私達は努力すれば良いのではないかと思う。 アメリカが上手く行ってきた。アメリカという国は様々な国難に直面した際に、フロンティア政策によって蘇ってきたという歴史を持っている。 1929年に世界大恐慌が起こった。後に就任したルーズベルト大統領がニューディール政策を発表し、立ち直ることが出来たということがあった。 このニューディール政策というのは、アメリカに残っていたフロンティアを開発したのである。 例えば、水の便がなくて農業が出来ない、交通の便がなくて人が住めない、という地域にダムをつくって水を行き渡らせる、道路を造り人が住めるようにするということを行い、従来使われていなかった国土を開発するということがニューディール政策の重要な役割であったのだが、それによって成功した。 1957年にスプートニクショックが起き、アメリカは大打撃を受けた。 その後、ケネディ大統領が登場してニューフロンティア政策を提言し、アメリカ人に宇宙へ出ていこうという希望を与えてアメリカは蘇り、ソ連を逆転するということにもなった。 1990年に日本のNTTがVI&P計画を発表した。これは、現在政府が推進しているIT基本計画を11年前に提案していたという内容であるが、2015年までに日本のすべての家庭に光ファイバー網を張りめぐらすという計画を立てた。これに驚いたアメリカがつくり出したのがサイバーフロンティア政策であり、クリントン政権になってからインターネットをはじめとするITがつくり出す世界へアメリカ企業が進出していこうという号令をかけ、アメリカのIT戦略が成功した。 アメリカは、様々な大問題に直面する毎にこのような政策を行ってきた。我々もフロンティアを考えたらどうだろうかと思う。 フロンティアというのは幾つか良い点がある。1つは新しい技術革新が展開するということであるが、それだけではなく、新しい経済活動も発展するということである。現在はITバブル崩壊で旗色が悪いが、アメリカがニューエコノミーと言われる、従来の経済学では理解出来ないような発展をした時期があった。 収穫逓増の原理により、時間と共に拡大していく経済活動が可能だということを言い、それが実践されてきた。それは従来の理論では説明出来ないと多くの経済学者が言っていたが、その通りであり、従来とは全く違う経済活動であった。 日本では構造改革が難しいという現実だが、それは従来の社会を引きずりながら行っているためであり、新しい世界へ入っていくと理解すれば、社会秩序を変えることも出来るということになる。そういう点で、フロンティアというものを考えてみてはどうか。 5つのフロンティアを紹介させていただく。 1番目はサイバーフロンティアで、これは森内閣から日本も進めているものである。従来の物質を中心とした、つまり工業を中心としたアトム技術ではなく、情報の単位であるビットを中心とした技術で新しいフロンティアを形成していこうということである。 これまでは、経済は拡大することが良いと考えられ、拡大を追求してきた。しかし、これからは速度が重要であるということである。いかに早く新しいビジネス、新しい産業を興していくかということが競争力になると言われており、このような変化が経済に起こると考えられる。 社会秩序というのは、地理空間のような距離、位置、規模というものに影響される社会ではなく、別のものが支配する社会になる。 例えば、現在、情報ビジネスが札幌や那覇などへ急速に移行し始めている。顕著な例としては、アメリカのアマゾンという会社が日本に進出する際に、カスタマーセンターは札幌に設置した。これまでであれば必ず東京であったが、情報空間を駆使するということであれば、東京も札幌も差はないが、家賃、人件費、居住環境ということを考えれば、札幌の方が良いという判断で、アメリカの企業がいきなり札幌へカスタマーセンターを設置するということが起こった。 このように、日本の端にあるからだめであるという時代ではないことが起こる。これを是非本格的に推進するべきである。これはフロンティアというよりは、既に我々はその渦中にいると言ったほうが良い。 2番目は畑村先生の専門分野であるが、ナノ、ピコという非常に小さい単位の世界である。 ナノというのは10億分の1という単位、ピコというのは1兆分の1という単位である。すなわち、ナノメートルと言うと10億分の1メートルという単位になる訳だが、そういった小さな部分に新しいフロンティアを発見するということであり、原子や分子を扱い、我々が必要とするものを製造するという社会である。 ここでも技術革新が起こっている。従来では歯車を作るという場合、鉄の塊から削り出して必要な形状を作るとか、非常に小さな歯車でも、半導体技術を使いシリコンのウエハーから目に見えないような歯車を作るということであった。ところが、ナノ、ピコというオーダーの技術になると、歯車は必要な分子を歯車の形に寄せ集めて作るという形になり、新しい技術が出てくる。 その結果、モノを必要に応じて作るということになり、これまでのように大量に作って供給する必要はなく、その都度、分子、原子を寄せ集めて作るということも出来るようになってくる。 これまで私達は、外部の視点から物というものを見ていたが、これからは分子、原子という内側の視点で社会を見るという方向に変わるということになると、社会の秩序が大きく変わる可能性もある。 3番目はインナーフロンティアである。インナーというのはいろいろな意味に使われ、例えば、海の中もインナーと言われているが、ここでのインナーは脳の中であるとか、心の中を解明していくということである。 これは科学哲学的な話になるが、現代までの科学は物事を分けていくということで本質を理解するということになっていた。 この机は何で出来ているか、木で出来ている。木は何で出来ているかと、細胞で出来ている、更に細かくしていけば分子、原子で出来ているというようにして真理を極めるということであった。 そのような中で、人間というものを、精神と肉体に切り離して科学の対象にしてきたということが問題であり、これをもう一度統合して新しい科学をつくるという動きが出てきている。 そのためには、精神というものを科学の対象として理解することが必要だということになってきている。 4番目は、話題の分野であるが、バイオフロンティアである。 ヒトゲノムをはじめ様々な遺伝子の解明が進むことにより、従来は実現出来なかったようなことが実現出来るようになってきた。 植物の中に動物の遺伝子を組み込むことにより、人間の食料にとって都合の良い生物を作る。 それは良いことかどうか分からないが、そのようなことさえ現在は可能になった。これまではいろいろな種を交配させては偶然出来たものをさらに育てるという方法で、新しい植物、動物を作ってきたが、これからは必要とするものを遺伝子レベルで作ることが出来る。 そのような分野を新しいフロンティアとして取り込んでいくということも必要である。 最後はエコフロンティアで、環境問題が危機的な状態になってきた。これに取り組んでいくために、生活水準やビジネス効率を向上させるけれども、資源やエネルギーの消費は縮小していくというような新しい技術体系を考え出す必要があるだろうということである。 それから、グローバルに拡大していく経済活動に対し、地域経済を見直すということも必要だろう。 1例を挙げると、地産地消という活動が日本国内でも活発になっている。 ある地域で生産した食料や工芸品を世界に売るのではなく、その地域で消費していこうというような新しい活動が出てきている。 それを裏づけるために地域通貨という概念も出てきたが、グローバル化していった経済とは対極的な新しい経済をつくるということも考えれば良いと思う。 また、キリスト教、ルネッサンス、近代科学が進めてきた人間中心という概念も、もう一度生物平等という視点に立ち、科学というものも考え直す必要があるだろう。 最後に、このような分野を開発していくためには、過去の常識や成功体験を捨てるということである。 規模が拡大していくということが良いというような哲学や理念も捨てていく。 これまでの蓄積の上に重ねていくということもフロンティアでは必ずしも妥当であるとは言えない。 完全に捨てるということではないが、見直す必要があるだろうということである。 以上、100年、1000年単位の技術が何をすべきかということをお考えいただいたらどうかということで、従来とは少し違う視点で3つほど話をさせていただいた。 |